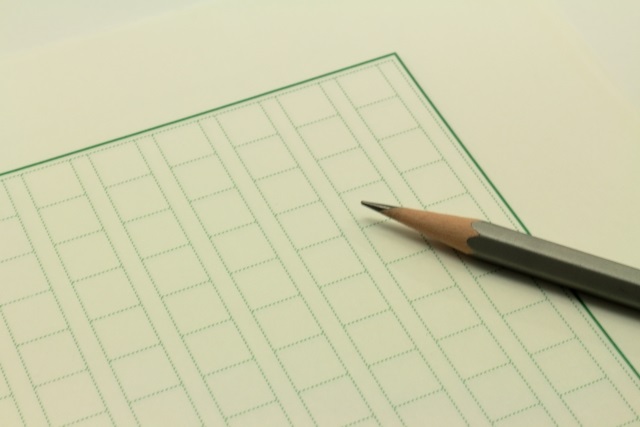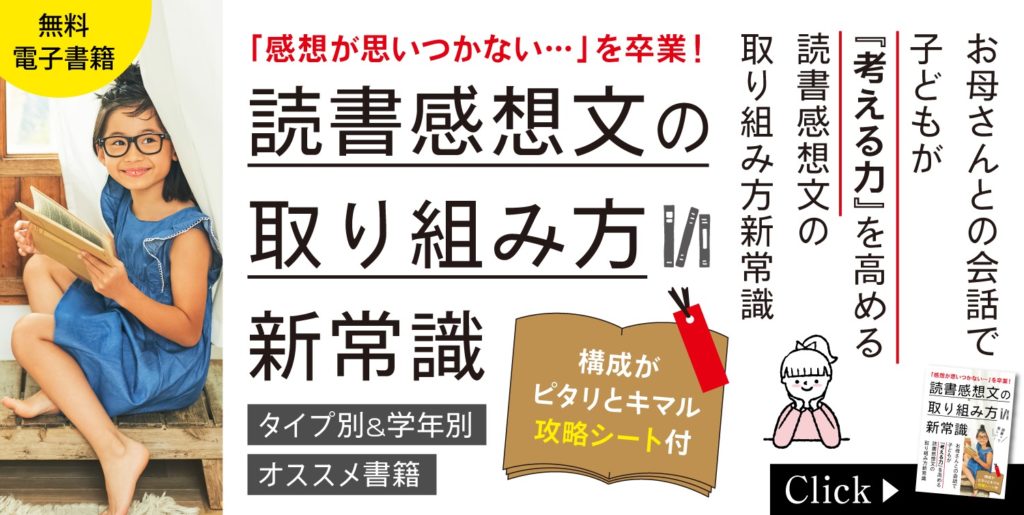小学生になると、日記や作文など長い文章を書くことを求められます。感想が思いつかない・作文が書けないという悩みは、発達障害の有無に関わらず多くの親子が持っていると思います。そこで、今回は「たった1時間」で感想文が書けちゃう秘密を大公開します!
【目次】
1.「感想が思いつかない・作文が書けない」と発達障害の子どもが困っていませんか?
2.子どもが「何を書けばいいのか分からない」と言い出す理由
3.文章が書けない問題を解決する!構成がピタリとキマル攻略シート無料プレゼント
1.「感想が思いつかない・作文が書けない」と発達障害の子どもが困っていませんか?
小学生になると、国語の宿題で長い文章を書く機会が増えますよね。
日記、読書感想文にその他もろもろ…
「感想が思いつかない・作文が書けない」と悩む親子は発達障害の有無に関わらず多いのではないでしょうか?
特に、長い文章を書くのが苦手!というお子さんは、たくさんいらっしゃると思います。
私が小学生の頃は、毎日必ず音読と日記が宿題に出されていました。これが毎日となると文章を書くのが苦手な子はつらいですよね。
夏休みは、宿題で絵日記や作文が出される学校も多いと思います。
お子さんは日記や作文と聞いただけで嫌がったり、辛そうな顔、面倒くさいと言ったりしませんか?

文章を書くのが苦手な子にとってはまさに苦行です!発達障害を持っているお子さんにとっては、集中力が必要で時間のかかる作業は、とても辛いです。
さらにお母さん方のなかにも、「文章を書くことが苦手」「どうサポートすればいいのか分からない」という方がいるかもしれません。
実はあなただけではないんです!
2.子どもが「何を書けばいいのか分からない」と言い出す理由
お子さんは「何を書いたらいいのか分からない」「感想が思いつかない」と言っていませんか?
「何でも好きなことを、好きなように書いたらいいのよ」と伝えても、なぜかぴんと来ていないみたい…ということ、ありますよね。
これには理由があるんです。
◆①テーマを1つに絞ること自体が難しい!
発達障害の子どもたちにとっては、テーマを1つに絞ること自体が難しいのです。
しかも発達障害の子どもは過去を振り返らず、未来を考えず、「今」を生きているタイプ。
過去を振り返らなくては書けない日記や作文は、そもそも合っていないのかもしれません。
◆②同時並行の作業が苦手
また、日記や作文は、頭で思い出したり考えたりしたことを、文字でアウトプットしなければなりません。
2つの作業を、同時に行わなくてはいけないのです。
発達障害の子どもで、この同時の作業を苦手とする子どもはたくさんいます。
脳への負荷が高くて、やりたくない気持ちが沸き起こることで、「何を書いたらいいか分からない…」とぼやいたり、どうしたらいいのかわからなくなってパニックを起こしたり、癇癪を起したりするお子さんもいるかもしれません。
特に読み書き障害(ディスレクシア)の子どもは文字を書くことが困難ですのでかなりハードルの高い作業となります。

ただ、この先社会に出るときには、エントリーシートや履歴書、経歴書、企画書など、長い文章で表現することを求められることは多くなります。
苦手意識を植え付けないようにしていきたいですよね。
では、発達障害の子どもが長い文章を書くとき、お母さんがどんな風にサポートしていけばいいのでしょうか?
3.文章が書けない問題を解決する!構成がピタリとキマル攻略シート無料プレゼント
発達障害の子どもは、そもそも何を書いたらいいのか分からない、というテーマ設定の段階からつまづいています
そして、そのテーマを説明するためには、どのような内容をどのような順番で伝えていけばいいのか、文章構成も整っていません。
お母さんも、普段から「話が飛ぶ」「話してくれてるけれど、正直良く分からない」と感じることが多いのではないでしょうか?
脳の発達の順番として、話す→書くの流れで発達していきます。順序だてて分かりやすく話すことに課題があるのなら、もちろん分かりやすく書くことは難しいということ。
だからこそ、何をどのような順番で考え、伝えていけばいいのか、ナビゲートするものが必要でなんです!
そこでパステル総研では、おうちで子どもの考える力を伸ばしながら伝える順番をナビゲートして、短時間で読書感想文を仕上げられる攻略シートを開発しました!
分かりやすく「読書感想文」というタイトルを付けましたが、もちろん作文や日記にも応用していただけます。
このシートを利用して、たった1時間で感想文を仕上げられた!という声も多数いただいています
ぜひたくさんの方に利用していただきたいと思っています。
\無料プレゼント/
文章が書けない問題がたった1時間で解決する!
”考える力”を伸ばしながら
感想文がすらすら書けちゃう方法はこちら!
文章が書けない問題がたった1時間で解決する!
”考える力”を伸ばしながら
感想文がすらすら書けちゃう方法はこちら!