| 春休みや夏休みの長期休み明け、ゴールデンウィークなどの連休明けには学校には行けるけど「教室に入れない」と不登校になる子どもが増えます。発達障害のある子どもはなおさら登校しぶりになりやすい!そんなときにお母さんにできることを紹介します。 |
【目次】
1.学校には行けるけど、教室には入れない、なんてことはありませんか?
2.なぜ発達障害の子どもは教室に入れない?
3.子どもがつらいと感じている場合にママがやるべき対応
4.学校に配慮をお願いするときのポイントは?
5.学校で学ぶために子どもにとって大切なこと
1.学校には行けるけど、教室には入れない、なんてことはありませんか?
春休みや夏休み、冬休みなど長期の休み明けやゴールデンウィークなどの連休明けに「学校に行きたくない」と言い出す発達障害・グレーゾーンの子どもが多いですよね。
例えば、新学期だとクラスや環境が変わり、始めのうちは子どもたちも変化に対応しようと頑張っています。
子どもが大きく崩れる事なく1ヶ月がたち、楽しく学校に通えているなと安心していると、ゴールデンウィークなどの連休後に突然教室に入れない子どももでてきます。
ママからすると今までちゃんと学校に行けていたのに「突然何があったの?」と思うかもしれません。
けれども、どうして学校に行けないのか、もしくは学校に行けても教室に入れないのか、子どもに聞いたとしても、親が納得できる答えが返ってこないことも多いのです。

我が家の長男が小学校低学年だったときにも、ゴールデンウィーク明けから、徐々に学校を行き渋るようになりました。
学校に行きたくない理由をたずねると、「給食がイヤ」「みんながうるさい」「なんか疲れる」とのこと。
頑張って登校していたのに、特別いじめや問題があったわけじゃないのに、教室に入れないまま、結局不登校になってしまう・・・。
こんな様子が続くとママも不安になってしまいますよね。
一体子どもに何が起こっているのでしょうか?
2.なぜ発達障害の子どもは教室に入れない?
4月は先生やクラスの友達がかわり、発達障害やグレーゾーンの子ども達も必死でその環境についていこうと頑張っています。
けれども、もともと学校で頑張りすぎていたり、無理をしている場合には、長期休みや連休をきっかけに学校に行くのが怖くなってしまうのです。
例えば学校生活では、こんな気持ちを感じているかもしれません。
「勉強が難しくて授業が分からない。」
「友達と仲良くできない。きついことを言われる。」
「先生が怖い。みんなの前で怒られる。」
「次に何をしたらいいのか、自分だけ分からない。」
「ママと離れたくない。」
そして最も分かりにくいのは、発達障害の子どもにみられる感覚の過敏性が原因の場合です。
・教室のいろんな人の匂いが気になる。
・制服の化学繊維に痛みを感じている。
・椅子や机のガタガタした音が耳にさわる
・音楽の授業の合唱の不協和音が苦しい。

・日差しに他の子どもよりも肌に痛みを感じている。
・給食の食感や味に耐えられないのに残さず食べるようにうながされている。
・問題用紙が白くまぶしくて、見にくい。
・不器用で動きがぎこちない、転びやすい
ただでさえ、学校に行くと家とは違って周りにあわせたりして自分の自由な時間もほとんどない、ストレスが高く緊張する環境です。
長いお休みでは、自由な生活で充電できる子もいますが、一方で十分にリフレッシュできず、休み明けの登校の日を絶望的な気分で迎えている子もいる子もいるのです。
また、子ども自身は自分が感じていることが、周りの子とは違っている、特別なことだとは感じていません。
ですから、なぜ自分はこんなにしんどいのか?教室にいることがつらいのか?なぜうまくできないのか、子ども自身には理解ができないのです。
そのため、さらにストレスに感じたり、自己肯定感が下がったりして余計に学校に行きにくくなってしまいます。
では、どうしたらいいでしょう?
3.子どもがつらいと感じている場合にママがやるべき対応
子どもが教室に入れない、学校に行くのがつらいと言えたことは、とても勇気の必要なこと。
ですから、まずは子どもが自分の気持ちをきちんと言葉にできたことを認めて、子どもの気持ちをしっかりと受け止めて話を聞くことが大切です。
子どもは話を聞いてもらって、安心できる声かけをしてもらうことで、ずいぶんと気持ちも軽くなるはずです。
気持ちをはき出すことができても、教室には入れない状況があれば、遅刻や早退、欠席をすることを積極的に検討してください。
現時点では、一旦教室に入れないのなら、入らないでいい、登校できないのなら、登校しないでいいとママが決めることが大切なのです。
なぜなら、「子どもの心を壊してまでやらなければならないことは何もない」のですから。

まずは子どもの気持ちが安定するまで、しっかりとお家で好きなことをして、ゆっくり心を休めることを優先に考えてあげましょう。
気持ちが前向きになってきたら、ここでやっと学校に行くための問題を解決することに目を向けていきます。
ですが、様々な問題が絡み合って、簡単には解決しない場合も多いので、焦らずにいることが大切です。
特に、感覚の過敏性がある場合には、感覚過敏を軽減する必要がでてきますが、子どもの努力だけでは解決は難しいかもしれません。
こうした場合には、ママが子どもの代わりに感覚過敏について学校に説明をしたり、配慮を求め、連携を図っていくことが必要となってきます。
4.学校に配慮をお願いするときのポイントは?
学校にお願いするときは、伝え方にポイントがあります。
まず、先生方に日頃の配慮への感謝を伝えることが大切です。
感謝もなく、要求ばかりされると、先生方もだんだんその保護者を怖くなってきます。
学校と良い関係をつくっていくためにも、日々子どもに関わってくださる先生方に見守りや声かけへの感謝を忘れずに伝えていきたいものです。
そして、なんとなく困り感を伝えるより、困っていることに対して具体的にどのような配慮をして欲しいのか伝えることが必要です。

わが家では過去に校長先生に、給食の配慮をお願いしたことがあります。
最初は、「学校の給食では、偏食が強くてほとんどの物が食べられません。給食でご配慮いただけることは何かあるでしょうか?」というような伝え方をしました。
すると、校長先生に「どういうことでしょう?」と聞き返されました。そこで、
「味覚の感覚過敏とこだわりが強く(①困っている特性)、
ほとんど給食を食べることができません(②どんなときに困っているか)。
食物アレルギーでお弁当を持ち込みされているお子さんもいるとお伺いしました。
食べられるものが何もない日だけ、お弁当の持ち込みは可能でしょうか?(③お願いしたい配慮)」
と、言い換えてみました。
すると、快くお弁当の持ち込みの許可をいただけました。
①困っている特性
②どんなときに困っているか
③お願いしたい配慮
を具体的に伝えることで、支援の必要性を理解してもらいやすく、受け入れていただきやすくなります。
5.学校で学ぶために子どもにとって大切なこと
登校しぶりの原因は、実際には複合的で、感覚過敏だけではないことが多いでしょう。
まずは、何に苦しんでいるか、子どもと話しながらしっかりと把握していくのがオススメです。
今回は感覚過敏に注目して、我が家で実際に学校にお願いした配慮も含めてご紹介しました。
感覚過敏で学校生活でつらい思いをすると、「またあのつらい思いをしなければいけないのか」と学校生活が不安なものとなっています。
いじめのような特別なエピソードがなくても、毎日学校に行き教室に入るというだけでとても疲労します。
「学校に行くと、とても疲れる」その場にいるだけで精一杯な状態が続くと、徐々に登校しぶりになってきます。
「学校に行けない」「教室に入りたくない」と言われると、お母さんは焦って、なんとか学校に行かせようとするかもしれません。
しかし、過敏に苦しむ状態で、支援なく無理に学校に行かせても、疲弊して、その場で学ぶことは難しいですよね。
無理をさせて教室に戻れない状態にならないように、学校に配慮をお願いして、少しでも子どもが安心して学べる環境を用意してあげてくださいね。

感覚過敏についてはこちらにも情報があります!ぜひチェックしてくださいね。
感覚過敏のある子が「楽しかったはずのお出かけ後に荒れてしまう」問題は解決できます!▼
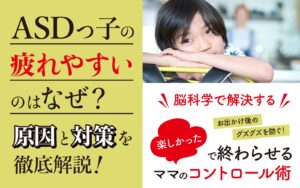
執筆者:森富ゆか
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)





