マイルールが手放せず困っている発達障害(ASDタイプ)のお子さんはいませんか?実は、周りが気が付かないこだわりでも子ども自身はとらわれて苦しくなっていることがあります。今回は強いこだわり行動を手放すための対応法をお伝えします。
【目次】
1.マイルールのこだわりが強い子どもが心配になっていませんか?
2.なぜ発達障害(ASDタイプ)の子はこだわりが強くなるの?
3.強いこだわりを困りごとにしないためにお家でできる簡単な対応
◆周りの大人の失敗やいいかげんな様子を身近に感じる経験
◆子どもにちょっとしたルール違反を経験させる
4.自分で代替案を考えられるようになってきました!
1.マイルールのこだわりが強い子どもが心配になっていませんか?
○○しなきゃいけない、やらなきゃ気が済まない!
発達障害、特に自閉スペクトラム症(ASD)傾向の子どもの多くは、子どもなりの変えられない、強いこだわりをもっていることがあります。
・帰り道はいつも同じでないと落ち着かない
・好きな服しか着たがらない
・モノの置き場所にこだわる
・好きな服しか着たがらない
・モノの置き場所にこだわる
など、年齢や特性によってこだわり行動の現れ方は様々です。
ただ、こだわりがあるにもかかわらず、周りの大人からは見えにくい、分かりにくいこだわりを持っている子どももいます。
大人からすると、どっちだっていいと思うようなことにこだわって、1人嫌な気分になっていたり、イライラしていることもあるのです。

わが家の娘もASD傾向がありますが、小さいころから一般的によくある勝ち負けに執着したり、思うようにいかなくて癇癪を起すこだわり行動はそれほど目立ちませんでした。
気に入らないことがあっても怒って暴れたり、八つ当たりするというわけではなく、行動が止まる、動かない、すねる…といった様子が主でした。
そのため、私も子どもってみんなこんな感じかなと思って、娘が強いこだわりにとらわれていることに気が付いていなかったのです。
しかし、娘が小学生になってから、実は独自のマイルールにとらわれ、強いこだわりに苦しんでいたことに気が付きました。
例えば
・寝る前には家中の戸締りを一通り確認しないと気になって寝られない
・宿題はなんとしてでもやり遂げる
・学校の先生がいうことはいつも正しい
・交通や社会のルールは絶対に守らないといけない
・宿題はなんとしてでもやり遂げる
・学校の先生がいうことはいつも正しい
・交通や社会のルールは絶対に守らないといけない
一見、娘がこだわっていたとしても、周りが困ることは何もありません。
むしろ、きちんとできている、まじめで几帳面だとプラスに受け取られることもあるでしょう。
しかし、
体調不良で宿題ができそうにない
誰かが横断歩道を斜めに横切ったのを見た
学校の先生が冗談でウソを言った
誰かが横断歩道を斜めに横切ったのを見た
学校の先生が冗談でウソを言った
というように、娘がこだわっているマイルールが守られない状況が起きると、人知れずイライラしたり、落ち着かなくて日常生活がうまく進まないこともあるようでした。
2.なぜ発達障害(ASDタイプ)の子はこだわりが強くなるの?
そもそも、なぜ発達障害の子どもは強いこだわりをもっているのでしょうか?
発達障害ASDタイプの子は先の見通しが立たないことが苦手です。
これは、脳の機能の未熟さから周りの情報を集めて判断する力が弱いため、これから何が起こるのかを予測立てることが難しいのが原因です。
そのため、これからどうなるのか、何が起きるのか分からないわけですから、目新しい出来事に特に強い不安を感じてしまいます。
逆に考えてみると毎日繰り返される当たり前のルーティンであれば、必ず次はこうなると分かるわけですから、マイルールに沿っていると安心して行動することができるのです。
つまり、発達障害の子どもは自分が安心できる毎日を守るために、普段の当たり前をくずさないでいることにこだわってしまうのです。

失敗することも発達障害の子にとっては大きな不安の1つです。
そして、○○して失敗したらどうしよう、うまくいかなかったらどうしようと先を心配するあまり、最初から挑戦しない方法をとってしまうのです。
挑戦をしないで毎日をこなしていると安心して行動することはできますが、逆にちょっとした変化にも不安を感じてしまうのです。
不安を収めるために儀式として行うこともあるこだわり。
これをやらなきゃいけない!という思いが強すぎてしまうと、そのことにとらわれてしまい日常生活に支障がでることも心配ですね。
それでは、子どもにとって、ママや周りの家族はどのような対応をすることがよいのでしょうか?
3.強いこだわりを困りごとにしないためにお家でできる簡単な対応
私としては、「そんなことはどうでもいい」という考え方もある、そしてルーティンが崩れても大丈夫ということを知ってもらえたらと思っています。
もちろん、子どもが大事にしているこだわりは周りや本人に困ったことがなければ、個性の一つとして無理にやめさせることもないでしょう。
けれども、強いこだわりから「これだけはやらないと気が済まない!」という脅迫観念になってしまったり、不安を増幅させたりすることだけは避けたいですよね。
そんな気持ちで私が子どもにとった対応法をご紹介します。
◆周りの大人の失敗や適当な様子を見せる
子どもにとって親は影響力が大きいものです。
いつも完璧なできるママでいると、子どもにとっては「正しいこと=やらないといけないこと」だと知らないうちにインプットされてしまいます。
なので、時にはうっかり忘れたり間違ったりする姿をあえてさらけ出して見せるようにしました。
例えば、今日はカレーを作るよ!とママが宣言しておいて、カレールーを買うのをわざと忘れる。
それで「今日は肉じゃがにしちゃいました~」と開き直ってニッコリしてみせたりします。
また、あえていつもと違う道を通っては、「気分転換に散歩ができていいね~」なんて言いつつ、といつもの道を通らない選択をしたりします。
すると、子どもは拍子抜けしてしまうでしょうし、最初はこだわりから居心地の悪さのようなものも感じるでしょう。

けれども
「まあ、いいじゃん。死ぬわけじゃないし」
「小さいことを気にしても時間がもったいないよ、さあ、切り替えよう!」
「小さいことを気にしても時間がもったいないよ、さあ、切り替えよう!」
と子どもにあっけらかんとした様子を見せつけるとどうでしょう?
子どもも、「なんだ、〇〇じゃなくってもいいんだ」「困ることはないんだ」という経験を積むことができるのです。
こうして普段からママが適当な調子を見せることで、子どもの中に「ま、いいか」「仕方ないね」という考え方が当たり前のこととしてインプットされます。
◆子どもにちょっとしたルール違反を経験させる
次に、ルールを守ることが絶対で人にそれを強いたり、ルールが守らない人に嫌悪感を抱かせないために、子どもにちょっとしたルール違反を体験させてみました。例えば、
・点滅信号を走って渡る。
・図書館のような飲食禁止の場所でアメやチョコレートをすすめる。
・遠足のおやつを300円のところを400円分いれておく
など、マイルールに厳しい子どもにしてみれば「え!大丈夫なの?」とびっくりするようなことです。
「いつも頑張ってるんだから、今日は特別」 「例外という言葉もあるんだよ」 と、言葉を添えて、ママがちょっとしたルール違反させてみるのです。
すると、ルールを破っても特別なことは起こらない、何も困らなかったという経験をすることができます。
4.自分で代替案を考えられるようになってきました!
わが家では「ま、いいか」そして「失敗しても死ぬわけじゃあるまいし」をよく使うようになりました。
そのせいか、子どももうっかり宿題用のノートを忘れて帰ってもイライラすることなく、「ま、いいか。しょうがないね」と言えることが増えてきました。
さらに、忘れた宿題の代わりに他の課題を自分で提出するという代替案も考えられるようになってきたのです。
もちろん、まだまだマイルールのこだわりはあるようですが、「時には柔軟に」という方法があることを経験できたことは、子どもにとってもこだわりを手放すきっかけになっているようです。

マイルールにこだわることは、そのすべて悪いわけではありません。
きちんと決まりを守れる。
決まったことは最後まで遂行できる。
決まったことは最後まで遂行できる。
という、真面目で約束を大切にする姿勢は、成長しても大切な素質ですから、マイルールにこだわる子どもの強みでもあります。
子どもは周りの環境に影響を受けて育っていきます。
ルールを守ることはもちろん大切ですが、周りの大人がそのルールをきっちり守ることに必死になってしまうと、子どもはその影響を受けてルールは絶対になってしまう可能性もあります。
こだわりのある子にはあえて、「ま、いいか」という選択もできるということを普段の生活で伝え、気持ちを楽にしてもらえたらいいですね。
▼▼マイルールに振り回されず笑顔で対応できる方法が知りたい方はこちら▼▼
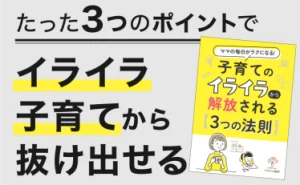
発達凸凹の子の困り事を長引かせないちょっとしたコツ、お伝えしています!
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
3つの質問で
今のあなたにぴったりな情報を
お届けします!
↓↓
執筆者:井上喜美子
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)





