お子さんが不登校になると、どのくらいの期間続くのかと不安になりますよね。ついつい平均を調べたくなりますが、不登校の期間は原因や特性により様々です。我が子が不登校のどの段階にいるかをよく観察することが、対応を考えるカギになりますよ。
【目次】
1.小中学生の不登校はどのくらい続くの?
2.不登校期間の平均に意味はないけど、不登校回復には段階がある
3.お子さんの段階を知る上で大切なこととは?
◆子どもとのコミュニケーションをしっかりとる
◆他の子どもと比べない
◆焦らない
1.小中学生の不登校はどのくらい続くの?
皆さんは、不登校の小中学生が全国に何人ぐらいいるか知っていますか?令和3年(2021年)度の文部科学省の調査によれば、不登校の小中学生は24万人を超えるようです。

また、この調査では、不登校の小中学生が前年度から継続して不登校であるかどうかも分かります。
小学生は、1年生を除いた2年生から6年生の不登校の子どものうち、41.8%が前年度から継続して不登校であることが分かりました。同様に、中学生は、51.1%が前年度から継続して不登校でした。
つまり、不登校の小学生の4割と中学生の半数が、少なくとも1年間は不登校状態なのです。
2.不登校期間の平均に意味はないけど、不登校回復には段階がある
現在中学生の息子が不登校になってから、1年半が過ぎました。
息子が小学6年生の秋に不登校になったとき、私は中学生になったら学校に戻れるのではないかという希望を持っていました。
本人も、その時は中学には行きたいと思っていたようでした。しかし、入学式に出席したあと、中学校がコロナのために突然休校になってしまいました。
その後、休校が明けた時には、不登校になった当初と同じように、再び「お腹が痛くて行けない」と言い出し、不登校が続いてしまったのでした。
先ほどの文科省の調査では、1年間は不登校の小中学生が半数近くいることが分かりましたが、ネットには、不登校を克服するまでの期間は一般的に3ヶ月〜1年程度と書かれているものもあり、不登校が続いた時には正直落ち込みました。
私は、再び不登校になった息子がどうなっていくのか不安になり、本やネットを調べたり、スクールカウンセラーの方のお話しを聞いたりして、不登校には段階があることを知りました。
段階をどのように区切るかによって、4段階から7段階に分かれますが、回復していく順番はだいたい同じです。
・行きしぶり期
腹痛や頭痛を訴え、行きしぶりがある時期
・葛藤期
不登校が始まり、感情的になって悩み葛藤する時期
・安定期
ゲームやネットにハマり、昼夜逆転することもある時期
・ムズムズ期
ヒマだと言うようになったり、外に目を向けるようになる時期
・リハビリ期
フリースクール、塾などに通い始めたり、少しずつ学校に通い始めたりする時期
・活動期
安定して学校に行ったり、自分の居場所を見つけて生き生きと過ごせるようになる時期

それぞれの期間の長さは子どもによって違いますし、息子のように、時には逆戻りするときもあります。回復するまでの期間の平均を調べて人と比べても、落ち込むだけで意味はありませんでした。
でも、子どもがどの段階にいるかを知ることで、この先どのような状態になっていくか見通しが立ち、私の気持ちも楽になりました。
3.お子さんの段階を知る上で大切なこととは?
不登校の子どもがいるお母さん、我が子が先ほど説明した段階のうち、どの段階にいるのか分かりますか?
これらの段階は、今日からこの段階に入ったとはっきり区別できるわけではありませんが、「うちの子はこの段階にいるのかな?」と判断することはできると思います。
すると、先の見通しが立つことで気持ちが前向きになったり、お子さんへの対応を考えるヒントになったりします。
では、お子さんの段階を見きわめる上で大切なことをお伝えしますね。
◆子どもとのコミュニケーションをしっかりとる
お子さんとのコミュニケーションがなければ、お子さんの状態を知ることはできません。
今、あまり会話ができていない場合は、まず、お子さんのやっていることに興味を持って話しかけてみたり、できていることに目を向けて、肯定的な声かけから始めてみることをおすすめします。
そうすれば、少しずつお子さんとのコミュニケーションの量が増えていき、お子さんの状態がわかってきます。

◆他の子どもと比べない
不登校の子どもも様々です。不登校の期間が長い子、短い子、昼夜逆転している子、毎日勉強している子、自分の好きなことを見つけて頑張っている子、ゲームをしたりYouTubeをみている子など。
それぞれの段階の期間も子どもによって違います。早く回復しているように見える子どもと自分の子どもを比べて落ち込んでしまうこともあるかもしれません。
自分の子どもの方が不登校の期間が長いのに、全く勉強していなかったり、ゲームやYouTubeばかりだと、ついつい子どもにガミガミ言いたくなってしまうかもしれません。
でも、それは意味のないことですし、気をつけないと子どもの回復を遅らせてしまうこともありますので注意が必要です。子どもの段階は、それまでのお子さんの状態と比べて判断するようにしましょう。
◆焦らない
親は「早く学校に戻ってほしい」「早く居場所を見つけてほしい」と思って、子どもに期待してしまいますよね。
特に、ムズムズ期やリハビリ期になって、子どもが元気になったように見えると、ついつい余計なプレッシャーを与えてしまいがちになります。
まだ十分に回復していなときに、親の期待にこたえようとして学校に戻ったとしても、また不登校になってしまう可能性もあります。お子さんの段階に迷ったときは、まだ前の段階にいると考えたほうが安全です。
いかがでしたでしょうか?子どもの不登校が続くと不安になりますが、私と同じように、不登校の段階を知ることでお母さんの気持ちも楽になるのではないでしょうか。
これらの段階が全てのお子さんにピタッと当てはまるとは限りませんが、参考になったら嬉しいです。
▼YouTubeやゲームの時間が増えがちでイライラするママは、こちらの対応もぜひ試してみてくださいね▼
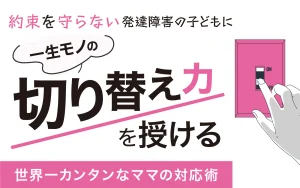
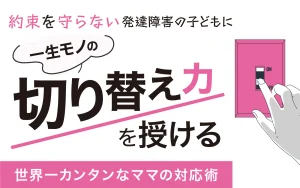
不登校の子どもへの対応のヒントも多数あります
執筆者:佐藤とも子
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)





