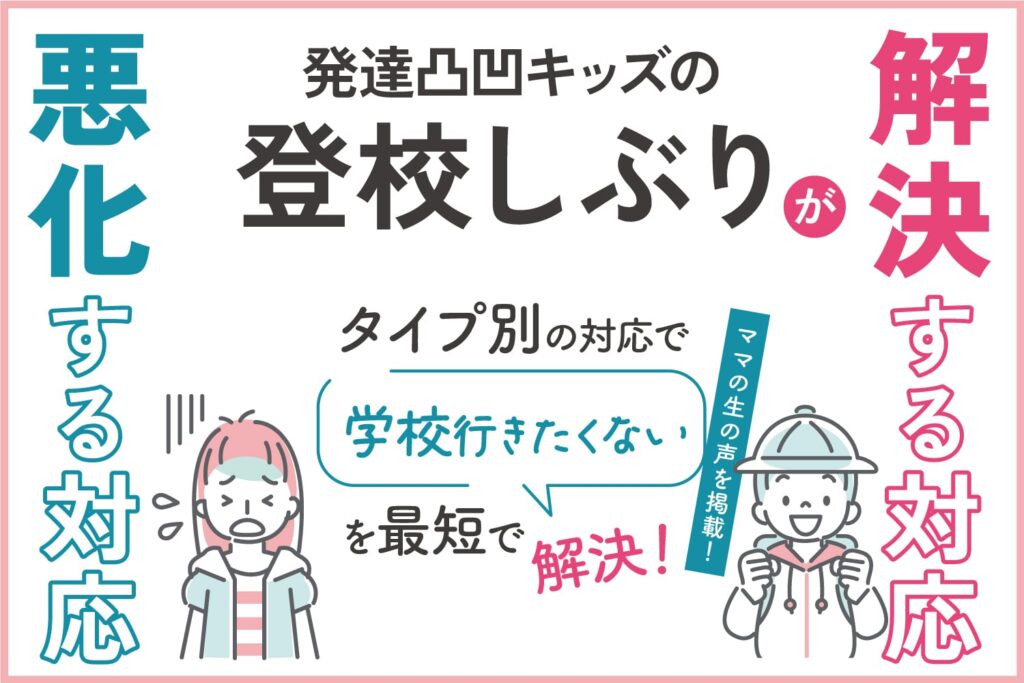| 「何度言っても寝ない」「どうしたら寝てくれるの」寝ない発達障害の子どもに苦労されているママも多いはず。ママも睡眠不足でイライラしてしまいますよね。そんなお子さんに快適に眠ってもらえる睡眠不足解消テクニックをご紹介します! |
【目次】
1.発達障害の子ども、寝ないことに困っていませんか?
2.夜中に泣き叫んで暴れるのはなぜ?
3.気付いたら夜中…親子で睡眠不足な毎日
4. 発達障害・ADHDの寝ない子どもにやりがちなNG行動
5.ぐっすり眠れるとっておきのテクニック!
1.発達障害の子ども、寝ないことに困っていませんか?
発達障害のお子さんの半数が何かしらの睡眠障害を発症しているといわれています。
寝つきが悪い
夜中に起きる
一度起きると眠れない
など、症状はさまざまです。

寝ないには、発達障害の特性でもある「感情のコントロールの苦手さ」や「切り替えの苦手さ」が関係しています。
お昼寝したくない
(遊びから切り上げることができず寝たくない。寝るのに時間がかかる)
↓
眠くて夕方ぐずる
↓
夕方に疲れて寝てしまう
もしくは、お昼寝が長すぎて体力が余っている
↓
夜なかなか寝ない、眠っても無意識に泣き叫ぶ、泣いて起きてしまう
↓
疲れが取れず朝から不機嫌
どんどん悪循環になっていきます。
2.夜中に泣き叫んで暴れるのはなぜ?
我が家には今年5歳になる発達障害・ADHDグレーゾーンタイプの息子がいます。
息子も1歳頃から睡眠障害の症状が出始めました。
最初は、遊んでいる途中やごはん中にうとうとしたり、夜、眠るのが遅かったりすることが気になり始めました。
そして、2歳になると、「夜驚症」の症状が出てくるようになったのです。
「夜驚症」は、夜、無意識にまるでパニックを起こしたかのように泣き叫び暴れることです。
病気ではなく、その日の興奮状態や疲労具合によって特に幼児期に現れる症状で、年齢とともに治まってくると言われています。
息子の場合は、ものすごい量の汗をかき、「やだー!!」と叫びながらのたうち回っていていました。
抱きかかえるとかえって危険なため、周りに危険なものがないかだけを確認し様子を見ていることしかできませんでした。

ただ、年齢が上がるに従い落ち着くということを知ってからは、できる限りお昼寝をさせたり、夜は落ち着く環境を心掛けていました。
けれど、感情のコントロールが下手な発達障害・ADHDの子どもの睡眠不足はそんなことでは解消しなかったのです…
3.気付いたら夜中…親子で睡眠不足な毎日
3歳になり、体力のついた息子。週末はお昼寝をすることがほとんどなくなり、早寝早起きという規則正しい生活になったことで夜驚症の症状は減っていきました。
しかし、問題は平日!
平日は保育園に通っていたので、2~3時間という長時間きちんとお昼寝をしていました。
つまり、体力を温存して帰ってくるんです…!
当時の私はフルタイム勤務をしていて、お迎えは19時、帰宅して急いで夕食とお風呂を済ませても落ち着くのは21時前でした。
やっとお迎えに来た私と一緒に遊びたいのに、家事に追われて遊んでくれない。
落ち着いたと思ったら「寝る時間だよ!」と言われる。
今思えばこの状況は息子にしてみたら不満足な状態だったと思います。

体力も遊びたい気持ちもまだ十分にあったら、我慢できないですよね。
いくら照明を落としたり、絵本を読んで落ち着かせようとしても効果はありませんでした。
私は寝かせようと必死!
息子は遊び足らなくてイライラ!
電気が暗いまま、「寝ようよ」「いやだよ、遊ぶ」を繰り返し、気付いたら24時近くに…
さすがに私もイライラしてきて「もういい加減に寝てよ!」と怒鳴り、息子は泣きながら眠りにつくことがしょっちゅうでした。
4.発達障害の寝ない子どもにやりがちなNG行動
怒鳴ると一時的に静かになります。
私も当初はほかに方法が見つからず、その場で静かになっていればいいと思っていました。
正直、仕事に家事にスムーズに動いてくれない子どもに…私も極限状態だったのです。
とにかくなんでもいいから寝て…!
子どもの気持ちを置き去りにして、イライラしながら押さえつけるように寝かせていました。

実は、これこそがNG行動なんです。
子どもは怒られたというネガティブな記憶が残った状態、つまりストレスを抱えたまま寝ることになってしまいます。
それと同様に𠮟りつけて寝かす行為は、ただでさえ睡眠障害で寝つきの悪い子に追い打ちをかけるように脳に刺激(負荷)をかけることになってしまうんです。
そうすると夜泣きをしたり、朝もぐずぐずしてご機嫌斜めだったり…結局はお母さんのストレスも疲れも溜まり、負のループに陥ってしまいます。
では、どうしたらリラックスしてしっかり眠れる状態を確保することができるのでしょうか。
5.ぐっすり眠れるとっておきのテクニック!
添い寝しても、絵本を読み聞かせても、電気を暗くしても、どうしてもダメなときがあります。
そんな時は“一度寝るのをあきらめる”ことをしてみてください。
え?寝かさなきゃいけないのにどうして?と思われる方もいらっしゃると思います。
ただご自身が子どものころ、眠れなかった時どうしていましたか?
きっと「早く寝なさい!」と言われながらも暗い部屋でこっそり何かをしていた…なんて経験をお持ちではないでしょうか。
子どもにとって「寝なさい」と言われても、寝られないものは寝られないんです。
むしろ怒られた、否定されたという負の記憶が残ってしまい、夜泣きをしたり、朝もすっきり起きられなかったりしてしまいます。
ですから、お勧めしたいのは
①「眠れないんだね?じゃあ後15分遊んで、その後寝ようか」と眠れない気持ちを肯定してあげること。
②短時間でいいので時間をお約束したのちに思いっきり遊んであげること。
③もう一度入眠儀式(絵本やハグなど短時間なもの)を行うこと。
この3つです。
こうすることで、気持ちに寄り添ってもらえたという満足感が生まれ、結果すーっと眠りに入ることができます。

ただし、この時間にテレビや携帯等刺激の強いものは逆効果なのでやめましょう。本人が落ち着いて好きなものを選択してあげると良いと思います。
我が家はこの方法でリラックスして眠れるようになり朝も元気に起きてきてくれるようになりました。
どうしても寝かしつけにお困りでしたら一度試してみてくださいね!
▼無料電子書籍▼
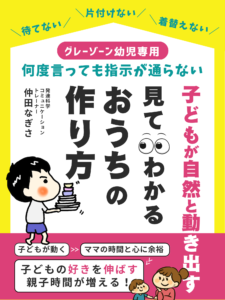
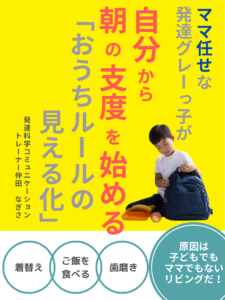
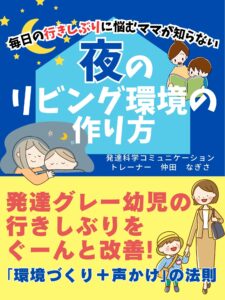
▼毎日の行き渋りに悩むママさんはこちら
▼1アクションできるお家の環境づくり!つい手が出てしまう発達凸凹幼児の対応にお悩みのママさんはこちら▼


発達障害グレーゾーンのお子さんがリラックスできる過ごし方を提案しています
執筆者:仲田なぎさ
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)