ゴミをゴミ箱に捨てられない子どもにイライラしていませんか?その原因は、目の前のことに惹かれる好奇心旺盛な特性かもしれません。この記事では、子どもの好奇心をくすぐりながら、ゴミ捨てを習慣化してママもラクになる対応策をご紹介します!
【目次】
1.ゴミをゴミ箱に捨てられないのは病気?原因とママのモヤモヤの正体
2.ゴミを分別しないとどうなる?好奇心旺盛な子の『気づけない理由』
3.ママがラクになる!やりきる力を育てる“ゴミ捨て習慣”3つのコツ
1.ゴミをゴミ箱に捨てられないのは病気?原因とママのモヤモヤの正体
お菓子を食べた後のゴミ、口を拭いて丸めたティッシュ、工作後の紙切れを置きっぱなし。
「どうしてゴミ箱に捨てられないの?」
「これって病気なの?」
そんなふうにモヤモヤしていませんか。
ゴミを捨てるくらい、できて当たり前だと思ってしまいますよね。
ゴミをゴミ箱に捨てられない原因は、目の前にあるゲームや漫画に注意が向く好奇心旺盛なことから起こります。
それを理解できず頭ごなしに叱ったりしてしまいがちですが、まずはゴミを捨てやすい環境を整える工夫が大切です。
まだ今の段階は、「すぐゴミ箱に捨てられなくてもいい」時期です。
我が家の息子も私が 仕事を終えて帰宅すると、部屋の各所に点々と置いてあるお菓子の袋や折り紙の切れ端。
食べ終えた袋や紙切れが置きっぱなしなので、 この場所でおやつ食べていたんだな、ここで工作してたんだな、というのがわかるのです。
ゴミが散らかっていて気にならないの? と聞いたことがありますが、「ああ、うん。あんまり気にならないかも?」 と驚きの回答。

気にならないとはいえ、 自分で出したゴミくらい自分で片づけて欲しいですよね?
なぜゴミが気にならないのか?捨てられないのか? 次の項目で説明しますね。
行き渋りや不安を、一人で抱えずに整理できる小冊子はこちら
▼▼▼
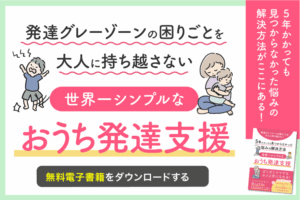
▼小冊子はこちらから読めます
2.ゴミを分別しないとどうなる?好奇心旺盛な子の『気づけない理由』
「何度言ってもゴミを捨てない…」
「ワザと?病気?」
そう感じてしまうこと、ありますよね。
しかし、ゴミを捨てられないのはやる気やしつけの問題ではありません。
好奇心旺盛な子や注意欠陥多動性障害(ADHD)の特性がある子は、
・目の前の興味あることに注意が強く向きやすい
・関心のないことは後回しになりやすい
・「このあとどうなるか」という先の見通しを立てにくい
という特徴があります。
そのため、ゴミが目に入らなかったり、ゴミ箱があっても意識にのぼらなかったり、「あとで捨てよう」がそのまま抜け落ちてしまうことが起こるのです。
これは、ワザとしているわけでも怠けているわけでもありません。

私の息子もADHDで、関心の強い方へ注意が向きやすく、忘れものが多いタイプです。
ゲームをしながらおやつを食べていると、注意はゲームに向いたままになり、食べ終わった袋をその場に置いたままになってしまいます。
「ゴミが出たらゴミ箱に捨ててね」と声をかけても、耳からの情報を処理することが苦手なため、言われたことをすぐに行動に移したり、覚えておいたりすることが難しいようでした。
また、「ゴミを分別しないとどうなるのか」という先のことも、息子にとってはピンと来ていなかったように思います。
中には「ゴミ箱を認識できない」「ゴミが気にならない」というADHD当事者の声もあります。
だからといって、いつまでもママが後始末をし続けるのは、正直モヤモヤしますよね。
だから必要なのは、叱ることではなく、子どもが“気づきやすくなる工夫”です。
次では、今日からできる小さな工夫をお伝えしますね。
判断を急がず、子どもの気持ちを受け取る関わり方がわかる小冊子はこちら
▼▼▼

▼小冊子はこちらから読めます
3.ママがラクになる!やりきる力を育てる“ゴミ捨て習慣”3つのコツ
何度言っても、ゴミをゴミ箱に捨ててくれない。
だけど、ゴミ捨てがうまくいかない原因は子どもではありません。
親の関わり方や環境を少し変えるだけで、子どもがゴミを捨てやすくなります。
そしてその積み重ねが、やりきる力につながっていきます。
他の家族やともに過ごす人たちに負担をかけずママもラクになる!
そんな「やりきる力」を育てるゴミ捨て習慣のコツを2つご紹介します。

A portrait of a happy elementary school schoolboy in hallways.
◆①ゴミ箱を“使う場所の近く”に置く
子どもがゴミを捨てられないのは、「やらない」のではなく、「気づけない」ことがほとんどです。
だから最初にやることは、捨てやすい環境を先に整えること。
・子どもがよく座る場所の近く
・目に入りやすい位置
・チラシで作ったBOXをお菓子入れ兼簡易ゴミ箱にする
これだけで、ゴミ捨てのハードルはぐっと下がります。
チラシで作った入れ物をゴミ箱として利用すれば、ゴミをわざわざ捨てに行く必要がなくなります。
また、チラシで作った簡易ゴミ箱は、消しゴムのカスや工作の紙クズも、気づいたときにサッと捨てられます。
このように今は、「ゴミ箱に捨てられる状態」を作るだけで十分です。
◆②ゴミを捨てる理由を説明する
ゴミを捨てられる経験が増えてきたら、
・虫が来るから
・においが出るから
など、短く理由を伝えるくらいでOKです。
できたときは、
・「捨ててくれてありがとう」
・「きれいになって嬉しいな」
と、行動そのものを認める声かけを意識してみてください。
ゴミ捨ては、一度で身につくものではありません。
今は親が工夫する。
それが、子どもが自分で動き、やりきる力を育てる近道になります。
息子自身も家の中ではゴミ箱に捨て忘れることもありますが、声かけひとつですぐに捨てるようになったので、実施した対応策に効果があるのだと実感しているところです。
ゴミ箱にゴミを捨てないお子さんでお困りのママ、ぜひ試してみてくださいね。
伝えたいことが伝わらない!そんなママの声がスッと届く方法をまとめた動画はこちら
執筆者:村上恵子
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
発達障害グレーゾーンの子どもに不安があればこちらをチェックしてくださいね!
執筆者:村上 惠子
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)



