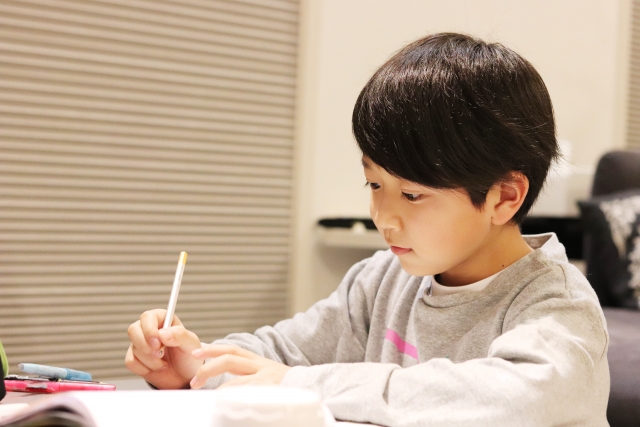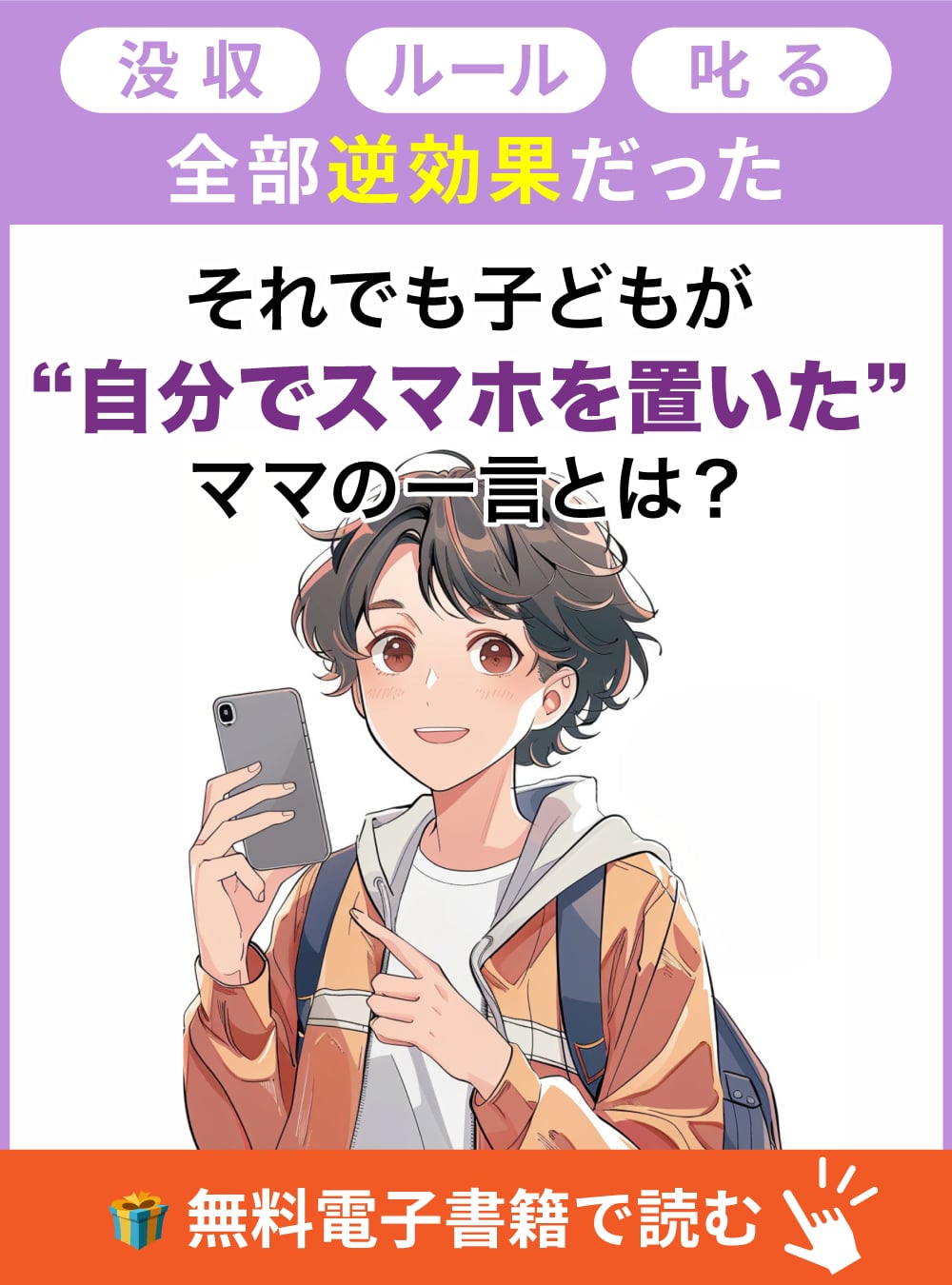早産児の注意力の弱さは『やる気の問題』ではなく、脳の特性。注意機能の理解と工夫で、苦手をカバーできます。苦手の克服に疲れた私が、脳の仕組みに合った工夫で楽に過ごせるようになった4つの関わりを紹介します。
›
【目次】
1.早産児の長男は、なぜ注意が続かないのか?
2.注意機能って何? 不注意は特性だった!?
3.早産児の苦手は“工夫”でカバー!わが家の実践例
1.早産児の長男は、なぜ注意が続かないのか?
『もっと集中して!』
『最後までやって!』
『ちゃんと周りを見て!』
超マイペースな長男に何度も声をかけ、私も本人も疲れ果てていた時期がありました。
私の長男は2か月早産(31週)で生まれた、現在小学3年生の男の子。
発達障害グレーゾーンで、自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠陥多動性障害(ADHD)の傾向があります。

以前はこんな様子が目立ちました
・サッカーの試合中にチョウチョを追いかけてしまう
・片付けを始めたはずが途中で遊び始めてしまう
・読書に夢中でお風呂に入らない
・ 話題がどんどん変わって、会話がかみ合わない
『こんな調子で集団生活が送れるの?』『学校についていけなくなるのでは?』と、私は不安になり、厳しく叱ったり、あの手この手で“ちゃんとした行動”をとらせようとしていました。
外ではいい子なのに
家では癇癪に悩むママへ
家では癇癪に悩むママへ
指示出しゼロの子育てで
たった3週間で
手が付けられない癇癪が着く!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2. 注意機能って何?不注意は特性だった!
実は一部の早産児(在胎週数32週未満)では、以下のような傾向があることがわかっています。
・正齢12か月時点で「注意を切り替える力」が弱い
・この力が弱い子どもほど、18か月以降の認知や社会性の発達が遅れやすい
このデータは、赤ちゃんが視覚的なターゲットをどれだけ追えるかを調べた実験に基づいています。
つまり、赤ちゃんのときに「対象に注目する」「対象を目で追う」力が弱いと、その後の成長でも「集中する」「切り替える」といった行動が難しくなりやすいのです。
この“注意する力”は、脳の高度な機能のひとつです。
私たちは目・耳・皮膚などから膨大な感覚情報を受け取っていますが、その中から必要な情報を選び、集中しています。
この注意する力(注意機能)には次の4つがあります。
1.注意の持続(集中し続ける)
2.注意の選択(どれに集中するか選ぶ)
3.注意の配分(複数の対象に同時に集中)
4.注意の転換(ひとつのことから別のことに切り替える)
例えば:
・授業中、先生の話を聞き続ける → 持続
・雑音に気を取られず、友達の話に集中する → 選択
・運転しながら会話する → 配分
・作業中に電話が鳴って中断して出る → 転換
長男は集中力が切れやすいのに、いまやっていることをやめられないという“矛盾”を抱えていましたが、これは注意機能のコントロールが未熟だからだとわかったのです。

また、《何かに注目する》力が弱いと、言葉の発達にも影響します。
たとえば、お母さんと同じものを見る「共同注視」が難しく、同じものを見る事によって活発になる会話のキャッチボールが出ずらくなります。
こうした脳の仕組みを知ってから、私は長男の困りごとの原因が「やる気の有無」ではなく「脳の特性」だと理解できるようになりました。
毎日の声かけで“脳のクセ”は変えられる!
子どもが持つ力を発揮できるようになる
4ステップの声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3. 早産児の苦手は“工夫”でカバー!わが家の実践例
早産児や発達障害のある子どもの特性は、生まれ持った脳の仕組みによるものであり、決して育て方や本人の努力のせいではありません。
そして、苦手を克服しようと頑張りすぎると、親子ともに疲弊してしまいます。苦手は無理に直すのではなく、工夫して“付き合う力”を育てることが大切です。
我が家の長男は、4つの注意機能すべてに弱さがありましたが、それぞれに合った工夫で対応しています。
①注意の持続が弱い → 短時間&変化をつける
例)計算プリント3枚→国語音読1回→休憩→漢字練習、という流れでメリハリを。
②注意の選択が苦手 → 指示を分解して明確に
例)「片付けしてね」ではなく「レゴを黄色い箱に入れてね」と具体化。
③注意の配分が苦手 → 遊びでトレーニング
例)サッカーやボードゲームなど、楽しさの中で自然に周囲に注意を払う力が育つ。
④注意の転換が難しい → 自分のタイミングで切り替えさせる
例)「いつやめるか決めてね」と子どもに選ばせ、切り替えられたら褒める!!
こうした関わりを通じて、私はできないことを叱るのではなく、できるようになる工夫を一緒に考えるスタンスに変わりました。
子どもの苦手に合わせた工夫を積み重ねたことで、我が家の長男の苦手意識が徐々に緩くなりました。
克服にこだわるより、親子で笑顔になれる関わりを見つけていきましょう。

いかがでしたか?
・ 早産児の注意機能には発達の偏りが出やすい
・「できない」は「努力してない」ではなく「脳の特性」による
・工夫次第で子どもの行動は変わる
苦手は、付き合い方で変わります。
そして、親の見方が変わると、子どもの毎日も変わります。
パステルキッズの学校生活をより良くするためのヒントが多数あります!
執筆者:大島さくの
(発達科学コミュニケーション トレーナー)
(発達科学コミュニケーション トレーナー)