夏休み、宿題もせずゲーム三昧の中学生にイライラして「早く宿題しなさい!」と叱っていませんか?中学生が宿題をしないのは理由があります。叱るより、得意を活かして自分からやる気になる関わり方が効果的!この記事では親の対応3つをご紹介します。
【目次】
1.夏休み宿題をしない中学生!ガミガミ言いすぎて親の方が限界
2.なぜ勉強しない?中学生のやる気が出ない本当の理由
3.ママのイライラを手放す!子どものやる気を引き出す親の関わり方3選
1.夏休み宿題をしない中学生!ガミガミ言いすぎて親の方が限界
夏休みに入り
「もう毎日ガミガミ言うのに疲れた…夏休みの宿題、いつやるの?」
そんな思いでイライラが限界に来ていませんか?
しかし実は思春期の中学生に叱るのは逆効果。
親の関わり方を変えることで、ママはイライラを手放し、子どものやる気を引き出すことができます。
私には2人の息子がいます。
注意欠陥・多動性障害(ADHD)傾向の長男が中学1年生の頃、夏休みになると毎日遅くまでゲームをし、朝も起きられないことが多い状況でした。
私が「宿題早めにした方がいいんじゃない?」と声をかけても「まだまだ時間あるし大丈夫」と一向に宿題にとりかかる気配がありませんでした。
夏休みも半分以上過ぎたころに、「宿題多すぎやねん!」とキレて、結局親子バトルを繰り広げながら最終日までかかって何とか宿題をやり切るという感じでした。
早くから計画的に宿題に取り組まない自分のことは棚に上げて、「お前の教え方が悪い」「宿題の量を考えない学校が悪い」とつい人のせいにしてしまう息子。
そんな息子に「それって私のせい?」とモヤモヤした気持ちが積み重なり私自身疲れ果てていました。
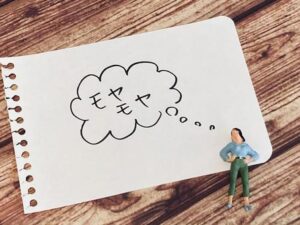
しかし宿題にとりかかれない理由は、思春期の心の変化やADHDの特性が関係していることに気づきました。
親はただ夏休みの宿題をしない中学生の息子に叱るのではなく、その背景を理解し子どもを認める関わり方に変えることがスッとやる気を引き出すコツだと知ることができました。
この記事では、中学生宿題しない子が宿題に取り組めない理由と子どものやる気を引き出す親の関わり方をご紹介します。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.なぜ勉強しない?中学生のやる気が出ない本当の理由
夏休みの宿題に手をつけない中学生の子に、つい「宿題しなさい!」と叱りたくなりますよね。
しかし実は、宿題をしないのにはちゃんとした理由があります。
その理由は、大きく3つあります。
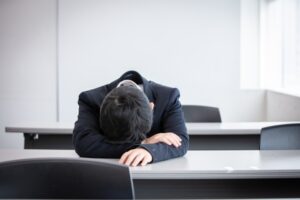
◆①思春期特有の反発心
中学生になると、自分の考えや意見を持つようになります。
これは成長の証でもありますが、親から何か言われると「言われたくない」と反発しがちです。
特に「勉強しなさい!」という言葉は、逆効果になることもあります。
◆②勉強に対する興味関心の薄さ
「何のために勉強するのかわからない」という疑問や、勉強への苦手意識から、やる気が湧かなくなります。
また、夏休みは長いから「まぁいっか」という段取り力の無さも重なって「全然終わってない!」「どうやればいいのか分からない」と手が止まってしまうこともあります。
◆③衝動性の強さ
目の前にあるゲームやYouTubeなどの誘惑に流されやすいのも中学生の特徴。
特にADHD傾向がある子は、興味のあることへの集中力が強く、勉強は後回しになってしまいがちです。
こうした背景を理解せずに「しつけ」として叱り続けると、思春期中学生の子の攻撃性を強め反発心を高めてしまいます。
その結果、さらにやる気を失わせてしまうことにもなりかねません。
「しつけ=正すこと」と考えるより、今の子どもの気持ちや成長段階に合わせて関わり方を見直すことが大切です。
勉強しない子の末路は、「いい高校へ進学できない」ことだけが問題ではありません。
一番の問題は、「自分にはできない」「どうせムリ」と感じる状態が続くことで、自己肯定感が育たず、前向きに取り組む力が育ちにくくなることです。
その結果、挑戦や努力を避けてしまい、大人になってからも「どうせ無理」と新しい一歩を踏み出せなくなることも…。
そうならないためにも、今できる親の関わりがとても大切です。
次では、子どものやる気を出す“親の声かけ・対応”を具体的にご紹介します。
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.ママの「スルーする力」で、子どもの怒りグセをなくそう!
宿題しなさい!の声かけにうんざり・・・
そんな毎日のバトルを減らし、子どもが自分から宿題に向かうための、ママにできる3つの関わり方をご紹介します。

◆①叱る前に「本当に叱ること?」と自分に問いかける
思春期の子どもに毎日ガミガミ言っていると、お互いにストレスが溜まるばかり…。
本当に叱るべきこと(人に迷惑をかける、ルール違反)だけにしぼることで、子どもに「信頼されてる」「任されてる」という気持ちが芽生えます。
◆②”好き”を入口にして「とりかかりやすい工夫」をする
中学生の「宿題しない」子にやる気を出させるには、最初の一歩が肝心。
「さぁ勉強するぞ!」と机に向かうのではなく、ハードルをぐっと下げる工夫が効果的です。
たとえば、好きな音楽を流しながら取り組んだり、ゴロゴロしながらYouTubeで解説動画を見るなど、子どもの“好き”を入り口にすると自然と宿題に向かいやすくなります。
ちなみに我が家の息子は、「好きな曲を聴いてると落ち着いて宿題できる」と言って、音楽を流しながら取り組むようになりました。
この“とりかかりやすさ”が、自分から動ける大事な一歩につながっていきます。
◆③好きなことを繋げて「できた」を体験させる
子どもが宿題に向かうために一番大切なのは、「できた!」「わかった!」という小さな達成感を積み重ねることです。
そのための近道は、子どもの“好き”を勉強に繋げる工夫です。
たとえば、社会が苦手だった息子も、YouTubeで流れてきた各政党の動画をきっかけに、政治や経済に関心を持つようになりました。
「日本ってこんな問題あるんや」「国内総生産GDPって何?」と自分から調べ始め、自然と社会という教科にも興味を広げていきました。
子どもにとって「興味がある=自分ごと」になるので、学びがグッと近くなります。
親はその芽を見逃さず、「それってどういう意味?」と声をかけることで人に教えることも身につくと同時に自然と勉強への橋渡しができます。
このように親が子どもの心の成長と特性を理解した対応を知ることで、思春期の親子関係を悪化させることを防げます。
また親が子どもを尊重し子どもの好きを生かした声かけや関わりに変えることで、中学生の夏休みの宿題をしない子の”前向きに取り組む力”が育ちます。
宿題ができたかどうかより、「自分で決めてやれた」という経験が、子どものやる気の芽を育てます。
親子で笑顔の夏休みを過ごすために、まずは関わり方を一つだけ変えてみませんか?
思春期特有のイライラに効くアレの正体。親子の笑顔と取り戻す親の関わり方
子どもの癇癪に困り果てているママ!対応策をご紹介しています!
執筆者:平野 可奈子
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)





