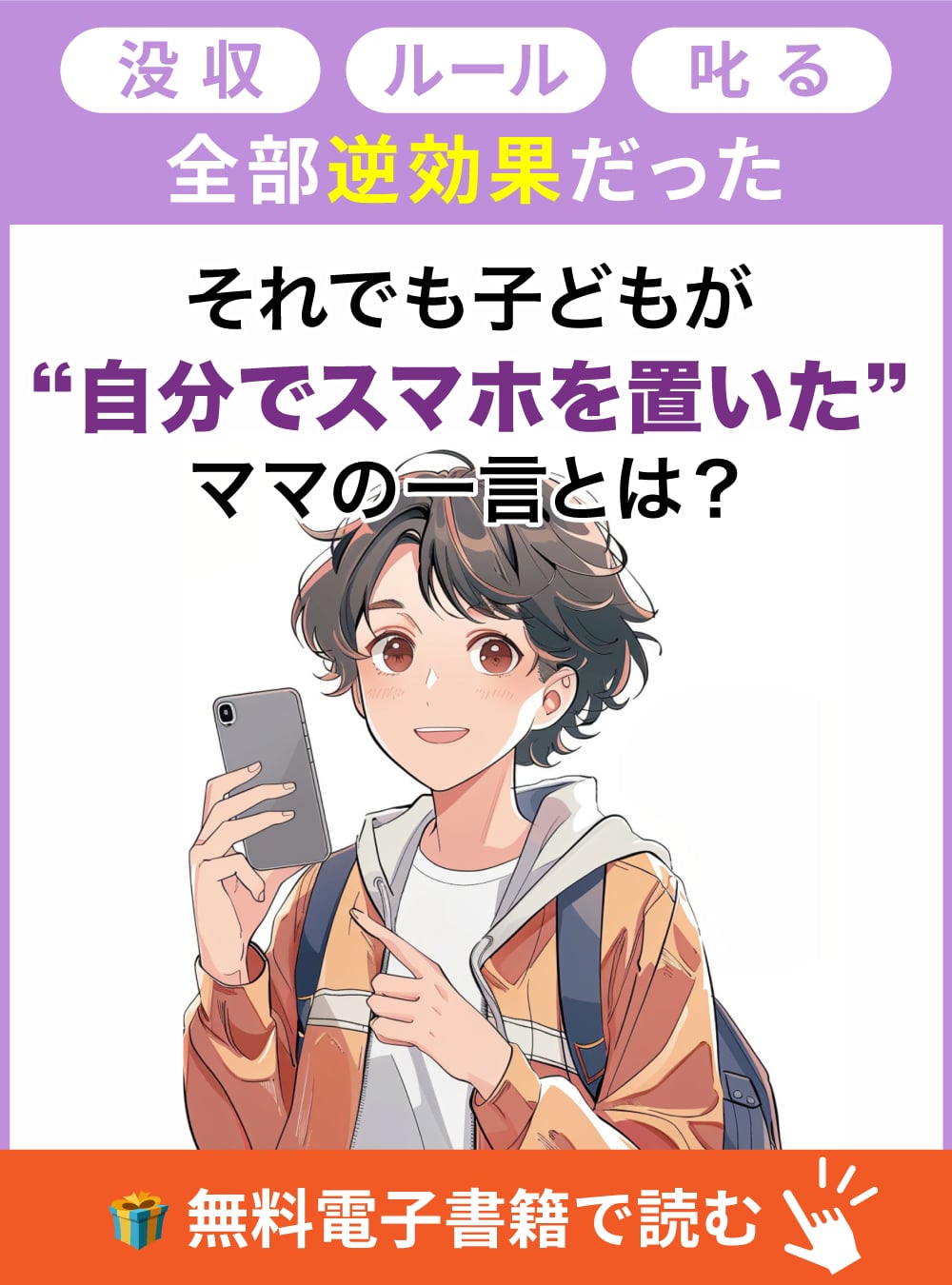どこでも奇声をあげてしまう知的障害のある子ども…。周囲の目が気になってつい叱っていませんか?でも実はそれ、逆効果になることも。本記事では、奇声の原因とすぐに始められる正しい関わり方を、我が家の体験をもとにお伝えします。
【目次】
1.知的障害キッズが外でも家でも奇声を出して辛い日々
2.知的障害キッズの奇声をあげる原因
3.奇声が激減!我が家で効果のあった接し方
1.知的障害キッズが外でも家でも奇声を出して辛い日々
知的障害のある息子が、家で「キー!」や「キャー!」と大きな声で奇声を発して困っていました。
家だけならまだしも、外出先の病院やスーパーでも大きな声で奇声を出すようになり、周りの目が気になって、しんどい思いをしていました。
奇声は間違った対応をしなければ、長引かずに済みます。
我が家の知的障害の息子は、わざとやっているかのように大きい声で奇声をよく出していました。
その度に、「静かにして!」「もうやめて!」「ここではシーだよ!」と言って聞かせて、対応していました。

だけどもやめようとする姿はなく、ニヤニヤしながらわざとやっていて、エスカレートしていく。
そんな姿に本当にイライラしていました。
なんで言うことを聞いてくれないの?
なんでママのことを困らせるの?
この子は一体何がしたいの?と頭を悩ませていたのです。
この記事では、子どものエスカレートする奇声に対して、対応を変えて、落ち着つかせた方法をお伝えしていきます。
外ではいい子なのに
家では癇癪に悩むママへ
家では癇癪に悩むママへ
指示出しゼロの子育てで
たった3週間で
手が付けられない癇癪が着く!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.知的障害キッズの奇声をあげる原因
知的障害の子はなぜ奇声を発するのか、説明していきますね。
息子の行動をよく観察していく中で、我が子の奇声には主に2つのパターンがあることに気づきました。
① 奇声を出して楽しんでいる(感覚の快感・興奮)
単純に、子どもは声を出すこと自体を楽しんでいることがあります。
響く声を聞いて楽しんでいて、探求する遊びの一環という感じでした。

② 退屈している、または注目してほしい(コミュニケーション手段)
我が家の息子は話し始めたのがゆっくりで、3歳でようやく単語を話し始めました。
子どもは、親や周囲の人々の注意を引きたいと思うことがあります。
息子は「こっち見て~」を言葉にすることができず、その度に奇声をあげることで、自分に注意を向けていたのです。
奇声をあげる度に、ママが振り向いてかまってくれる!と誤学習してしまっていたため、奇声がエスカレートしていました。
つまり、ママに見てもらおうとしたり、何かをしてほしいというサインとして奇声を使っていたんですよね。
そのまま反応し続けると、子どもにとってはママの注目が得られるご褒美になってしまうので、どんどん行動が定着していきます。
だからこそ、いますぐ対応を変える必要があるのです。
いますぐできる対応方法を次項でお伝えしていきますね!
毎日の声かけで“脳のクセ”は変えられる!
子どもが持つ力を発揮できるようになる
4ステップの声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.奇声が激減!我が家で効果のあった接し方
どうしたら奇声が減るのか?そんな悩みに、私がたどりついた対応法を紹介します。
大事なのは、「奇声が出ている時」ではなく、「出ていない時」に注目することでした。
◆① 奇声が出ても“気づかないフリ”をする
最初はとても勇気がいりましたが、「うるさい!」「やめて!」と言いたくなる気持ちをぐっとこらえて、スルーすることを徹底しました。
なぜなら、反応すればするほど、「ママが反応してくれる=もっとやろう」となってしまうからです。
そして、静かになったタイミングで「静かにしてくれてありがとう」と伝えるようにしました。
落ち着いた時に注目する。
この繰り返しで、息子の伝え方が徐々に変わっていったんです。
◆② 静かなときに、実況中継で関わる
奇声が出ていない「普通のとき」って、ついスルーしがちですよね。
ですが私は意識して、静かに遊んでいるときほど声をかけるようにしました。
「今○○で遊んでるんだね〜」
「お!電車走ってるね、楽しいね」
病院や外出先では、静かに待っているときこそ
「静かに待てているね」
「今の○○くん、かっこいいよ!」
こんなふうに、実況中継のような声かけを増やしていくと、「静かにしているとママに見てもらえる」と気づくようになっていきました。

◆③ 機嫌のいいときに、理由を伝えておく
奇声を出しているときは聞く耳が開いていないので、お風呂や寝る前の穏やかな時間に、ルールの説明をしました。
「外でキーって声を出すと、びっくりする人もいるんだよ」
「おうちではいいけど、お店ではアリさんの声で言おうね」と、伝えていくことをしました。
最初は何のことか伝わらなくても、繰り返すことで少しずつ分かるようになっていきました。
今では、奇声が出るのは「疲れてるとき」や「ストレスがたまってるとき」だけです。
以前のように振り回されることはなくなり、「サインを出してくれてるんだな」と、穏やかに見守れるようになったんです。
いちばんのポイントは、「静かなときこそ注目すること」
声を荒げるより、静かな瞬間に寄り添う関わりが、子どもの安心と落ち着きを育てていきますよ。
知的障害キッズの行動力と会話力を引き出す対応をお伝えしています。
執筆者:みやび 楓
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)