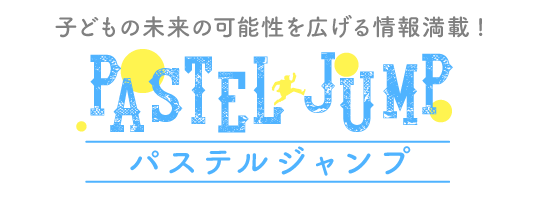1.「新学期はがんばりたい!」と言う不登校の子。不安になる親の気持ち
一般的には新学年・新学期の時期は生活を変えるのに良いタイミングと言われることが多いですよね。しかし、発達凸凹・不登校のお子さんにとってはそうとは言い切れません。
発達凸凹で不登校のお子さんのお母さまより、こんなお悩みをお寄せいただきました。
ーーーーーーーーーー
子どもは「次はがんばる」と言っています。
ですが、「行けなかったらどうしよう」と親が不安になってしまいます。
この時期を、どうサポートしてあげたらいいでしょうか?
(小学校5年生 不登校 ADHD・ASDグレーゾーンのお子さんのお母さまより)
ーーーーーーーーーー

不登校のお子さんが再登校すると言ってきた。こんなときの対応、案外むずかしいんです。
親御さんの不安に感じる気持ちを発達凸凹の子どもは敏感に感じ取ります。
この時期に焦りは禁物!
お母さんが、冷静にお子さんの状態を見極めることができると焦らないでどっしり構えることができますよね。
そのためには一番最初に必ずやってほしいことがあるんです!
今このサイトをお読みのあなたにおススメ
7500人の親子が実践中の声かけが無料!
▼詳しくはこちら▼
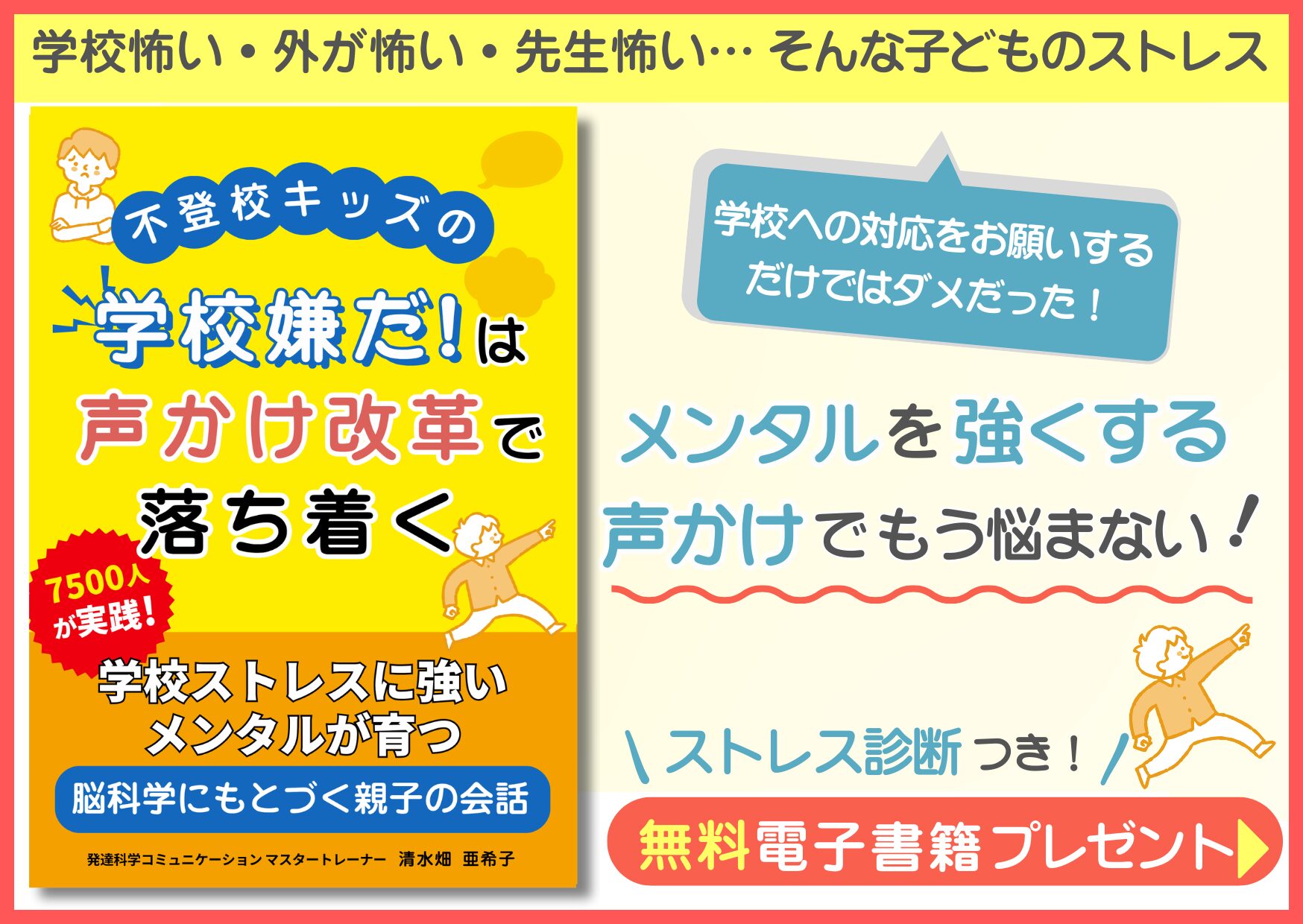
2.不登校のお子さんの状態を知るための5つのチェック項目
最初にやってほしいのはお子さんの「コンディションチェック」です。
実は大切なのはお子さんのコンディションを「見極める目」なんです!
5つのチェック項目でお子さんの状態を観察してみましょう。

✔夜寝る前に不安を訴える、眠れない
✔朝なかなか起きない
✔ため息が多い
✔口数が減っている
✔泣いたり怒ったりする頻度が増えている
皆さんのお子さんは上記5つのチェックをするとどうですか?
5つともチェックが入らなかった!という場合、お子さんの動き出すマインドが整ってきている状態です!
お母さんはおウチでしっかりお子さんを充電させてあげたことに自信を持って大丈夫です!
おウチで元気に過ごせるようになって、「学校頑張りたいな」と思えているのなら、登校にチャレンジしてもいい時期です。
今回は上記の5つともチェックが入らなかった、動き出すマインドが整ってきているお子さんへ、実際に登校を始める際の具体的なサポート方法をお伝えしますね!
"毎日学校に行けなくても大丈夫です!"
毎日の声かけを変えて
子どもの脳を育ててストレスをリセット!
▼今読めば進級進学前に間に合う!▼
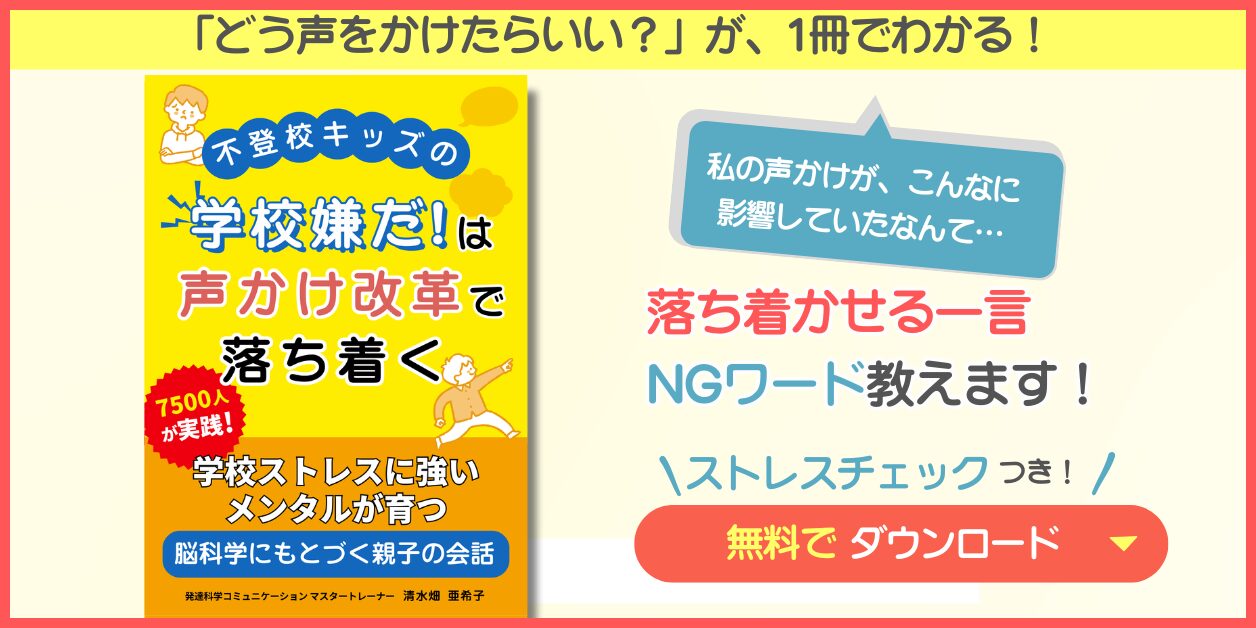
3.再登校へ動き出したお子さんにしてほしいサポート法
不登校だったお子さんが、学校に行くことを決意すると、
「学校に行きたい。けど不安…行けなかったどうしよう」と心配になったり…
登校してみたことでたくさんのストレスを抱えて嫌な気持ちをため込みすぎてしまったり…
再登校したお子さんが不安定な状態になるかもしれません。
そんなときはお子さんのネガティブな気持ちに引っ張られずに、サポートしてあげることが大切です。
◆サポートその1 登校できてもできなくても自信を失わせない準備
「学校に行くことだけ」をゴールにするとお子さんが「やっぱり無理」となったときに自信を失います。
だから、やってほしいのは
「学校に行くこと」「学校を休むこと」に優先順位をつけない
ということです。
『「学校に行ったら◯◯が楽しみだねー」』
『「学校休んだらママと◯◯して過ごそうね。そっちも楽しみだね。」』
どっちを選んでも大丈夫!と感じさせてあげる準備をしておきましょう。
◆サポートその2 ポジティブな感情を育てる
登校することでお子さんはストレスを抱えます。
不安が強まったり感覚が過敏になったりしやすい時期。
だからそのストレスやネガティブな記憶を和らげる「安心」「楽しい」の感情を育てるコミュニケーションがとっても大切です!
・その1:スキンシップ
低学年くらいのお子さんならハグをしたり、頭をなでてあげたり。
高学年以上のお子さんでも、ものを受け渡すときにしっかり目を見て渡す、声をかけるときに肩や背中をポンっとたたいてあげる。
そんなこともスキンシップになりますよ。
・楽しい音楽を聞く、テレビや動画を見て笑う
子どもが好きな音楽を笑顔で一緒に聞いたり、番組を見たり、お母さん一人で聞いて鼻歌を歌いながら笑顔でいる、これもOKです!
・子どもの好きなことを家ではやらせてあげる、喋らせてあげる
お子さんの好きなことを、喋らせてあげて笑顔で聞いてあげましょう。
「うんうん、それで?」
「それってこういうこと?」
「いいねいいね!」
と、相槌をうったり、お子さんが教えてくれたことをわかりやすくまとめて聞き返したり、肯定することばを伝えていきます。
こんな風に、五感を活用してプラスの感情が育ちやすい刺激をいれてあげましょう。
不安が軽減されて前向きな心が整っていきます。
これらのサポートを行ったとしても、スムーズに毎日登校できるようにはならないかもしれません。
親が一喜一憂しないことが大切です。
学校に行けても行けなくても大丈夫!と、お子さんをまるごと肯定して安心基地としての居場所の家庭環境づくりに心がけましょう。
学校に行くか、行かないかよりも、子どもが発達しているかどうかが重要です!
不登校さんの「学校頑張りたい発言」をどうやってサポートするかをお伝えしました。
多くの不登校さんにとって再登校は大きなエネルギーが必要なことです。
エネルギーが満たされて動き出したお子さんには、無理のない範囲で、観察しながら温かくサポートしてあげてくださいね。

執筆者:清水畑亜希子
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
再登校できてもできなくても!おうちでできるサポートがあります!
▼こちらで無料登録できます