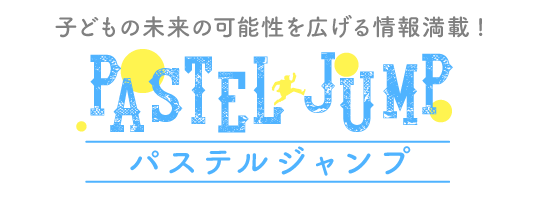1.また始まる毎日の宿題問題にため息ついていませんか
夏休みが終わり、また毎日の宿題バトルが始まる…とため息がでてしまう。
宿題、明日の準備、夕飯、お風呂…スムーズに進まなくてイライラ…
宿題なんてさっさと終わらせればゆっくり遊べるのになんでやれないんだろう。
・ゲームをやる前に宿題しなさい!と言えば不機嫌になるお子さん
・学校や習い事で疲れてぐったり…宿題どころではないお子さん
・「やればいいんでしょ」とばかりに雑に取り組むお子さん
こんなお子さんの様子に頭を抱える親御さんも多いのではないでしょうか。

今回の記事では、宿題をやる気がなかなか出ない、さらには宿題のできの悪さにしびれを切らし、子どものために指摘すると、途端に機嫌が悪くなってさらに宿題が進まない悪循環…
毎日のように宿題バトルを繰り返していた親子が、宿題を楽しく進めることができるようになった方法をお伝えします!
「3学期も学校行けないかも…」
進級進学までに間に合うおウチ対応で
学校ストレスを溜めない子になる!
↓↓↓
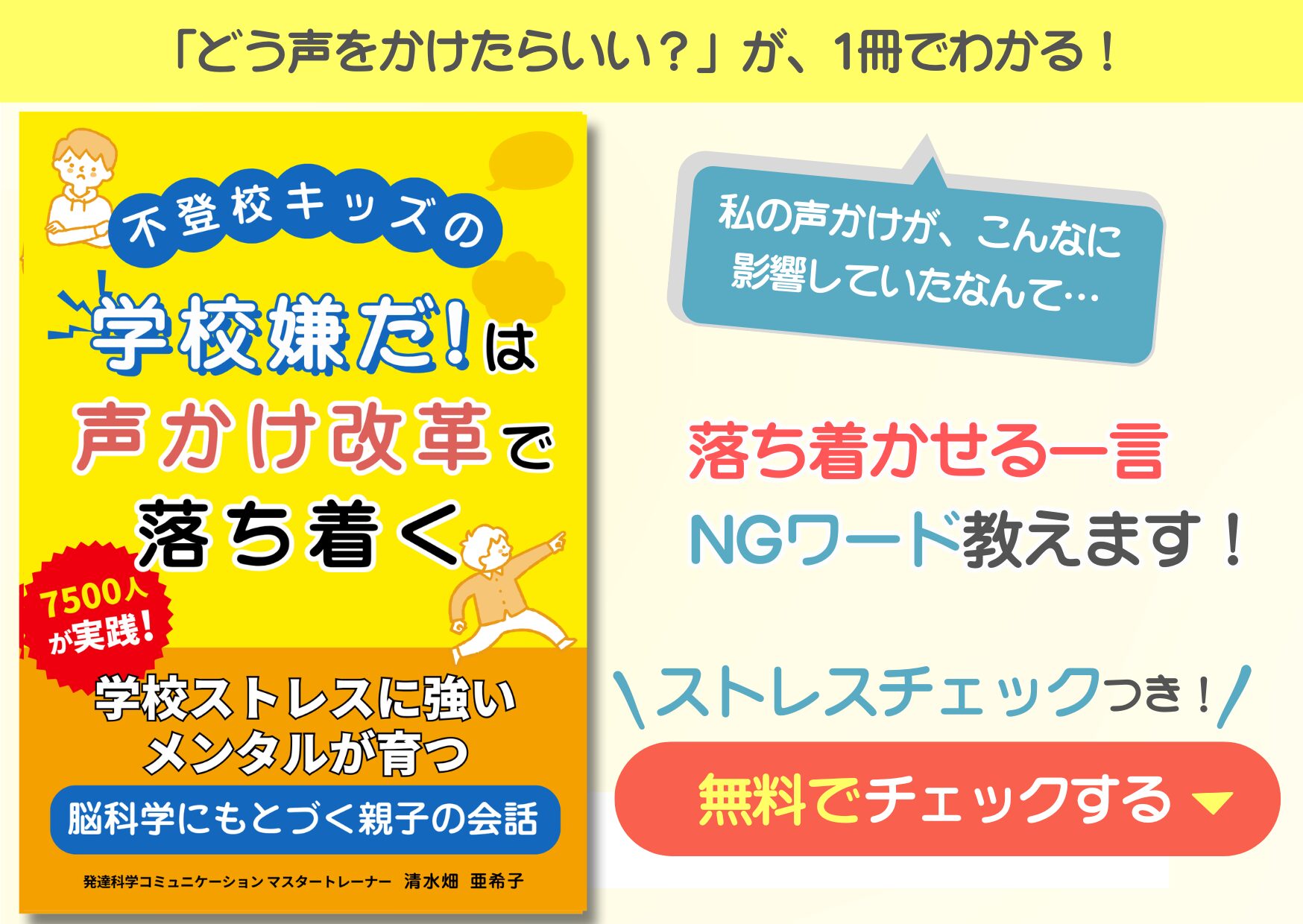
▲メールアドレスの登録で無料でダウンロードできます!
2. 宿題バトルに疲れたママが常識を変えたら…
今回レポートでお子さんとママの変化を伝えてくれたのは発達科学コミュニケーションNicotto!Project (ニコットプロジェクト)不登校チームのパステルジャンプアンバサダーのまつおかたえさんです。
やっと宿題を始めたと思っても、途中で気が散り進まない。
漢字を書けば、筆圧が薄く字が乱れている。
計算問題は、字が汚くて読みにくい上に間違いもちらほら。
そんな様子のお子さんのことが気になって、ますます子どものそばで宿題を見守るようになっていました。
横から間違いを指摘すると、とたんに怒って不機嫌になり、やる気も出ない、そこからさらに宿題が進まないという状況でした。

まつおかさんのお子さんは、繊細で不安が強い小学4年生です。
今まで、間違いや字の汚さを見つけたら、その都度、指摘していました。しかし、これでは子どものやる気を削いでしまったので、その場で指摘することはやめました。
代わりに、別の方法で宿題にやる気の出ないお子さんがスイスイはかどるようになったそうです。
不安の強さが宿題の進みに関係していることをレポートで紹介してくださいました。
3. 不安の強い子どもが宿題にやる気が出ないワケ
不安が強いお子さんは、ネガティブな記憶が残りやすいので、不安や恐れの記憶ではなく、楽しい記憶や“できた”という記憶をさせてあげる必要があります。
宿題で言うと、
間違いを見つけてガミガミ、チクチクとダメ出ししたり、文字がきれいに書けていないと直させる。
せっかく頑張って取り組んだ宿題をダメだしされ、自分はダメな子というネガティブな記憶が強く残り、自分を守るために宿題になかなか取り組まない、取り組んだとしてもなかなか進まない、間違いを指摘されると怒りで反撃する、という状況に陥ってしまいます。
逆に、楽しくお母さんと一緒に「芽」という漢字を書いたなら、のちにエピソードが削られて漢字の「芽」を覚えられていきます。
楽しく・できた!という記憶は頭に入りやすいということになりますね。
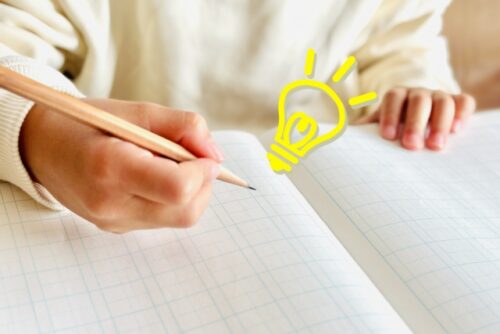
くわえて、宿題楽しくできた!と感じられるようになるよう、まつおかさんは次のように工夫されて取り組まれました!
<不登校の子の新しい育て方>
無理せず見守っているけど
本当に大丈夫なの…?
いつもダラダラ過ごす我が子を
動かす脳の育て方プレゼント中!
▼▼▼
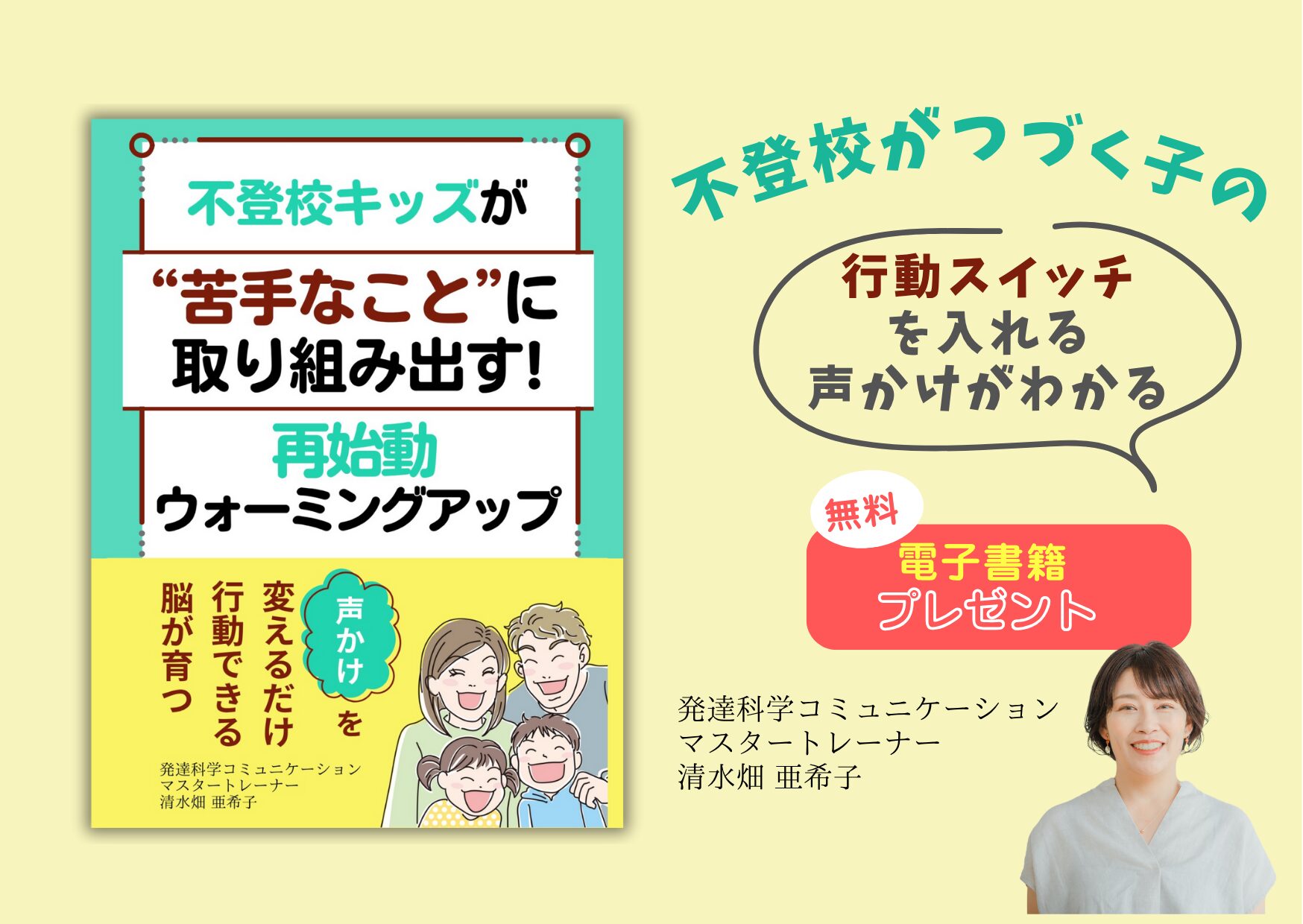
▲今すぐダウンロード!
4.宿題を楽しい記憶にする『やる気スイッチ』の押しかた!
◆まずは間違いは指摘せず、できているところを探す
ほとんどの字が汚くても
「この字、濃い字で書けててかっこいいね!」
「うわぁ、この字、とってもきれいに書けているね」
「ここ、お母さんはハネちゃうけど、本当は止めるんだね!よく先生の話を聞いてたんだね。」
少しでも行動できたことを認めて肯定する
「宿題始めたんだね!」
「1問解けたね!」
「もう2行も書いたの!早ー」
◆宿題の時間に楽しみを入れる
また、なかなか、宿題にやる気が出ないときや取りかかれないときは…
「今日は、宿題がとっても早く進むグミを買ってきたよ。1粒食べれば、漢字が1行書けるんだって!」
と言って、息子さんの好きなグミを渡しました。
すると「1粒で2行書けたよ!もう1粒食べる!」と言って、さくさく漢字ノートが進んだそう。
また別の日は…
「ちょっと、洗濯物を入れてくるね!3分で戻ってくるけど、漢字1行くらい書けるかなぁ⋯」とぶつぶつ言いながら、子どもの側から離れます。
子どもの進捗状況を遠目で確認しつつ、子どもの元に戻ります。(集中していれば戻る時間を少し調整)。
宿題が進んでいないときは、そのことには触れず、宿題が進んでいたときは
「え!?1行って言ったのに、3行も書けてたの!?スゴ!」や
「今の間に、もう算数全部解いちゃったの?」と「驚き」の肯定を入れました。
◆宿題が負担であれば軽くしてOK
学校でもがんばり、家でも宿題をするのは、負担が大きい日もあります。
今までは、「宿題は全て自分ですべき」と考えていましたが、あまり意味のない苦行的な宿題はママが肩代わりすることにしました。

例えば、漢字ノートを1ページ書いた後の「読みがな書き」が息子さんは大嫌い。漢字の読みは、読めたらOKと考え、ママが代わりに書くことにしました。
また、計算ドリルの問題の書き写しでは、写し間違えも多く、問題を写すだけで疲れてしまっては本末転倒と考え、問題を解くことに力を注げるように、子どもから訴えがあれば、問題写しもママが快く代筆しました。(先生にバレないように、子どもの字を真似て書きました。)
肯定され、気分の良くなった息子さんは
「じゃあ、次はもっといい字を書いてみるね!」と言って、急にきれいな字を書き始めたり
「ママ、少し向こう行ってて」と言って、ママが見ていない間に、さらに算数の問題を数問解いて、ママを驚かせようとしたり!見違えるような変化です!
いかがでしたか?
「間違いを指摘する」「宿題は全部自分でやりきる」という常識を手放し、間違いはスルー、少しでもできているところをを探して肯定、といった関わりに変えたことで、漢字や計算問題の宿題はスイスイ自分で取り組めるようになったそうです。
毎日のように繰り広げられる宿題バトルにお疲れのお母さん。ぜひとも試してみてくださいね!
執筆者:岡千恵
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
やる気が出ない宿題もママとのコミュニケーションで楽しくできる方法があります!