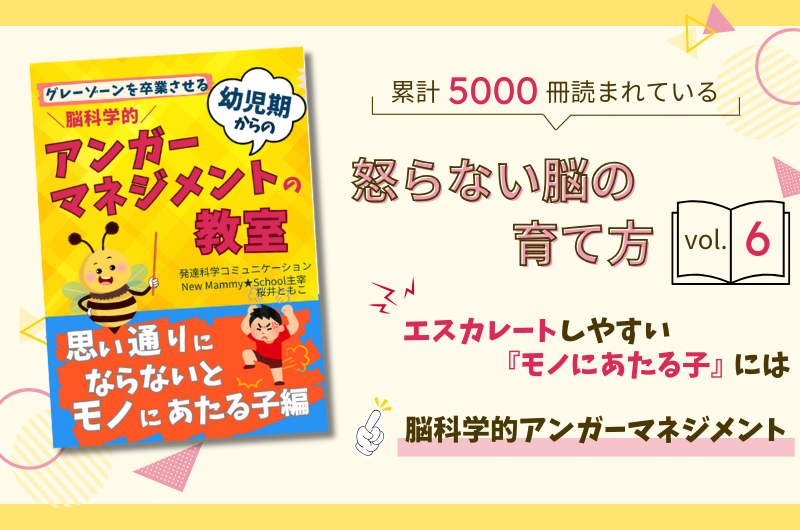褒めると怒る子には「褒め」も「肯定」も「共感」もできない!
子育てにおいて「褒めてあげましょう」「肯定してあげましょう」「共感してあげましょう」など聞いたことがある方も多くいらっしゃるでしょう。
実はこのwebサイトでも、子育てにおける声かけのコツとして、上記のようなことをたくさんお伝えしています。
ですが、「褒めると怒る子はどうしたらいいですか?」とよくご質問でいただきます。
Sさんからちょうどこのようなメールをいただきました!
ーーーーー
年中・年少の男の子です。
不機嫌なとき、優しく「嫌だったんだね〜」と言うと「その言い方キモい」と言って、余計に暴れたり蹴ったりしてきます。
いつもの言い方に戻しても時すでに遅しです。
『気持ちが落ち着くまで距離を置く』でいいですか?
ーーーーー
褒めたり、肯定したり、共感したり…というスキルを実践したいのにできない!ということ、ありませんか?
スキルを学んでも、そのスキルを活かすこともできず、子どもにどう接したらいいのかわからなくなってしまいますよね。

シリーズ累計1万ダウンロード突破!
今一番読まれている「癇癪卒業のバイブル」
24時間イライラしない習慣術
↓↓↓

褒めると怒る、本当の理由
子どもは褒めると喜ぶものだと思いますか?
確かに褒められたら嬉しいし、喜ぶお子さんもいらっしゃるでしょう。
褒められて嬉しいのは、その「褒め」が子どもにきちんと届いているからです。
届けるためには、脳が育っていることが大前提なんです。
そもそも脳を育てていない人がただ褒めても、ただ寄り添っても、ただ気持ちを代弁しても、うまくはいきません。
発達科学コミュニケーションでお教えしている\幼児期からの/脳科学的アンガーマネジメントの癇癪対応の基本的な考え方は、癇癪が起こっていないときに脳を育てる!
これが大前提なんです。
ですから、脳を育てていない子には、ママのどんな褒めや肯定のテクニックも、全く効果がないばかりか、Sさんのようにかえって癇癪が悪化してしまうこともあります。
まずは「脳を育てる声かけ」をしていくことです!

「脳を育てる声かけ」には、会話の順番があり、その習得の順番も実は決まっています。
「会話の順番」と「習得の順番」が「怒らない脳」を育てるキーポイントになります。
毎日癇癪から卒業!
本当に必要な新しい教育がわかります
↓↓↓

「褒めると怒る」「褒めなくても怒る」の泥沼にハマる要注意な視点
子どもが癇癪を起こしているとき、あなたはどのような対応していますか?
A:怒り出したら気持ちが落ち着くまで距離を置く
B:そもそも不機嫌なときは声をかけない
さあ、どうでしょう?
答えは…
これどちらも不正解なんです!
もちろん、状況やその前にどんなことが起こっていたのかなど色々な要因があるので、一概には言えません。
ですが、子どもが癇癪を起こしていたらママはその場をスッと離れて、落ち着くまで待ちましょう、と聞いたので離れてみたら、余計に癇癪が悪化してしまった経験ありませんか?
「癇癪が起きたら落ち着くまで距離を置く」というような表面的な理解だけしていると、「褒めたら癇癪」「褒めなくても癇癪」の泥沼にハマっていってしまいます。
このような対応や声かけなどのスキルの表面的な部分だけ見ているとキケンですので、「そもそも」「癇癪対応ってどうやるの?」というところにに立ち戻ってみましょう!

褒めると怒る子への毎日の声かけのコツ
わりとすぐに癇癪を起こすタイプのお子さんは、どこに地雷があるかわからないので、ママがうっかり踏んでしまわないよう声かけをためらってしまうこともあるでしょう。
ですが、脳を育てるためには、毎日の声かけが必須です。
褒めても怒る、何をしても怒ってしまうお子さんには、まずは「事実のみを伝える」ということをやっていきましょう。
事実を伝えるので、そこには嘘はありませんし、おだてることもありません。
たとえば、食事をしていたら「よく噛んで食べてるね」「こぼしたところ拭いてくれたんだね、ありがとう!」というように、ただ「できていること」を伝えるようにします。
「よく噛んでいてえらい!」とか「拭いてくれたのー!えらーい!」というような評価をしないことがポイントです。
子どもが既にできていることであり、これからも続けてほしい状態のことを、そのまま実況中継するように、子どもの行動をママが言葉にしていきます。
子どもが不機嫌になっているときや癇癪を起こしてしまっているときは、これからも続けてほしい状態とは言えませんので、そのときは伝えることはありません。

毎日、毎日、できていることを伝えていくことで、成功体験を積み上げていくことができます。
できていること一つ一つは小さなことかもしれませんが、この小さな成功体験の積み重ねで、ママの声かけを聞くことができるようになっていきます。
このように脳が育っていきますので、まずはできている事実のみを伝えていきましょう!
執筆者:桜井ともこ
(発達科学コミュニケーションマスタートレーナー)
子育てがもっとずっとラクになるママの声かけをお伝えします!
▼無料メール講座の登録はこちらから