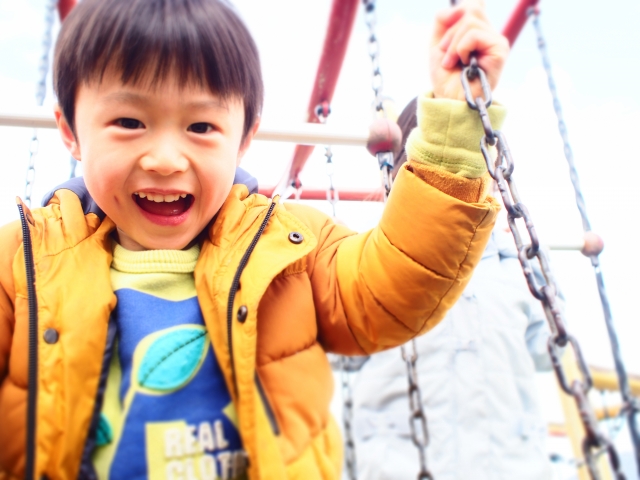ADHDタイプのお子さんが「食事中に立ち歩く」原因とは?
ご飯の最中に立ち歩いたり、食べ始めたと思ったらふざけて集中できない。
注意すると逆に癇癪になって大荒れ。
本来楽しいはずの食卓がいつの間にか「注意とバトルの時間」になっていませんか?
実はそれ、ADHD(注意欠陥・多動性障害)タイプの脳の特性と食事中の関わり方が 関係しているかもしれません。
ADHDタイプに見られる脳の特性
①じっとしているのが苦手
脳のブレーキ機能が未発達なため、「じっと座る」こと自体が強いストレス になります。
また「おもちゃが気になる」「水を飲みたい」と思った時、その衝動を抑える力が弱いため、つい立ち歩いてしまうのです。
②集中力が長く続きにくい〈不注意〉

食べることよりも周囲の刺激〈テレビ、兄弟、音など〉に注意が移りやすいのも特徴です。
つまり、「立ち歩き=しつけ不足」ではなく、子どもの脳の特性が背景にあるのです。
だからこそ、「注意で抑え込む」よりも「座れる時間を少しずつ育てる」視点が大切になります。
③親の関わり方
立ち歩くとつい「座って!」「立たないで!」と何度も注意してしまいますよね。
でも実はこの注意そのものが子どもにとって「ご褒美」になってしまうことが あります。
子どもにとっては、ママの声かけは「見てもらえた!」「かまってもらえた!」 という安心や嬉しさにつながります。
その結果、「立ち歩いたらママが反応してくれる」と学習し、立ち歩き行動が強化されてしまうのです。
さらにやっと座った瞬間に「こぼさないで!」「ちゃんともって」など注意が重なると、子どもにとって食事が叱られる時間に変わってしまいます。
楽しいはずの食卓がプレッシャーになれば、当然イライラや癇癪にも つながりやすくなりますよね。
大切なのは、「出来ていないこと」ではなく、「出来ている瞬間」にママが注目すること。
ママの注目をご褒美として、活かせば少しずつプラスの行動が増えていきます。
シリーズ累計1万ダウンロード突破!
今一番読まれている「癇癪卒業のバイブル」
24時間イライラしない習慣術
↓↓↓

私自身も経験した「食事中の立ち歩き」と癇癪へのイライラ
息子は、少し食べては椅子から降り、おもちゃを触ったり 遊びに行ったり。
そんなことを何度も繰り返していました。
そのたびに私は、「もう立たないで!」「ご飯食べて!」 とつい何度も注意してしまっていました。

ようやく座ったと思ったら、今度はスプーンを使わずに手で食べたり、 わざとふざけて笑わせようとしたり。
「ちゃんと座って!」
「ほら、こぼれるよ!」
「また汚れたでしょ!」
そんなふうに、気づけば私は注意ばかりしているママになっていました。
当然、食卓は「楽しい時間」ではなく毎回がバトルの場になってしまっていたのです。
なぜ私がそこまで注意してしまったのか。
今振り返ると、その背景には私自身の育ち方がありました。
小さい頃、私もよく「ちゃんとしなさい!」「静かに食べなさい」 と繰り返し注意されて育ちました。
だから自然と 「しつけは厳しくするもの」「食事中は静かに座って食べるもの」 と信じこんでいたのです。
けれど、発達科学コミュニケーションを学んでから、私は大きな気づきを得ました。
注意ばかりしていても、子どもは変わらない。
むしろ注目=ご褒美になって、 立ち歩きやふざけが強まっていたんだと。
この視点を知ったことで、私は自分の関わり方を見直しました。
すると少しずつ、息子の立ち歩きやふざけが減り、食卓に笑顔が戻ってきたんです。
毎日癇癪から卒業!
本当に必要な新しい教育がわかります
↓↓↓

ADHD傾向のお子さんでも「食事中の立ち歩き」が減る3つの対策
食事中の立ち歩きうあふざけ行動は、「叱る」よりも「関わり方を変える」ことでぐんと減っていきます。
ここでは、ADHDタイプのお子さんでも楽しく座って食べられるようになる3つの工夫をご紹介します。
①座っている瞬間を褒める
子どもが立ち歩いた時に注意するよりも、 座っている時こそ声をかけることが大切です。
「座って食べれてるね」
「上手におはしもてたね」
そんな具体的な褒め言葉を重ねることで、 子どもの脳は「座る=ママに認められる」と学習していきます。
叱るより、見つけて褒める。
この切り替えが立ち歩きを減らす第一歩です。
②短時間から成功体験を積む
「最初から最後まで座って食べる」はADHDタイプの子にはハードルは高め。
まずは3分でもОK! 座って食べられたらすぐに「出来たね!」と伝えましょう。
この「できた!」という小さな成功体験が「やればできる」という 自己効力感を育てます。
自然に座れる時間が長くなっていきます。
③食事を楽しい時間に変える工夫
注意ばかりの食卓は、子どもにとってプレッシャーの場になります。
楽しさを感じられる工夫を取り入れていきましょう。
1〉ワンプレートで「量の見える化」
大きなお皿や山盛りご飯は「終わりがみえない」状態に。

ワンプレートに小分けにするだけで、「あとこれくらい」とゴールが見え、達成感を得やすくなります。
2〉クイズや会話で笑顔を増やす
「お味噌汁の具、何が入っているかな?」
「この中に入っている野菜はなんでしょう?」
食事中にちょっとしたクイズを加えるだけで、楽しい時間に変わります。
3〉お手伝い役で「役割感」を持たせる
お皿を並べる、スプーンを配るなどお手伝い役をお願いするのも効果的です。
子どもは「自分も役に立ってる!」と感じることで、貢献欲求が満たされ、食事への関わり方が前向きになります。
「食べさせられる時間」から「自分も関わる楽しい時間」へとシフトしていくのです。
子どもの立ち歩きやふざけは、「しつけ不足」ではなく脳の特性と親の関わり方の 影響によるもの。
叱ってやめさせるのではなく 、座っている瞬間を褒める、短い時間から成功体験を積む 、食卓を楽しい時間に変える。
この3つを意識するだけで、少しずつ食卓の空気が変わっていきます。
食事中の立ち歩きと癇癪が減り、食事が楽しい時間に変わった我が家
以前の私は毎日のように「座って!」「立たないで!」「ちゃんと食べて」と注意ばかりしていました。
食事の時間はいつの間にか「楽しむ時間」ではなく、「バトルの時間」になっていたんです。
でも声かけを変えて「できている瞬間」を見逃さず認めるようにしたら 少しずつむすこに現れました。
・食卓に座っていられる時間が伸びた
・手で食べらりふざける時間が減った
気づけば、食事中にイライラすることも減り笑顔で「美味しいね」と話せる時間が増えていきました。
食卓は「注意される時間」から「親子で笑顔になれる時間」へと変わっていきました。
「注意してもしつけても変わらないんだ」そう気づけたことが 私にとって大きな成長でした。
子どもは認められることで変わっていきます。
そしてママの関わりかたひとつで、食卓はもっと楽しく、安心できる場所になるんです。
もし今、「食事中に立ち歩いてしまう」「ふざけて全然食べてくれない」そんなお悩みを抱えていたら、 お子さんが座っていられる時間に是非、注目をして声をかけてみてくださいね。
執筆者:大下せいこ
(発達科学コミュニケーショントレーナー)


「怒らない脳」を育てる声かけをたくさん紹介しています
▼無料メール講座の登録はこちらから