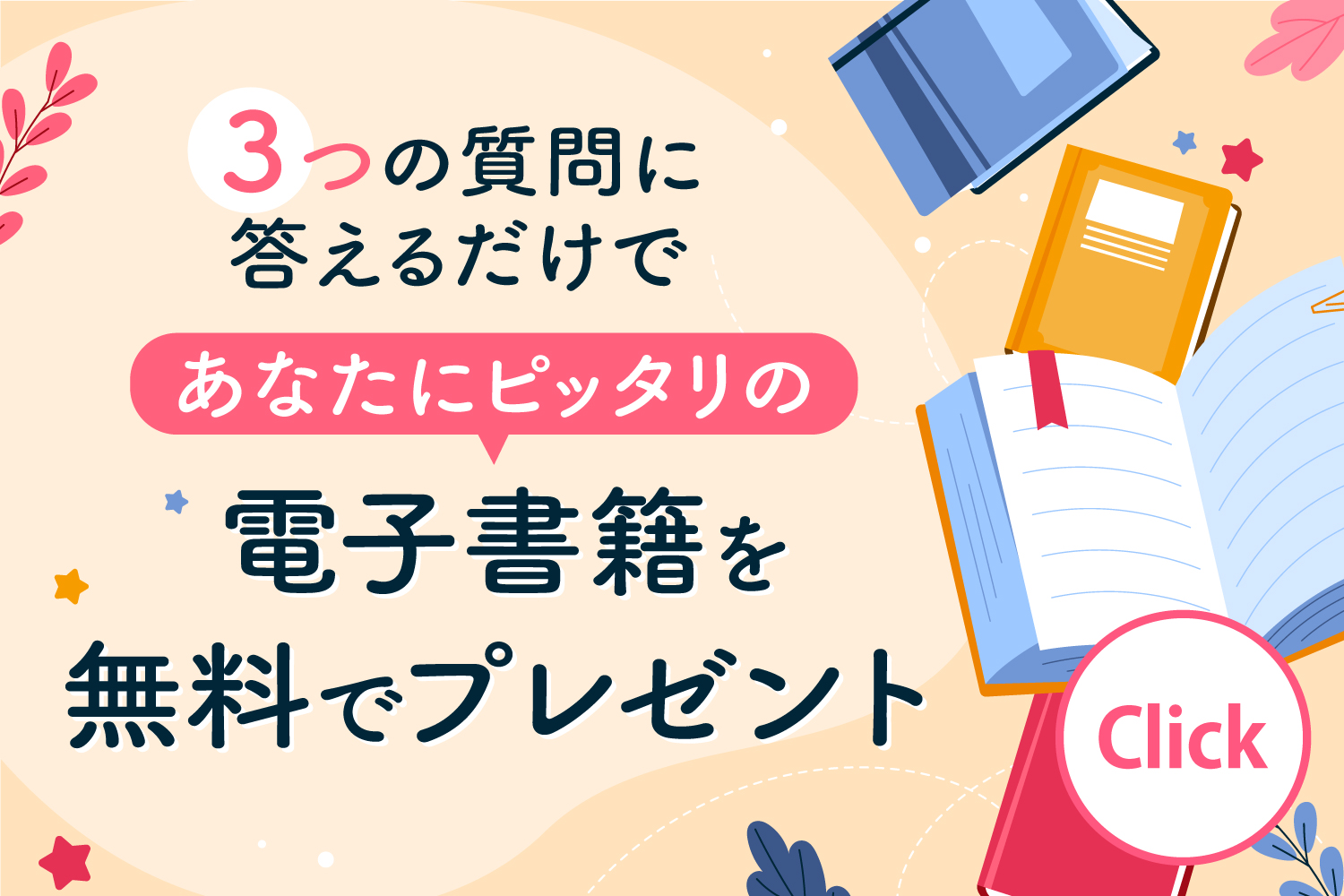| 小学一年生の3学期だけどなかなかひらがなが書けないお子さんにひたすら練習を強いていませんか。いくら練習して書けるようにならなくて困られている場合は、学習障害の書字障害・ディスグラフィアかもしれません。この記事では、原因と楽しく学べる術をお伝えします! |
【目次】
1.小学一年生でひらがなが書けない・字を書くのが嫌いな子どもに困っていませんか?
小学一年生でひらがなの学習が始まったけれど、
お手本を横に置いて見ながらでも、字を書くのに苦労している
文字が大きすぎてノートのマスからはみ出す
小さすぎたり形のバランスが悪い
見た目が似ている文字を書き間違える
促音や拗音を書くのが難しい
ゴミしゅうしゅうしゃを
ゴミしうしょうしぁ
きっとをきと
のように書き間違えてばかり…
こんな様子が見られていませんか。
そんなお子さんをみてちゃんと書けるようになるために練習させないとと思って
「ここがちがうよ」
「はみ出たからやり直しね」
とお母さんが消しゴムでゴシゴシと消してやり直しをさせていると、すぐに子どもの機嫌が悪くなる。

字を書くのを嫌がる子どもを前に「練習しないとできるようにならないのにどうしよう…」と困られているお母さんもいらっしゃると思います。
練習を重ねていたらお子さんがどんどん字を書くことを嫌がるようになってしまっている場合は、書字障害・ディスグラフィアの可能性もあります。
書字障害・ディスグラフィアは、知的障害はないけれど、「読み」「書く」「聞く」「話す」「計算する」「推測する」のうち字を「書く」ことが極端に苦手な学習障害(LD)です。
「読む」事が苦手な読字障害・ディスレキシアがあって「書く」事が難しいこともあります。
診断は専門機関でしてもらう必要がありますが、ここでは、字を書くのが嫌いな子、字が書けない障害・ディスグラフィアの傾向があるお子さんの書く力の基礎をお家で伸ばせる非常識な方法をお伝えします!
2.字が書けない書字障害・ディスグラフィアの子どもが楽しく学べる非常識な3つの方法!
字を書くのが嫌いで、字が書けない障害・ディスグラフィアの傾向があるお子さんへできるサポートは、一般的には、
✓筆記用具や紙を使いやすいものにする
✓正しい字の書き方のトレーニング
✓筆圧や筆跡のコントロールのトレーニング
✓読み書きの練習
✓パソコンを使った文字入力のトレーニング
などがあります。
ただ字を書くのが嫌いな子どもに「練習をしなさい!」と言っても、なかなかスムーズには取り組んでもらえないですね。
嫌なこと・苦手なことを無理やりやらせても、なかなか上達しないものです。また、書くためには、そのための基礎となる力が育っている必要があります。
ここでは、ひらがなが書けない・字を書くのが嫌いな子どもに書かせるトレーニングはしない!楽しみながら書く力の基礎を育てる非常識な3つの方法をお伝えします!
◆①手遊び歌で遊ぶ!
ひらがなを書くためには、頭の中にある音を文字に換える力、音韻を処理する力が育っていることが重要です。
例えば、「さくら」という言葉を聞いて、「さ」「く」「ら」と分けられることです。これを拍がわかることといいます。これが、音韻処理をする力のファーストステップです。
その拍を手遊びで楽しみながら育てることができます。
子どもも大人も楽しいことをしているときが一番脳が発達します。そのため、楽しみながら行うことが大切です!
手遊び歌は、よく子どもの頃皆さんもやったことのある「おせんべ焼けたかな」や「ちゃつぼ」「アルプス一万尺」などの手遊びがオススメです。
また、字を書くときに必要な見本の動きをよく見る力、視覚のエリアも育ちます。そして、マネをして手を動かすので視覚系と運動系のつながりが強化でき、字を書くために必須の「目と手の協応」も育てることができるんです!
・最初は指を指されたら手のひらを返す初心者レベル「おせんべ焼けたかな」からスタート
二人でもできますが、三人以上いた方が盛り上がるかもしれませんね。
遊び方は、
・それぞれ手のひらを下に向けて両手を出します。
・一人の人が「お・せ・ん・べ・や・け・た・か・な」と順番に手の甲を指差します。
・「な」にあたった手は「おせんべいの下が焼けた」のでてのひらを上に向けてもらいます。
・てのひらが上に向いた状態でもう一度「な」になったら、焼き上がりで手を後ろに隠します。
・最初に両手のおせんべいが焼けた人が勝ちです。
まずはお母さんが指のさし方の見本を見せてあげて、次からはお子さんにやってもらってもいいですね。
・「ちゃつぼ」は一人でも二人でもできる手遊びです。「ちゃつぼ 手遊び」で検索していただくとたくさん動画や説明が出てくるので、ぜひ参考にしてください。
歌(拍)に合わせて手を動かすことで字を書くために必要な音韻処理の力と「目と手の協応」も育てることができます。
最初はゆっくりと歌いながら見本を見せてあげましょう。
両手を順番にグーにして動かすのが難しい場合は、片手だけグーにして、もう片方の手のひらをグーの上下に当てる動きからスタート。その動きも難しいようでしたら、拍手で合わせるのでもOK!
・「アルプス一万尺」は一番だけで十分。二人でやると楽しめます。小学校低学年・中学年のお子さんも楽しめる手遊びです。
字を書くために必要な音韻処理の力や視覚のエリアと運動のエリアを育てて、つながりを太くしてあげましょう!そうすることで字を書く力が育っていきます!
注意点としては最初から全ての動きをやるのは難しすぎるので、最初は手を叩いて交互に相手の手をタッチする動きだけでOK。音韻処理の力と見本を見てマネをして自分も動くので、「目と手の協応」が育ちます。
「ア・ル・プ・ス・一・万・じゃ・く
こ・や・り・の・う・ー・え・で・
ア・ル・ペ・ン・お・ど・り・を・さ・あ・お・ど・り・ま・しょ
こ・や・り・の・う・ー・え・で・
ア・ル・ペ・ン・お・ど・り・を・さ・あ・お・ど・り・ま・しょ
ラン・ラン・ラン ラン・ラン・ラン ラン・ラン・ラン ラン・ラン・ラン
ラン・ラン・ラン ラン・ラン・ラン ラン・ラン・ラン ラン・ラン・ラー」
これがスムーズにできるようになってから、少しずつ手の動きをレベルアップしてあげてくださいね。

間違えても「あーおしい!」と楽しそうに声をかけてあげてください。
学校や学童でも小学校低学年ぐらいからよく子ども達がやっている遊びなので、お子さんも見たことがあるかもしれません。
「できるようになりたい!」と子どもが思えたならこっちのものです。
◆②言葉遊び!
音韻処理の最初のステップ、拍の理解が育ってきたら次に、言葉の最初と最後の音が分かる力・言葉を音に分けて聞き取れる力を育てる「しりとり」や「さかさ言葉」などの言葉遊びがおススメです。
しりとりは、動物や食べ物などカテゴリーを決めてやってもいいですね。
とにかく楽しみながらやることが大事なので、お子さんが好きなもの「ポケモンの名前」やサッカー選手の名前、車のメーカー名などをお母さんがあえて言ってあげると乗ってくるかもしれません。
さかさ言葉は、自分や家族、友達の名前をさかさまに言ってみるだけでも、印象が全然違うので楽しめます。
どちらも、車の中で手が離せない時や、お風呂の中、何かを待っている時など、ちょっとした時間にも、手軽にできますね!
◆③全身の動きをマネをする!
字を書くために必要な「目と手の協調」を育てるには、視覚のエリアと運動のエリアを一緒に使ってつながりを育てることが大切です。
手や指を使った細い動き、微細運動をマネする前に、まずは全身の動きをマネすることがオススメです。
微細運動はただでさえ苦手なお子さんたちなので、まずは「できそう!」と思えて、楽しめる全身の動きからスタート。
マネをするためには、目でジーッとみることが必要になります。そのため視覚のエリアが育ち、見ながらマネをして動くので、視覚と運動のエリアのつながりも育つのです。
例えば、ダンスや料理など。お手本をマネをして体を動かすことができます。
戦隊モノが好きなお子さんだったら、変身ポーズのマネやエンディングに流れるダンスなどもマネをして動くことも楽しみながらできるかもしれません。テレビを見ながら戦闘シーンをマネするのでもいいです。
好きなモノならマネをすることも楽しめます。ぜひ、お子さんが好きなものから何かマネをして動くことはないか、アイデアを探してみてくださいね!
家で少しずつ書く力の基礎を育てることができたとしても、学校や親戚などからのプレッシャーもあってしんどい思いをされている方も多いと思います。
そういったお悩みが解決できる秘策をこのメルマガでお伝えしています!
↓↓↓
小学一年生でひらがなが書けない・字を書くのが嫌いな子どもへの対応の秘訣はこちら!
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
育てにくい子が3ヶ月で変わる!
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
↓↓↓
執筆者:山田ちあき
(発達科学コミュニケーションリサーチャー、臨床心理士)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー、臨床心理士)