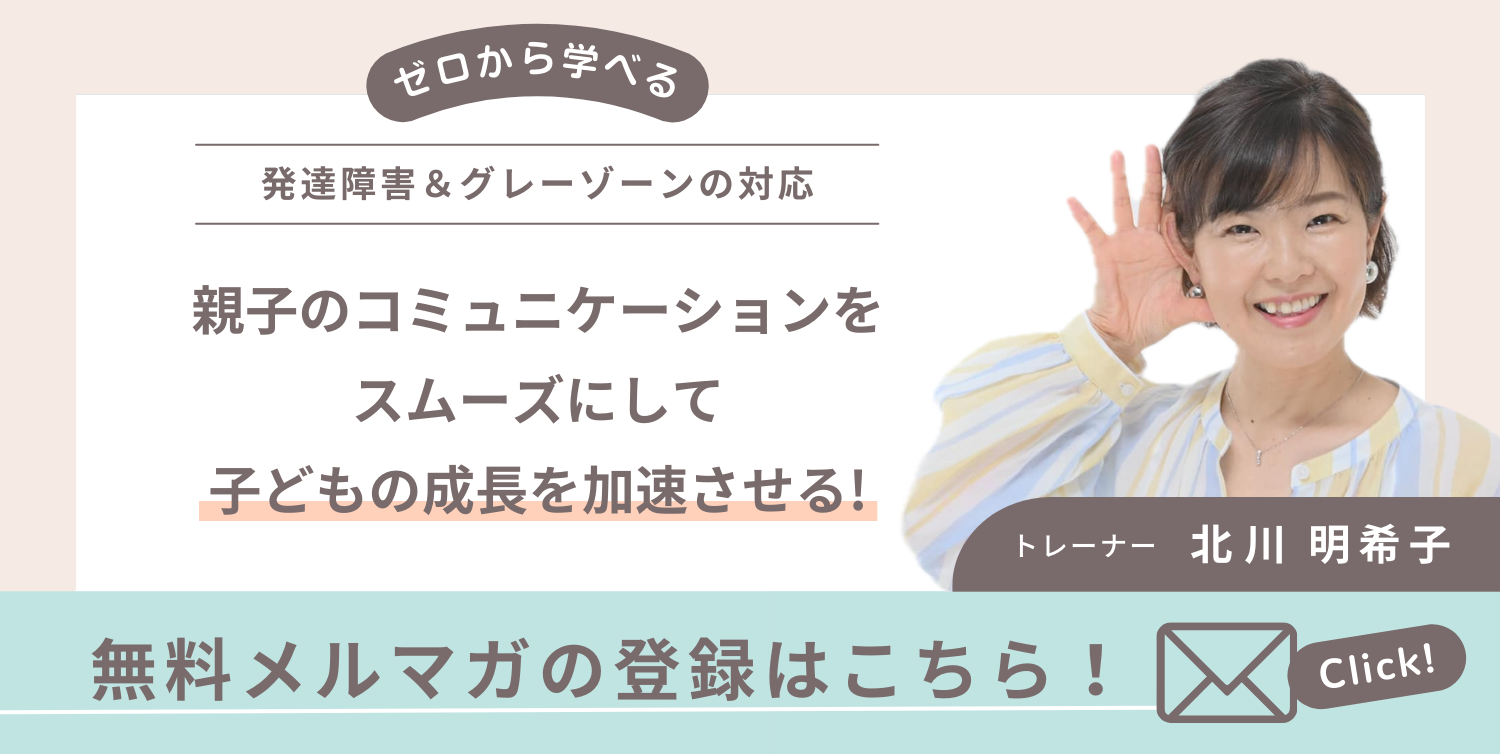思春期に入った女子は何が原因なのかイライラすることが多くなってきませんか?「9歳の壁」と言われる中学年から複雑になる勉強や人間関係、体の変化からご説明します。イライラに真正面に対抗しない上手な宿題サポート法、参考にしてみてください。
【目次】
1.思春期女子のイライラに巻き込まれていませんか?
2.9歳の壁×思春期女子に特有なイライラの原因は?
①学習面の変化
②対人面の変化
③ホルモンバランスの変化
3.思春期女子の宿題サポート術
①共感
②気分転換
③距離感
④自分で気づかせる一言サポート
4.思春期の子どもの能力UPはおうちがカギ
2.9歳の壁×思春期女子に特有なイライラの原因は?
①学習面の変化
②対人面の変化
③ホルモンバランスの変化
3.思春期女子の宿題サポート術
①共感
②気分転換
③距離感
④自分で気づかせる一言サポート
4.思春期の子どもの能力UPはおうちがカギ
1.思春期女子のイライラに巻き込まれていませんか?
学年が上がるごとにどんどん難しくなってくる勉強。
低学年から積み上げてきた知識を応用する問題になってくるので、一度つまづくと苦手意識がつきやすいですよね。
小学3年生、4年生は「9歳の壁」または「小3の壁」「小4の壁」といい、勉強がいきなり難しくなることで壁にぶち当たり、うまくいかないイライラを抱える子どもが多くいます。
加えて、思春期の女子は口が達者ですから、お母さんとの会話も反抗的になってきます。
現在小学5年生のわたしの娘は、小学3年生の終わりごろから口調がとげとげしくなってきました。
「は?」「だから~(怒)」「何言ってんの?」

発達障害の診断はありませんが、不注意や繊細さがあるグレーゾーンの娘です。
2年生の頃は、わたしにべったりで「学校にいても何回もママのことを考える」と母子分離不安の様子だったのが、発達科学コミュニケーションで子どもを褒めるコミュニケーションを学び、随分と落ち着きました。
自分の部屋で過ごす時間が増え、夜も1人で寝るようになり自立と自我の芽生えを感じるようになったのです。
同時に勉強が難しいことや宿題が多くて終わらないことにイライラすることもあり、この思春期女子特有のイライラ、何が原因なの?と思っていました。
2.9歳の壁×思春期女子に特有のイライラ
「9歳の壁」「小3の壁」の壁とはいったい何なのか、この時期の女子のイライラが重なる原因についてご説明します。
9歳の壁、これは学習や対人面の変化です。ご説明しますね。
◆①学習面の変化
学習面では抽象的概念が取り込まれてきて、難易度がぐんと上がります。
・算数 分数や小数点
・国語 作者の意図を読み取る
・理科 電流の大きさや流れる方向
子どもにとって頭でイメージしにくい内容ですよね。
それまで順調に学習についていけていた子でも、この抽象的概念につまづいてしまい、自信をなくしたり、勉強に苦手意識を持ってしまうことがあります。
学校でわからない、難しいと思う勉強を家でも宿題でやらなければならないイライラ、わかる気がしませんか。
◆②対人面の変化
この時期の子どもたちは、先生や友達から刺激を受け自分なりの価値観を持つようになり、人間関係が複雑になります。
仲間意識が強くなり価値観の近い子同士で行動するようになり、特に女子はグループ意識が強くなります。
「なかよし」に条件が付くようになるのです。
例えば
・なかよしグループに入るためには共通の話題や趣味が必要
・グループならではのルールが強い、ルールから外れると仲間ではないと思われたりする
こういった条件つきのお付き合いは、結束を強くもするし、一方であやふやな対人関係にもなりえます。
お母さん方も同性ですから経験をお持ちでしょう。
このような気を使った人間関係にストレスを抱える子は多いのです。

◆③ホルモンバランスの変化
8~9歳ごろから性ホルモンが活発に分泌され、女の子は女性らしい体つきに変化していきます。
胸が膨らんできたり、生理が始まったり。その生理も最初の頃は安定しません。始まったと思っても毎月ではなく、数か月後に次の生理がきたり周期もバラバラだったりします。
最近は生理が始まる年齢も低年齢化しているようで、娘のお友達では3年生で初潮がきた子もいるそうです。
このようにホルモンの分泌が急激に活発になり、ホルモンバランスが崩れやすくなります。
そのため、不安をおさえリラックスさせることが難しくなり、ちょっとしたことでも不安になったりイライラしやすくなったりするのです。
お母さんも生理が始まる前などはPMS(月経前症候群)で頭痛やお腹の張り、イライラしやすいなどの症状は経験があると思います。
思春期の女子は経験したことのない体と心の変化に影響を受け、ちょっとしたことで不安になったりイライラしやすいのです。
3.思春期女子の宿題サポートのコツ
ある日、学校から帰ってきた時からイライラしていた娘。苦手な算数の宿題が出たというので思春期女子向けの関わりすぎない宿題サポートを試みてみました。
ポイントは4つです。
◆ ①共感
まずは取り組む前の「面倒くさい」「嫌だな」という気持ちには「大変だよね」と共感。
間違えた理由がわからないイライラには、「学年が上がると、どんどん難しくなるよね~」「ママも難しく感じるよー」と、とにかく娘のネガティブな気持ちを否定せず、共感する言葉を返すようにしました。
◆②気分転換
帰ってきた瞬間から疲れていて不機嫌だったので、いきなり宿題を始めるのはNG!
まずおやつタイムで気分転換し、愚痴にも「ふんふん」と耳を傾けます。
宿題に取り掛かっても、途中でわからない問題にイライラし始めました。
そんな時は途中休憩だと思って「ココア入れたよ」とクールダウンの時間を設けます。
ネガティブな気持ちがどんどん悪化していく前に、その状況から切り離して落ち着かせることを意識しました。

◆③距離感
横に座らず、立ったまま横にいて家事をしながらのぞき込むスタイルで付き添ってみました。
これはあえて距離を離すためにしたことです。
低学年の頃は、私が真横に座り「ここはこうだよ」とマンツーマンの指示をしていましたが、思春期女子にはうざがられます。
わたしまで座ってしまうと「字をもっと綺麗に書こうよ」「そこ違ってない?」など、余計な指摘までしてしまうので、必要とされている時だけ関わるようにしました。
◆④自分で気づかせる一言サポート
わからない問題があるなら、教科書や問題集のヒントが書かれている箇所だけ気づかせてみましょう。
子どもの「わからない!」は意外と単純な計算ミスだったり、イライラが先走って基本の解き方に戻る冷静さを欠いていることがあります。
娘の場合も、間違えた箇所しか見えておらず単純な計算ミスに気づけていませんでした。
ページ上部に書かれているヒントに誘導するために「ここに何か書かれているよ」と声掛けは一言。
目線をヒントに移せたので、一緒に解き方の解説も確認しました。
これで理解ができたので、加速して宿題を終わらせ部屋に引き上げていきました。
5.思春期の子どもの能力UPはおうちがカギ
このように4つのポイントを意識しながら、関わりすぎないサポートをしてみました。
一貫して大切なのは、子どもの様子をよく観察すること。
関わりすぎないサポートはタイミングが大切、だからよく観察するのです。

高学年になってくると、子どもの様子も変わってきますね。
口出しはされたくないだろうし、娘から返ってくる言葉も「説明がわからないよ!」などと強めになり、こちらがムッとしたりすることもありました。
低学年の頃と同じ対応ではぶつかってしまうな、と感じます。
そして、これから学年が上がり中学生や高校生になったら、塾や教室を頼ることになると思います。
ただ、プロに教わることになっても、基本はおうちで勉強をしますよね。
大事なのはおうち環境とママの声掛けです。
思春期女子のイライラをうまくかわしながら、親子のコミュニケーションを育む対応上手なお母さんになれますよ。
▼▼会話のはじめ方を意識するとコミュニケーションが変わる
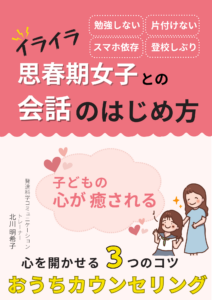
https://www.agentmail.jp/lp/r/19066/156416/
執筆者:北川明希子
(発達科学コミュニケーション トレーナー)
(発達科学コミュニケーション トレーナー)