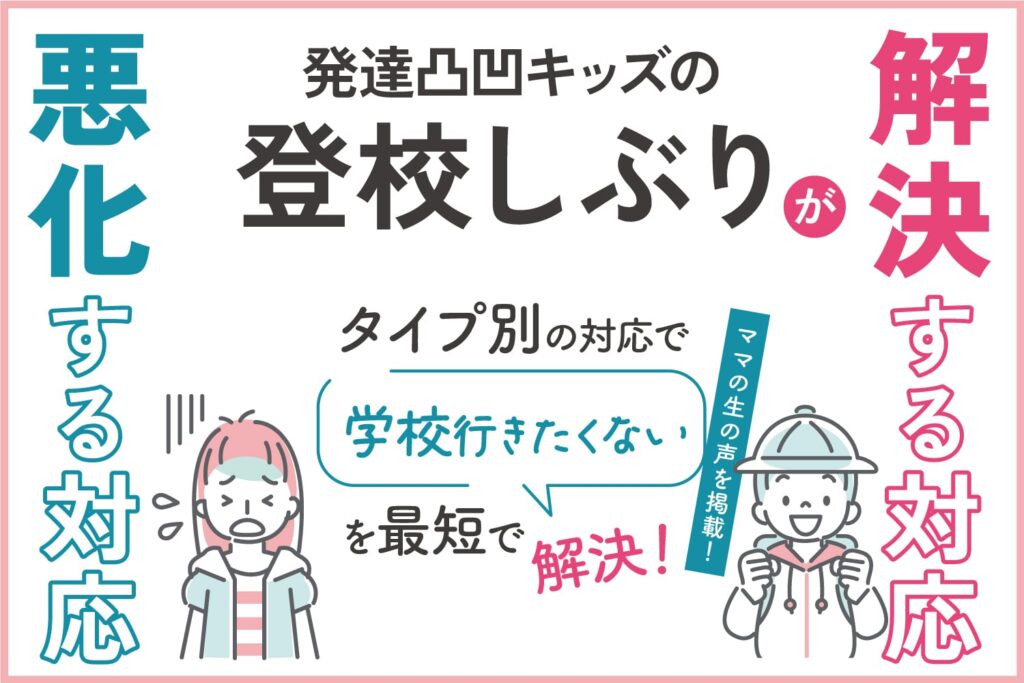発達障害・アスペルガーの運動苦手な子は鉄棒も縄跳びも簡単にはできずに自信をなくしがちです。運動音痴というセルフイメージを払拭して運動が楽しくなる親のたった一つの声掛けと運動苦手な子におすすめの運動をご紹介します。
【目次】
1.運動音痴?体育の授業に参加しなかった息子
2.発達障害・アスペルガータイプには運動が苦手な子が多い
①発達障害の一つである発達性協調運動障害(DCD)とは?
②なぜ運動は発達障害児に必要なのか?
3.親の声かけと対応で、運動嫌いにさせず運動が楽しくなる!
①運動へのハードルを下げる親のたった一つの声掛け
②運動苦手な不器用っ子におすすめの運動
1.運動音痴?体育の授業に参加しなかった息子
我が家の息子は発達障害・アスペルガー傾向で、幼い頃から外遊びよりは家で遊ぶのが好きという子どもでした。
公園に連れ出してもなかなか遊具で遊ぼうとせず、本を読んだりパズルをしたりするのが好きな様子。
子どもが自然と触れる機会のある鉄棒や縄跳びには近づかないままに入園し、クラスで鉄棒をやった日は「鉄棒苦手…できなかった」と言うこともありました。
運動会やお遊戯会といった体を動かす行事となると、練習を嫌がり、逃げ出したり、全然動かなかったりという様子も。
とはいえ、年少・年中はクラスメイト達もまだまだ幼く、できないことが際立って目立つことはありませんでした。
無理やりやらせてもなと、こちらも運動に関してそこまで気にしていなかったのですが…
年長時の運動会で組体操があり、周りの子はできているのに自分は先生に言われたように体が動かないことで、自分ができていないことにはっきりと気付いたようなのです。
運動会の練習が始まったころは登園渋りが出てしまうようにもなってしまいました。
そんな幼稚園時代を過ごした息子は、「自分は運動が苦手」、「僕は運動音痴だからやらない!」とセルフイメージを持ってしまったようなのです。

小学校に上がり、勉強に対しては意欲的で国語、算数の授業は楽しく受けているようでした。
しかし体育の授業となると… 全く参加せず!
別室で先生とマンツーマンで過ごさせてもらったりという報告を受けました。
当時一番ショックを受けたのは、息子が自分で「僕は体育が苦手だから…」と発言したことでした。
自信をなくしていることに気付き、何とかしたい!と思いました。
2.発達障害・アスペルガータイプには運動が苦手な子が多い
◆①発達障害の一つである発達性協調運動障害(DCD)とは?
発達障害児はなんとなく不器用な子、運動音痴な子が多いという感じを受けるかもしれません。
発達障害の中の一つに、発達性協調運動障害(DCD)というものがあります。
手と足、目と手など別々に動く機能をまとめてひとつにして動かす協調運動が苦手という特性です。
これは注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)、知的障害と高い確立で併発すると言われています。
また、運動といってもいわゆるスポーツのことだけではなく、体全体を使う粗大運動と手先を使う微細運動の2種類のことをさします。
体や手先の不器用さがあることで基本的な生活を送るのに困難さがあったり、できないと思うことでさらにやらなくなり、自信をなくしてしまい、対人関係が上手く築けなくなるなどの弊害が起きるとも言われています。
息子はDCDの診断を受けたわけではありませんが、粗大運動も微細運動も苦手で不器用な面が見られました。
小学生になり、家庭では鉄棒やマット運動などは苦手ながらも多少取り組むこともあり、運動を全くしないわけではありませんでした。
しかし、小学校では「体育=やらないもの(できないもの)」として、体の発達を促したりクラスメイトと一緒に体を動かす機会を逃し続け、さらにやらなくなるという負のループに陥ってしまっている状態でした。

◆②なぜ運動は発達障害児に必要なのか?
子どもの頃は体を動かすことが大事、というのは皆さん持っている認識だと思うのですが、脳科学的に言ってもそれは非常に正しいことです。
運動を司る脳の部位(運動野)は脳全体の発達の土台となるもの、例えて言うならば木の幹の部分です。
木の幹がしっかりと育っていなければ、枝も葉っぱもちろん育たないことになります。
発達障害児の脳はそれぞれの脳部位の発達に凸凹があるため、得意と苦手の差が大きく出てきますよね。
ここで苦手なところを育てるトレーニングをしても脳の土台である運動野がしっかりと育っていなければ、脳全体が育ちにくかったりアンバランスな育ち方になってしまいます。
逆に言うと、体を動かして運動野をしっかりと育てることで、枝葉が広がるように他の脳の部位、例えば言語の発達や感情面の発達も促されることに繋がるのです。
子どものあらゆる面の発達を促すためには、運動に対するハードルを下げることはとても重要なのです!
3.親の声かけと対応で、運動嫌いにさせず運動が楽しくなる!
◆①運動へのハードルを下げる親のたった一つの声掛け
ここで私は発達科学コミュニケーション(発コミュ)で運動が苦手な子どもに効く声かけを学び、取り入れていきました。
それは「真似して一緒にやってみよう」という声かけです。
運動が苦手な子には、やらせようとするのではなく「一緒にやってみよう」「真似してごらん」という声かけで子どもを運動へと誘うというものです。
大人が「こうやってやるんだよ」「ここに足をのせて次はここに手をかけて」などと言葉で説明もしながら実際に目の前で体の動きを見せてあげるのです。
体の使い方が不器用な子どもは、どうやって遊具を使っていいのか自分では分からないことがあるため、言葉で説明すると同時に動きも見せてあげたり、隣で一緒に手足の動きを合わせることが有効です。
自分一人ではやろうとは思わないけれど、お手本があったり一緒にやってくれる大人がいると取り掛かりのハードルが下がり、挑戦してみようかなという気持ちが沸き上がります。
これまでを振り返ってみると、運動をさせようと外に連れ出すものの、公園の遊具を「やってごらんよ、きっとできるよ。」と私自身は動かずに息子にやらせようとしていたことが多かったということに気付きました。
◆②アスペルガーの運動苦手な子におすすめの運動
これまで以上に、意識的に外遊びの予定を週末に入れるようにしていきました。
また、一緒に出かけて声を掛けるタイミングがある夫にも「一緒にやってみよう」「真似してごらん」の声かけを共有し、息子を誘うようにしてもらいました。
その際、親も一緒になって自然と体を動かせるような場所はどこか、という視点でもお出掛け先を決めるポイントにしていました。
公園ももちろんいいですが、遊具によっては大人は立ち入れないルールがあったり、狭すぎて大人には入れないような遊具、また子どもの発達段階ではまだ難しい遊具があるなど、公園選びも考慮しました。
おすすめは暑い時期によく行った簡単なハイキングコースやプール、川遊びなどです。
大人も一緒に活動でき、自然と触れ合うことで五感が刺激され、大人も子どももリフレッシュできる外出だと思います。

ここで忘れてはならないのが、「一緒にやってみよう」「真似してごらん」という声かけで運動へ誘ったあとの肯定の声かけです。
すかさず、「挑戦したね!」「前回はここまでだったのが、今回はここまでできるようになったね!」など、夫婦でほんのわずかな挑戦や成功も見逃さずに、肯定することを意識していきました。
すると少しずつできなかったことができるようになり、以前よりも色々な遊具や遊びに挑戦する姿が見られるようになりました。
このように過ごしながら小1の夏休みを終え、2学期がスタートしました。
すると驚くことに、1学期の間体育の授業に1度も参加しなかった息子が、なんと2学期からはすんなりと体育の授業に参加し出したのです。
そして、「やってみたら大丈夫だった!」という発言も出てきて、「僕、体育好きかも」と言うようにまでなったのです。
運動への取り掛かりのハードルを下げて、小さな挑戦・成功でも肯定し続けることで自信を取り戻し、意欲的になった結果だと思います。
ぜひ、「真似して一緒にやってみよう」の声かけをしてみてくださいね!
アスペルガー傾向の子どもに自信をつける仕掛けが満載です!
執筆者:菅美結
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)