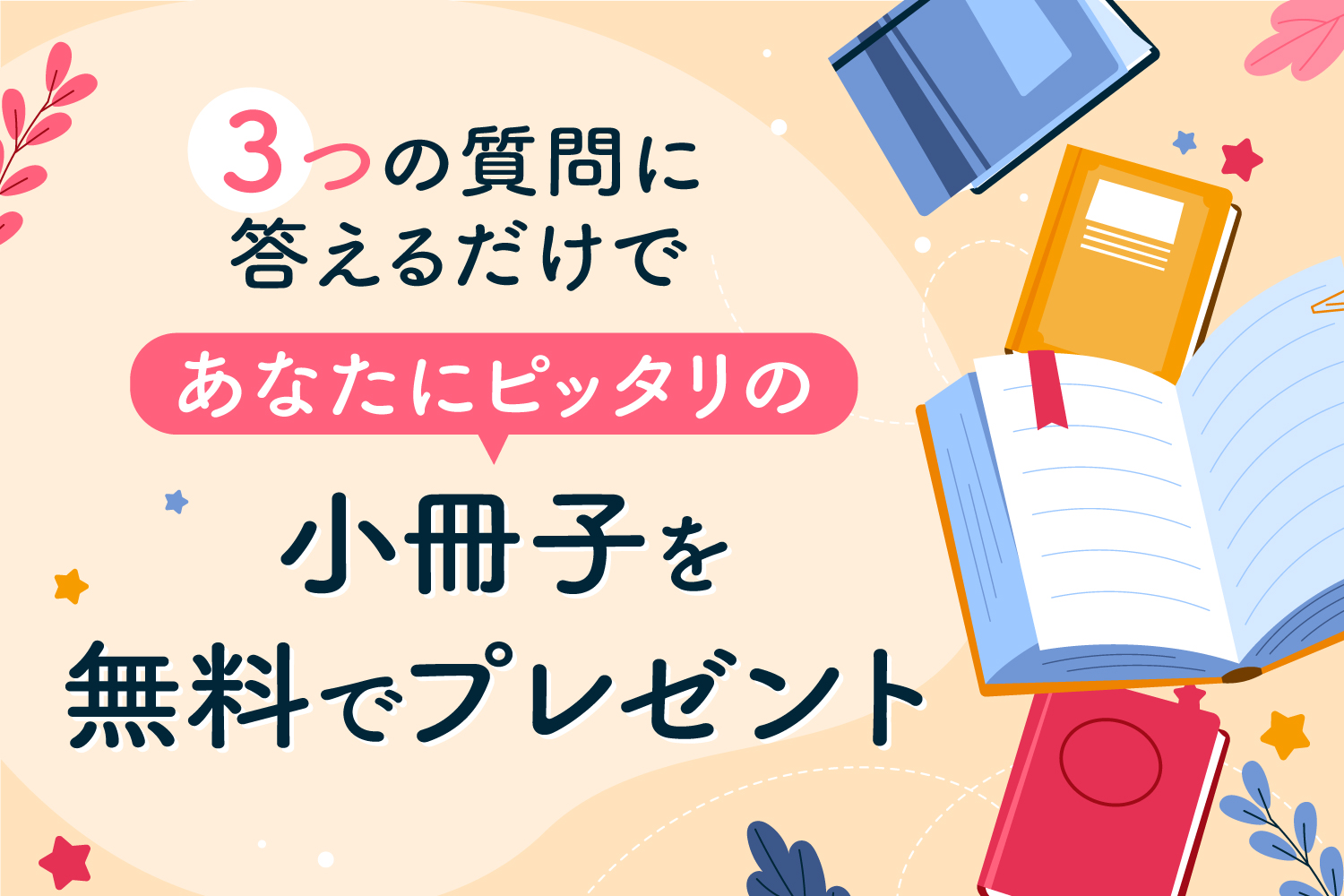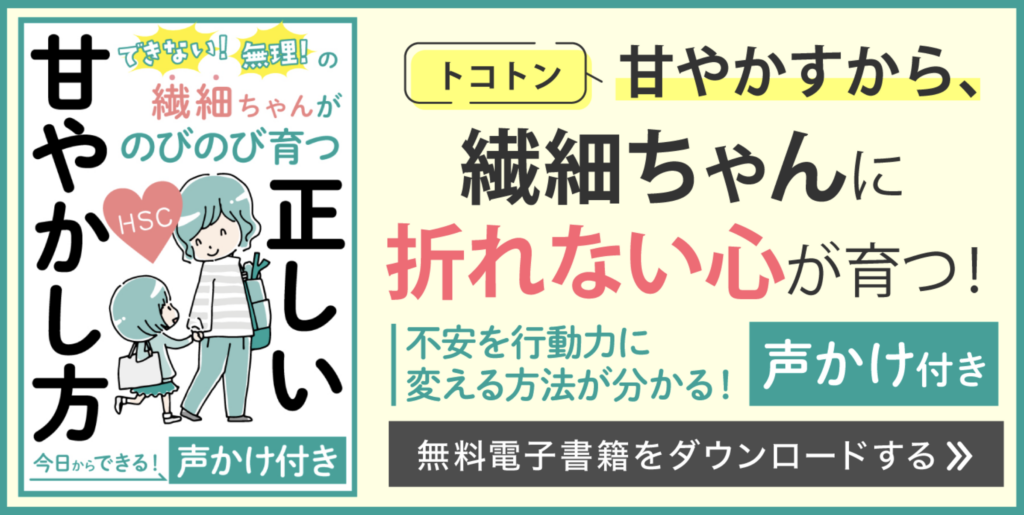「暇」と言いながら「めんどくさい」と動かない不登校の子どもはとても無気力に見えますが、その裏では動きたいけど動けない状況と闘っています。この記事では無気力の原因を紐解き、無気力を克服する3ステップをご紹介します。
【目次】
1.「暇だけどめんどくさい!」無気力に見える不登校児
2.無気力の原因は?「めんどくさい」に隠れた子どもの気持ち
3.無気力を克服する3ステップ
4.無気力を克服!やる気が回復してきた息子
1.「暇だけどめんどくさい!」無気力に見える不登校児
長引く不登校生活、ゲームやYouTubeに没頭しつくして 荒れていた気持ちが落ち着いてくると、ゲームやYouTubeの最中でさえも「暇!」と言い出します。
だったら他のことをすればいいのに、別の楽しめそうな活動を提案しても、一緒にやろうと誘っても「めんどくさい!」と言って動かない不登校の子どもはとても無気力に見えます。

暇だけど動くのがめんどくさいから学校に行けないのが不登校の子どもたちです。
勉強しない、外出しない、人と会わない、着替えもトイレもご飯を食べるのもめんどくさい!
ソファに辿り着いたら寝るまでそのまま、だらしない姿をしている子どもたちですが、彼らなりに動けない自分と闘っているのです。
この記事では、暇だけど動けない不登校の子どもが抱える「めんどくさい」の原因を紐解きながら、無気力を克服するコツを3ステップでお伝えしていきます。
2.無気力の原因は?「めんどくさい」に隠れた子どもの気持ち
暇なら簡単にこちらの誘いに乗ってくれそうなのに、どうして動けないのでしょうか?
不登校の子どもが無気力でなんでも「めんどくさい」と言ってしまうのには2つ理由があります。
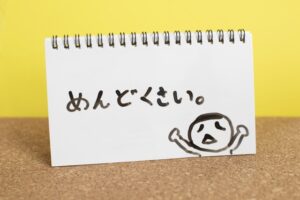
ひとつめはエネルギー不足。
これまで頑張りすぎてエネルギーを使い果たした状態が不登校です。
「暇」と言えるようになったのはちょっとエネルギーが回復してきた証拠。
けれども、自分から動くだけの量には達していない状態です。
ふたつめは不安を感じやすいこと。
いままでの失敗体験の積み重ねから、何をするにも不安を感じやすくなっています。
本人にもわからない、モヤモヤとした見えない不安を感じてしまうため、一歩踏み出せない状態です。

どうせまた失敗するし
やっても上手くできないし
だったら同じことやってる方が楽だし
エネルギー不足と不安の強さから、こんな思考が働いてしまいます。
ひとつひとつ言葉で説明する気力がなくて、全部ひっくるめて「めんどくさい!」
めんどくさいからママ手伝って!
無気力な姿の裏には不登校の子どもたちのこんな気持ちが隠れています。
3.無気力を克服する3ステップ
脳は行動することで発達します。「めんどくさい」を真に受けて行動のチャンスを逃すのは勿体ない!
チャンスを逃さず、無気力を克服して子どもが行動する3ステップのサポートをご紹介します。
◆STEP1:「めんどくさい」をスルー
まずは無気力な言葉に惑わされずスルーすることです。
「暇」が本心なので何かしたいけど自分を動かすエネルギーが足りていないだけ。
「そっか」「そう思うんだね」と一旦その気持ちを受け止めて、「めんどくさいからママ助けて」という無気力な言葉の裏に隠れている気持ちにフォーカスをします。

◆STEP2:行動のハードルを下げる
あとはやるだけの状態までにハードルを下げると、行動を邪魔する不安を和らげ、エネルギー不足を補うことができます。
なにか行動を始めるときは最もエネルギーが必要で、誰でもが「めんどくさい」と感じます。
私たち大人も座ってテレビを見てるときにインターフォンが鳴ったら立ち上がって応答するのを「めんどくさい」と感じることありますよね?
インターフォンの子機が手元にあったらすぐに応答できると思いませんか?
不登校で無気力な状態ならなおさら、やりたくても行動すること事態が「めんどくさい」のです。
トランプなら配ってやるだけの状態、工作なら道具を揃えてやるだけの状態、無気力でも動けるところまでハードルを下げます。
初めから最後までやり遂げるとこではなく、なにかひとつでも行動することが大事です。

◆STEP3:飽きさせない褒め
行動しはじめた後は、無気力な思考が戻ってこないようこまめに褒め続けます。
・「〇〇したね」「〇〇してるんだね」 とやっていることの実況中継
・「なに作ってるの?」 「何色使ってるの?」など興味を示す
・「〇〇までできたね」 できたところまでを確認する
・「じゃ、次は〇〇しよっか」 次の行動の提案
褒め=肯定の声掛けをその場に応じてに浴びせ続け、ひとつひとつの行動を成功体験の記憶にし、動き始めた行動に飽きないようにします。
行動し始めたことを褒める事から始まり、最後までできなくても、できたところまでを褒めて終わります。
4.無気力を克服!やる気が回復してきた息子
我が家の息子は小学2年生。小学1年生のゴールデンウイーク明け、しばらくしてから不登校となりました。
不登校になってからそれまで自分でやっていたこと、できていたことも「めんどくさい」と言ってやらず、ゲームとYouTubeに没頭していました。
半年ほどたったころ、飽きてきたのか大好きなYouTubeを観ていても、ゲームをしても「暇」と言うのでモノ作りが好きな息子に工作を提案してみました。
返って来たのは「え~、めんどくさい。ママ、携帯作って~」と無気力な発言。
私は「そっか!携帯作りたんだね!」と返事をし、作るものは決まっているんだなと受け取って、携帯作りに必要なものを準備してみました。
「ちょっと手伝って」とお願いをして、私が箱を押さえ、子どもに箱のサイズを紙に写してもらうと、さっきまでやる気なさそうにゴロゴロしていた子どもが勝手に動き出しました!

自分でハサミを持って紙を切ったり、使いたい色のペンを取りに行ったり、自分がイメージしている携帯の画面の絵を書き始めました。
「ハサミで切ってるね」「ペン取りに行ったね!」と実況中継をしたり「何かいてるの?」と興味を示す声掛けをしました。
「ちょっと失敗しちゃった」と自信なさそうに言ったときは
「四角の中に三角があるね」「色分けできてるね」「楽しそうにやってるね」とできていることを伝えました。
その後も自分でテープを出してきて貼り付けたりしていましたが、エネルギーの限界、飽きてしまったのか「後はやって!」と作業をやめてしまいました。
その時には「頑張ってここまでできたね」とできたことを伝え、残りの作業を私が引き受け、携帯を完成させることができました。
完成した携帯を見た息子は「これがねYouTube」「これがカメラ」と嬉しそうに完成した携帯の説明をしてくれました。
イメージしていたものができ上って達成感でいっぱいの息子にはさっきまでの無気力な姿はなく、久しぶりにイキイキとしていました。
その後、勢いがついた息子はその携帯を使って警察ごっこをして遊び始めました。
最後までできなくても大丈夫!何かひとつでも、行動したら、できたら、大人が言葉にして伝えることで成功体験の記憶になります。
この小さな積み重ねで、「暇」と言い出して半年経った今では無気力を克服し、スキーにチャレンジするまでになりました。

引きこもりがちな不登校生活、動き出すきっかけを逃さず活動量を増やしていきたいですよね。
「めんどくさい」の裏側には子どものメッセージが隠れています。無気力を克服する3ステップ、試してみてくださいね。
不登校でも迷わないママのマインドお届けしています
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
育てにくい子が3ヶ月で変わる!
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
↓↓↓
執筆者:福原かおり
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)