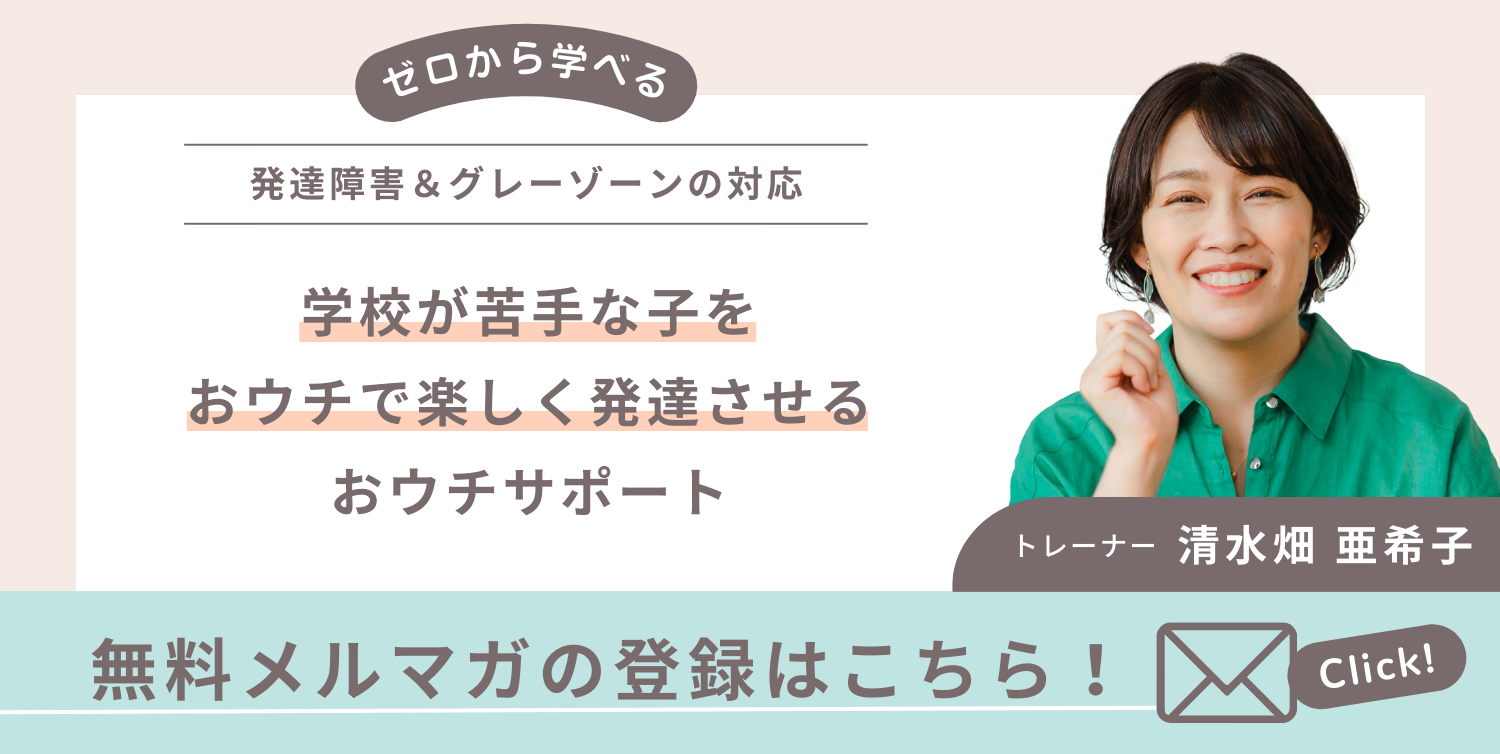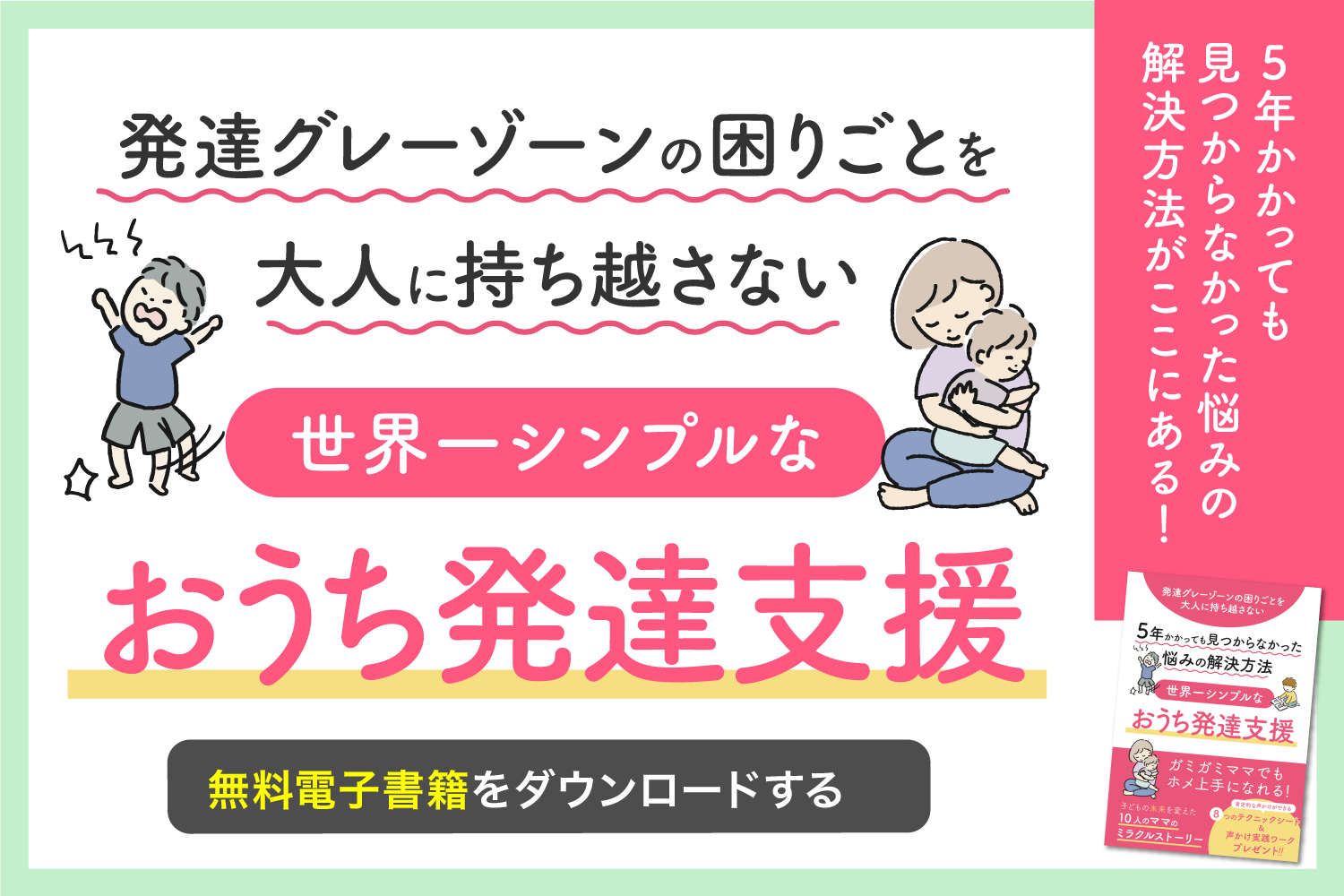| 不登校の小学生の家での過ごし方で気になるのは、ゲーム・YouTubeですよね!依存症にならないか心配な方もおられると思いますが、ゲーム・YouTubeは使い方次第ですよ!上手く活用して楽しく脳を伸ばす方法をお伝えしますね。 |
【目次】
1. 不登校小学生の家での過ごし方に悩んでいませんか?
2. ゲームをやめさせるより大事なこと
3. ゲーム・YouTubeの賢い活用法
4. おすすめゲーム3選
①◯◯を言ったら負けだよゲーム
②目隠し鬼ごっこ
③料理音痴クッキング
5.ゲームやYouTubeを受け入れると、新たな希望がみえてきます!
1.不登校小学生の家での過ごし方に悩んでいませんか?
子どもが不登校になり家で過ごす時間が増えてくると同時に訪れるお悩みが、ゲーム・YouTube問題ですよね。
ゆっくりと休ませてあげようと思う一方、ゲームしかしない子どもを見ていると、どうしてもイライラしてしまうママも多いのではないでしょうか。
ゲーム・YouTube依存にならないかも不安になりますよね。
・勉強が遅れないように、家で勉強してほしい。
・せめて、お手伝いくらいしてほしい。
・このまま、引きこもりになってしまうのでは…
と、心配にもなりますよね。
私の息子は当時、小学4年生の頃に不登校になりました。
休み始めた当初は二次障害にもなっており、家の中ではうずくまるような生活をしていました。
ただボーッとYouTubeを再生して動かないような状態でしたので、好きな事だけをさせてあげたいと思い見守りつつも、なるべく一人で黙々とさせないように気をつけていました。
しかしYouTubeを見ている時間がかなり長く、依存症にならないか本当に心配でした。
学校を休ませた方が良いというものの、休ませたところでいったいどう過ごしたらいいの?
結局ゲーム・YouTube・テレビばかりの子ども、どうやって接すればいいの?
イライラや不安、焦りを感じてはいませんか?

2.ゲームをやめさせるより大事なこと
不登校の小学生が家でゲームばかりする!ゲーム・YouTubeをどうやって制限しようかと考えられているママは多いと思います。
しかし不登校、ましては二次障害にもなっている子どもは、まず心の元気を取り戻すことが最優先です。
心のよりどころであるゲームを制限することは、子どもを追い込んでしまい兼ねません。
子どもの元気を取り戻し自信を回復させるためは、まずできていることを褒めて自己肯定感を高める事です。
YouTube を見ているのであれば
「それ、面白いねぇ。」
「そのユーチューバー誰?」
「難しそうな動画だね。よく理解できるなぁ。」
などと、YouTube を見ている子どもに関心を向けて話しかけるようにします。
興味関心を向けられることでも自己肯定感アップにつながりますよ。
きっと目をキラキラさせて、動画の内容について説明してくれるはずです。
不登校で勉強が遅れてしまうことよりも、まずは子どもの元気を取り戻すことに注目して下さいね。
このように、楽しみながら脳の発達を促していれば後々勉強する気力が出た時にも役立ちますよ!

3.ゲーム・YouTubeの賢い活用法
それでは、我が家で実践したゲーム・YouTubeの活用法をお伝えしますね。
まず子どもが見ているゲームやYouTubeに興味関心を持つようにします。
そして一緒に見ながら会話します。共感したり、質問したり、一緒に笑ったり… 「これすごいね!おもしろいね!」 「あれについて調べよう!」 「こんな情報見つけたからやってみよう!」
ただボーッと見ているのではなく、バランスボールで跳ねながら見たり工作をしながら見たりする中で、徐々に主体的に自分で考えて行動するようになりました。
気が付けば、息子にとってYouTubeは教科書の代わりのようになっていました。
そして息子が「このゲーム面白いんだよ!みんなでやりたいなぁ」と提案するようになりました。
ゲームを家族全員で楽しむようになり、 家族という安心感のある中で、息子は楽しく生き生き過ごせる時間が増えていきました。こうして息子自身も徐々に元気を取り戻しました。

4.おすすめゲーム3選
次に、我が家でやってみて楽しかったゲームを紹介します。ゲームは悪と思われがちですが、脳の発達に良いゲームもありますよ!
◆①◯◯を言ったら負けだよゲーム
参加者は2名以上。それぞれに「言ったら負けワード」を決めて、ワードを書いた紙をおでこや頭に貼りつけます。
自分につけられたワードは見てはいけません。相手の「言ったら負けワード」を言わせたら勝ちです。
相手の「言ったら負けワード」を言わせるために、「どんな話題なら言っちゃうかな?」と推測する力が必要です。
また、逆に相手からの質問に対して、「自分の言ったら負けワードはこれかな?」と考えて言わないようにするという行動を抑制する力も必要となります。
なんどもやっていくうちに話術が巧みになっていき、相手を負かすことができるようになっていきます。
◆②目隠し鬼ごっこ
鬼役の人は、目隠しをしてゲームに参加します。
鬼は視覚が使えない状態なので、聴覚や触覚を働かせて他の人達を探していきます。
周りの障害物にぶつからないように歩き、声や気配のする方向へ注意を向けなければならないので、とても集中力を使います。
へっぴり腰で探し回るその慎重な様子を、周りの人達で見るのが面白いですよ。
◆③料理音痴クッキング
メニューを決めるグループ、料理をするグループに分かれます。
メニューは外国の料理など、子どもも大人も知らない、または作り方がわからないメニューの方が楽しいです。
例えば、ビーフストロガノフ、ラープガイ(タイ料理で、鶏ひき肉のサラダ)など。
全く料理のしないお子さんやお父さんが作る場合、身近な料理などでも良いですね。
材料も作り方もわからないので、メニューの名前から想像して作っていきます。 料理という作業はワーキングメモリー(手続き記憶)という、同時に複数の作業をするときに必要な脳の機能を大いに使います。
楽しいだけではなく、脳にもいい影響を与えるのでぜひやってみてください。
これら3つのゲーム以外にも、子どもとやりたいゲームを探すのも楽しいですよ

5.ゲームやYouTubeを受け入れると、新たな希望がみえてきます!
いかがでしょうか?親子で一緒に楽しめればYou Tube も意外と悪くないと思いませんか?
私はゲーム・YouTubeを否定せずに肯定し、ゲーム・YouTubeを家族で楽しむことで、息子の自己肯定感を増やすことができました。
息子は自分が苦手なことを言葉で伝えられるようになり、何が負担で不登校になったのかを知ることができました。
そして好きな活動を通し興味の幅が広くなり、また以前のように友達とも交流を持つことができるようになりました。
一度は辞めてしまったスポーツを再び始めたりと意欲的にチャレンジする行動が増えてきました。
ギフテッド傾向で、読み書きが苦手な中学2年生になった長男は、現在オンライン通学をしています。自分のペースで学び、学校のシステムにとらわれないスタイルはとても息子に合っていると感じています。
不登校という、マイナスにも思える長い時間をプラスに考え、家庭でしっかりサポートすることで不登校前よりも大きく成長できたと思います。
不登校になってから3年がたちますが、YouTubeをひたすら見ていたおかげで動画作りにも詳しくなりました。
英語のゲーム実況や映画を見て英語を自ら勉強するようになりました。
不登校の小学生も家での過ごし方次第で、大きく成長できます。
ゲーム・YouTubeを否定するのではなく、上手く活用することで得意なことに磨きをかける時期がやってきていますよ。

こちらの記事では、起立性調節障害によって不登校となった現役大学生が、不登校の頃のメディアの必要性を語ってくれています。
こちらもご覧ください。YouTubeを使った子どもの記憶力の鍛え方がわかります!
不登校の子どもの将来に悩んだら…元不登校の家庭教師さんが大学受験について教えてくれますよ!
▼YouTubeをやめさせたい!と思うママへ、発コミュトレーナーが動画で解説しています▼
▼YouTube活用法が分かります!▼
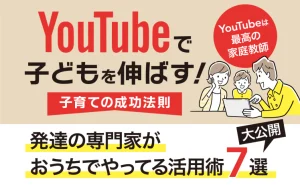
不登校で学校に行かなくても、お家でお母さんと会話するだけで発達を伸ばすことのできる情報をまだまだお届けします!
執筆者:すずき真菜
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)