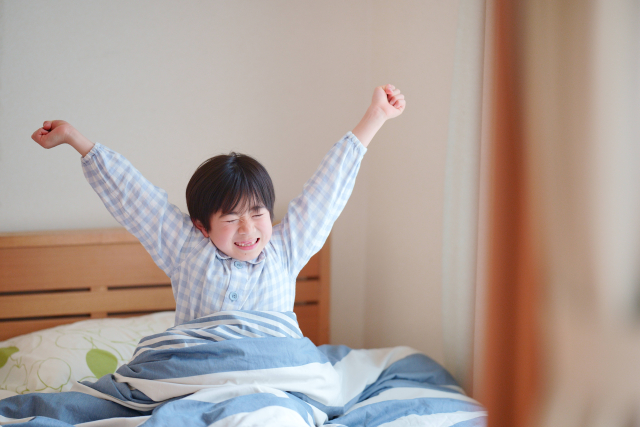高学年の子どもが朝起きないのは、脳や体の仕組みの問題かもしれません。小学生のうちに「朝起きない子どもの起こし方」を知って早起き習慣をつけると、思春期の起立性調節障害の予防にも。この記事では原因と具体的な習慣づけを紹介します。
【目次】
1.小6の子どもが朝起きないのはわがまま?小学生のうちに解決したい理由
2.小学生がスッキリ起きれないのはなぜ?隠れている3つの原因
①低覚醒とは? ― 朝なのに脳がまだ眠っている状態
②セロトニン不足が関係している?
③起立性調節障害の予兆かも?
3.小6の朝スッキリ起きれない子対策!わが家で成功した早起き習慣“1ルール”
4.まとめ|朝起きない小学生でも習慣づけで変われる!
1.小6の子どもが朝起きないのはわがまま?小学生のうちに解決したい理由
「子どもが朝起きない」のは“怠け”や“わがまま”ではありません。
とはいえ、毎朝小学生の子どもが「朝起きない」「起こしても布団から出てこない」と、ママもイライラしてしまいますよね。
子どもが朝起きないのはわがままではなく脳や体の仕組みが関係していて、放っておくと思春期に起立性調節障害につながることがあります。
だからこそ、小学生のうちに「自分でスッキリ起きられる習慣」をつけておくことが大切です。

わが家の娘も以前は毎朝ゴロゴロ…。何度起こしても布団から出られず、私も叱ってばかりでした。
ところがちょっとした工夫を取り入れたことで、今では 朝5時半に自分で起きてくる子に変わったのです。
この記事では――
・小学生が朝起きない原因
・なぜ今、解決しておきたいのか
・わが家で成功した“早起き習慣”の作り方
をわかりやすく紹介します。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.小学生がスッキリ起きれないのはなぜ?隠れている3つの原因
小学生が朝起きない背景には「低覚醒・セロトニン不足・起立性調節障害」など、脳や体の仕組みが関わっています。
単なる“甘え”と片づけてしまうと、子どもの困りごとを見逃してしまうことも。
ここでは3つの原因を解説します。

◆①低覚醒とは? ― 脳がまだ眠っている状態
朝なのに動き出せない、頭がぼーっとしている…。
これは「低覚醒」と呼ばれる状態です。
脳のスイッチがまだ入っていないため、支度が遅れたり、学校でも集中しにくかったりします。
落ち着きがないように見えることもあり、先生から注意を受ける子も少なくありません。
◆②セロトニン不足が関係している?
子どもの低覚醒の大きな要因のひとつが「セロトニン不足」です。
セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、脳をシャキッとさせる働きがあります。
ところが――
・朝の光を浴びる機会が少ない
・ストレスが強い
・運動不足
などで分泌が減り、頭がなかなか切り替わらないのです。
その結果「ずっとイライラしている」「朝から元気が出ない」といった不調が見られることもあります。
◆③起立性調節障害の予兆かも?
さらに注意したいのが「起立性調節障害(OD)」です。
自律神経のバランスが崩れることで、
・朝なかなか起きられない
・立ちくらみや頭痛がする
・午前中に調子が出ない
といった症状が起こります。
特に思春期に多いのですが、朝が苦手な小学生もリスクが高め。
だからこそ 小学生のうちに生活リズムを整えることが、予防にもつながるのです。
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.小6の朝スッキリ起きれない子対策!わが家で成功した早起き習慣“1ルール”
何度起こしても子どもが起きてこない。
そんな子でも「好きなこと」「やりたいこと」なら脳が働き、自然とスイッチが入るのです。
そこでわが家で導入したのが――
「朝6時半までは自由時間!」という1ルール。

このシンプルなルールで、起こしても起きなかった娘が、朝5時半に自分で布団から出てくるようになりました。
◆わが家で効果のあった3つの工夫
・自由時間はゲームもOK!何時までか決める(ダラダラ防止)
・やめる時間になったら次の活動を用意しておく(行動の切り替えがスムーズ)
・やめられたら「やめられたね!」と肯定する(セロトニンが分泌され気分安定)
目的は「早起き習慣」をつけること。
多少時間が過ぎても「やめられたこと」を本人に伝え続けました。
小さな成功体験を積んだことで、娘は自分で「次はどうする?」と自然に行動を切り替えるようになったのです。
◆さらにプラス!朝のスイッチを入れる工夫
朝起きても、自由時間が終わってからボーっとする時間を作ると行動が止まるので、次の活動は楽しいものにします。
・好きな朝ごはんを出す
・みそ汁の味見をしてもらう
・卵を焼いてもらう
「やってみたい!」「できた!」という体験は子どもの自己効力感を高め、さらに朝起きやすい好循環を作ります。
結果、娘は夜9時には自然と眠くなり、翌朝もスッと起きられるようになりました。
私自身も一緒に早寝早起きができ、自分時間を取り戻せたのです。
「今日も早起きだね~」「お母さんもね~」と笑顔で交わす言葉が、わが家の朝を穏やかにしてくれました。
4.まとめ|朝起きない小学生でも習慣づけで変われる
子どもが朝起きないのは怠けではなく、脳や体の仕組みが関係しています。
・低覚醒
・セロトニン不足
・起立性調節障害
といった要因を理解し、早めに対応することが大切です。

わが家のように「朝は好きなことからスタート」「褒めて終わらせる」だけでも効果があります。
まずはママ自身も 朝は自分の好きなことからスタートしてみてくださいね。
子どもと一緒に笑顔で迎える朝が、家族の一日をきっと変えてくれます。
低覚醒についてわかりやすく動画で説明しています▼▼
小学生の子どもが朝起きないことについてのよくある質問(FAQ)
Q1:小学生が朝起きないのはなぜ?
A1:小学生が朝起きない背景には、低覚醒・セロトニン不足・起立性調節障害など、脳や体の仕組みが関係しています。単なるわがままではなく、体がまだ“朝モード”に切り替わっていないことが多いのです。
詳しくは 発達障害の子どもの「朝起きられない」を解決!サッと目覚めるコツとは を参照。
Q2:小学生の理想の睡眠時間は?
A2:文部科学省の推奨では、小学生は 9〜11時間程度の睡眠が理想とされています。十分な睡眠をとることで、朝の目覚めや日中の集中力が安定しやすくなります。
Q3:朝起きない子どもの起こし方は?
A3:“朝6時半までは自由時間”など、子どもが楽しみにできるルールを作るのがおすすめです。やる気スイッチが入り、自然と行動がスムーズになります。
具体例は “習慣化大作戦! をどうぞ。
子育ての常識が変われば、ママの毎日も子どもの未来も変わります!オンライン子育て塾開催中!
↓↓↓
↓↓↓
▽ご登録はこちらから▽
起こしても起きない!そんな子への根本対応を知りたい方はこちらから▼▼
執筆者:本田ひかり
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)