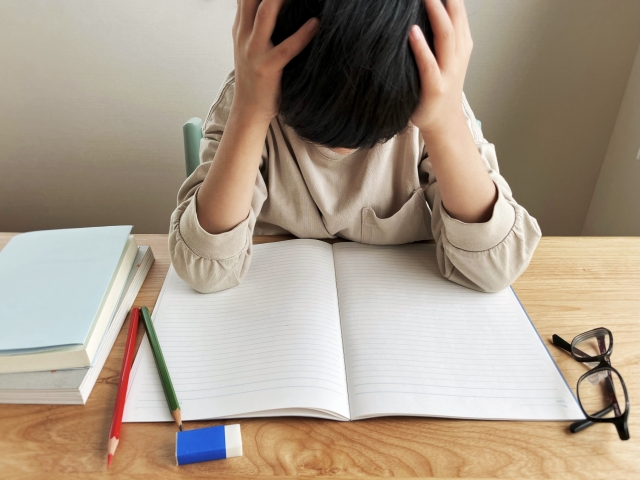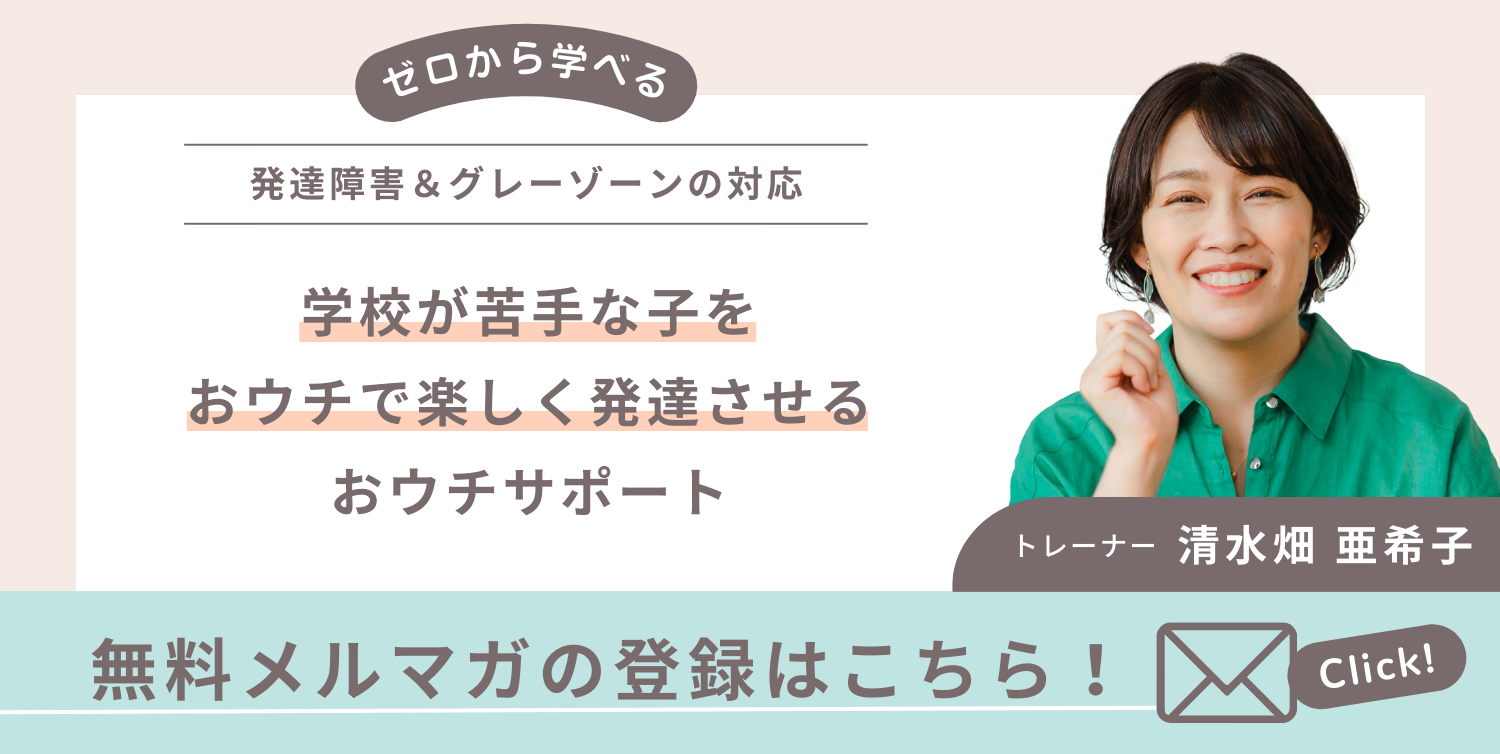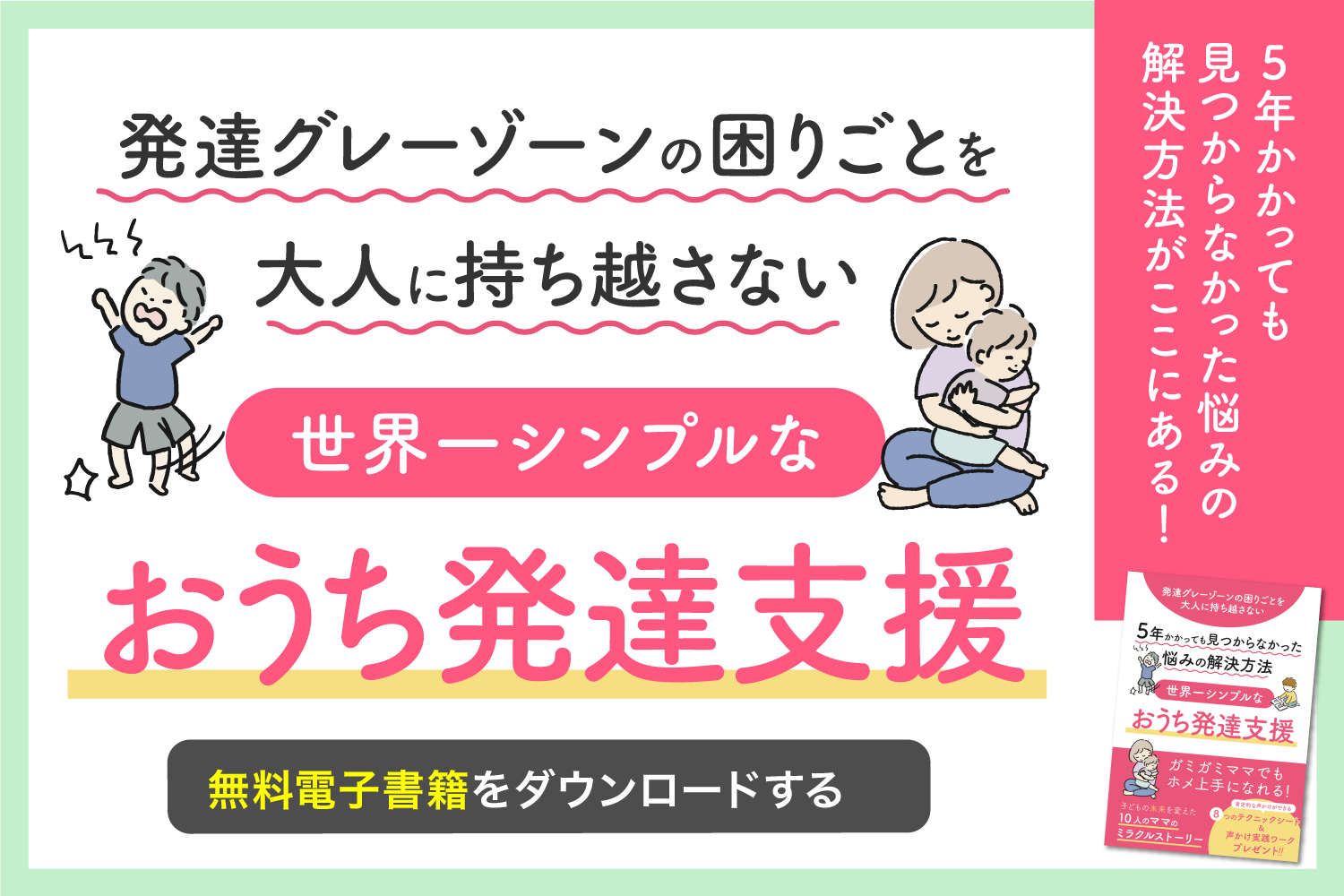| 「うちの子どうしてノートを取らないんだろう。」とお困りではありませんか?発達障害・学習障害グレーゾーンのお子さんの勉強の苦手さは不器用さからきています。お子さんの勉強嫌いをこじらせないために、親が意識すべき接し方をお伝えします! |
【目次】
1.ノートを取らない発達障害の子どもの様子にお困りではありませんか?
2.発達障害グレーゾーンの勉強が苦手な子の3つのタイプ
◆タイプ1:見るチカラに苦手があるタイプ
◆タイプ2:書く作業な苦手なタイプ
◆タイプ3:情報を整理できずに結果的にアウトプットが雑になる(ワーキングメモリの弱さ)
3.勉強の苦手が気になった時の対応方法
①先生のサポートをお願いする
②その子に合った苦手をカバーする環境を整えてあげる
4.勉強が苦手な子の困りごとをこじらせないために最も重要なこととは?
1.ノートを取らない発達障害の子どもの様子にお困りではありませんか?
お子さんがノートを取らない、取っていたとしても字がぐちゃぐちゃ。
勉強にもついていけていないようだし、どうすればいいんだろうとお困りではありませんか?
実はママから寄せられる「勉強の苦手」の相談の中で多いものの1つが
「字が汚い」
「ノートを綺麗に書かない」
という不器用さのお悩みなんです。

そんな不器用さのある発達障害・グレーゾーンの子ども達は、みんなが当たり前にできていることに苦手があるので、授業についていくのが必死です。
そのため最初は頑張っているものの、どんどんまわりとの差を感じて「自分はこんなこともできないなんて、もうダメだ。」と自信ややる気をなくしている可能性があるんです。
そんな不器用さを理解してあげて、支援してあげることで子どもたちは勉強する力をどんどん発揮してくれます。
ご自分のお子さんのタイプを理解することでママ自身もイライラせずに対応できますよ。
2.発達障害グレーゾーンの勉強が苦手な子の3つのタイプ
それでは不器用さのタイプ別に解説をしていきたいと思います。
◆タイプ1:見るチカラに苦手があるタイプ
例)字や数字の形を覚えるのが苦手
例)字が枠からはみ出してしまう
文字の形を見て覚えること、空間や枠を把握するチカラに苦手さがあったり、焦点を移す”目の動き”に苦手さがあったりします。
目の動きに苦手さがあると、板書(黒板とノートを交互に見ること)が不得意になることもあります。
◆タイプ2:書く作業が苦手なタイプ
例)揃えて文字を書くのが苦手
例)筆圧の調整が難しい
このようなタイプのお子さんは、手を使うこと自体に苦手さがあります。
体の動きの中でも「微細運動」(指先などの細かい動き) が苦手なタイプは、学習時の動作にも苦手さが出ることがあります。
◆タイプ3:情報を整理できずに結果的にアウトプットが雑になる(ワーキングメモリの弱さ)
例)板書が苦手
ワーキングメモリとは一時的に情報を記憶したり、整理する脳の働きのことです。
例えば、板書なら黒板を見る、一時的に記憶する、頭で整理して、ノートに書く、この一連の流れを行うのですが、こういった複数の処理を同時に行うのが苦手なので、結果的にノートをグチャっと書いてしまう。
つまり、ワーキングメモリ(作動記憶)が弱いと、聞きながら書く、読みながら意味を考える、など一度に複数の処理をすることに対して苦手さがでてきます。

グレーゾーンのお子さんの書くことの不器用さには、こういった様々な要因が影響しています。
話をさせたら流暢に話すのに書かせると雑。こんな様子をみた大人は「やればできるのにやらない」「努力不足」と勘違いして、子どもを叱ったり注意したりしがちです。
そんな時こそ得意なこと、できていることを活用して学習することを考えてみてほしいのです。
3.勉強の苦手が気になった時の対応方法
それでは実際にこんな困りごとを抱えているお子さんにはどのように対応すればいいでしょうか?
◆①先生のサポートをお願いする
先生に個別の支援をお願いすることでサポートしてくれる先生を手配してもらったり、個別対応を先生に理解していただくだけでも本人の負担は減っていきます。
・読むことに苦手がないのであれば、黒板の読み上げ係に徹してもらいノートは加配の先生に書いてもらう。
などサポートの先生がついてくれる場合は苦手なところを代行してやってもらったり、手伝ってもらったりすることができます。
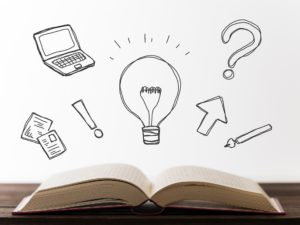
◆②その子に合った苦手をカバーする環境を整えてあげる
・タブレットなどの端末を利用して書かずにノート代わりに記録を取れるように交渉する。
・書くのに時間がかかるのであれば昼休みにゆっくり書いたり、別にプリントをもらったりと書かなくてもいい方法を考える。
・枠の中におさめて適切なサイズの文字を書けない子でも大きい文字がかけるならマス目の大きめのノートを用意してあげる。
というようにその子にあった道具や環境を整えてあげるのも一つの方法です。
苦手な部分をカバーする方法を検討するときには今できているところを有効に使うということに重点を置いて環境を整えてあげましょう。
4.勉強が苦手な子の困りごとをこじらせないために最も重要なこととは?
上記の例のように学校の理解、協力を得られればラッキーです。とてもラッキーです!ですが現実の学校生活はそう甘くありません。
「●●君だけ特別扱いをすることはできません」
「やる気がない子にはそういったサポートはできません」
中学に上がれば 「教科ごとに担当が違うのでそういった対応は無理です」
などなど、個別対応を拒否する先生もいらっしゃいます。
しかし、先生は「学級全体をいかにスムーズに運営するか」 これが最重要事項なのでそれって当然なのです。
発達支援の知識を持っている先生もまだまだ少ないですし、どう対応していいかもわからない。
それまで学んできた「集団で子どもたちをみる」というやり方を変えるのが難しいのでグレーゾーンの子どもたちを、集団の中へなんとか収めようとしたくなるのです。
だからこそお母さんがしっかり知識をもって学校の先生を「育てていく」コミュニケーションをとってほしいのです。
先生にお子さんのことを理解していただくために、お子さんについての詳しい情報を伝えましょう。
例えば
得意・不得意
好きなこと・嫌いなこと
お子さんの特性や、感覚の過敏性の有無
また、日頃のお子さんとのコミュニケーションの中で見つけた関わり方のヒントなどについてお伝えいただくといいですね。

万が一、先生が協力してくれなくても家での対応を整えておけば安心です。
学習のこと、成績のこと、学校のこと、となるとつい学校ばかりを頼りにしたくなりますが、実は「学校」だけでなく「家」での対応を整えておきましょう。
その対応を誤らなければ、子どもたちが今よりも勉強嫌いや、困りごとをこじらせるリスクは減ります。
先ほどお伝えしたようにその子の苦手をカバーできるiPadや教育アプリなどを活用し、先生にお子さんについての詳しい情報をお伝えしていくこと。
学校と家庭の連携がとれるような環境を整え学習への意欲を失わせないこと。
学年が上がればあがるほどこれを意識して接してほしいと思います。
▼勉強嫌いなお子さんへの対応はこちらで一気読みできます!▼
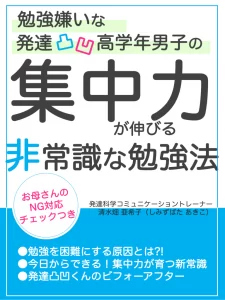
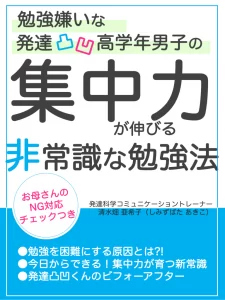
発達障害グレーゾーンの勉強が苦手な子の勉強嫌いをこじらせない対応をお伝えします!
執筆者:清水畑亜希子
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)