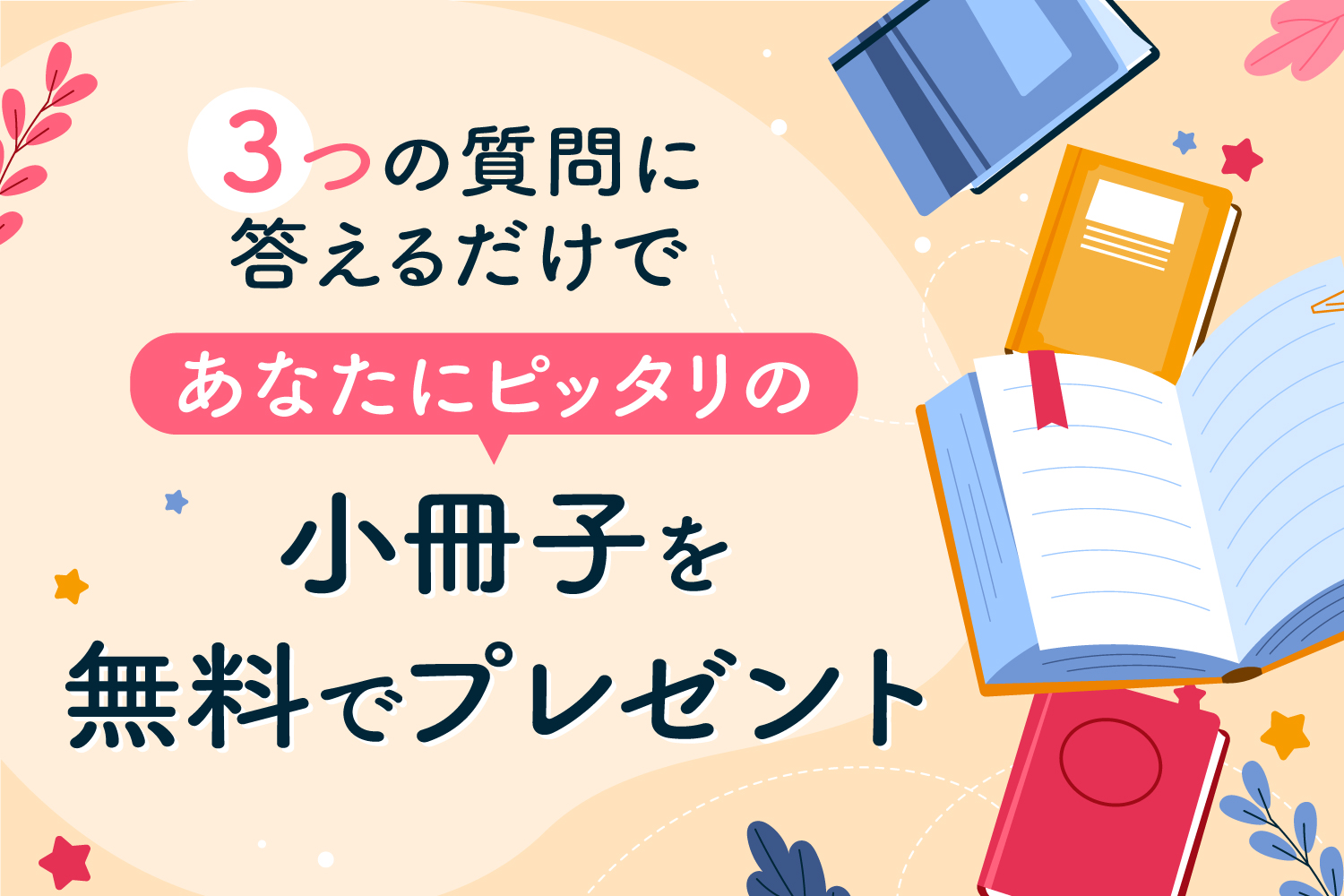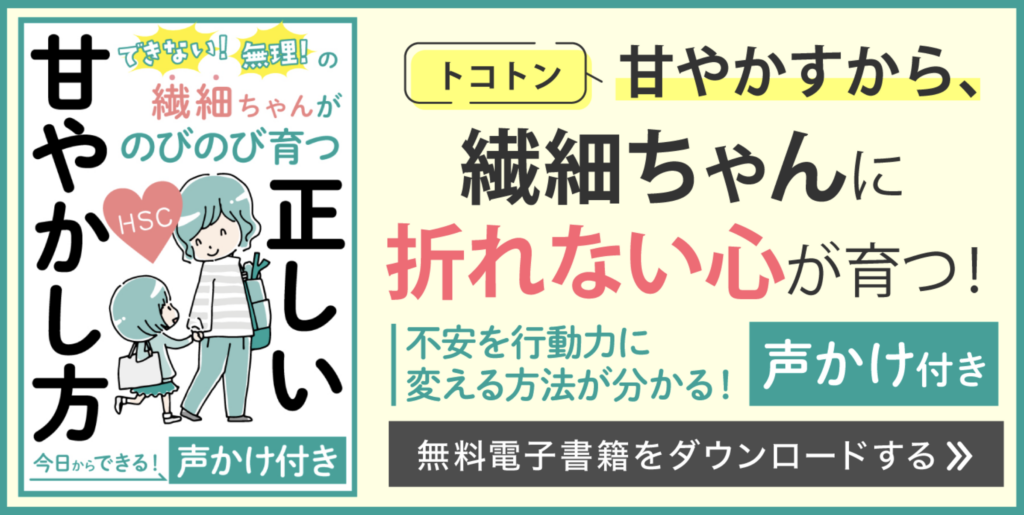|
感覚過敏があるASDの子は、触られるのが嫌いで抱っこを嫌がる子もいますよね。スキンシップは大事だと思う一方、上手くできず悩んではいませんか?そこで感覚過敏がある発達障害の子の脳を育てる、親子で楽しむスキンシップ方法についてをお伝えします。 |
【目次】
1.触られるのが嫌い!抱っこ嫌がる!ASD感覚過敏の子に悩んでいませんか?
2.親子のスキンシップが大事なワケ
3.スキンシップがASDっ子の感情脳を育てる!?
4.感覚過敏ASD、触られるのが嫌いな子とのスキンシップ方法
1.触られるのが嫌い!抱っこ嫌がる!ASD感覚過敏の子に悩んでいませんか?
「親子のスキンシップって、とてもいいんですよ!」
こんな言葉を一度は耳にしたことがありますよね。
それではお子さんとスキンシップはとれていますでしょうか?
発達障害ASDの子の脳の発達には欠かせないスキンシップですが、
・スキンシップってどうやってとればいいの?
・スキンシップをとりたいけど、触られるのが嫌い!
・抱っこも嫌がる子だから…
などと悩まれているママも多いのではないでしょうか。
ASDタイプの子には感覚過敏があり、抱っこを嫌がる、触られるのが嫌いな子がいます。
他にも、音、光や色、味覚、温度や湿度などに独特で過剰な敏感さがある子もいます。
脳の感覚のエリアが未熟でうまく処理できていないために、過敏な反応、または鈍感な反応として現れています。
脳の発達が進むにつれて、だんだん改善される場合もあります。
しかしこうした感覚の過敏さは、周囲の人や家族にも気づかれにくく、その苦痛が理解されにくかったり、過小評価されてしまうことが多いです。
そして日々ストレスを抱えている子も多いのが現状です。このような感覚過敏は生活のしにくさと直結してしまいます。

実は私の娘も小さい頃から、抱っこを嫌がる、音に敏感で耳をふさぐなどの感覚過敏がありました。
大好きな娘とスキンシップを楽しみたいと思うのですが、抱っこを嫌がる子を無理矢理抱きしめることもできず、寂しく感じることもありました。
\画像をクリック!/
今の子育てのお悩み、解決します
今の子育てのお悩み、解決します
↓↓
2.親子のスキンシップが大事なワケ
一方発達障害の子に関わらず、スキンシップには沢山の効果がありますね。
肌と肌が触れ合うことで安心感が得られるのは、大人も子どももちろん同じです。
実はスキンシップをとることで身体の中では、オキシトシンという「幸せホルモン」が分泌さ ています。
この幸せホルモン”オキシトシン”には、次のような効果があります。
・幸福感を感じる
・ストレス低下
・痛みや緊張の軽減
・愛情や信頼の形成
このオキシトシンの分泌を促すための一番手軽で効果的な方法が、実は親子のスキンシップです。
人間の五感には発達の順序があります。その中でも触覚は一番最初に発達し、老後も一番最後まで衰えないと言われています。
触覚、つまり”肌で感じること”は人間の一生を通してとても重要で、ある意味原始的で、動物的なコミュニケーションなのかもしれませんね。

3.親子のスキンシップがASDっ子の感情脳を育てる!?
発達障害、特にASDのお子さんは、感情の脳の発達がゆっくりな場合があります。
感情の脳の発達がゆっくりだと、喜怒哀楽などの感情を表現するのが苦手なので、キレやすい、空気が読めないなど、うまく人間関係が築けない場合があります。
その結果、集団が苦手、人嫌いなど、学校でのお友達トラブルにつながってしまいます。
私の娘もASDタイプで、実年齢に比べて情緒が幼く、感情の脳の発達がゆっくりだと感じていました。
実は感情の脳の発達がゆっくりで、気持ちが不安定になりやすいお子さんも、スキンシップを通して脳を発達させることで情緒が落ち着き、学校でのお友達トラブルも減らすことができるのですよ。
なぜなら脳の中にある感情を司る部分は、皮膚からの刺激との関連が深いことがわかっているからです。
そしてこの部分は、一生かけて発達していく部分なのでお子さんが何歳からでも、いくらでも発達させることができるのです。

繊細ちゃんに折れない心が育つ!
正しい甘やかし方がわかります
↓↓↓
正しい甘やかし方がわかります
↓↓↓
4.感覚過敏ASD、触られるのが嫌いな子とのスキンシップ方法
感情の脳を発達させられるのなら、スキンシップを積極的に取り入れたい!と思いますよね。
しかしいくらスキンシップがいいからといって、抱っこを嫌がる、触られるのが嫌いな感覚過敏があるASDの子を無理に抱きしめることはできません。
ストレスにならないよう工夫する必要があります。
なぜならせっかくのスキンシップも、お子さんが不快に感じてしまっていてはオキシトシンが分泌されることもなく、逆にストレスになってしまうからです。
身体のどこなら嫌じゃないのか、どんな触り方なら大丈夫なのかをよく観察してみましょう。
オススメは「手を動かす触り方」ではなく「圧をかける触り方」です。
背中を少し強めにゆっくり上から下に動かすなど、優しく触るより少し強めで圧をかけるのがポイントです。
ASDの子は特に圧迫されることで落ち着く子もいます。
ギューっと少しずつ圧をかけていくマッサージもオススメです。 娘も脚をマッサージされると喜びます。
特にマッサージには、される側はもちろん、する側にもオキシトシンが出るのでリラックス効果が期待できます。
子どもが大きくなって抱っこができなくなっても取り入れやすいスキンシップになります。
しかしマッサージってする側は結構大変ですよね。
子どもが横になっている状態で、その上に乗っかるようにして圧をかけると楽ですよ。

スキンシップは、お互いが触れたい!と思っていることが重要なので、無理せずに行ってくださいね。
時間がない時は、朝子どもを起こすときなどの短い時間でも効果がありますよ。
どうしても触れられないという方も安心して下さい。
実は幸せホルモン”オキシトシン”はスキンシップだけでなく、「優しい声かけ」など 相手への思いやりでも出ると言われているのです。
お子さんが思春期や青年期になっても、日常的にポジティブな会話をすることで心のスキンシップをとり続けていきたいですね。
▼ストレスを感じやすい子への対応はこちら▼
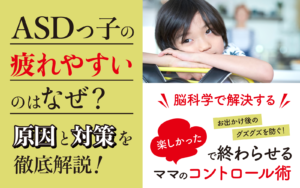
親子関係をよくするコミュニケーション方法を詳しく解説しています!
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
育てにくい子が3ヶ月で変わる!
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
↓↓↓
執筆者:永作瑛里
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)