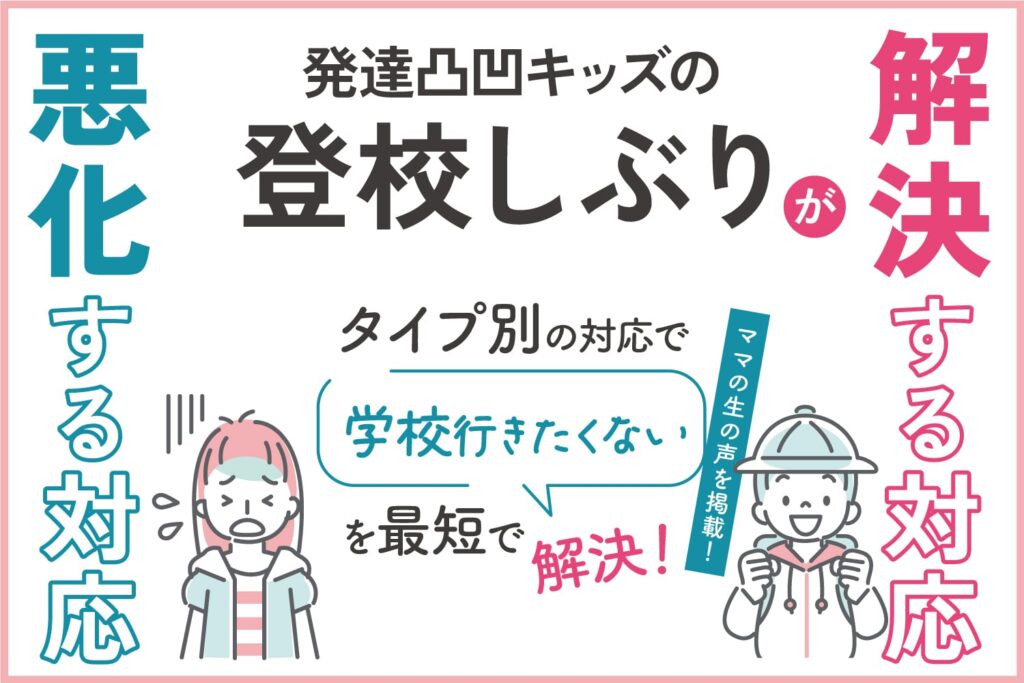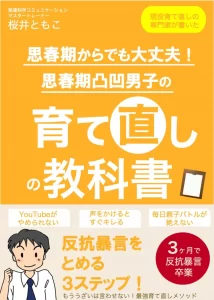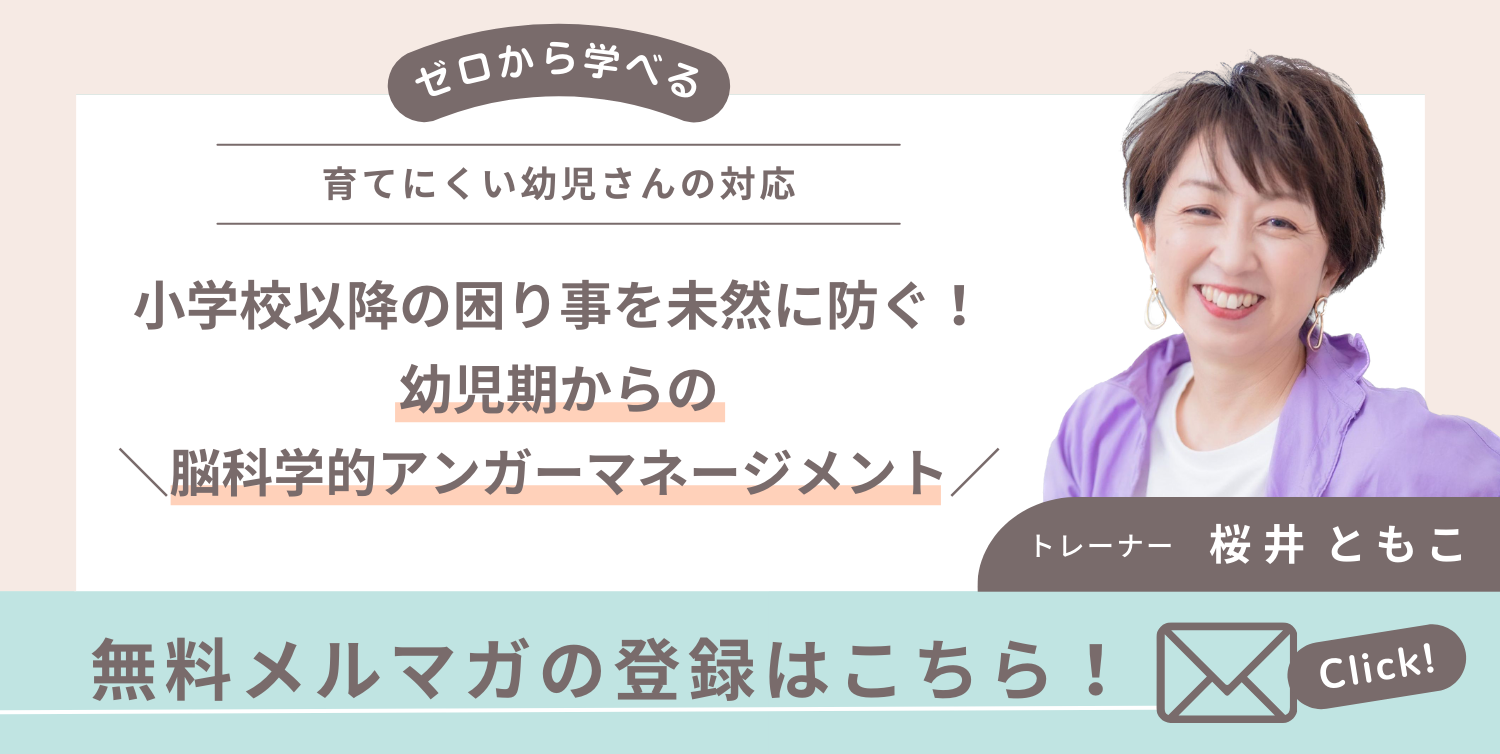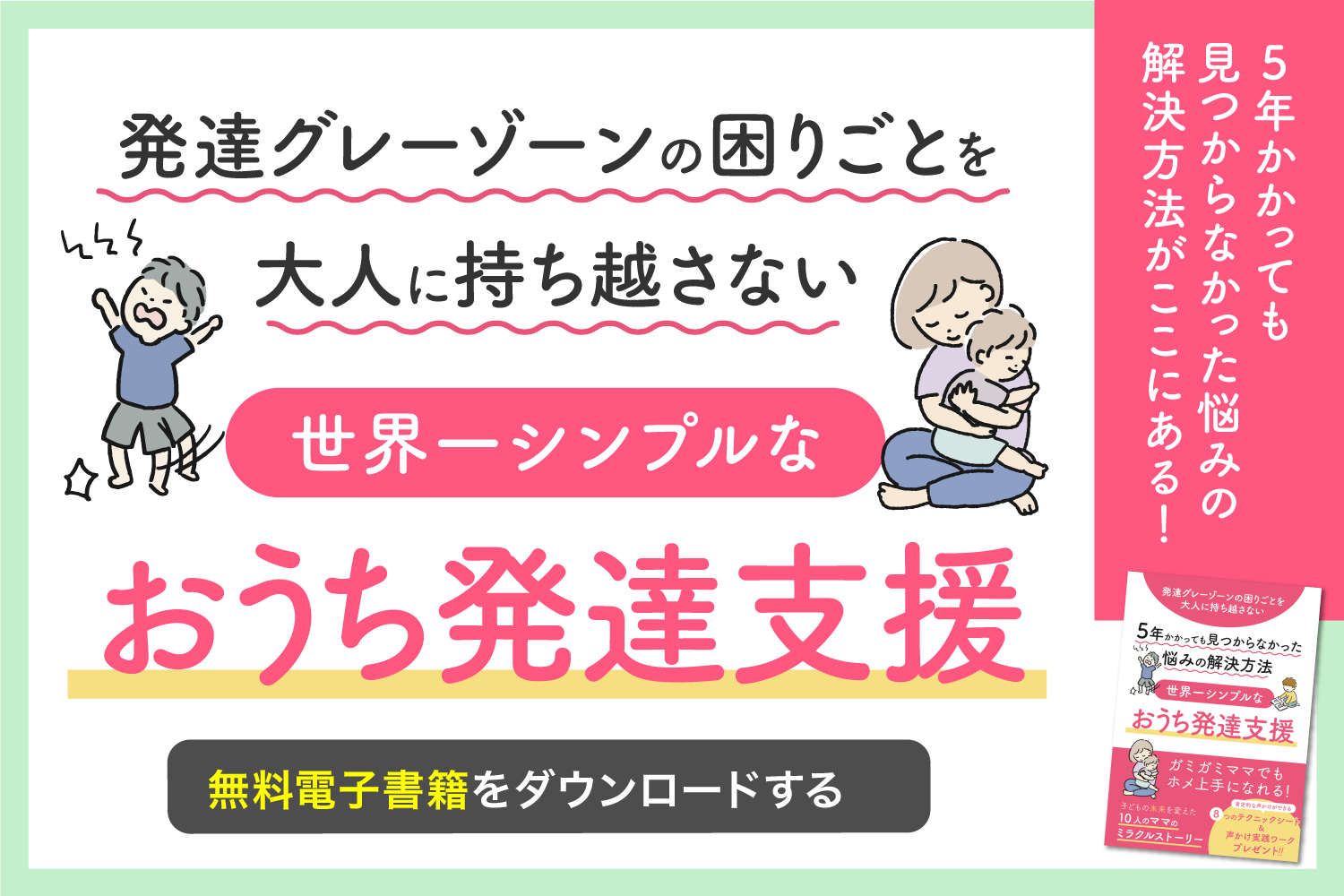ギャングエイジ期の発達障害・ADHDの子育てでは、すぐカッとなるなど衝動性のせいで、いろいろなトラブルを起こして困ることが多いと思います。実はADHDの衝動性って長所なんです! 困りごとN0.1の衝動性を「キラッと輝く長所」に変えるたった1つの声掛けをお話します。
【目次】
1.ギャングエイジかな?すぐカッとなる発達障害・ADHDの息子は問題児でした
我が家には発達障害・注意欠陥多動障害(ADHD)の息子がいます。特性として不注意・衝動性・多動性がありました。
小学校1、2年生の間は、周りとのトラブルがなかったので、学校から指摘されるのは本人の姿勢のことなど。全体的にはヤンチャで元気のいい男の子という評価でした。
しかし、いわゆるギャングエイジと呼ばれる小学校3、4年生の頃から、衝動性が目立つようになりました。
ちょっとしたことですぐカッとなっては、毎日お友達と取っ組み合いの喧嘩をするようになってしまいました。
あっという間に乱暴な子、危ない子、何をやるかわからないクラスの問題児というレッテルがついてしまったのです。
先生も周りも、私も、とにかく彼を叱り続けました。
わかってもらえない息子はイライラを募らせ、次第に導火線はなくなり、瞬時に怒りに火がついてしまうスーパー問題児になってしまいました。
そうなってしまうとそこからは悪循環が始まります。今思えば、彼の主張が別にあり、彼が悪くなかったことあったかもしれません。

そもそも衝動性=乱暴で悪いことという認識は、正しかったのでしょうか?
2.衝動性は悪いこと?長所にもなる理由とは
ADHDの特性として不注意・衝動性・多動性の3つがあります。
不注意と多動性は、周りに直接危害がないことも多いので、本人の問題として扱われることが多いです。
しかし、衝動性が強いことは、突発的に道路に飛び出すなど自分への危険な行為以外に、ちょっとしたことでイライラしがちで、怒りへの導火線が短いのが特徴です。
そのため、すぐカッとなっては周りの子とトラブルになり、手や足が出てしまうので、幼稚園や学校に行く年齢になると、いわゆる問題児として扱われてしまうことが多くなります。
このように、衝動性とは思いついたことを深く考えずにパッとやってしまう行動特性のことなので、マイナスイメージをお持ちの方も多いと思います。
ところが衝動性は必ずしもマイナスのものばかりではないのです。
例えば、
・思いついてものすごい工作を作る、面白い遊びをひらめくなど、特性で周りを楽しませる
・パッと反射的に反応するので、スポーツをやる際の瞬発力になる
・「これやりたい!」「あれやりたい!」という衝動性は、「これやってみようかな!」「あれやってみようかな!」という好奇心につながる
このように衝動性は、発達障害・ADHD傾向の子の素晴らしい長所にもなります。
将来仕事についた際に、「発想力が豊かで、好奇心、行動力があり、他の人が思いもつかないようなことを創造したり、周りの人が無理だと思うことをやり遂げたりして、大活躍する!」という人もたくさんいるのです。

すぐカッとなって周りを攻撃し、怒られてイライラしているという負のスパイラルの状態では、自分のエネルギーをプラスの方向に向けることはできません。
攻撃性やイライラを取り除き、衝動性をその子の長所として、輝き出してあげる必要があるのです。
3.ADHDの衝動性を長所に変えるたった1つの声掛け
衝動性のあるADHDの子はすぐカッとなり手が出てしまうということがあります。けれど、理由を聞いてもらえた経験は少なく、大体は頭ごなしに叱られ、さらにイライラを募らせてしまっていることが多いです。
つまり、攻撃的な面が目立つ子は、常に周りから怒られ続け、人との否定的な関わりが多いことで自信が育たず、ちょっとしたことでさらに周りを攻撃してしまっているのです。
ですので、肯定的な関わりを増やし、子どもの心のコップを肯定の言葉で満たしてあげることが必要になります。
まずはお母さん一人でいいので、子どもとのコミュニケーションを否定から肯定へ変えるだけで子どもはグッと変わってきます!
「この子は褒めるところなんて何もない」と思っているお母さん、安心して下さい。
声掛けのコツは子どもが何かをやろうとしているときに肯定の声を掛けることです!
お風呂に入ろうとしたとき、ご飯を食べに来たとき、宿題を出したとき、ベットから降りたときに、
・「お風呂入るの」
・「お!来たね」
・「宿題やるんだ!」
・「おはよ。起きたね」
など、やろうとしていることをそのまま声に出して伝えます。
実際は今やろうとしていることや、やっていることを、「それあってるよ!いいね!」と口に出して伝えてあげるだけで、肯定の声掛けになっています。
私が肯定の声掛けを実施すること3週間。我が家のスーパー問題児だったADHDの息子は、周りへの攻撃性が嘘のようにピタッとなくなりました。
攻撃性がなくなった息子は、お友達もどんどん増えて、元々明るい性格なので、学校の行事の際は盛り上げ役としてリーダーを務めるほどになりました。

できるだけ早いうちに、周りとのトラブルの原因になる攻撃性を抑える声掛けを、お母さんが取り組んでください。
攻撃性のなくなったADHDの子は、自分の思いつきをプラスの方向に生かすことができるようになります。
衝動性は短所ではありません!親子のコミュニケーションを変えるだけで、お子さんの衝動性をキラッと輝く長所に変えることができます。
ぜひ今日から、しっかりとお母さんが、肯定的な関わりを増やし、肯定の声かけのシャワーをたくさんお子さんに浴びさせてあげましょう!
発達障害・ADHD傾向の子が輝くためのコミュニケーション術をたくさんご紹介しています。
執筆者:桜井ともこ
(発達科学コミュニケーショントレーナー)