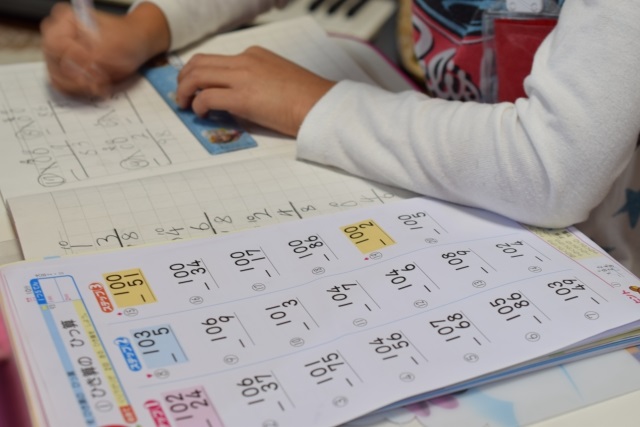小学校で算数につまづかないために、まずは足し算の教え方を工夫する必要があります。ドリルをガツガツ解けばいいわけではありません。計算が苦手な子や発達障害の子どもが抵抗なく計算を習得し、算数嫌いにならないためのおうち対応を始めましょう.
【目次】
1.新入学!ママが学習のつまづきポイントを把握しておきましょう!
2.算数嫌いを防ぐ!計算をしっかりマスターしよう!
3.足し算の教え方の新常識!指で数えてOK。
4.発達障害の子どもたちにもオススメ!家族みんなで楽しくできる暗算ゲーム
1.新入学!ママが学習のつまづきポイントを把握しておきましょう!
小学校入学!お子さんはもちろん、ご家族にとっても一大イベントですね。
楽しみな反面、新しい環境にお子さんがついていけるかどうか不安や心配になることも多いのではないでしょうか。
気にかかるのは勉強のこと、小学校はどうしても勉強の比重が重くなります。学年が上がるにつれてどんどん難しくなっていきますから、お母さんも心配ですよね。

国語の漢字でつまづく。
音読が不自然。
繰りあがり・繰りさがりが苦手。
計算が遅い、手を使わないとできない。
など、小学校低学年でも、学習面で不安を抱える子もいると思います。おうちで何とかサポートしたい!というお母さんのために、いくつか方法をお伝えしたいと思います。
2.算数嫌いを防ぐ!計算をしっかりマスターしよう!
算数はつまずくお子さんが多い教科です。小学1年生でたし算・ひき算、小学2年生でかけ算・わり算を習うと、計算の基礎である「四則計算」が完成します。
つまり、わり算の学習以降は、問題文からどの計算を使うか、自分で判断していかなければなりません。それまでに、基礎的な計算能力をしっかり身につけておく必要があるのです!
計算が苦手だけど算数は得意!という子はいません。算数嫌いにさせないためにも算数の基礎の計算はしっかりマスターしていきたいですね。

3.足し算の教え方の新常識!指で数えてOK。
算数の学習において基礎になる四則計算。この計算には2つの方法があります。1つは暗算、もう1つは筆算です。小学2年生で九九を暗記すると、暗算で計算できる範囲が広がります。
さて、この2つの方法の前段階で、実はもう1つ方法があります。
それは、指を使って数えることです。小学生以上で、指を使ったり、自分で絵を描いてそれを数えていると心配になりませんか?
頭の中で考えて解くようにしてほしくて、ついつい「数えないで考えて解きなさい」って言いたくなりませんか?
実はこれ、逆効果!
指を使って数えているのは、数量のイメージができていないからです。イメージができているかどうかをチェックする方法はとても簡単です。
子どもの目の前にキャンディーをいくつか置いて、それがいくつあるのかクイズを出してみましょう。
最初は目で見ただけで「2個!」と答えられるはずです。少しずつキャンディーの数を増やしていき、指をつかって数え始めた数からは、数量のイメージがない可能性が高いです。
頭の中でイメージできないから、指を使って実際に数えてみる。とても自然なことです。これをやめさせると、結局数量のイメージがつかないままになるかもしれません。

これは算数学習においては致命的です。算数・数学の問題はすべて「数量」を求めるものだからです。
指で数えて回答する子どもは、そのやり方を見守ってあげてください。コレが足し算の教え方の新常識です!
指で足りない場合は、100玉そろばんなどを利用して、心行くまで数えさせてあげましょう。
4.発達障害の子どもたちにもオススメ!家族みんなで楽しくできる暗算ゲーム
計算のなかで、より多くの数を暗算で計算できるようになることは、1つのポイントです。
計算が苦手になると、どうしても筆算で答えを求めたくなってしまいますが、筆算は手を使って計算するもの。頭で考える暗算の方が早く処理できます。
また、日常生活、特に買い物しながら筆算で計算する…なんて現実的ではありませんよね。暗算は生活スキルをあげるために、必要な能力でもあります。九九を覚えて暗算の範囲を広げるのは、理にかなった方法なのです。
さて、計算が得意な子になってほしい!暗算がしっかりできるようになってほしい!だからといってドリルをたくさんやらせると、子どもは楽しくありません。
発達障害やグレーゾーンの子どもは、自分がやりたくないものはとことん拒否します。勉強には、どうしてもネガティブなイメージがつきまとうもの。特に暗算のトレーニングは単調で面白みに欠けますよね。
発達障害やグレーゾーンの子どもが自分から勉強するようになるには、ゲーム感覚のような「楽しい」要素がとても大切です。
また、子どもが1人でコツコツ勉強するのはやはり楽しくない!家族みんなで遊びながら学習できる方法をご紹介します。
カンタンな方法はサイコロです。まずはサイコロ2つを使い、振って出た目を使って暗算します。サイコロだと、小学2年生ならたし算、ひき算、かけ算ができます。
どんな数字が出るか分かりませんから、その場ですぐに計算しなくてはいけません。暗算のトレーニングにはとても有効です。慣れてきたら、多角サイコロを使って数字のバリエーションを増やすと、トレーニングを強化することができます。
時間制限を設けてドキドキ感を演出し、家族みんなで楽しくゲーム感覚でできるなら、子どもも抵抗なく勉強できるはず。正解したらみんなで拍手して、たくさん褒めあいましょう!
発達障害やグレーゾーンのお子さんを持つお母さんに知っていただきたいのは、机に向かってワークをやるだけが勉強ではないということです。

今回は家族みんなが一緒にできるということで「サイコロ」というアナログな方法をご紹介しましたが、子どもが楽しく身につけられるなら、ゲームアプリもいいと思います。
今では、足し算・引き算の段階から、教え方のツールはたくさんあります。お子さんが楽しめる方法を選択できる時代なんです!
子どもが自分から勉強するようになれば、「勉強しなさい!」からは卒業できます。ぜひお子さんに合った勉強方法を考えてあげてくださいね!
教科書を使わない勉強法はこちらで詳しく解説しています!もちろん小学生にも応用可能♪
学習習慣をつけるために必要な環境づくりについて解説しています。「勉強しなさい!」という前に環境を見直しませんか?
▼▼どうして覚えられないの?ママの疑問にお答えします!漢字学習などが苦手なお子さんの脳の仕組みとサポート法をお伝えします。▼▼
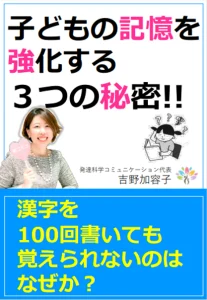
脳機能や脳の発達に合わせた学習方法が分かるのはココだけ!
執筆者:丸山香緒里
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)