発達障害小学生のお子さんで音読が苦手だなと感じることはありませんか?音読は発達障害小学生のワーキングメモリを鍛えて困りごとを減らすのに効果抜群。毎日の宿題になる音読を活用して、困りごとの解決や勉強の効率アップが期待できるコツをご紹介します。
【目次】
1.毎日ある小学生の音読の宿題
2.発達障害の小学生に音読は効果抜群!
◆ワーキングメモリを鍛える
◆脳のウォーミングアップ
3.音読の宿題の効果を最大限に引き出す方法とは?
◆高速で読む
◆毎日行う
4.音読の宿題を親子でラクに続けよう!
1.毎日ある小学生の音読の宿題
小学生の音読の宿題は、どうして毎日あるのでしょう?
音読が毎日あるのは、音読が学習面や生活面でのスキルを向上させるための効果的な方法だからです。
小学生になると、毎日の宿題や家庭学習が出されます。
その中でも、もっともポピュラーで学年を問わずに出される宿題が音読ではないでしょうか。
我が家の長男も、1番初めに出された宿題が音読でした。
「クジラぐも」「スーホの白い馬」など、何度も子どもが読んでくれるうちにこちらまで覚えてしまうほどです。

ドリルや漢字練習と違い、音読の宿題は「聞いてくれる人」が必要なので、お母さんも毎日お子さんにお付き合いされていることと思います。
「おうちの人のサイン・コメント」という欄もあったりして、毎日のコメントに困ってしまうこともあるのではないでしょうか。
「音読の宿題って毎日付き合うのが大変だけど、いったい何の効果があるのかな?」なんて思っていませんか。
実は、発達障害の小学生にはこの音読はとてもうれしい効果があるのです!
今回は、お母さんがお子さんの毎日の音読をさらに応援したくなるような、音読の効果に関する役立つ知識や情報をお伝えしますね!
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
指示出しゼロの子育てで
たった3週間で癇癪が着く!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.発達障害の小学生に音読は効果抜群!
発達障害小学生の音読の効果は、記憶力を向上させ物事を理解する力をアップさせる効果があります。
また言葉にたくさん触れることで自分の気持ちを言葉で表現することでできるようになり、発達障害の子どもにはうれしい効果がたくさんあります!
毎日宿題として出される音読。音読には、たしかに「毎日やってほしい!」と思ってしまう、たくさんの効果を1つずつ解説していきますね!
◆ワーキングメモリを鍛える
音読でワーキングメモリを鍛えられるのは、目でみたものを理解して行動を起こすという一連の作業が含まれているためです。
この一連の作業を繰り返すことで、発達障害の子どもの困りごとである記憶力の向上や感情のコントロールができるようになるんです。
音読は、文字を「目で見て理解」「声に出す」「自分が発した声を聞く」という動作を同時に行います。
この「2つ以上の動作を同時に行う」ことで、脳の前頭前野が刺激を受け、ワーキングメモリを鍛えるトレーニングになるのです。
ワーキングメモリとは、短期記憶や作業記憶とも言われ、情報を一時的に記憶して処理・操作する能力のことを指します。
「ワーキングメモリ」は「作業をするときの机の広さ」、「記憶」は「机の上に置いた道具」に例えられます。

机でなにか工作をするときのことをイメージしてみてください。
画用紙、折り紙、のり、色鉛筆、はさみ、カッター、セロハンテープなどを使って、これから何かを作るところです。
・ワーキングメモリが高い
広い机であれば、机の上に道具をたくさん置けます。
使いたい道具を使って、作業しては道具を取り換えてをくりかえし、スムーズにたくさんの作業をすることができます。
・ワーキングメモリが低い
狭い机ですと、道具を置くところ少ないので一度にたくさんの作業ができません。
また、狭いところに無理に道具を置こうとすると、すぐ机の上がいっぱいになってしまいます。
道具が机から落ちてしまったり、机の上が散らかってしまったりうまく作業ができません。
ワーキングメモリが高ければ、いくつもの作業を一度にこなすことができます。
ワーキングメモリが低ければ、一度に多くの作業ができませんし、自分の許容範囲をこえた記憶がこぼれおちることもあります。
ワーキングメモリが低いとすぐに許容範囲をこえてしまうので、混乱してイライラし癇癪を起こしたりします。
発達障害やグレーゾーンの小学生には、このワーキングメモリが低いケースが多いです。
そのために「忘れっぽい」「うっかりミスをしてしまう」「怒りっぽい」「気持ちのコントロールができない」という困りごとが起こります。
音読の宿題にはこのワーキングメモリを高めることで、発達障害の困りごとも改善されていくといううれしい効果があるのです。
◆脳のウォーミングアップ
朝に音読する習慣をつければ、起きてすぐに脳がなかなか活動しない発達障害小学生の脳もしっかり活性化することができます。
音読をしているとき大脳の70%以上もの部位が活性化するので、脳のウォーミングアップになります。
勉強に取り掛かる前に音読をすれば効果的に学習を進められます。
発達障害の小学生は、朝の目覚めが悪く起きていてもぼーっとしてしまう子が多いですね。
朝起きてから音読の宿題をすれば、脳が活性化して学校に行く前に脳をしっかり起こしてしてあげる効果も期待できます。
これで午前中の授業もばっちり聞けますね!
毎日の声かけで“脳のクセ”は変えられる!
子どもが持つ力を発揮できるようになる
4ステップの声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.音読の宿題の効果を最大限に引き出す方法とは?
音読でワーキングメモリを鍛えるのはもちろんですが、その効果を最大限に引き出すためのコツがあります。
そのコツとは、子どもの負担を少なくして毎日楽しく継続的に音読できる読みやすい環境を整えることです。
詳しくご紹介しますね。
◆高速で読む
スピーディに読むことで脳内に入ってくる文章の量、すなわち情報量も飛躍的にアップします。
学習障害や読字障害のお子さんにとっては読むこと自体がとても大変ですよね。スピードはもちろん先の目標で良いのです。
初めは指で文字を追いながらゆっくり読むことからスタートでもちろん構いません。
リーディングルーラーという道具を使うなど、補助を用いるのも有効ですね。
お子さんの負担を小さくして音読がしやすくなる環境を整えることも考えてみてください。
◆毎日行う
週に2日より、継続して毎日音読することで、その分ワーキングメモリを鍛えることができ、ワーキングメモリを高める効果が期待できます。
毎日の音読の宿題で脳機能のトレーニングをしていることになります。
とはいえ、毎日続けるのはなかなか大変です。
特に発達障害の子どもは、定型発達の子どもよりも常に頭をフル回転させている状態で、とても疲れやすいです。
負担が大きすぎると読むこと自体に苦手意識を持ってしまいます。
はじめは全部できなくても、もし難しそうなら量を減らすなど、スモールステップで楽しくできることが毎日続けるコツになります。

4.音読の宿題を親子でラクに続けよう!
音読をラクに続けるためのコツは、子どもには音読ができたらご褒美をあげる。親はコメントをいくつかパターン化して事前に準備しておくことです。
また、ご褒美を準備したり事前にコメントをパターン化することで「毎日継続する」ということのハードルが下がりラクに音読の宿題を続けられますよ。
いくら大人が「音読は脳にいいよ!」「勉強ができるようになるよ!」なんて言っても、読むのが苦手な子はなかなか取り掛かることができませんよね。
また、お母さんにとって負担となるのは毎日のサインやコメントです。
ここでは、毎日の音読をラクに続ける工夫をご紹介します。

◆シール・スタンプを利用する
我が家では100円ショップで子どもと一緒にシールを選び、宿題セットに一緒に入れています。
音読の宿題を始める前に子どもに好きなシールを選んでもらい、そこで会話をすることでお母さんと楽しいコミュニケーションがとれますね。
取り組む前にお母さんとの楽しい会話で気分を上げて、さらに「音読をしたら好きなシールが張れる」という音読前後にちょっとしたご褒美があることで、宿題に取り掛かりやすくなります。
◆コメントを数種類考えておく
コメント欄には何を書こうか迷うことがありますね。
もし、コメントを書くのが苦手でしたら、あらかじめコメントを何種類か考えておくのがおすすめですよ。
コメントは小学生のお子さんをほめるいい機会です。
毎日続けていくと、お母さんからほめられた記録がコメント欄にたくさん書かれていくわけですから、目に見えやすいご褒美効果でやる気アップにつながります。
ぜひ、コメント欄を上手に活用してお子さんのがんばりをほめてあげてくださいね!
いかがでしょうか?
ワーキングメモリが低い発達障害の小学生には、音読でワーキングメモリを鍛えることができ、ワーキングメモリを高められる効果があります。
小学生に出される毎日の音読の宿題を続けることで効果も上がりますので、ぜひお子さんとラクに続けられる工夫をしてみてください。
音読の宿題を通じて親子のコミュニケーションが、より温かく楽しいものになるように応援しております。
▼▼スキマ時間にワーキングメモリと注意力が鍛えられます!▼▼
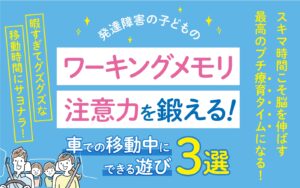
小学生の子どもがスムーズに宿題にとりかかれる効果的な声かけを多数公開中!
執筆者:葉山めぐみ
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)




