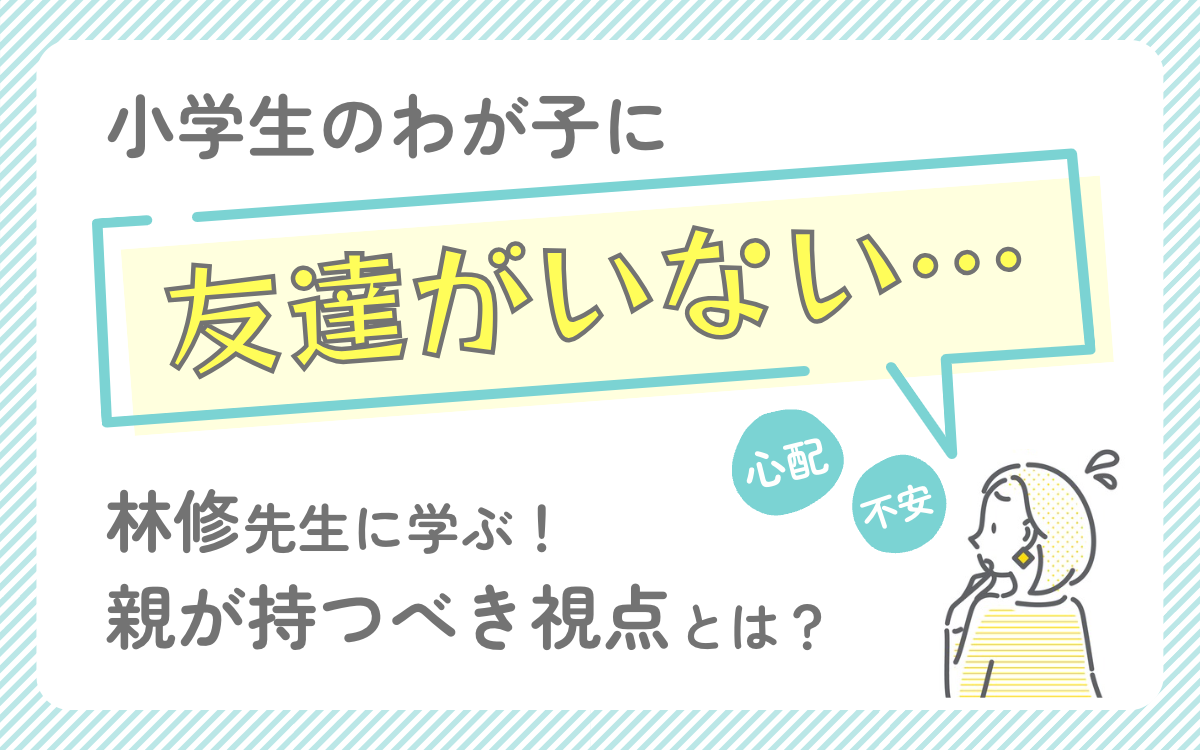結論:子どもに友達がいないのはママのせいではありません。発達特性や環境が影響することも。将来安定した人間関係が築けるようになるための親の関わり方を紹介します。
【目次】
執筆者:丸山香緒里
パステル総研編集長 発達科学コミュニケーションリサーチャー
発達障害グレーゾーンの困りごとを大人に持ち越さない!5年かかっても見つからなかった悩みの解決方法が5分で見つかる「パステル総研」編集長。パステル総研オープン以来、子育ての悩みを解決できるコンテンツを毎日お届けしています。子育ての「できない…」を「できた!」に変えるヒントをぜひパステル総研で手に入れてください!
パステル総研主宰:吉野加容子
発達科学コミュニケーション創始者、学術博士、臨床発達心理士
慶応⼤学⼤学院(博⼠課程修了)卒業後、企業で脳科学研究、医療機関で発達⽀援に従事。15年間発達に悩む親⼦へのカウンセリング、発達⽀援を⾏ってきた実績から得た「家庭で365⽇の発達⽀援が1番!」という考えのもと、脳科学、教育学、⼼理学のメソッドを合わせた独⾃の発達⽀援プログラム「発達科学コミュニケーション」を開発。
専門:脳科学、神経心理学、発達心理学、特別支援教育
1.小学生に友達がいない…大丈夫?
小学生の我が子に仲のいい友達がいないと、ママはとても心配ですよね。
ですが、友達がいない状態は、必ずしも問題ではありません。なぜなら、小学生は人付き合いの練習期だからです。
友達とのかかわりを持たせたい!と集団に放り込むのは絶対にNG!
本人のペースで「人と話したり遊んだりするのって楽しいな」という経験を積み重ねていくことこそ、将来、他の誰かと信頼関係を創っていく土台になります。
この記事では、友達がなかなかできない我が子に親としてどうかかわればいいのかをお伝えしていきます。
2.小学生で友達がいない子の特徴チェック
友達関係がうまく行かない原因は主に2つ。発達と環境の要因です。
年齢が大きくなればなるほど人間関係は複雑化し、特に女子は小学校2,3年生頃になるとグループ化が進み、うまくグループに入れないと孤立してしまうケースがあります
まずはお子さんの様子をチェックしてみましょう。
◆かんたんチェック(3つ以上あてはまれば要フォロー)
- 話題が一方通行になりやすい/自慢が多い
- 距離が近い・急に触る・呼び捨てになりがち
- 輪に入る/抜けるきっかけ作りが苦手
- 誘われても「断り方」「受け方」の言葉が出てこない
- 放課後や休み時間に一人でいる時間が長い
もっと詳しく解説していきますね!
◆注意欠陥多動性障害(ADHDタイプ)
ADHDタイプのお子さんは人が大好き!だからこそ、距離が近すぎてしまったり空気が読めなかったりしてしまうことがあります。
・ちょっかいを出しすぎてしまう
・調子に乗って一言多くなる、とにかく喋る
・友達との距離感が近い
・みんなのテンションが落ち着いてもまだ一人で盛り上がっている。
など、周囲に合わせることを求められる日本の社会では、浮いてしまいがちなタイプです。
相手との関わりがある分、こじれると大きなトラブルになることもあり、対応するママもストレスを抱えやすくなります。
◆自閉症スペクトラムタイプ
ADHDタイプとは逆に、自分から積極的に人と関わらないのが自閉症スペクトラムタイプ。
・なかなか友達の輪に入っていけない
・友達との会話がうまく続かない
・そもそも友達に興味がない
・本当は嫌なのにNOと言えない
という、そもそも人と関わることにストレスと感じてしまうタイプです。本当に興味がない子もいますし、興味はあるけれど自分から動けない子もいますから、子ども本人がどんなことに困っているのかを見極める必要があります。
◆1年の明暗を分けるクラス替えの影響
集団生活を送る上で避けて通れないのが「クラス替え」そして「担任の先生の変更」です。
せっかくできた仲良しのお友達と離れてしまった…という進級進学時のエピソードは誰しもが持っています。
仲のいい子と離れてしまった上、自分から話しかけられない子は孤立してしまいます。また、空気が読めないタイプだと、早々にトラブルを起こしてクラスから浮いてしまって悪目立ちしてしまうことも少なくありません。
また、低学年であればあるほど、担任の先生の影響は大きいもの。
先生が良かれと思って提案する「昼休みはみんなで外で遊ぼう」は、一人が好きな子にとってはつらいものです。
このように、小学生の友達関係がうまくいかない原因は、子どもの発達特性はもちろんのこと、クラス替えや担任の変更などによる環境の変化にうまく適応できないことにあるんです。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓

3.小学生の子どもに友達がいないのは親のせい?
検索でも多い『子どもに友達がいないのは親のせい?』という疑問に答えます。ズバリ!親のせいではありません。
ママ自身に友達が少なかったり、なかなか人の輪に入っていけなかったりするママは確かにいらっしゃいます。
本当はもっと友達と遊べる機会を作った方がいいと分かっているのに…
私に友達がいないから、この子も友達と遊べないんだ…
と自分を責めているママが多いんです。
実は、ママの交友範囲が狭いから我が子の友達の輪が広がらないわけではありません。なぜなら、社会性は1:1からはじまるからです。
一気に何人もの人と仲良くなるのではなく、最初の”たった一人”と深い関係を築くことが人間関係を築いていく最初の一歩になります。
クラス替え・担任・学年の雰囲気などの影響に加えて、発達特性のある子どもたちがうまく人間関係を築いていくには、自然に任せておくだけでは不十分。だからこそママにやってほしいのは、
①ママ自身が”最初のひとり”になって【人と関わる成功体験】をつくること
②【おうちを安心安全基地】にして、子どもが本音をさらけだせる環境をつくること
③“みんなと仲良く”の【プレッシャーをかけない】こと
この3つなんです。
4.友達トラブルがないって本当にいいコト?
わが子の友達関係が心配なママは、
「とにかく今日トラブルを起こさないようにしてほしい」
と考える方がものすごく多いんです。ですが、トラブルがなかったからといって友達関係がうまく行っているわけではありません!
なぜなら人間関係は、小さな争いを何度も繰り返して、お互いの妥協点を探って、お互いを知って仲良くなるものだからです。
トラブルがないからといって、
・遊びたいのに入っていけない
・発言したくても自分の意見を我慢してしまう
・ひとまずニコニコうなずいておく
というものであったとしたら…それでいいわけないですよね!

ADHDタイプの場合、お子さんのテンションにみんながついていけず、遠巻きにされているという可能性だって否定できません。
自閉症スペクトラムタイプのお子さんの場合は、元々1人遊びが大好き!トラブルがないということは仲よく遊べたわけではなく、同じ空間にいただけという可能性だってありますよね。
このように友達付き合いがなかなかうまくいかない発達障害のお子さんが友達との時間をやり過ごすことで、友達との付き合い方がいつまでたっても学習できない可能性もあるんです。
友達関係、つまり人間関係は学習して体得するもの。まずママにこの視点を持ってほしいんです。
5.林修先生に学ぶ、子ども時代の人間関係の本質・親が持つべき視点とは?
人間関係は学習して体得するからこそ、友達がいないお子さん、友達とのトラブルが多いお子さんは「人間関係の練習期」という考え方がオススメです。
練習期だから、自分のペースで構わない。
練習期だから、多少トラブルが起こっても大丈夫。
そんな風に、ママがどーんと構えてほしいんです!
◆今のお付き合いは一生続かない
たとえ友達トラブルが起こったとしても、今の人間関係が一生続くことはほとんどありません。
「いつやるの?今でしょ!」で有名な林修先生が「初耳学」というテレビ番組で「小中の友だちなんてクソみたいなもの」とおっしゃっていました(2017年11月19日放送)。
実際に、そのときの番組ゲストの方も、小中の同級生とは年に1回会うかどうかという方がほとんど。
私自身も小中の友達とは何十年も会っていませんが、特に支障はありません。今は今で信頼できる友達や仲間を得ているからです。
私に限らずこのような方は珍しくないですし、これからの子どもたちにとっても珍しいことではなくなるはずです。
人間関係はいくらでもリセットできる。だから遠慮することなく一生懸命練習してほしいんです。
◆人間関係の練習ポイント
練習のポイントは必ず「誰かと話すって、遊ぶって楽しいな」という成功体験を作ってあげること。
そのために最低限のルールを作る…というのもいいのですが、必ず成功体験で終わることができる、一番いい練習方法があります。それは…
ママがお子さんの大親友になることです!
子ども同士なら譲れずにトラブルになる場面でも、ママだから譲ってあげられる。
学校では緊張してしまう子も、おうちならリラックスして遊べる。
クラスメイトには遠慮してしまうけれど、ママなら本音を言える。
大事なことは譲り合いや配慮を学ぶのではなく、「人と関わって楽しい」という記憶を残すことです。
人と関わって楽しかった記憶があれば、じゃあどうすればもっと楽しく過ごせるか、自分だけではなく相手も楽しいと思ってくれるか、考えられるようになるからです。
社会性の発達は1:1からスタートします。ぜひママにはお子さんの最初のひとりになってほしいと思います。
今日からできる“人間関係の練習”3ポイント
1.口角を上げて、笑顔で接する
2.肯定的な声かけから会話をスタートする
3.ママは聞き役に。子どもにたくさん話をしてもらう
狙い:ポジティブなコミュニケーションをとることで、子どもの「もっと話したい!」を引き出します。
◆将来、本当に大事にしたい人を大事にできるために
なぜ人付き合いの「練習」をするのか。それは大切な人に出会えたときに、その人を大切にできる大人に育ってほしいからです。
林先生のこの発言は、「クソ」という言葉が持つインパクトもあって、当時ネットニュースでかなり騒がれました。
私なりの解釈ではありますが、林先生は
友達関係はもっとメリハリをつけていい
とおっしゃりたかったのだと思っています。
結局のところ、本当に大事にしたい「人生の親友」は数人です。しかも、いつ出会えるのか分かりません。
小学校時代・中学校時代に人生の親友に出会えず、友達とうまくいかなかったからと言って「この子は友達がいない、できない」「一生友達付き合いが苦手なまま」ではないのです。
「友達100人できるかな♪」と言われますが、大人になると
「大事にしたい人を大事にする」
「それ以外の人とはそれなりに付き合っていく」
「結局のところ、たいして大事でもない職場の人と過ごす時間が一番長い。」
「同い年の人よりも、年齢が違う人との付き合いの方が多くなる」
残念ですが、これが現実。学校でクラスのみんなと仲良くしましょう、は現実とかけ離れています。
みんなが仲良しなんて幻想なことは、もう十分ご存じのはずです。だったら子どもにそれを望むのはやめましょう!
私は、小学2年生の息子に常々「嫌な子とは無理に話さなくていい、遊ばなくていい」と伝えています。息子も、「今日○○くんにこんなことされて嫌だったから遊ぶのやめといた」と伝えてくれます。
まだ2年生なので、その子自体が嫌いという感じではなく、特定の場面でいじわるをされて嫌だという段階だと思います。
嫌な人の顔色を窺って、それでも仲良くなれるように頑張るのって、大人でも相当しんどいこと。ただでさえ友達付き合いが苦手な子どもがうまくやれるとは思えません。それで人と付き合うのがイヤになるなんて、本末転倒です。
今はインターネットで世界とつながっている時代です。それだけ多くの人に出会えるチャンスがあります。付き合う人はいくらでも選べます!
だから、大事な人に出会えたときに、大事に付き合っていけるだけの経験をそれまでに積み重ねておく。それだけなんです。
こういう考え方をすれば、小学生のわが子に友達がいない…などと友達関係を心配せずに、おおらかにとらえられるのではないでしょうか?
むしろ今、子どもにとって一番大事な人って、友達ではなくお父さん・お母さん(ご両親)ですよね!お母さんがお子さんを大事に思うように、子どもに家族を大事に思う気持ちを伝えていく。まずはここからです!
友達付き合いが苦手なお子さんに友達がいないみたい…とお悩みのお母さん、ぜひ違った視点からも考えてみてくださいね!
小学生で友達がいない子のコミュニケーション力を、ママの関わりで優しく育てる方法を動画でご紹介!
小学生の友達関係についてのよくある質問(FAQ)
Q1:小学生の子どもに友達がいないのは問題ですか?
A1:結論、過度に心配しすぎる必要はありません。 今は“人付き合いの練習期”。大人になった時に大事な人を大事にできるよう、家庭で小さな成功体験を積ませる視点に切り替えましょう。
詳しくは 友達の輪に入れない子が学べる唯一の対応法 を参照。
Q2:トラブルが多い子にはどう対応すればいい?
A2:大失敗を避ける“ルール”を子どもと一緒に作りましょう。トラブルが多い子は叱られ続けて人間関係が嫌になりがち。うまくやれたらを即肯定します。実践例は ADHDタイプの友達作りが上手くなったワケ にまとまっています。
Q3:親がやってはいけないことは?
A3:“みんなと仲良く”を強要するのはNG!友達がいないことを叱責するのはもっとNG! まずは人と人とのコミュニケーションスキルをおうちで育てましょう。
具体例は “気持ち乗っけ”会話術 をどうぞ。
執筆者:丸山香緒里
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)