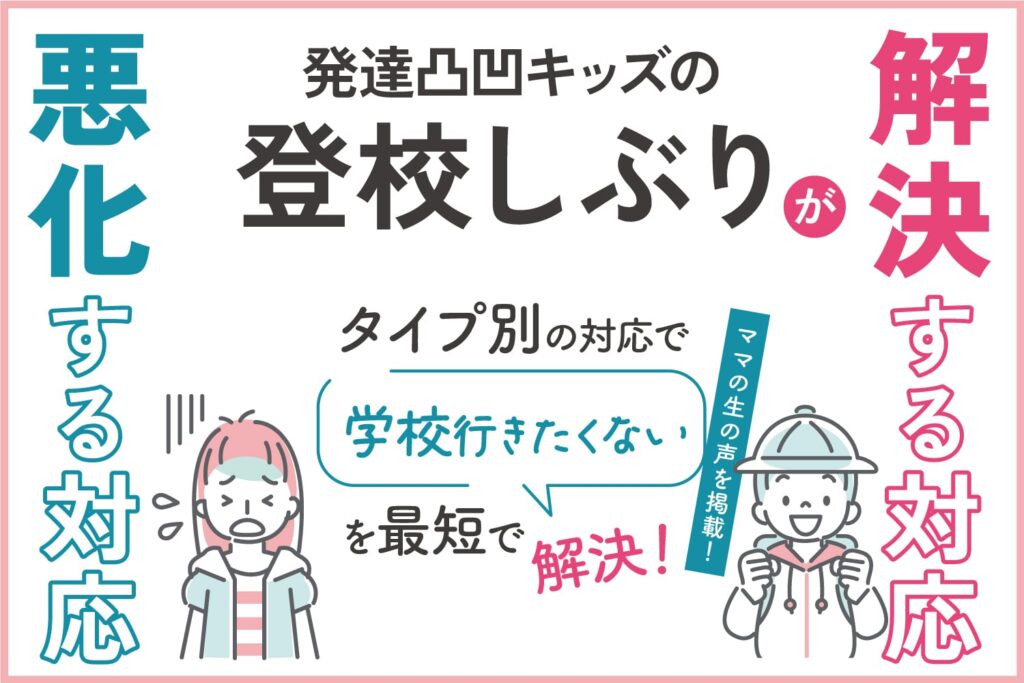入学を控えて、先生の一斉指示が通らない…と悩む発達障害の子をもつママはいませんか?小学校生活をスムーズにするためには、先生の指示が通ることが必須!そして指示が通るためには、まず「聞く耳」を作るのがポイントです!
【目次】
1.一斉指示が通らないと悩む発達障害の子を持つママへ
来年の4月に小学生になるお子さんは、少しずつ学校生活に向けて意識し始めるころですね。
お子さんの就学を控えたママは、幼児時代とがらりと変わった生活に、不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
小学校生活では、先生の話をきちんと聞けるか?先生の指示に従い動けるか?というところが、学習面も含め生活全般がスムーズにいくかどうかの大事なポイントになります。
ただでさえ、新しい環境に入り不安な時に先生の指示が理解できないことで、不安感が増したり、まわりについていけずに自信をなくしたりするのは避けたいところです。

入学当初は、指示が通らず行動が遅い子も先生がある程度フォローしてくれるかと思います。
しかし、その後は先生の一斉指示についていくことが求められます。
特に、運動会や遠足などの行事が始まると、指示を聞き漏らさず、集団に遅れずに行動することが求められる場面が増えますので、早めに対策したいですね。
ここでは、学校生活での一斉指示を理解してスムーズに行動に移せるためにはどうしたらよいのか、考えてみます。
2.発達障害の子に一斉指示が通らず行動が遅いワケ
お子さんは、お母さんの指示を聞いて行動に移せていますか?
お母さんとのコミュニケーションで指示が通らないことで行動が遅い場合、小学校で先生とのコミュニケーションでもつまずいてしまう可能性があります。
発達障害やグレーゾーンの子は、お母さんが指示をしたときに、全く聞いていない、
または、自分の世界に入っていて耳がシャットダウンされている感じで反応しない場合などがあります。
脳の特性上、聴覚に機能的な問題があるわけではないのに、言われたことに注意を向けて聞く力が弱い、ということがありえます。
この場合、視覚や聴覚から様々な情報が入ってくる中で、今自分に向けて言われていることに意識を向けて、それを理解するだけの注意を払うことができていない可能性があります。

さらに、ネガティブな情報はすっと耳に届きにくい傾向があります。
ママの指示は、子どもにとって、耳が痛い指示のことが多いので、子どもが無意識にシャットダウンしている可能性があります。
一方で、「おやつたべなさーい」などの子どもにとって嬉しいポジティブな指示は、すっと届いていることがありませんか?
では、子どもにとってたとえ聞きたくない指示でもすっと届くためには、どのような工夫が必要なのでしょうか。
3.就学前からできる!一斉指示が通らない発達障害の子を伸ばす鉄則~「聞く耳」づくり~
子どもに指示をする場面について、流れをみてみましょう!
◆まず、聞く耳を作る!
まず、子どもの耳を「聞く耳」状態にしてあげる声掛けが必要です。
ママとしては、注意や指示の声掛けをしたい場合であっても、決してネガティブ感を出さないのがポイントです。
笑顔でやさしい声で「ねえ、●●ちゃん!」と近づいて、肩に手を置きます。
子どもの脳は、言葉の中身よりも表情や声色の方が先に処理される傾向がありますので、何を言うかよりもどんな感じで話しかけるかの方が大事です。
このような声掛けをすることで、まず子どもが「聞く耳」を持つ状態になります。
自分に話しかけられているとわかりやすく、またポジティブな声掛けは届きやすいからです。
◆さらに笑顔で指示を伝える
そのうえで、さらに笑顔で指示を穏やかに伝えます。
「そろそろお風呂入ろうか~」
「お風呂に入るのと、歯を磨くのと、どっち先にする?」
「お風呂入ったら、好きな本読んでから寝ようか。」
など、指示をする際には、選択肢を与える指示やご褒美を使った指示が効果的です。
選択肢を与えることで子どもが選んで動きやすくなりますし、ご褒美があると行動したくなるからです。
子どもが行動しやすくなるような指示の出し方がポイントになります。
◆指示に従うそぶりを見せたら、すかさず褒める!
そして、指示に従うそぶりを見せたら、すかさず褒めましょう!
指示に従ってすっと動くと褒められる(=すぐに動くのは良いこと)という認識を、子どもに定着させることができます!
脳(聞く力を担当する部分などを含む)は、使えば使うほど発達するという特徴があります。ですので、ママの指示を聞ける経験を積めば積むほど、子どもの聞く力自体が伸びていきます。
お家で聞く力自体をアップさせておけば、小学校で先生が子ども全体へ一斉指示を出した場合でも指示に従えるのです。

お子さんの「聞く耳」をつくって聞く力を伸ばし、小学校生活を順調に過ごせるよう今から準備しておきましょう!
「聞く耳」づくりについては、こちらでも詳しく紹介していますので是非ご覧ください!
↓↓↓
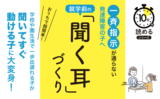
【10分で読めるシリーズ】一斉指示が通らない発達障害の子へ就学前の「聞く耳」づくり
集団生活に必要な”聞く力”をおうちで簡単に伸ばす方法がわかります! ママのたった一言で聞いてすぐ動ける子になれる! 知っていますか?発達凸凹キッズママの2人に1人のお悩みが「先生から集団へ出す指示で動けない」ことです 毎日ママがお家...
発達障害を大人に持ち越さない!5年にわたる悩みを5分で解決するパステル総研の無料メール講座!
執筆者:三島希実
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)