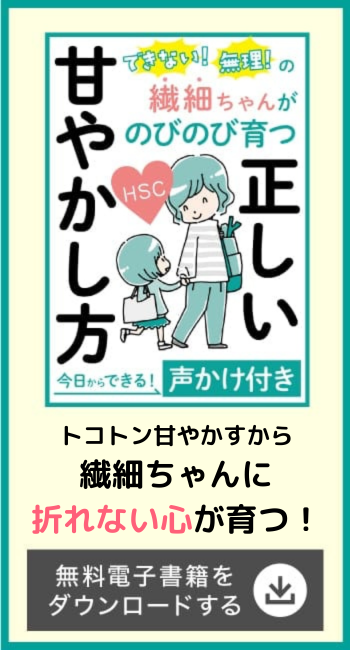休み明け、「学校行きたくない」と泣く子に「休んでいいよ」と言ったら、逆に怒られた。そんな経験、ありませんか?励ますでも、休ませるのでもなく、「待つ」という対応で、不安の強い子が、自分で「行ってくるね!」と登校できた対処法をお伝えします。
【目次】
1.夏休み明け、「学校行きたくない」と泣く子にやめた声かけ
2.「休んでいいよ」と言ったら子どもが怒る理由
3.「行きたくない」と泣く子が「行ってくるね!」と自分から登校できた、ママの関わり方
①見守ることで、行動力は引き出せる
②気持ちを整えるには、使っている脳を変えてあげる
1.夏休み明け、「学校行きたくない」と泣く子にやめた声かけ
休み明けの朝。 「学校行きたくない」と泣き出した娘に、私はとっさに「休んでいいよ」と言ってしまいました。
しかし娘は、泣きながら怒って、自分でランドセルを背負い家を出ていきました。そして、校門の前で涙ぐんで立ち尽くしていたのです。
校長先生からお電話をいただいた時には本当に焦りました。以前の私は、こうした登校しぶりにどう対応すればいいのか、わかりませんでした。
私がやめたのは、「休んでいいよ」という声かけです。
なぜなら、一見やさしさに聞こえるこの言葉が、子どもにとっては「行きたい気持ちを否定された」と受け取られることがあると気づいたからです。
最近は、行き渋りへの対応として「無理に行かせない」「休ませてもいい」という情報が多くなっています。
その背景には、「子どもの心を守るべき」「子どもの心を大事にしよう」という、優しさの表れがあると思います。
しかしながら、実際には、「休んでいいよ」と言ったことで、子どもが怒ったり、もっと不安定になることがあるのです。

もちろん、次のようなメンタル面のサインが見られるときには、ゆっくり休ませてあげることが大切です。
・頭痛・腹痛・吐き気などの身体症状が続く
・爪噛みなどの落ち着かない行動が増える
・よく泣く/怯える/無気力に見える
・強い緊張や神経質な様子がある
・努力や挑戦を避ける傾向がある
・自己否定が強い
だけどもこのようなサインがないのに「行きたくない」と言う場合には、「行かせるか休ませるか」という2択ではなく、子どもの不安の強さや特性に合わせた、もうひとつの関わり方が必要です。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
指示出しゼロの子育てで
たった3週間で癇癪が着く!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.「休んでいいよ」と言ったら子どもが怒る理由
実は「休んでいいよ」は、子どもが安心する言葉ではないこともあります。なぜなら、子どもの「行きたくない」には、別の気持ちが隠れていることがあるからです。
◆「行きたくない」は本音じゃないこともある
子どもの「行きたくない」は、実は本音ではない場合もあります。
「どうしよう」「学校やだなぁ」と、一旦マイナスに揺れることで、気持ちを整えようとしているだけ、と言うこともあるんです。
これは、子ども自身がスイッチを入れるための『心の準備時間』
だから、すぐに言葉で介入せず、そっと見守る時間も大切なのです。

◆余計な刺激で、気持ちが逆戻りすることもある
そんなときに、「頑張って行こうよ!」とか 「じゃあ休んでいいよ」と言ってしまうと… 本当は「行こうかな」と思っていた子が、「やっぱりムリ」「やっぱりやだな…」と、逆戻りしてしまうことがあります。
子どもは、「不安だけど頑張りたい」「でも今はそっとしておいてほしい」 と心の中で揺れているのかもしれません。
だからこそ、子どもの様子をよく観察して、「今は声をかけるときなのか?」「それとも黙って見守るときか?」を見極めることが大切なんです。
繊細ちゃんに折れない心が育つ!
正しい甘やかし方がわかります
↓↓↓
3.「行きたくない」と泣く子が「行ってくるね!」と自分から登校できた、ママの関わり方
「学校に行きたくない」と泣いていた子どもが、自分から「行ってくるね!」と登校できるようになるには、ママの関わり方がとても大切です。
「休ませる?行かせる?」ではなく、その中間にある『待つ』という対応が、子どもの行動力を引き出すカギになります。
◆①見守ることで、行動力は引き出せる
娘は、長期休み明けや、授業や給食に不安がある日は、朝から不機嫌になったり、「行きたくない」と泣いたりすることがあります。
そんな時、以前の私は「じゃあ休んでもいいよ」と声をかけていました。
だけどある日、「本当は行きたいのに、ママが背中を押してくれなかった」と娘が感じていたことに気づきました。
それからは、すぐに答えを出すのではなく、少し待ってみることにしたのです。
これは、発達科学コミュニケーションで学んだ「保留」という関わり方。アドバイスや指示をする前に、一度ママの気持ちを止めて「待つ」ことです。
子どもの感情がまだ整っていないときに、周りの大人がどれだけ正しい言葉をかけても子どもの脳に届きません。
だから私は、「今はどんな気持ちかな?」「もう少ししたら、自分で動けるかもしれないな」 と、娘の様子を見て、『待つ』と言うことをするようにしました。

◆②気持ちを整えるには、使っている脳を変えてあげる
不安が強いと、脳の中で「ブレーキの役目」をしてくれる部分の働きが弱くなって、感情が暴走しやすくなります。
朝の娘が不安定なのは、まさにこの状態でした。しかし、ずっとその不安な感情にとらわれていると、動き出すのがもっと難しくなります。
そんなときは、「感情の脳」ばかりを使うのをやめて、 別の脳の部分――たとえば『考える力』や『手を動かす力』を使うことで、心が落ち着いてきます。
私は見守る中で、娘が自然と「気持ちを整えるための行動」を選んでいることに気づきました。
・今日の嫌なこと・楽しみなことの書き出し
・席替え後の理想の座席イラスト
・チラシの人物切り抜き工作
・あみだくじを作って遊ぶ
・漢字表で画数当てっこクイズ
どれも、感情の波に巻き込まれたままでいるのではなく、『考える・作る・遊ぶ』という行動を通して、少しずつ気持ちを整えていたのです。
私はその時間を大切にして、娘がやりたいことに付き合い、「それ楽しそうだね」「面白いアイデアだね」と声をかけていました。
そして毎回、娘がスッと切り替わった瞬間にこう言うのです。
「今なら行けそう。行ってくるね!」
自分で気持ちを整え、自分の意志で登校できるようになっていきました。
ママの『待つ力』で、子どもの行動力は変わる。
子どもの行き渋りに必要なのは、「行かせるor休ませる」の二択ではありません。
「この子に今、必要なのは何か?」と考える『間』を取ること。それが、ママの『保留』という関わり方です。
無理に励まさなくていい。 休ませるばかりでもない。 その中間にある『待つ』という対応が、 子どもの行動力と自信を引き出していきますよ。
繊細で不安が強い子の育て方に悩むママを応援する「脳科学の子育て情報」をお届けしています!
執筆者:藤井ハナ
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)