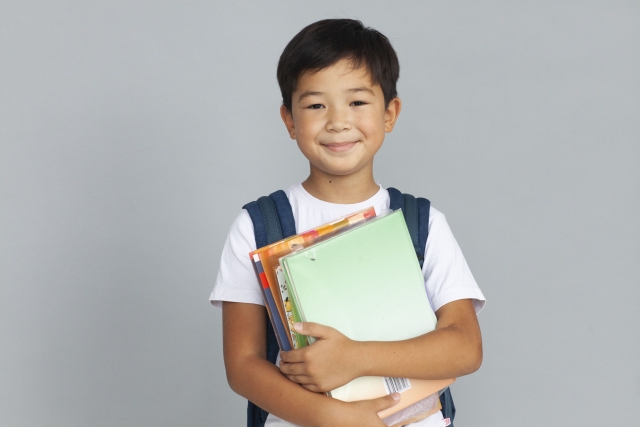「さっき言ったでしょ?」が口ぐせになっていませんか?知的障害の子の記憶力は覚えさせようと思っても上手くいきません。記憶の仕組みを理解し、日常でできる工夫とサポート方法をお伝えします。
【目次】
1.知的障害のわが子に「また忘れたの?」とついイライラしてしまう毎日
2.知的障害の子の記憶力が育ちにくい本当の理由
3.知的障害の子の記憶力を伸ばすためにおうちでできるサポート方法
1.知的障害のわが子に「また忘れたの?」とついイライラしてしまう毎日
「さっき言ったよね?」
「何度言ったら分かるの?」
知的障害のある子の子育てをしていると、こうしたやり取りが毎日のように繰り返されて、思わずイライラしてしまうことはありませんか?
記憶力の仕組みを理解してママがサポートする声かけに変えれば解決できます!
さっき「歯磨きするよ」と伝えたのに、別のことをやり始めて忘れている。
お出かけ先に「カバンを持っていくから準備をしてね」と伝えても、忘れて家を出ていく。
お出かけ先でカバンを置いてきて紛失するなど…
何度言っても覚えてくれない、忘れて違うことをしている姿を見て、ため息ばかりついていました。

これが“わざと忘れている”わけではなく、記憶力の問題なんだと知ったとき、はじめて「叱ることじゃない」と気づき、息子への見方が大きく変わりました。
何度も注意しても忘れ物が減らない、そんな忘れっぽい息子に対して、記憶力を伸ばす関りをすればいいんだと気付き、私は声かけを変えていくことをしました。
この記事では記憶の仕組みを理解し、実際にどんなサポートをしたら上手くいったのかお伝えしていきます。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.知的障害の子の記憶力が育ちにくい本当の理由
何度注意しても覚えられないのはなぜ?と思うのも無理はありません。
実は、「覚えられない」のではなく、脳の記憶の仕組みが影響しています。
人には大きく分けて2種類の記憶があります。
◆短期記憶
・一時的に覚える力(保持時間は約30秒〜1分程度)
・数に限界があり、すぐ消えてしまう
◆長期記憶
・繰り返し思い出すことで残る記憶
・感情や体験と結びつくと強く定着する
知的障害の子は「短期記憶(ワーキングメモリ)」が弱いことが多く、言われたことを一度で保持するのが難しいのです。
短期記憶(ワーキングメモリ)とは一時的に情報を覚えながら、頭の中で処理するための作業机のようなもの。

脳のキャパシティのことなんです。
ワーキングメモリが弱いとどうなるか?というと、一度に複数の情報を扱うと、脳がフリーズしてしまうんですね。
つまり、忘れ物が多い、言われたことをすぐ忘れるのは、脳の特性でキャパが足りていない状態だったんです。
でも安心してください。記憶は「短期記憶」だけで成り立っているわけではありません。
「長期記憶」につなげる工夫をすれば、弱さをカバーして力を伸ばすことができるんです。
長期記憶は「倉庫」のようなもので、繰り返し思い出したり、感情とセットにしたりすることでどんどん定着するんです。
つまり「記憶力=思い出せる力」を繰り返し・感情と結びつけることで記憶は強くなります。
「どうしてできないの?」と責めるように注意することは、記憶力は伸びるどころか萎縮させてしまいます。
でも、「記憶の仕組み」を知れば、対応を変えることができるのです。
事項では詳しい対応方法をお伝えしますね。
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.知的障害の子の記憶力を伸ばすためにおうちでできるサポート方法
記憶力は「覚えさせる」のではなく「思い出す経験を増やす」ことで伸びます。
ここからは、私が実際に取り入れて効果を感じた方法を3つご紹介します。
◆① 感情とセットにする
「面白い!」「なるほど!」と感じた情報は長期記憶に残りやすいです。
・九九を替え歌にして覚える
・漢字を電車の駅名や看板で見せる
・好きなキャラクターを使ってクイズにする
息子は電車好きだったので、駅名の漢字を一緒に読みながら楽しむうちに、自然と漢字に興味を持つようになりました。
息子の場合、電車という“好き”から広げていくことで、自然に記憶力の定着につながりました。
「好きなこと=得意分野」を入口にすると、苦手なことや一見関係なさそうな学びにもアプローチできるんです。
例えば、電車好きなら駅名から漢字に触れる、料理好きなら材料の数を数えて算数につなげる、といった具合に。
子どもの「好き」は、記憶を強く残すための最高のスイッチになります。
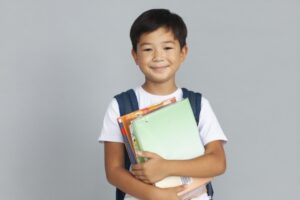
◆② 思い出す回数を増やす
何度も言いますが、「覚える」よりも「思い出す」方が記憶は定着します。
・指示をやめて、クイズ形式で質問する
・「ご飯が終わったね!次は何するの?」
・「準備できたね!何を持っていくんだっけ?」
・「今日は電車に乗るよ!何が必要かな?」
会話の中でさりげなく復習すると「覚えなきゃ!」とプレッシャーを感じずに自然と記憶が強化されます。
思い出せたときに、
「今日もICカード持ってこれたね!」
「カバンを自分で持ってるね!いいね」
「歯磨きを自分で覚えてたね!」
と伝えることで、自信にもつながり、さらに次の成功体験へと広がっていきます。
◆③ 成功体験を強調する
忘れたときに叱るのではなく、覚えられたときに「よく思い出せたね!」と伝える。
さらに「どうやって覚えたの?」と聞くと、自分なりの工夫が言語化され、次の成功につながります。
息子も段々カバンを意識して持つようになったり、自分で何が必要なのか出かける前に準備をするようになり、忘れ物が減っていきました。
知的障害の子が記憶できないのは、「能力がないから」ではなく「記憶の仕組みに合ったサポートがされていないから」だけなんです。
感情とセットにし、思い出す回数を増やし、成功体験を強調することを意識するだけで、子どもの記憶力は確実に育ちます。
「さっき言ったでしょ?」のイライラを、「よく覚えてたね!」の喜びに変えていきましょう!
知的障害キッズの行動力と会話力を引き出す対応をお伝えしています。
執筆者:みやび 楓
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)