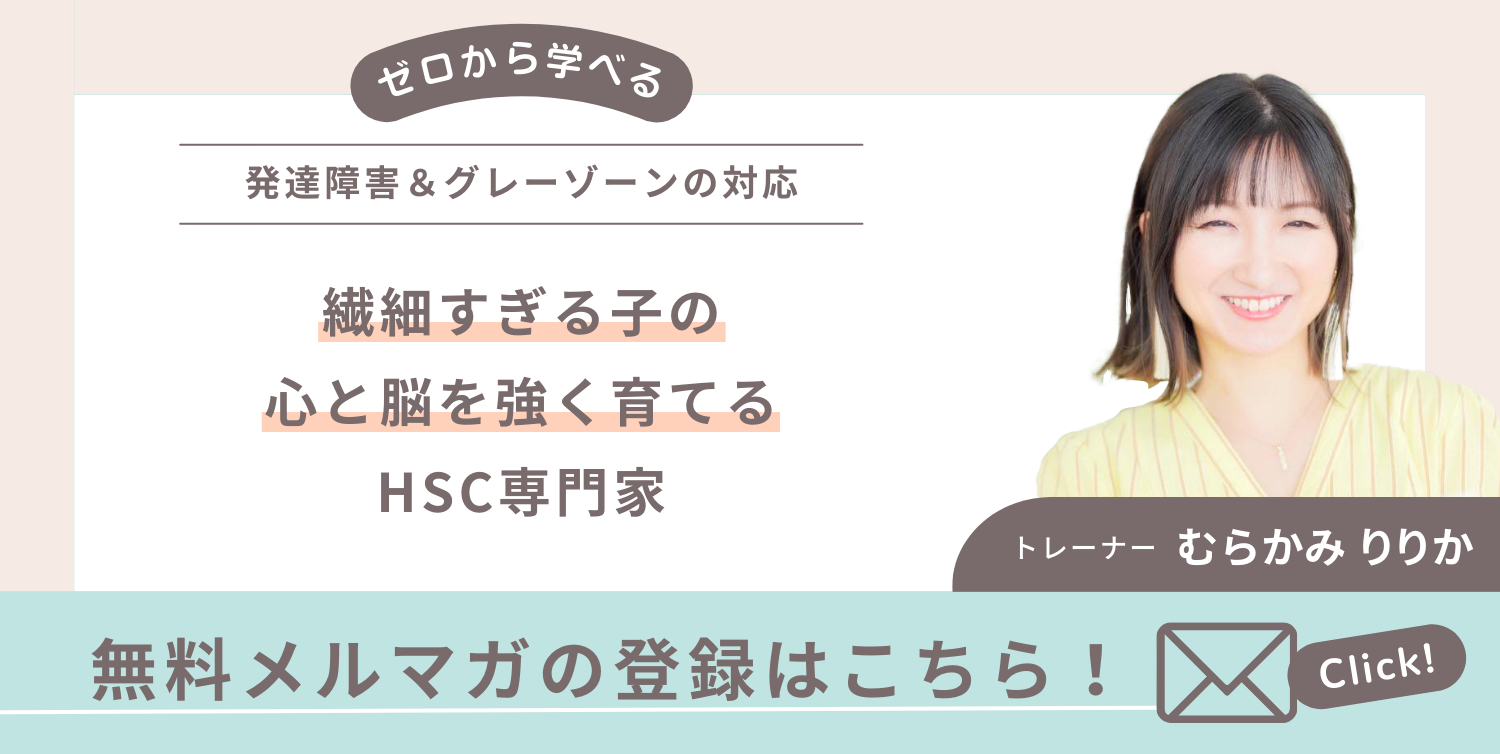小学生の繊細なわが子に友達がいない…。そんな事実を知ると心配になってしまいますよね。繊細な子は、脳の特性から友達とのコミュニケーションが苦手な子が多いです。その理由とママができるサポートをお伝えします。
【目次】
1.繊細な子が友達関係でつまづきやすい理由
◆刺激を受け取りやすい
◆ネガティブな感情と記憶を貯めやすい
2.「ぼく、お友達いない」と言うようになった息子
3.繊細な小学生のコミュニケーション力を育む秘訣
◆ママと1対1で「できた!」を積む
◆自己感情を育てる
1.繊細な子が友達関係でつまづきやすい理由
繊細な小学生の子どもを育てていると、
・友達がいない…
・うまくコミュニケーションが取れていない…
そんな様子を見て心配になることはありませんか?
繊細な子が友達関係でつまづきやすいのには、脳の特性が関係しています。
◆刺激を受け取りやすい
繊細な子が
・友達を作るのが苦手
・心が通うほどの仲になれない
・自分の気持ちが言えない
・気持ちのキャッチボールが苦手
・複雑な遊びや会話が苦手
このようになりやすいのは、脳が超高感度センサーを持っているからです。
周囲の音・声のトーン・相手の表情やちょっとした変化など、ひといちばい微細な情報も敏感にキャッチします。
「何か言われたけどどういう意味?」「何て言ったら分かってもらえるの…?」と、脳の中でぐるぐる大渋滞が起きて
・黙ってしまう
・固まってしまう
・アウトプットが上手くできない
そんな状況になってしまうのです。
そして「友達=苦手」とネガティブな感情と記憶が作られてしまいます。
「どうしよう」
「安心できる人と一緒にいたい」
「自分の殻にこもりたい」
という気持ちになり、「ママがいい」「お家がいい」と、安心を感じられる殻にこもって行きしぶりにもつながります。

◆ネガティブな感情と記憶を貯めやすい
人と関係を築くためには脳のあらゆる力が必要ですが、小学生同士のやりとりはお互い遠慮がないので、繊細な子にとってよりハードルが高いと言えます。
子どもたちの脳は、1対1のコミュニケーションから人との関わり方を学びますので、お家でのコミュニケーションが対人関係の基盤になります。
しかし繊細な子には
「寄り添いましょう」
「合わせてあげましょう」
「甘えさせてあげましょう」
と言われることが多いので、お家では大人が自分に合わせてくれるような親子の関係になりがちです。
自分の思い通りにならないような相手との、コミュニケーションに必要な言葉と感情のキャッチボールをする脳の力が十分に発達しておらず、
「同年代の友達=自分の思い通りにならない相手」と関係を構築していくことはかなりハードルが高くなってしまうのです。
外ではいい子なのに
家では癇癪に悩むママへ
家では癇癪に悩むママへ
指示出しゼロの子育てで
たった3週間で
手が付けられない癇癪が着く!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.「ぼく、お友達いない」と言うようになった息子
わが家の繊細くんもそうでした。
一人っ子で大人に囲まれて育ち、「外で頑張ってるし」「家では自由にさせてあげよう」と、お家では小さな王様のように、ある意味自由に育っていました。
合わせてあげられるので、大きく困ることはなかったのです。
集団生活がはじまると、自分に合わせてくれる先生とは話しても、心が通うお友達はできません。
最初は本人も気にしていない様子で、マイワールドを貫いているように見えていたのですが…年少、年中、年長と、どんどん周りの友達関係が進んでいくと
「ぼくお友達いない」
「ぼく嫌われてるの」
「遊ばないって言われたの」
と、悲しむようになっていきました。
どうにかしてあげたいものの、現場に私(母)はいません。
大人であっても対人関係の悩みって尽きないように、お友だち関係の苦手は一筋縄にはいかず長い戦いのはじまりでした。

私はそんな繊細くんと、毎日の会話でコミュニケーションのキャッチボールの練習を365日しました。
そしたら…緘黙と言われた子が、家族とも、先生とも、友達とも知らない誰かとも!上手にコミュニケーションがとれるようになり、友達関係で悩むことはなくなったのです。
「ぼくは体力をつけたいです。かぜをひいて学校を休んだ時、友達と遊べなくてつまらなかったからです。」
と、作文に書くほどに!
友達関係の悩みがなければ何でもない作文かもしれないのですが、長年友達関係をものすごく心配していた私は「良かった」と感動したのでした。
毎日の声かけで“脳のクセ”は変えられる!
子どもが持つ力を発揮できるようになる
4ステップの声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.繊細な小学生のコミュニケーション力を育む秘訣
「友達がいない」という繊細な子が、友達と関係を作れるようになるにはどうしたらよいのでしょうか?
その秘訣はお家でのママとのコミュニケーションで、自己感情を育てることです。
◆ママと1対1で「できた!」を積む
社会性の発達は「1対1」から始まります。
次に「1対2」「1対複数人」と徐々に広がっていきます。
発達には順番があるので、たとえ小学生でもここをすっとばして、集団の中で友達とのやりとりはうまくいかないのです!
なので、お家で安心できるママやパパと1対1で、自分の気持ちを伝える成功体験や「会話が楽しい!」という感情を育ててあげましょう!

◆自己感情を育てる
意識したいのは、子どもの感情の言葉化を手伝ってあげることで自己感情を育てることです。
子どもが何か言おうとする前に、良かれと思って子どもの気持ちを先に言ってしまったりしていませんか?
例えば、「お腹すいたの?おやつ食べる?」といった声かけです。
これでは、子どもが自分の気持ちを伝える場面がなくなってしまいます。
代わりに
「〇〇ちゃんはどうしたい?」
「〇〇くんはどう思ったの?」
こんなふうに問いかけてみてください。
お家で「わたしはこうしたい!」「ぼくはぼくでいいんだ!」と、自己感情が太く育っていけば、同級生が何て言ってこようが先生が何て言ってこようが自分軸を持てるようになります。
最初はなかなか答えられないかもしれませんが、少しずつできるようになっていきます。
小さな問いかけから繰り返していってくださいね!
コミュニケーションについてはこちらの動画でも解説しています!
▼人前で黙っちゃう繊細な子に言ってはいけないセリフ
この投稿をInstagramで見る
繊細な子どもの心と脳を強くする秘訣をお届けしています!
執筆者:むらかみりりか
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)