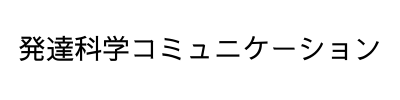おはようございます!
私が講座の中でお話ししている
環境づくりは
『構造化』
をもとにしています。
一見すると「片付け」なんですが
ちょっと意味合いが違うんです。
今日はそのお話をしますね^^
構造化とは
簡単に言うと5W1Hのこと。
どこで、誰が、いつ、どうするのか
を明確に整理することを指します。
これは日常にも実は溢れていて
例えば信号機
赤=止まれ
青=進め
誰に言われなくても
見ただけでルールを判断できますね。

「その場所を見ただけで
本人が気づいて適切な行動ができる」
要は言葉ではない「指示書」
の役割を果たすものなんです。
発達業界の中では
重度の自閉スペクトラム症の方々に
専門の施設などが取り扱ってきました。
元々の発祥は
アメリカのノースカロライナ州で
「Teacchプログラム」と言う名前で
活用されています。
私はこれを
お家でも簡単に取り入れられるように
行動を促す仕組みとして、
家の中が指示を出し
ママの声かけをサポートするような
役割を果たせるよう
講座の中でお話ししています。
では。
物事を整理し明確化する=構造化ならば
片付けとは何が違うのか。
片付けとは
散らかっていることを整理すること
え?同じでは?^^;
いえいえ、微妙に違うんです!!
片付けは実際に行動すること
構造化とは
行動できるように促す仕組みです
片付けが苦手なことの多い
パステルキッズの場合
そもそもそのやり方がわからない。
物が捨てられなかったり
定位置がどこかわからなかったり
片付けたくても
「何をどうしたらいいの?」
とわからないから動けない。
だからこそ
やり方が身につくまで
サポートしてあげる必要があります。
これは指示出しでもできることですが
コミュニケーションが
うまくいっていなかったり
受け止め方の違いから
ママの意図することが
伝わりづらく、
結局ママからしたら
「ちゃんとできてない!」
と指示したのにまた怒る
悪循環になってしまうケースも多い。
このミスコミュニケーションを
防げるのが構造化。

お互いの共通認識があるからこそ、
ゴールがここまでと言う
明確なものがあるからこそ、
必要以上の指示を出さなくても
環境が出している指示に気づいて
子どもが自分で動いてくれる
構造化には
そんなメリットがあるんです^^