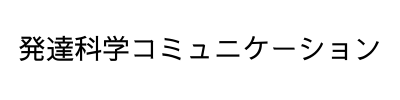ASDやADHDなど発達障害の特性は二次障害に発展しやすいと言われています。特に幼児の二次障害は、小学校に上がってからの不登校につながりやすく心配です。対応を間違えると悪化する可能性もある二次障害。わが家がどう克服したのかご紹介しますね。
幼児にも起こりうるASD・ADHDなど発達障害の幼児の二次障害
まだ幼児だけど、子どもの暴言・暴力、かんしゃくがひどくて…。
そんなお悩みをお持ちのお母さん、実は多くいらっしゃいます。
発達障害・自閉症スペクトラム障害(ASD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)などの特徴でもある癇癪や鬱々とした気持ちをそのままにしてしまうと、二次障害につながるおそれがあることをご存知でしょうか?
そもそも二次障害とはその人の特性に合わない環境化にいたことで、精神障害の合併や社会適応を困難にする行動の問題に至ってしまうことを指します。
例えば、人や自分に危害を加えたり、うつ病を発症することなどがそれにあたります。
「発達障害を持っているから二次障害も出る」ということでは決してありませんが、発達障害のお子さんは、対応を間違うと二次障害に陥りやすい傾向にあります。
幼児のうちに二次障害になると、小学校入学後の不登校へつながったり、うつなどの精神的な問題に発展してしまう可能性が高くなります。

そして、二次障害は放っておけばどんどん悪化します。
だから少しでも早く、それぞれの子どもの特性に合った対応をして、二次障害への進行を食い止めることが必要なのです!
ASD・ADHDの幼児が二次障害になりやすいのはどうして?
そもそも、ASDやADHDなどの発達障害の幼児が二次障害になりやすいのはどうしてなのでしょうか?
それは、ASDやADHDの特性が関係しています。
二次障害は、その原因の多くがストレスと言われており、長期間自分の中で蓄積されたものが表面化してしまうことで起こります。
発達障害の子どもたちはネガティブな記憶を残しやすいという特徴を持っており、私たちが思っている以上にストレスを抱えやすくなっているんです。
自分の言いたいことがうまく表現できなかったり、相手に伝わらなかったりという鬱々とした気持ちが積み重なることで、二次障害へと発展してしまうのです。

自身の衝動性や不注意という特性により、家族や保育園の先生などから叱られたり、お友達からからかわれたりする経験のある発達障害の子どもは多くいます。
どうしても失敗する経験が多くなってしまうことから、
「頑張っているのにどうしてうまくいかないんだろう」
「どうせ自分はダメなんだ」
という否定的な感情が大きくなり、自信を失っていきます。
このネガティブな感情の蓄積が、二次障害に発展するきっかけとなってしまうのです。
暴力、物の破壊…対応を間違えたことでどんどん手が付けられなくなった息子
我が家の長男は発達障害のグレーゾーンと診断を受けており、 自閉症スペクトラム(ASD)と注意欠陥多動性障害(ADHD)の特性があります。
その時々で出方が違うため、こだわりにより2時間近く何かに没頭していたかと思ったら不注意により急に興味が逸れることもあり、とにかくコロコロと変わる息子にどう対応してよいかずっと迷っていました。
更に感情はジェットコースターのようにふり幅が大きく、機嫌を損ねて癇癪に発展しないようにすることに必死。
とても本人の気持ちに寄り添う余裕なんてありませんでした。
結局これ!という方法がわからないまま、癇癪が出たときは力で抑えつけることしかできず、発達の特性が気になりだしてから1年近く経過した頃。
息子は次第に人に手を上げたり、威嚇したり、物を投げたりと攻撃性が強くなっていってしまいました。
まだたった3歳の幼児にも関わらず二次障害へと悪化させてしまったんです。
言葉が未熟なため暴言こそなかったものの、言葉にできない分、身体で怒りを表現しているようにも思えました。
ついには主人との取っ組み合いのすえ、家のドアに穴が空くという事態まで起こってしまったのです。
こんな状態にまでさせてしまった…。
当時は私自身も、
「こんな母親でごめんね。わかってあげられなくてごめんね」
と解決策を見出せない自分をただ責めることしかできませんでした。

二次障害を乗り越えるために一番優先すべきは子どもの気持ち
幼児という低年齢で二次障害を起こしてしまった息子ですが、5歳になった今では一切その攻撃性はなくなり素直で優しい子に成長してくれています。
どうして二次障害を乗り越えることができたのかを振り返ってみると、本人の気持ちに寄り添ったことが一番の理由でした。
これまでは、これはASDだからこういう対応がいいのかな?あれはADHDだからこういう対応がいいのかな?
と息子の行動を診断名に当てはめて、適当とされる対応をしてきました。
息子の本質と向き合った対応をしていなかったのです。
ASDであろうとADHDであろうと、息子は息子。
診断名で判断し、この問題行動はASDだからこう対処して… とマイナスなことに目を向けるのではなく、
彼の得意なこと、好きなことは何だろう?
何をしたら楽しいのかな?
と良いところやポジティブなことに目を向けるようにしていったんです。
そうすると、あんなに毎日、
「走らない!」
「早く支度して!」
「いい加減にしなさい!」
と怒鳴っていた自分から、
「ブロック、かっこいいの作ってるね!」
「もう着替えたの?はや~い!」
「〇〇君は、パズルが得意だね」
と自然と褒める声かけを増やすことができていきました。

息子自身も私に気持ちが伝わるということで安心してくれたのか、どんどん言葉を覚え、どんどん自分の気持ちを素直に話してくれるようになりました。
今では心から信頼してくれているんだなと息子の態度を見ていて感じています。
何より、暴れたり人に危害を加えるようなことが一切なくなったことで親子ともに大きなストレスから解放されることができました。
診断名はもちろん、子どもを知るうえでとても大切な指標です。その診断があるからこそ受けられる補助があることも事実です。
ただ、特性は環境やその子の成長によって出方が都度変わります。
以前の私のように診断に囚われてしまうがあまり、悪いことにしか目がいかなくなってしまっているお母さん!
今日からぜひ、お子さん自身のよいところに目を向けていきませんか?
▼無料電子書籍▼

▼1アクションできるお家の環境づくり!つい手が出てしまう発達凸凹幼児の対応にお悩みのママさんはこちら▼


お子さんの良いところを見つけるポイントを多数掲載しています。