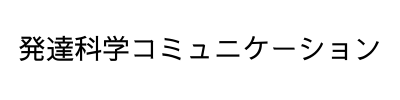おはようございます!
昨日は脳を育てると片付け力が上がるよ!
というお話をしました。
今日は我が家の
片付け力が皆無だった息子が
一人で片付けるようになった話をします。
息子はADHDとASD両方を持つ
グレーゾーンの小学校1年生です。
行動力があるADHDと
繊細なASD両面あるため
強引なんだけど傷つきやすい。
誤解を生じさせやすいタイプです。
そのため敢えて今は支援級に通い、
心のバランスの取り方を
ゆっくりと学んでいます^^
(勉強はいくらでもついていけますしね)
そんな息子さんは
元々は好きなことしかやらないため
着替えなどの支度や身辺自立
そして何と言っても
『片付け』をしない子でした。
一方、私は元々百貨店のバイヤーで
商品の陳列1つで売上が変わる
VMD(ヴィジュアルマーチャンダイジング)や
行動分析による『動線づくり』を
研究してきたのと
人生で10回以上
転居を繰り返した経験から
インテリアや
整理整頓、効率が大好き人間。
家の中も
簡単なDIYなどで棚を作ったり
常に快適に暮らせるには
どうしたらいいかを考えて
試すようなタイプでした。
なので、
いくら言っても片付けない息子と
常に散らかってる我が家は
とてつもないストレスだったんです。

(押入れの中を全部出さないと気が済まなかった当時)
散らかる度に片付けるから疲れる
けれども散らかってる状態も嫌。
ただでさえ、癇癪が酷く
切り替えができないから
一向に動かない息子との
日常生活をこなす中で、
子どもが散らかしたおもちゃや
登園グッズ
なんなら日用品まで
夜な夜な片付けては
何やってるんだ…
とため息ばかりでした。
当時は息子の特性が
どんなものでどう対応したらいいのか
なんてよくわからないまま
何度も何度も
配置を変え、
グッズを買っては試し
うまくいかずにイライラする
を繰り返していたんです。
ですが、今息子は帰ってきたら
ランドセルの中身を出して
定位置に片付けることが
習慣になっていますし、
おもちゃも
むやみに散らかさず
必要なものを取り出して
他のものは箱に戻すこともできています。

では、私が何をしたのか。
それが
私の声に「耳を傾けてくれる」
親子の関係性を構築する
声かけを学んだことでした。
環境づくりを専門にしておいて
こんなことを言うのも変な話ですが、
環境はあくまでキッカケです。
特に幼児は指示出しを理解する力が
まだまだ整っていないため、
指示しなくてもわかる環境は
とても重要です。
けれども環境を作ったらOKではなく、
その環境をどうして作ったのか
どうやって使うのか
それを子どもが理解して
やってみようと思わなければ
つまり、脳を発達させなくては
いくら環境を整えたって
それは自己満足でしかないんです。
私はずっと自己満足の環境を作り
それを守ってくれずに
散らかす息子にイライラしてたんですね。
「なんでまた散らかすの!」
「片付けないなら捨てるよ!」
これでは片付けることに対して
いいイメージが持てるわけはないですよね。
子どもへの声かけは
脳にダイレクトに届く発達支援です。
それがネガティブな声かけであれば
どんどん子どもは壁を作っていくし
ポジティブな声かけであれば
「ママが言うならやってみよう」になり、
行動するから脳が発達する
と言う好循環が生まれていきます。
片付けは正解がないからこそ
難易度は高い行動です。
低年齢の子にとっては
①やり方がわかる環境づくり
②片付けを習慣化する声かけ
この2つがあるからこそ
片付けと言う行動も
やれるようになるんです^^
やれるようになるんです^^