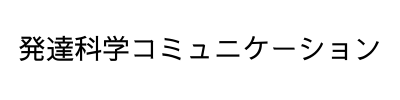おはようございます!
昨日は夏は子どものストレスが溜まり
ママの声が届きにくくなるから注意!
というお話をしました。
そもそもパステルキッズは
どういった時に
ストレスを感じるのでしょうか。
人によって個人差はありますが
光や音、皮膚などの感覚が過敏による
温度差や急な外的環境の変化や
うまく立ち回れず
怒られてしまった園や学校での生活や
イレギュラーな行事
など様々な理由が挙げられます。
中でも大きな要因と言われているのが
「意思が伝わらない」こと。
パステルキッズは
コミュニケーションが苦手な子が多く
喋れるけれど
気持ちを表現する適切な言葉を
その瞬間出すのが苦手で
誤解されてしまったり
怒られてしまうことが
何よりストレスを増やしています。
このコミュニケーション能力を
伸ばしてあげることで
子どもたちのストレスは
ぐんっと減るんですね。
そのためにも
まずはママとの関係性を
よくする環境づくりがとても大切。
なぜなら
今まで困りごとの多かった
パステルキッズに対する
「目」がママの中で
固まってしまっている場合が多いから。
「また何かやらかすんじゃないか」
「また何度言っても
動かないんじゃないか」
子どもの「できない」ことを探す
アンテナが
ママの中で育ってしまっているんですね。
そうすると
「やっぱりできなかった!」
というママのイライラを
起こしやすい状態になっているため
褒めることよりも
叱ることの方が
多くなってしまうんです。
ではどうしたら
その視点を変えられるか。
子どもの「できない」部分を観察し
「できる」ことまで
行動を分解します。
例えば
「着替えない」にも
そもそも着替える能力がまだないのか
着替える物がわからないのか
着替えるタイミングを
理解していないのか
着替えをすることを忘れてしまうのか
それによっても
ケアの方法は変わってきます。
着替える能力がない場合
例えば、
頭をくぐらせたら腕は通せる
のであれば
頭を通すまではママのサポートが
必要になりますよね。
年中さん、年長さんあたりになると
着替える能力はあるけど
朝着替えることを
忘れてしまっている
なんてことも結構多いので
それであれば
着替えを目の前に置いて
「あ、着替えるんだった」
と思い出す工夫をしてあげる。
こんな風に
我が子はどこができないんだろう
と観察して
できる環境を作ってあげる。

できることは
人間の脳にとって負担ではないので
自然と行動量を増やせますし
何よりママの「できない」探しが
徐々に「できる」探しに
変わってくるんです。
できる工夫をする
子どもが行動する
ママが褒める
(できる探しが上手になる)
コミュニケーションが増える
社会性が育つ
子どものストレスが緩和される
こんな図式ができていきます。
ぜひ困りごとの中の
子どもの「できる」ことを
まずは探してみてくださいね^^
では皆さま、良い週末を♪
\期間限定ダウンロード中/

▼ママの「できる探し」がうまくなるリビング作り▼