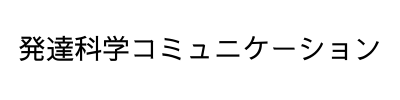発達障害・ADHD傾向の子どもにこそ身につけてほしい問題解決力。実は、片付けで身につけることができることをご存じですか?ここでは片付けを通して自分で積極的に問題に挑戦する力をつけていくポイントをお伝えします。
発達障害・ADHDにこそ身につけてほしい!問題解決力
日々生活をしていると、大きなことから小さなことまで様々な問題に直面します。
問題が起こるたびに、わたしたちは「どうしたらいい?」と考えて、ひとつひとつクリアしていっていますよね。
この力を問題解決力といいます。
具体的には、「発生した問題を分析して原因を洗い出し、解決策を考え、解決に導くスキル」のこと。
このスキルは、いろいろな場面でお子さんを助けてくれます。
特に発達障害・ADHDキッズは、学校や園で、特性による行動がトラブルにつながることが多いですが、
問題解決力が育ってくると、「こんな場面ではどうしたらいいかな?」と冷静に判断することができるようになるため、困りごとが少なくなります。

自分の状況を客観的に見ることができるようになるため、子どもにはぜひ身に着けてほしい力です。
この問題解決力、実はお片付けをすることで育てることができるんですよ。
日々のお片付けをするだけで問題解決力もアップできるなら、ぜひ子どもにはどんどんお片付けをさせたいですよね。
片付け上手になると問題解決力がUPする理由とは?
ではそもそも、片付けをすると問題解決をする力がつくのはなぜでしょうか?
お片付けとは、「散らばったものを適切な場所に戻す」ことを指します。
例えば、
遊んだあとのおもちゃをおもちゃ箱にしまう
物で散らかった部屋を整理整頓する
といった状況が思い浮かびますね。
この、部屋が散らかっている状態を「発生した問題」と捉えたとしたらどうでしょうか。
「どうしたら部屋がきれいになるのか」という解決策を考えていくかと思います。
まさにそれが「問題解決力」!
そのため片づけが習慣化すると、問題解決力が上がっていくと言われているんです。
お子さんが「片付けることはいいことなんだ!」と思ってくれたら それはもう問題解決力習得の第一歩です!

けれども、発達障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)キッズはお片付けが苦手な傾向にあるんです。
それは脳の発達がアンバランスなために 注意力が散漫だったり、記憶力が未熟だったりといった特性をもっているから。
そもそもADHD傾向のお子さんは、目から入る情報に強いと言われています。
そこに不注意さが加わることで、片付けている途中で他のおもちゃや興味惹くものが目に入ってしまい、そちらに意識が向いてしまうんです。
また、意外と多いのがお母さんが決めた片付ける場所を覚えていないということ。
子どもの脳は発達途中真っ只中のため、大人と比べても記憶力が育っていません。
特にADHD傾向のお子さんはワーキングメモリが弱いと言われており、決めたことを覚えておくということに高いハードルがあります。
どちらにしても、脳の発達が凸凹なために、「片付ける」という行為が苦手になってしまっています。
だからと言って、いつまでもお母さんが片付けるわけにもいかないですよね。
では、片づけが苦手な発達障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)キッズの問題解決力をアップするにはどうしたらよいのでしょうか?
問題解決力をアップさせるお片づけを習慣化させる2つのポイント
お片付けを問題解決力アップにつなげる 大きなポイントは2つあります。
◆「自分で決める」を経験する
最初から「どこに片付けるか自分で決めて」と言ったとしても、そもそもどうしてよいかわからないのです。
そのため、まずはお子さんがやりやすい片付けの方法を、お子さんと一緒に考えてあげてください。
導入としておすすめなのが、一番大切にしているおもちゃの定位置を決めることです。
例えばお気に入りのクレヨンがあったとします。
「クレヨン、どこに置いたらいいかな。いっぱい遊べるところがいいよね」と言った声掛けをお子さんにしてみてください。
おそらく大切なものは自分にとって取りやすい場所に置くと思います。
そこを基軸に、「じゃあ、他のお絵描き道具も一緒にしておこうね」 等とお母さんが同じようなおもちゃをまとめてあげてください。
もちろんすべてと言うわけではなく、興味があまりなさそうなものはお母さんでまとめてしまってもOKです。
ここでは1つでも「決める」という経験をすることが大切!
自分で決めたというエピソードが記憶として残りますし、なにより自信につながって、片づけることはいいことなんだ!というポジティブなイメージへ変わっていきます。
ここで気を付けたいのは、大人が片付ける場所を決めすぎないことです。
お母さんにとってよいと思う方法が子どもにとってもやりやすいかと言うと、 意外とそうではないことが多いのです。
特にこだわりの強い発達凸凹キッズにとってはその違和感が不快になり、「片付けたくない」 となってしまう可能性があるので注意してくださいね。
◆継続しようと思える声掛け
片づける場所がある程度決まったら、今度は片付けを習慣化させていきましょう。
ここでのポイントは声をかけるタイミングです。
よくありがちなのがすべて終わってから「よくできたね」と褒めること。
決して悪いことではないのですが、これだけだとお子さんが結果だけよければいいと判断してしまう可能性があったり、習慣化さる前だと途中で飽きてしまう可能性もあります。
そのため、1つできたら褒め、1つできたらほめ、というように途中経過で声をかけていきましょう。
「クレヨン片付けてるね!」
「あ、ブロックまできれいになってる!」
「え、じゃあぬいぐるみも一緒に片付けちゃおうか」
という風に、細かく声をかけてあげることでお子さんの「できた!」という自信につながっていきます。
ある程度慣れてくると、もしかしたら自分でやりやすいように少しずつ変えてくるかもしれません。
それこそまさに問題解決力が上がっている証拠!

子どもの脳は「どうしたらきれいに納まるかな」という思考でどんどん成長しています。
最初に決めた通りに片付けないからダメ! 結局ごちゃごちゃに箱に入ってる! とでき上がった形を評価するのではなく、
たとえ決めたところに片付けられなくても、「片付ける」という行動をしたことを褒めてあげてください。
そうすると、お子さんは自分で考えて片付けをするようになり、どんどん問題解決力が育っていくはずですよ!
▼無料電子書籍▼

▼1アクションできるお家の環境づくり!つい手が出てしまう発達凸凹幼児の対応にお悩みのママさんはこちら▼


子どもが自分で考えて行動する秘訣を多数お伝えしています。