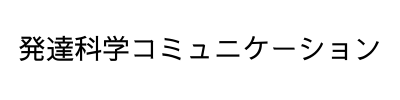天気が悪い日の子どものぐずぐずダラダラに悩んでいませんか?その原因は気圧の変化による自律神経が乱れ。特に発達障害で感覚過敏の特徴を持っているお子さんはより顕著に表れがちです。ここでは会話力が未熟な幼児のお子さんへの対応方法をお伝えします。
天気が悪いといつもぐずぐずする発達障害の子どもに困っていませんか?
みなさんは雨の日の前に頭が痛くなったり、なんとなくだるくなるご経験はありませんか?
我が家の発達障害グレーゾーンの息子は、天気が悪い時やぐずついている時は行き渋りが強かったり、いつも以上に切り替えがうまくできなかったりします。
この原因は自律神経の乱れが大きく関係しています。
気圧の急激な乱高下が自律神経を乱し、頭痛や吐き気、むくみ、倦怠感等につながっているのです。
この「なんだかだるい…」という状態を、専門用語で「気象病」と言います。

発達障害の子どもたちは、定型発達の子どもたち以上にそのストレスを強く感じてしまうため、結果的に気象病に陥りやすいんです。
ここ数年、異常気象や台風の乱発など気圧が変わりやすい天候が増えていますよね。
そのため、1年を通して心身の不調が出やすく、子どものぐずぐずやダラダラに困っているママも多いのではないでしょうか。
だからこそ、天候の変化にストレスを感じやすい発達障害の子どもの対応をママ自身が知っておくことが大切なのです。
どうして自律神経の乱れるとストレスが強くなってしまうの?
ではなぜ自律神経の乱れがストレスにつながってしまうのでしょうか?
自律神経とは血管や内臓などの働きをコントロールし、体内の環境を整える神経のことです。
自律神経には、私たちが活動している時に優位になる「交感神経」とリラックスしている時に優位になる「副交感神経」の2種類が存在しています。
人間はストレスを感じると、血管を収縮させ、体を興奮させるといった交感神経が活発になり、逆に、リラックスしている時は副交感神経により血管を広げていきます。
本来この二つの全く正反対な役割が交互に行われることで、私たちは健康的な暮らしができています。
ですが気圧の変化によりこの働きがアンバランスになることで、体や心にストレスを与え「なんだかだるい」につながっていくのです。
特に発達障害の子どもの中には、感覚過敏を持っている場合が多く、気圧の変化を敏感に感じ取るため、不調が出やすい傾向があります。
また、言葉の発達が未熟な幼児にとっては、不快な感情を言葉で表現することができないこともストレスに拍車をかける原因となります。
そのため。言葉にできないもやもやした気持ちが、癇癪やぐずぐずとした態度にでてしまうのです。

気圧の変化に備える!子どものストレスを予防するママの声かけ
自律神経は自分の意思とは全く関係なく作用するため、こんな時に
「いつまでダラダラしているの!」
と叱ってしまうのはかえってパニックを起こさせてしまうことにつながってしまいます。
そこで大切になってくるのは、「予防」という考え方です。
天気が悪くなりそうだなと思った時に、まずリラックスできる環境を整えてあげるのです。
例えばお風呂に長めに入ったり、好きな音楽をかけたり、寝る前のスキンシップとしてマッサージしてあげるのが効果的です。
特に体を温めてあげると副交感神経が優位になりリラックスできるので、入浴はおススメです。
湯船に浸かりながら今日の楽しかったことなどをおしゃべりできたら親子の会話力が上がってさらに良いですね。
また、即効性があるものとしては耳を温める方法です。
温めたタオルなどを耳の後ろあたりに当ててあげると、血行が良くなり自律神経が整う効果が得られます。
そして、環境以上に発達障害の幼児のお子さんへの対応として取り組んでいただきたいのが、お子さんの気持ちに寄り添ってあげることです。

まだまだ自分の感情が理解できない幼児のお子さんに対し、
「〇〇はやったの?」
「早く〇〇しなきゃ!」
というような声掛けは、かえって癇癪などの問題行動を起こしかねません。
そのため、もしいつも以上に行動がスムーズでなかったとしても 「天気が悪くなってきたからかな?」 と受け止めてあげ、ムリに行動させないであげてください。
「台風近づいてるから、なんだかだるいよね。ママもだよ~」
と寄り添ってあげると、お子さんの気持ちも軽くなります。
いかがでしたでしょうか?
気圧の変化によるぐずぐずダラダラを解消するには、
・リラックスする環境を作る
・子どもの気持ちに寄りそう
この2つがポイントです。
ママもお子さんも「なんだかだるいねぇ」の日はぜひのんびりすごしてくださいね。
▼無料電子書籍▼

▼1アクションできるお家の環境づくり!つい手が出てしまう発達凸凹幼児の対応にお悩みのママさんはこちら▼


子どものだらだらな行動にママがイライラしないで済む秘訣を多数お伝えしています。