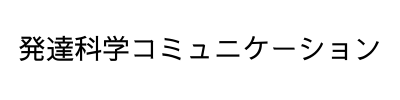おはようございます!
ちょっとトリッキーなタイトルですが笑
これは先日の年頭講義で
仲間と会話した中で出てきた言葉です。
「環境調整って実はママのため」
というお話を今日はします。
私は普段、
子どもの考動力を引き上げるための
環境づくりをお伝えしています。
例えばお片付け
子どもが片付けやすいように
散らかるのを防ぐために
どこに何を片付けるのか
ステッカーを貼ったり
物別ではなく、
色別で片付ける場所を分けたり
そもそものスペースを明確にしたり
いろんな方法があるわけですが、
そもそも片付けの良さがわからない子が
パステルキッズには多くいます。
さらに注意力散漫なタイプのお子さんは
次から次へと物を引っ張り出す。
片付けても片付けてもエンドレス!!
な状態にイライラするのは、
実はママなんですよね。

片付けの必要性を
理解していない子にとっては
片付けて!と言われても
「なぜ片付ける必要があるの?」
「なんか難しくてできない」
と中々行動に移せません。
けれどもママからしてみたら
「片付けてって言ったのに!」
「片付けないなら散らかさないで!」
とイライラが募る。
この感情のギャップが
親子トラブルに繋がるんです。
こんな時こそ、
環境調整の出番なわけです。
子どもは
「あ、これなら簡単だからできそう」
と思えば、自分から動き出します。
この動き出すのに必要なのは「脳の発達」
子どもの理解力や
行動力のレベルが上がることです。
そして脳の発達に必要なのは
「成功体験」です。
ママの声かけやお家の状態で
子どもが肯定され、
「できた!」を増やす必要があります。
もちろんこれが自然とできたら
苦労しないのですが、
日本はその子のレベルに合わせてではなく
「○歳でこれくらいできている」
という前提の元教育がなされています。
3年生になって急に授業が難しくなり、
学校が嫌いになる子も多いのですが、
これも「3年生になれば読解力が上がる」
という前提で問題が作られており、
突然授業のレベルが上がるために
起こっている現象です。
私たち自身が
そのような環境下で育っているため
つい
「○歳なのにこれもできない、
あれもできない」
とできないことにフォーカスしてしまい
イライラするんですね。
だからこそ、
環境を子どもの目線まで
落としてあげることが大切
なんです。
環境自体が
子どもが「できる」レベルになっていたら
子どもは言われなくても行動します。
行動が続けばママの目線がどんどん
「できている」ことに
向けられる癖がつくため
今までだったらイライラしていたことも
気にならなくなるどころか、
見えていなかった「できる」ことに
気づけるようになるんですね。
結局、環境調整って
子どもの発達フォローでもあり
ママの目線を変えるサポーター
でもあるんです。

本当は怒らずにいたいのに、
ついイライラして怒ってしまうママ。
接し方を変えたいと思っているママは
ぜひ環境調整から始めてみてくださいね^^