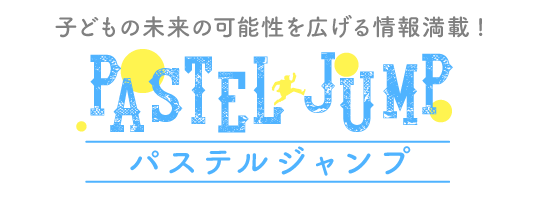1. クラス全体を巻き込んだ中学生男子の友達トラブルの原因
お子さんの学校での友達とのトラブルに悩んでいませんか?
友達とのコミュニケーションがうまくいかない、悪気なく言ったことで相手を怒らせてしまう…
我が家の中学一年生の息子がそうでした。
息子には発達障害、自閉症スペクトラム(ASD)があります。
不安が大きくなったり、強くやりたいことがあるときなど、相手の状況を考えられず一方的に話をしてしまうことがある、空気が読めない男子です。
例えば…
校外学習の前、班で準備に取り組んでいたときに、不安が大きくなると班長の友達になんでも質問していました。
最初はその都度答えてくれていましたが、あまりにもしつこく質問し続けたり、その友達が切羽詰まっているときでも変わらず一方的に話しかけたりした結果、限界を超え、
「いい加減にして!」
と大きな声で言われ、クラス全体を巻き込むトラブルに発展。
先生も加わり、授業時間をつぶし双方への聞き取りを行ったということがありました。
息子本人には悪気はなく、自分の不安を解消するために質問をしていたのですが、その友達の気持ちを察したり、表情や状況を考えたりせずに話しかけていたようでした。
息子には、
「相手の気持ちになってみて。」
「一方的に話さないで、話せる状況か考えてみて。」
と常々言っていたにも関わらず、起こってしまったトラブル。
今後、学校生活で同じようなことが起きれば、息子と関わることを避ける子も出てくることも考えられます。

どうしたら相手の表情、状況を見て行動することができるようになるだろうか、と悩みました。
私は息子が中学に入ったタイミングで発達科学コミュニケ―ション(発コミュ)を学び始めました。
そして、学ぶ中で、息子の友達トラブルの隠れた理由を知ることができました。
次にその隠れた理由を紐解きます!
今このサイトをお読みのあなたにおススメ
7500人の親子が実践中の声かけが無料!
▼詳しくはこちら▼
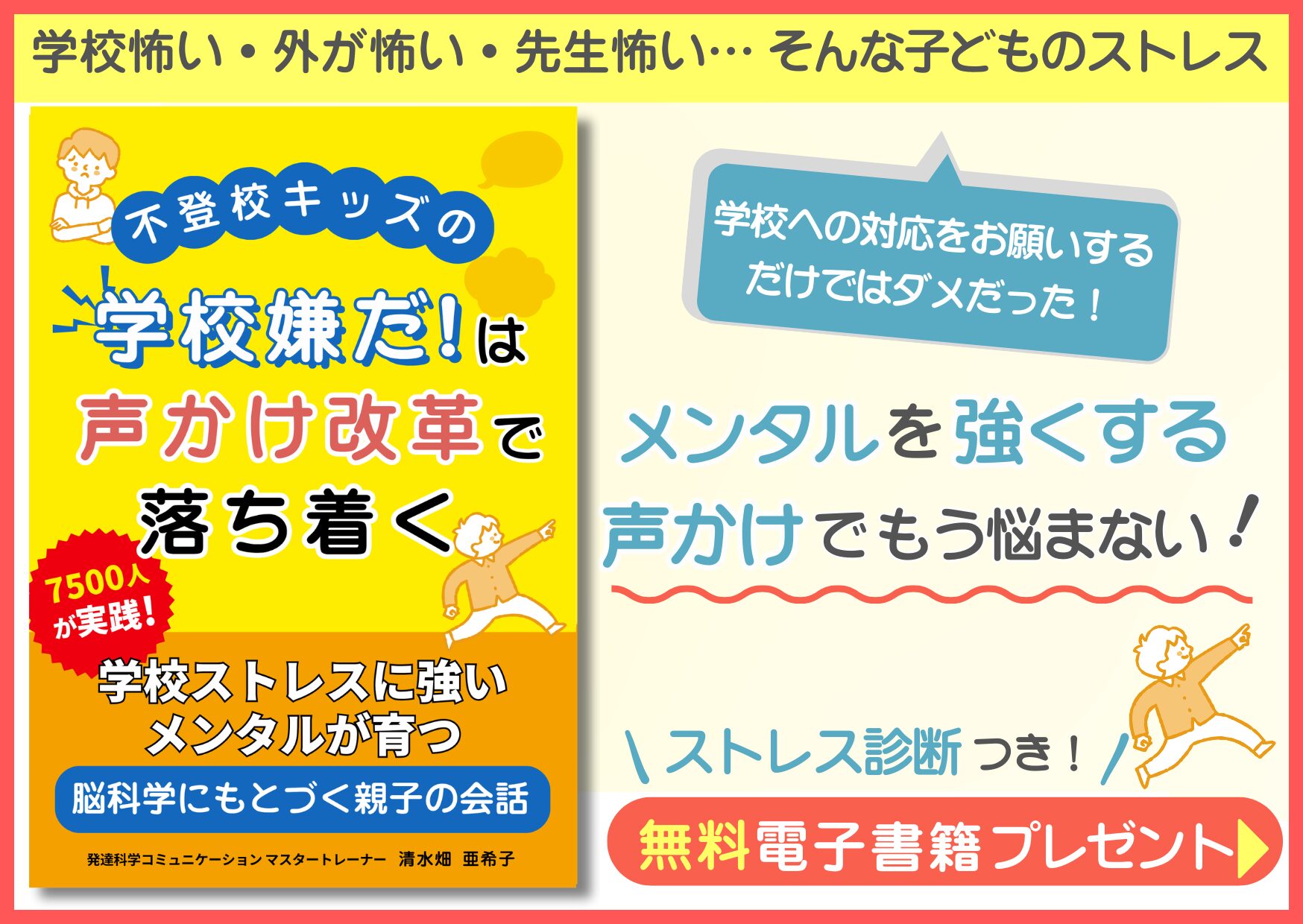
2. 発達障害の子のコミュニケーションを学んでわかった!空気を読むために育てたいのは「◯◯力」
相手の気持ちが考えられない、空気が読めない、その原因の一つは、状況理解の難しさだったのです。
状況理解には「見る力」が必要です。
「見る力」といっても色々あって、
・ぱっと見る
・じっと見る
・見ている人やものごとの状況を理解する
こんな3つの力にわけられます。
なかでも3つ目の「見ている人やものごとの状況を理解する」ことにつまずきがあり、状況や表情を見て、相手の気持ちを考えて行動することが苦手だと、友達トラブルが起こりやすくなる、ということなのです。
発達障害のある子の中には、この「状況を理解すること」が苦手な子がいます。
状況を理解しての発言、行動ができないため、しつこくして相手にいやな思いをさせてしまったり、場の空気を凍らせてしまったり。
トラブルを起こすことになります。
「状況」には、相手の都合や表情、どんな話をしているのか、何を話すときなのか、など、説明がなくても分からなくてはいければいけないことが含まれます。
そんな状況を理解・判断するためには、まず「目で状況を見ること」から始まります。
つまり空気を読めるようになるには、「意識して目で見る力」が必要になるのです。

友達とのトラブルの理由が、「見る力」の苦手さからくる状況理解の難しさであったことは、息子に相手の気持ちを考えて、一方的に話さないで、とばかり言っていた私にとって、意外なもので驚きました。
なかなか改善できなかった問題が改善できる「見る力」がつく方法をお伝えします。
"毎日学校に行けなくても大丈夫です!"
毎日の声かけを変えて
子どもの脳を育ててストレスをリセット!
▼今読めば進級進学前に間に合う!▼
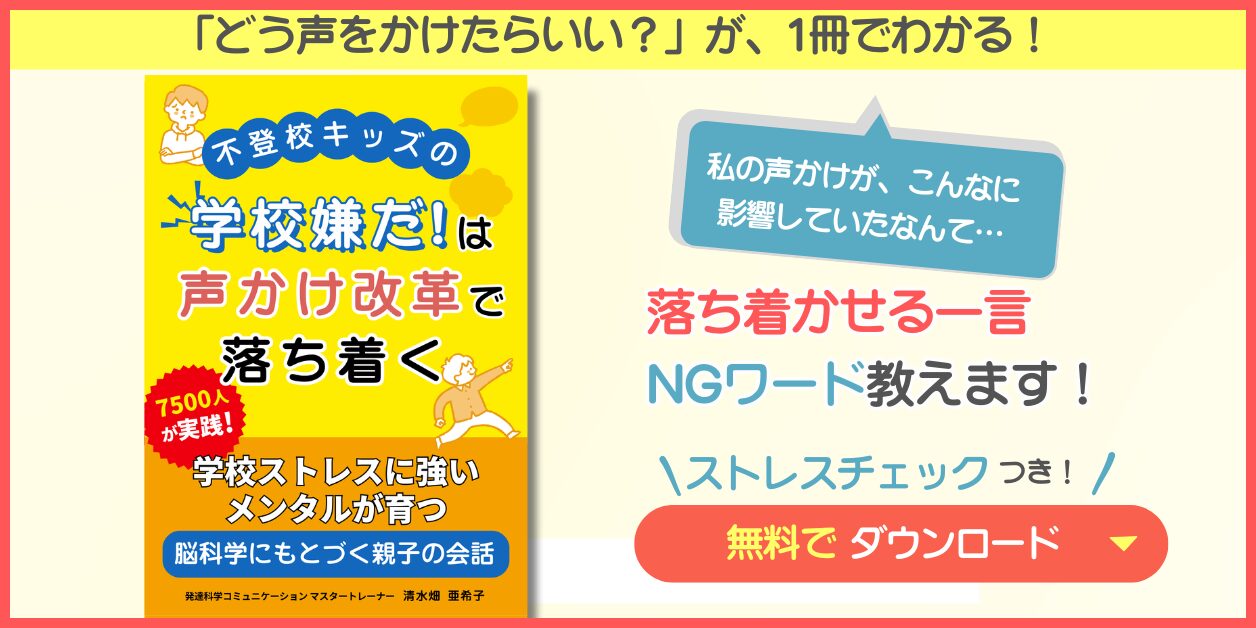
3. 親子で楽しく続けられる、隙間時間にできるおススメの取り組みはコレ!
発コミュで発達特性の正しい知識を学ぶ中で、息子の友達トラブルの意外な理由を知ることができました。
まずは
「相手の気持ちになってみて」
「人の気持ちを考えて」
「話せる状況か考えて」
などと言うことをやめました。
「見る力」をつけるために行ったのは、親子でできる楽しい人間観察です。
◆周りの人は何をしているかな?人間観察をしてみよう。
観察をすることで、何をしているのか、何が起こっているのかを予想していきます。
その時に、お母さんとの会話をしながら考えていることをアウトプットすることも大切です。
例えば、ショッピングモールで行きかう人を見ながら、
「あの女の子、泣いちゃってるね。どうしたのかな?」
「あの人の荷物、大きいけど、あの大きさのものって、何買ったんだろう?」
答えてくれたら、理由も聞いてみましょう。
正しい答えが分からなくてもいいのです。お母さんと一緒に考えてみて同じ答えだったら正解!とクイズのように行うのも楽しいですね。
通りすがりの人の観察が難しい場合、「仕事をしている人」の観察がおススメです。
例えば、フードコートのたこ焼きさんは並んでいるときに焼いているところが見えます。
「焼いている人は何を考えていると思う?」
「行列ができているけど、焼いている人から見るとどう思っているんだろうね。」
何の仕事をしているかが分かれば、それがヒントになり、考えやすくなりますし、表情や周りの状況も含めて、観察することで状況を理解する力がついてきます。
意識して自分の目で見ることが状況理解にはとても重要です。
情報を取り入れることで、はじめて状況を考えることができ、そして行動に繋がっていきます。
この積み重ねにより、相手の気持ちを考えられるようになったり、空気が読めるようになったり、コミュニケーションの改善に繋がっていくのです。
特別なトレーニングではなく、買い物に行ったときやお子さんの好きなものを食べにいったときなど、日々のお母さんとの会話で「状況理解」の力は鍛えることができます。

一緒に出かける機会が少ないなら、家でテレビを見ながら会話することでも同じようにできますよ。
「状況理解」の力を伸ばし、友達とのコミュニケーションがうまくできるようになってくると、学校生活での友達トラブルも少なくなってくるでしょう。


いかがでしたか?
思春期真っ只中の中学生は、トラブルについて正面から話そうとすると嫌がられることが多くなります。特に男子は母親に対して自分のことを話してくれなくなることも、お母さんを悩ませますよね。
そんなときには日常生活の中で、意識して「見る力」を伸ばすための会話をしてみてくださいね。
執筆者:三吉あいこ
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
▼中学生男子の友達トラブルには理由があります。親子の会話でお子さんをもっと伸ばしませんか?