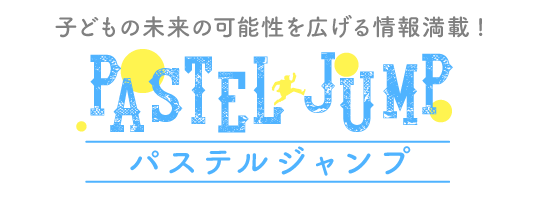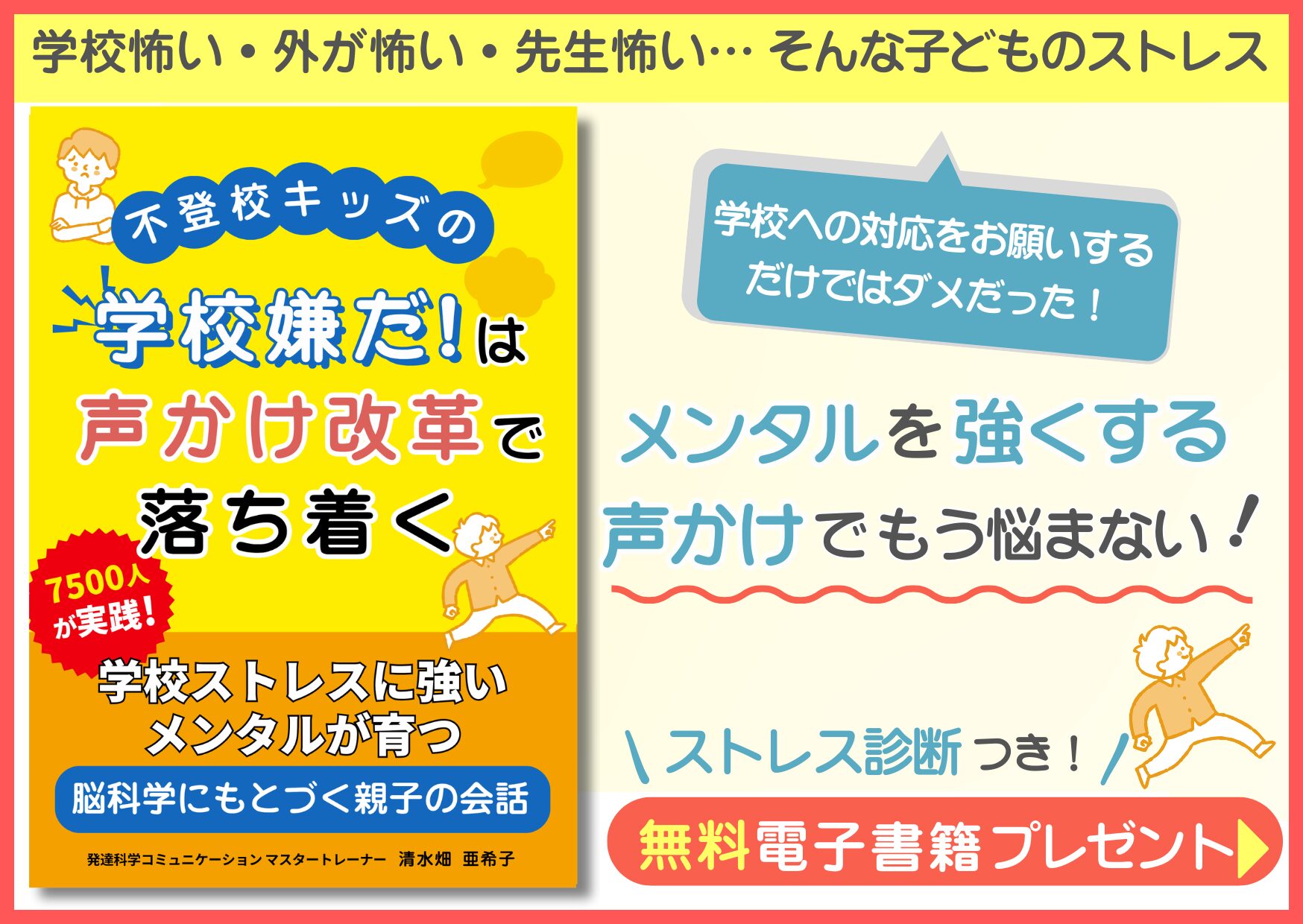1.自分の容姿に自信がない子どもの対応方法がわからなかった過去
思春期の女の子のお子さんが 、こんな発言をすることはありませんか?
「私って可愛くない」
「顔のここがイヤ!」
「整形したい!」
私には現在中学2年生の娘がいます。
娘はHSC(highly sensitive child ひといちばい敏感な子)です。自閉スペクトラム症グレー(ASDグレー)の特性も持っています。
小さなころから初めての場所や人がたくさんいるざわざわとしたところが苦手でした。
保育園に行くときも「行きたくない」と嫌がる毎日でしたので、仕事をしていた私は、無理やり支度をさせ嫌がる娘を保育園に送り届けていました。
小学校1年生の1年間は、学校だと母親の私と1メートル以上離れることができず、毎日母子登校をしていました。
私は、我が子の育てにくさや母子登校の経験から、心理学の先生に長くお世話になっていて対応がわからなければすぐ相談していました。 子育ての本も積極的に読みました。2年生になりひとりで学校に行けるようになってからも褒めることを続けていましたが、6年生になると徐々に体調不良の日が増え、夏休み明けに完全不登校になりました。
不登校になった娘はどんどん無気力状態になっていき、自分の容姿にも自信がなくなっていきました。

毎日鏡とにらめっこし「私は可愛くない」「奥二重じゃなくて二重になりたい」「整形したい!」というネガティブな発言ばかり言うようになりました。
「〇〇はそんな風に思うんだね」と寄り添ったり、「お母さんは〇〇の顔が好きだよ」「おばあちゃんが〇〇かわいいねって言ってたよ」と励ましたり気持ちを伝えましたが、褒めても「全然かわいくないよ」「家族だからそう思うだけだよ」と娘に伝わっていないように感じました。
私はこれまで子育てで困ったことがあると知識のある人に相談して悩みを解決してきました。しかし、トラブルがある度にどう声をかけるのがいいのかわからなくて不安になっていた私は自分で解決できる揺るがない軸がほしいと思い、 発達科学コミュニケーションで脳科学の知識とコミュニケーションを学び始めました。
発達科学コミュニケーションで学ぶことにより、今まで娘のできることを増やそうと思って頼まれたときに言っていた「自分でやってごらん」「〇〇ならできるよ」という言葉は逆効果だったということがわかりました。
2. 繊細な娘を頑張らせる言葉が心の自信も容姿の自信もうばっていたワケ
繊細すぎるHSCタイプの子どもは、人一倍敏感なので、視覚や聴覚などの五感や、新しい場所、新しいものなどすべてが刺激になります。
刺激になるのは、場所やものだけではありません。
まわりの人の気持ちを受け取る量や質にも敏感で、脳で受け取る情報が多くなり、とても疲れやすくなってしまうんです。
まわりの人の気持ちを察しすぎてしまうので、「きっともっと頑張れと思われている」「ちゃんとやらなきゃ認めてもらえない」
そんな風に思い、自分の気持ちを後回しにしてがんばりすぎてしまうこともあります。
周りに合わせて無理に頑張り続けることで、一見「いい子」に見えますが、自分の気持ちを見つめたり、落ち着けたり、人に伝える力はうまく育っていきません。
頭も心もいっぱいいっぱいになっているときに「自分でやってごらん」「〇〇ならできるよ」と声をかけられると、がんばりたい気持ちよりも「ひとりでやらなきゃ」「ちゃんとできないといけない」と焦りを感じてしまうことがあります。
本当は手伝ってほしかったり、そばにいてほしかっただけなのに、自分の気持ちをわかってもらえないと思わせてしまいます。
「自分でやってごらん」「〇〇ならできるよ」という子どもの自立を願ってかけた言葉は、子どもに「自分は大切にされていないのかもしれない」と認識させてしまう言葉なのです。
そんな自分に自信を持てない繊細な女の子が思春期になると気になるのが顔やスタイルのこと。
自分の気持ちに自信が持てないと、外見の容姿に対してもダメ出しをし始めます。
そして、
「もっと目が大きかったら自分は可愛い子になれるのに」
「もっと足が細かったら自信をもって人と関われるのに」
などと、歪んだ思考をもってしまいやすくなります。
本当に変えなくてはいけないのは、外見ではなく、「どんな自分でも尊い存在なんだ」と思える心なんです。

「自信がない子どもの自信を回復させ、「整形したい!」から「私って可愛い!」に変わり、自信が出てくる関わり方を2つお伝えします!
3. 今からでも遅くない!容姿に自信がない子どもの自信が回復する2つの方法
◆1「自分の要求は満たしてもらえる」と確信できる対応がカギ
子どもが、「あれ取って!」「あれやって!」「〇〇飲みたい!」「来てー!」と言ったときは決して突き放すのではなく、「親に甘えられる安心感」が伝わる対応をしてあげることが大事です。
まず子どものサインに敏感であることが大切です。愚痴っぽくなったり、怒ったりする前の小さなサインに気づいて声をかけることで、子どもは「自分の気持ちが伝わる」と安心します。
そして、できるだけ早く反応することも大切です。「困ったときにすぐ助けてもらえる」と感じることで親への信頼が深まります。
さらに毎回同じように対応することも大事です。日によって対応が変わると、自信がない子どもはどうしていいかわからなくなってしまいます。いつも変わらずに受け止めてもらえる経験を積むことで「自分は大切にされている」と感じ、自信を持つことができます。
私の娘は急に口数が少なくなったり、なんとなく元気がないように見えたとき、「話したくなったらいつでも聞くよ」と安心できる雰囲気作りをしました。
娘の横に座ったり、「ちょっと疲れてる?」とそっと声をかけたり、私を呼んだときには手を止めて顔を向けたり、目を合わせたりして「ちゃんと聞いてくれてる」と感じてもらうようにしました。
例えば、料理中ですぐに対応できないときは、「今ごはん作っているけど、あと5分で終わるから一緒に話そうね」とすぐ返事をします。無視されたと感じさせないことがポイントです。

しかし、子どもの心に寄り添うためには、まずお母さん自身の心が元気であることが大切です。自分の気持ちに余裕がないと、子どものサインにも気づきにくくなります。無理せず、自分をいたわる時間も大事にしてくださいね。
◆2「自分は大切な存在なんだ」と思える今からでも遅くない関わり
「自分は大切な存在」「自分にはできることがある」と思えると自信を持って行動することができます。
逆に「どうせ自分なんて…」と思ってしまうと、人の目が気になって自分らしくいられなくなります。
だからこそ、3歳まではたっぷり愛情を注いで「あなたがいて嬉しいよ」と伝えることが大切です。12歳から19歳の思春期には、批判せず認めてあげることがポイントです。
お子さんが、今すでに 思春期でも遅くはありません。今日からでも「あなたはそのままで大丈夫」と伝える関わりを始めれば、子どもは少しずつ自分に自信を持てるようになります。
子どもが朝起きてきたら、とびっきりの笑顔であいさつをします。発達障害やグレーゾーンの子どもたちは、目に見えないものを理解することが苦手なタイプが多いのでママの とびっきりの笑顔であれば褒められていることが伝わります。
「おはよう!」(あなたが起きてきてくれて嬉しいが伝わるような表情)
「おはよう!」(あなたを待ってたよが伝わるようなしぐさ)
「おはよう!今日も可愛い!」
子どもが話してきた内容が、自分の考えと違って意見を述べたくなっても「それはダメ!」と言わずに「そう思ったんだね」と気持ちを受け止めます。
何かを相談してきたとき、「あなたなら大丈夫」と信じて子どもに任せる姿勢を見せましょう。
"毎日学校に行けなくても大丈夫です!"
毎日の声かけを変えて
子どもの脳を育ててストレスをリセット!
▼今読めば進級進学前に間に合う!▼
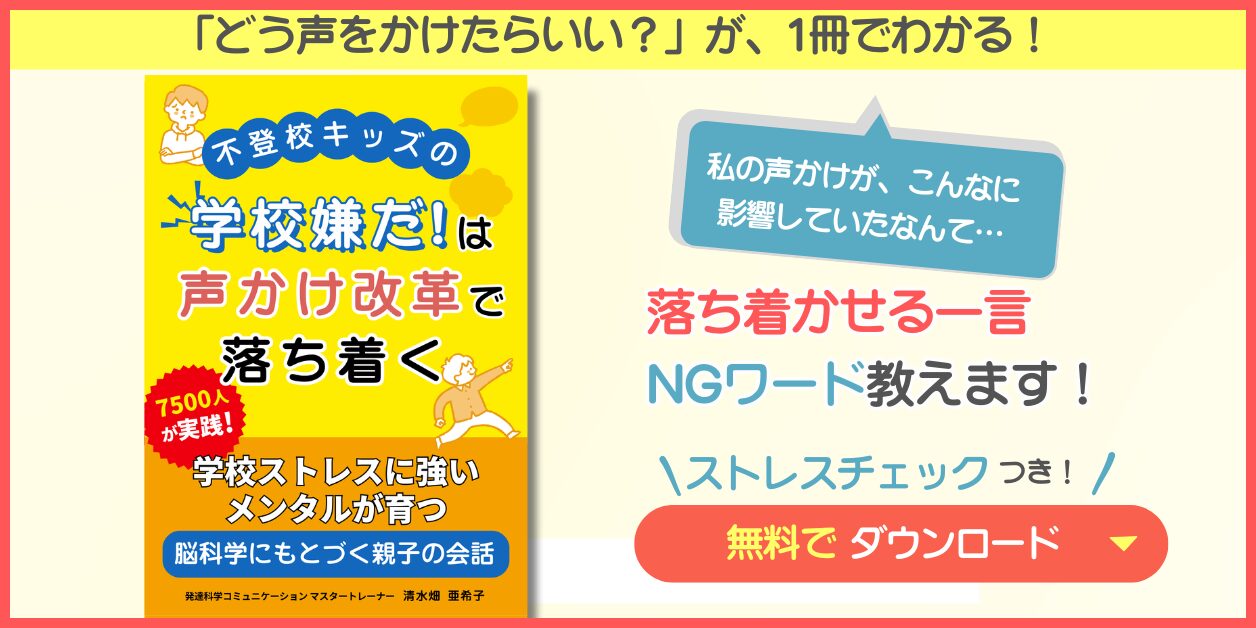
4.「私って可愛い!」に変わるくらいどんどん自信をつけていった娘
娘は、「私ってかわいい!」「私が私でよかった!」と、自信たっぷりの発言をするようになりました。
娘が憧れている人を教えてくれたときも「その憧れの人になれたら嬉しい?」と聞くと「私は私がいいから私以外の人になりたいと思わない」と言いました。
『ほおの出っぱりがイヤだからマッサージしてるよ』『リンパのツボをおしてあげると顔色が良くなるんだって!』と、自分なりに調べて『こうすればもっと良くなるかも』と考えて行動できるようになっていました。
「整形したい!」と娘が毎日のように真剣に悩んでいたときは、娘の自信回復のためなら…と、整形手術を信頼して受けられる美容外科はないか調べるほど、私も一緒に悩んでいました。
しかし、自信がない子どもに大切なのは、「見た目」ではなく「自分の存在そのもの」に価値があることを伝えることでした。

特別なことではなく、ただその子を信じて関わり続けた日々の積み重ねが、少しずつ、でも確実に心を癒していきました。
もし今、目の前のお子さんが自信をなくしているなら、あなたの関わりが、必ずその子の力になります。
ぜひ、あなたの大切なお子さんにも試してみてくださいね。
執筆者:黒柳ゆうみ
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
発達凸凹の自信がない思春期の子どもにたっぷり自信をつける関わりをお届けします。
▼▼▼