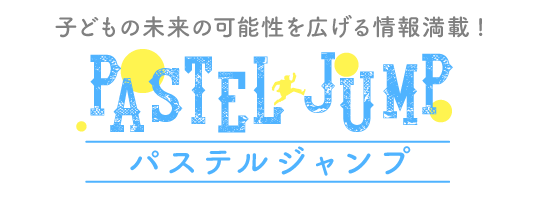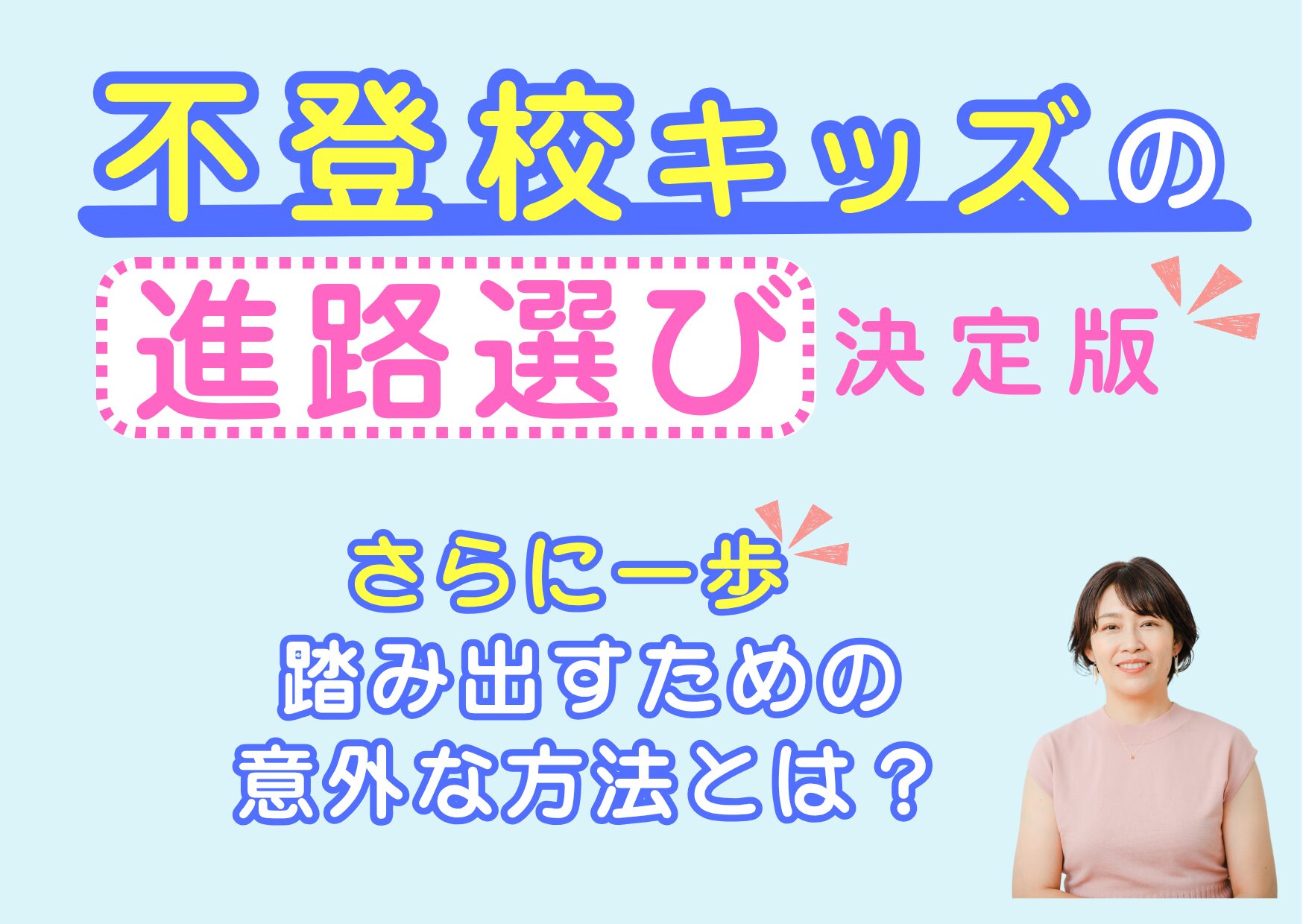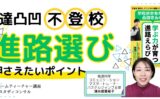1.不登校サポートは「安心づくり」だけでは足りない?
不登校キッズの回復ステップとして一番最初に到達したいのは「家が安心できる場所になること」です。
この状態を作ってあげるには、子どもへの要求値を”一旦”下げて、ストレスを軽くしてあげることが最優先です。
子どもの自尊心を傷つけずに、できていること、いいところに、目を向けることで子どもたちの傷ついた自己肯定感は回復します。
そうなると、子どもにとってはおウチが「快適」な居場所になるのですが、そうなると脳は居心地のいい状態を好むのでその状態がずーっと続いてしまうわけです。

よく、不登校サポートのいろんなメソッドで「見守りましょう」「エネルギーの回復を待ちましょう」と言われますが、それだけではうまくいかないのは、もしくは時間がかかるのは
次の一歩を踏み出すための戦略的な関わり方がないからなんですね。
「3学期も学校行けないかも…」
進級進学までに間に合うおウチ対応で
学校ストレスを溜めない子になる!
↓↓↓
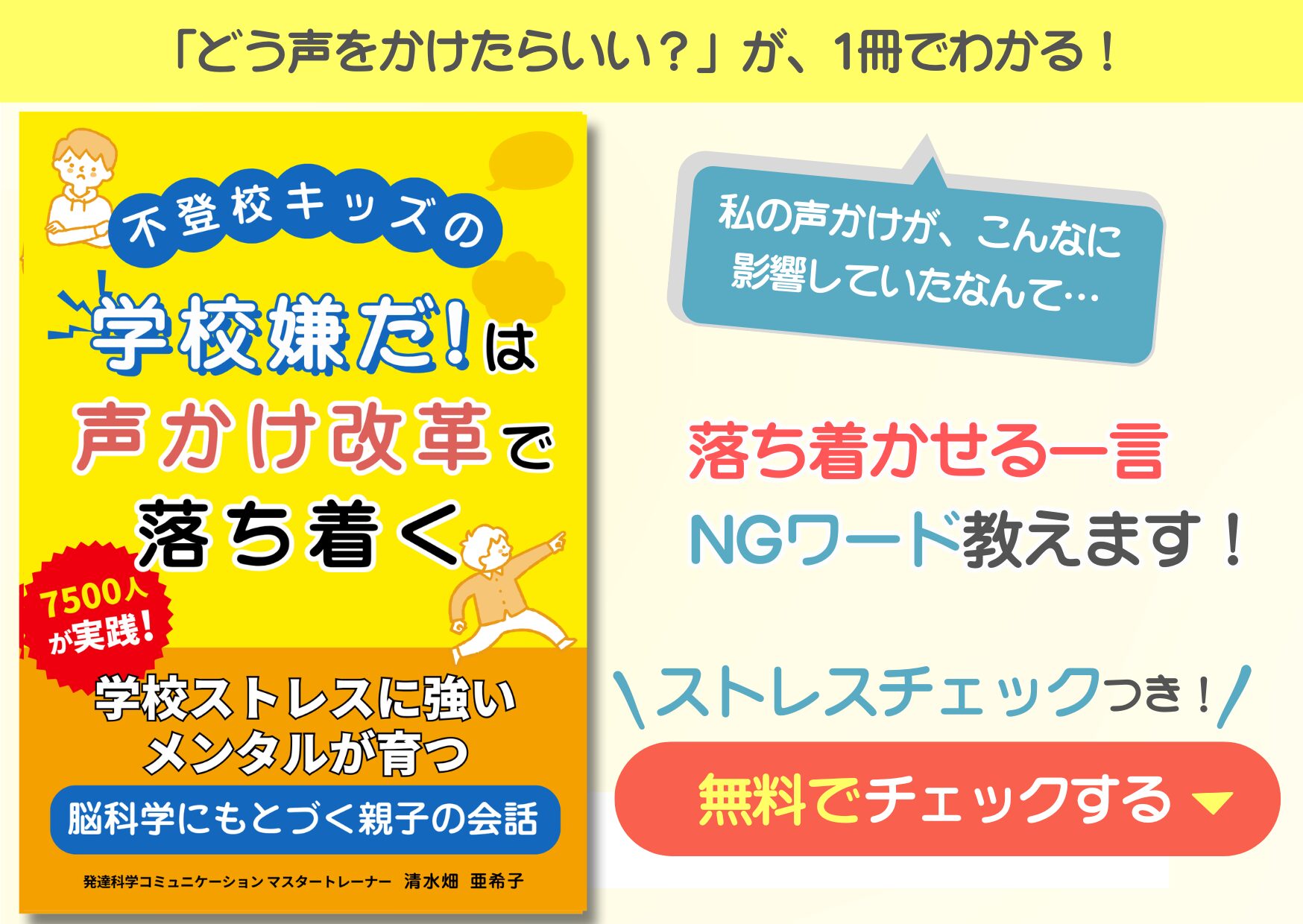
▲メールアドレスの登録で無料でダウンロードできます!
2.進路について話し合う前に、「行動する」ストレスに強くなることが必要!
家の中でやりたいことだけをやっている、毎日変わり映えしない生活ルーティンしか持っていない子は、脳が「楽な状態」から抜け出せないので
心理的ハードルの高い学校のことや進路のことを考える、というストレスレベルの高い行動はおこせないんですね〜。
学校や進路の話をできるようになるためには、行動の量を少しずつ増やしたり、バリエーションを変えてあげて
「行動することのストレス」に強くしてあげること。

今までと違う行動をすることは、脳にストレスがかかるんです。
ですが、その一方で、脳は、今のキャパをちょっと超えるくらいのストレスをかけることで成長していきます。
脳を使う範囲や場所を増やしてあげる・変えてあげるとぐーっと発達も加速します!!
3.ストレスのかけ方にはコツがいる!上手くいく方法とは?
えええ?
ストレスをかけていいんですか?と思いますよね?
これは、やり方を間違うとうまくいかないので注意が必要です。
じゃあどうすれば?
ポイントはストレスがかかっていると本人に気づかせずにしれっと脳に負荷をかけて脳を鍛えていくこと、です。
朝起きられない子に「早く起きなさい!」と言うだけなら、誰でもできるし(笑)
子どもはその声かけを聞くだけでイライラするから「ストレスを感じさせて」しまうし、結果、行動も起きない。
これを「朝ごはんのデザート、りんごがいい?ヨーグルトがいい?」
こんなふうに「好きなもの」を「本人に選ばせて」あげれば、嫌なことを言われた、命令された、強制された、というネガティブな受け取りにはならず、行動を引き出しやすくなっていきます。
お子さんが、「学校のこと、進路のことを、考えてもいいよー!」となるまでの2つ目のステップは、家の中での行動の量・バリエーションを増やしてあげること。
今回のテーマはここまでです。
次回はいよいよ、進路の話の核心にすすんでいきます。

学校が合わない凸凹さんの
学ぶ力が育つ進路選びガイドブック
無料プレゼント中です!
↓↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/9903/159520/
執筆者:清水畑 亜希子
(発達科学コミュニケーションマスタートレーナー)
学校が苦手な子でも自分で進路を選ぶためのヒントが見つかります▼