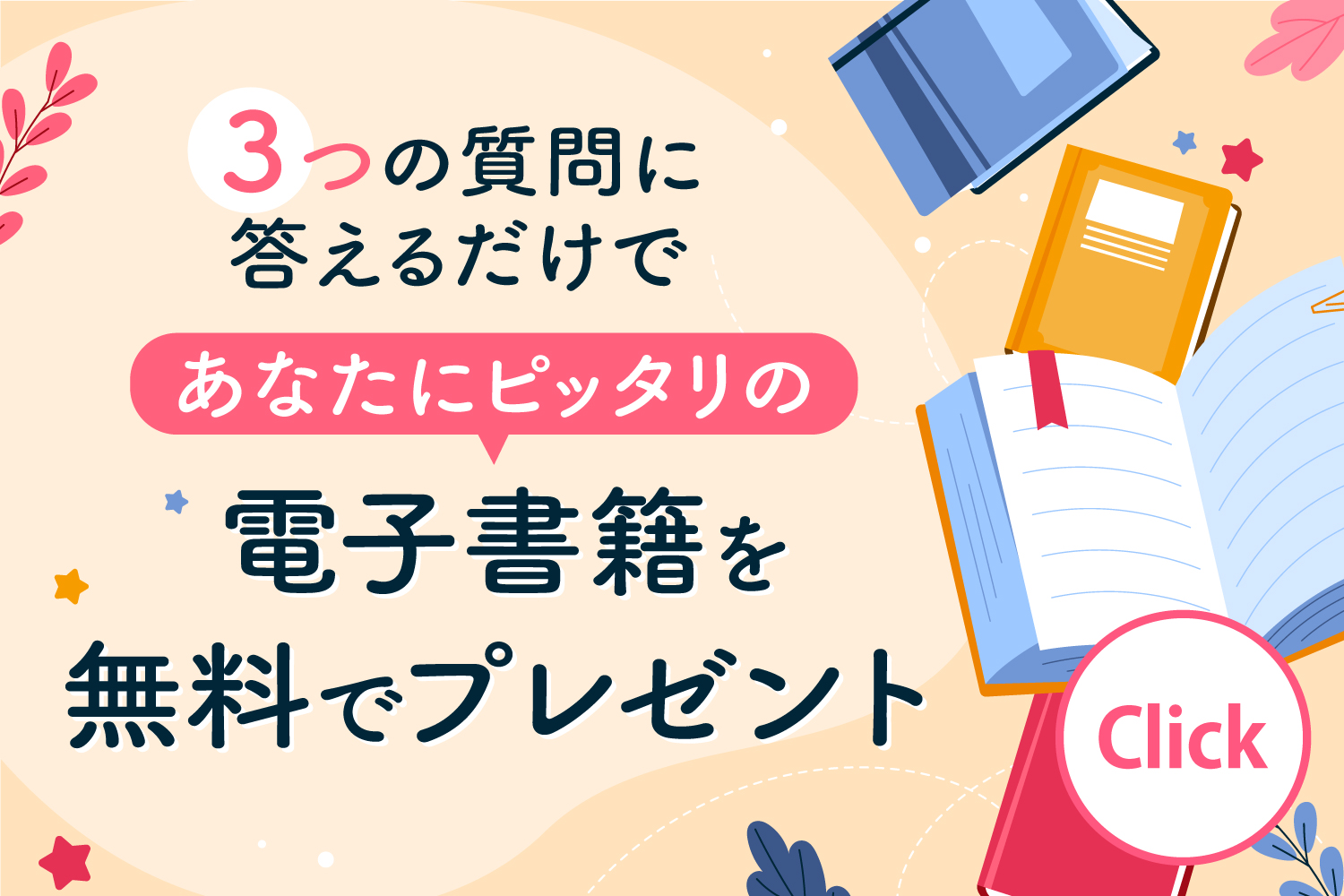境界知能のお子さんの知能を伸ばしたいとお考えではありませんか?境界知能の子どもは読解力・理解力をアップさせることで、ぐんと伸びるのです。授業についていけなかった息子がテストで高得点が取れるまでに成長した、読解力の身につけ方をお伝えします。
【目次】
1.境界知能の息子が授業についていけない
2.読解力はなぜ必要?
3.境界知能の小学生の読解力・理解力がない理由と困りごと
4.境界知能は伸びる!読解力UPでテストで高得点が取れる秘策
◆境界知能の子が夢中で本を読む環境づくり
◆知識と実体験を結び付けてアウトプットする
1.境界知能の息子が授業についていけない
境界知能のお子さんの知能を伸ばしたい!とお考えのことありませんか?
境界知能の子どもは読解力・理解力を上げることで、学習も理解できるようになり、ぐんと伸びるのです。
私の小学3年生の息子は、発達障害の注意欠如・多動症(ADHD)の傾向があり、知能検査(WISC)では6歳のときの知能指数(IQ)は73、8歳のときのIQは84と境界知能です。
息子は通常級に通っていますが、1年生の時は、授業に集中できず、聞いていないことも多く、1番前の席で担任の先生がサポートしてくださっていました。
音読の宿題も、文字を目で追うことがうまくいかず読んでいる場所がわからなくなってしまうことや、文字を組み合わせたまとまりを一つの意味のある単語として捉えることが難しく、文章を読んでも理解できていないことがありました。
またワーキングメモリーも低いため、読んだ文章を覚えていられないこともありました。

そのため、国語のテストの読む力を問われる問題では50点以下のことばかりでした。
当時の私は、1年生ですでに教科書やテストに書いてある文章を理解できない息子に対して、今後の学習面での不安を抱えていました。
このような読解力・理解力のない息子が国語のテストで高得点が取れるようになりましたので、こちらの記事ではその方法についてご紹介します。
子育てのお悩み解決BOOKプレゼント中!
↓↓
2.読解力はなぜ必要?
読解力をつけることは大切と一般的にいわれますが、なぜ読解力が必要なのかをお伝えしていきます。
読解力とは、文章を読み、書いてある内容の本質を理解し、自分なりに解釈することです。
そして本を読むときだけでなく、会話においても相手の意見の本質を理解することも含まれます。
読解力とは、文章を読み、書いてある内容や行間にこめられた思いをくみ取る力であり、筆者という人間と向き合うこと。読解力とは「人と向き合える力」のことなのです。「できる子は本をこう読んでいる小学生のための読解力をつける魔法の本棚」より引用
つまり、読解力があると、文章の理解だけでなく、他者とのコミュニケーションにおいても、相手の言いたいことを理解することができます。
そのため、学生時代においても社会人になっても、書かれている文章を理解すること、相手の話や気持ちを理解することは集団生活を送るためにもより良い人間関係を築くためにも必ず必要な力となります。
3.境界知能の小学生の読解力・理解力がない理由と困りごと
境界知能の小学生の場合、読解力や理解力がない理由として
・知っている言葉の数が少ない
・見る力が弱いことから書かれている言葉や文章を認識できない
・見る力が弱いことから相手の表情やその場の状況を読めない
・聞く力が弱いことから話している内容が理解できない
・覚える力が弱いことから書いてある内容・言われた内容を覚えておけない
・想像する力が弱いことから文章や会話の本質を推測できない
などがあげられます。

読解力がない理由はそのお子さんによりますが、読解力がないことにより、教科書や本に書かれている文章を理解できず、授業中に先生やお友達が話している内容が理解できずに、授業についていけなかったり、お友達との話し合いにもついていけないことにもつながります。
テストを受けても、書かれている文章を理解できない、問題の意図がわからないことで、何を答えたら良いかもわからず、答えを書くことができなかったり、ただ埋めるためだけに適当に書いてしまうこともあります。
休み時間や放課後にお友達と遊ぶときにも、相手の言いたいことや状況が理解できないと、うまくコミュニケーションが取れずに、楽しく遊ぶことができなくなります。
そのため、境界知能の小学生にとって、学習面や学校という集団生活、友人との交流においても、読解力・理解力をつけることはとても大切なことです。
境界知能の小学生は環境を整え、効果的な対応をすることでどんどん伸びることができます。
読解力をつけることで、より教科書の内容や授業が理解しやすくなり、お友達との交流も楽しめるようになります。
ぜひ読解力をつけてお子さんの学校生活も社会生活もより豊かなものにしていきたいですね。
発達グレーゾーンの困り事を
大人に持ち越さない
親子のコミュニケーションがわかります
↓↓↓
大人に持ち越さない
親子のコミュニケーションがわかります
↓↓↓
4.境界知能は伸びる!読解力UPでテストで高得点が取れる秘策
境界知能の息子に小3になった時から、意識的に関わり方を変えたことで、息子の読解力・理解力が伸び、学習面でうまくいくようになったので、その具体的な方法をお伝えします。
◆境界知能の子が夢中で本を読む環境づくり
子どもが楽しく、ママも楽に読解力を伸ばすためには、子どもの興味に合わせた読書環境を整えることが大切です。なぜなら興味のあることなら、自発的に読みたい!という気持ちになるからです。
私は息子の好きなこと・興味のあることは何かなと日頃からアンテナをはり、記録を残すようにしていました。
そして息子が例えば「イモリを飼いたい」「お金ってどうやって作るの?」などと言っていたときは、その興味はどんな本を読めば知ることができるかという視点で考え、調べるようにしていました。
そして実際に、イモリの生態や飼育の仕方の本、お金の作り方・歴史などお金にまつわる本を図書館で何冊か借りるようにしていました。
息子の興味のある本なので、息子も食い入るように読んでいました。
そして、どのページを読めば自分の知りたいことが書かれているのかを意識しながら読んでいたので自然と情報収集能力も身についていました。
息子は読みながら「ママ〜が載っているよ。〜なんだって。」と新たに発見したことを私に伝えてくれていました。
私は息子が何冊か読んでいた中で特に興味にヒットした、何度も読む本を購入するようにして、自宅の本棚に並べるようにしていたので、息子は何度も読むことができました。
息子の興味のある内容なので、知識の吸収も早く、また読んだ本の情報から「こんなところにイモリがいるから、実際に会いに行ってみたい」と家族で会いに行ってみるなど、息子の興味から世界が広がっていました。
このように、子どもの興味に合わせて読みたい本を読みたいときに読める環境があると、しぜんと子どもの読書時間が増えます。
つまり文字を目で追う回数が増えるため、追視の力、文字を音に変換する力、単語をまとまりで捉える力がつき、スラスラと文章を読めるようになります。
さらに子どもの興味あることなので、知的好奇心を刺激し、書かれている言葉や読んだ内容をどんどん理解し、語彙力や読み取る力につながります。

◆知識と実体験を結び付けてアウトプットする
読んだことを理解して、記憶に定着させていくためには、本に書いてあることと実体験を結びつけることが大切です。なぜなら、体験する時には五感を使って体感することができ、楽しみながら本の内容を理解することができます。
そして、わかった!楽しい!などの感情がわきおこるため、より記憶にも残りやすくなります。
実際に息子はイモリを飼いたいと思い、飼育の仕方の本を読んでいたので、飼育方法を覚えていました。
そして、実際にイモリを飼育することになったときも、「餌は〜をあげるんだよ」「水替えは〜日置きくらいがいいよ」など本から得た知識を使って飼育していました。
また、お金の本には、紙幣に隠されている偽造防止のための特殊な技が書かれており、実際に自宅にある紙幣を観察し「ほんとだ〜!光にかざすと線や人の顔が見えた〜」と感動していました。
息子は読書や実体験を通して、新しい発見による感動や面白いという感情を経験していました。
プラスの感情が伴うことはどんどん記憶に残ります。
そして、知りたい!という気持ちがあるので、本に書かれている文章や実体験の物事を読み取る力(読解力)・理解する力(理解力)がついていきます。
また、息子は新たに気づいたことを私に話してくれていたので、それも読解力をつけることにつながっています。
なぜなら、伝えるためにはそのことを理解し、記憶し、相手にわかるように自分の言葉で置き換える必要があるからです。
息子が本から得た情報を話してくれるたびに、私は「そうなの!?初めて知ったよ。教えてくれてありがとう」と肯定し、感謝することを意識しました。
時には質問することを継続していたので、息子はもっと話したいと思うようになり、どんどんアウトプットしてくれるようになりました。
このように、子どもの興味に合わせた読書環境にすること、本の内容と実体験を結びつけてアウトプットすることが、子どもの読解力・理解力の向上につながります。
その結果、小3の冬に持ち帰った国語テストの読解力を問われる問題が、数枚とも85~100点でした。
さらに自宅で教科書にそった問題集をしたところほぼ正解しており、息子の読解力・理解力が飛躍的に伸びたことに気づきました。
1年生のときに読解力がなく悩んでいたことが嘘のように、息子に読解力がついたのです。
興味のある本に囲まれ、好奇心に合わせて行動している息子はいつもイキイキと楽しそうにしています。
このように境界知能の小学生はいくらでも伸びることができるのです。
境界知能の小学生は可能性を秘めています。
関わり方次第でこれからも伸ばし続けることができるので、ぜひお子さんの興味に合わせた環境づくりでお子さんの力を伸ばしてあげてくださいね。
境界知能のお子さんの伸ばし方をご紹介しています!
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
育てにくい子が3ヶ月で変わる!
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
↓↓↓
執筆者:菅野 美香
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)