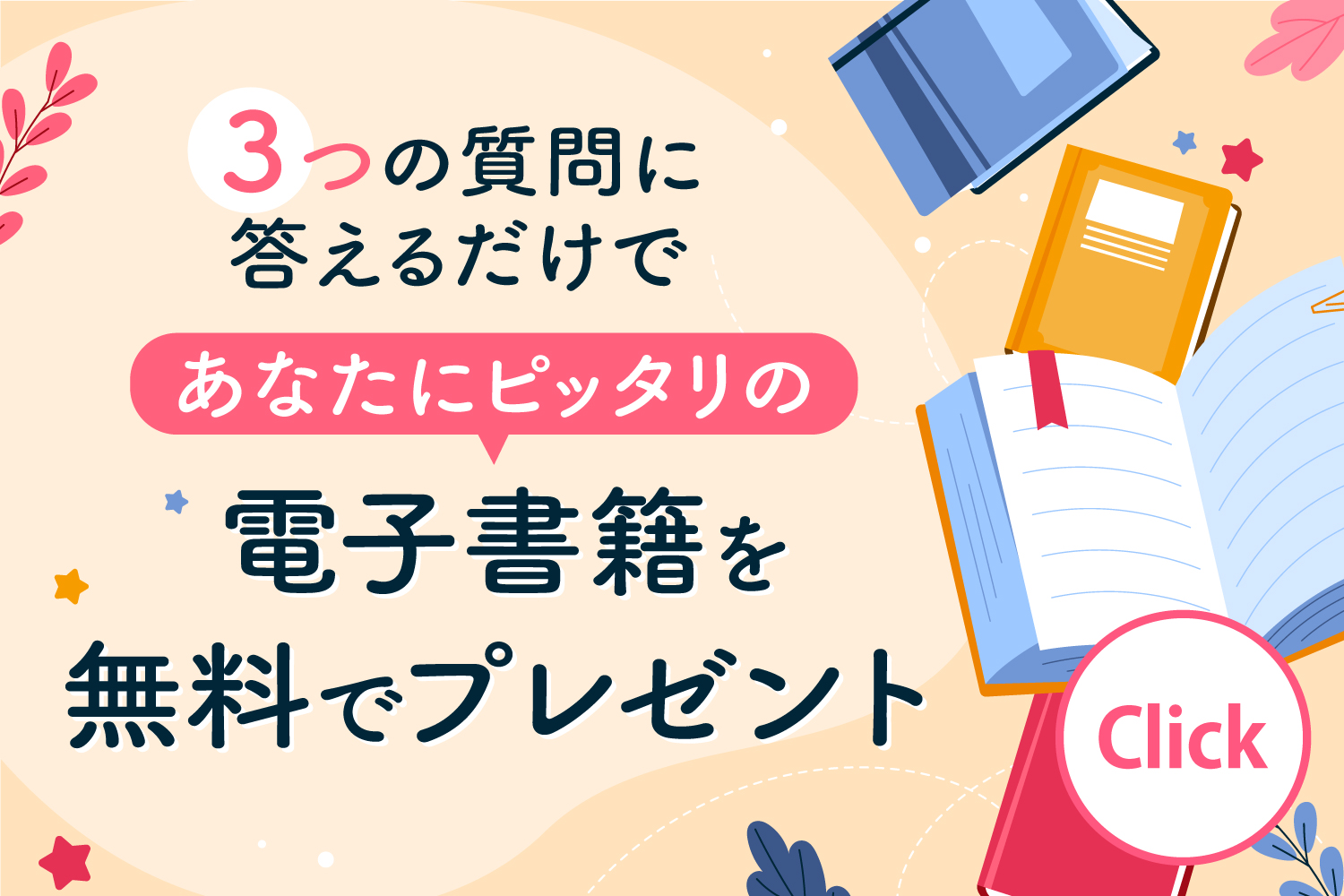車内でシートベルトを外して動きまわる、チャイルドシートは嫌がって座らないと悩んでいませんか?ママがある対応をすると、発達障害の子どもが3日で落ち着いて座れるようになりました。そんな驚きの方法をお伝えします。
【目次】
1.すぐにシートベルトを外す!チャイルドシートは嫌がる!車の移動に困っていた過去
2.なぜ、発達障害の子どもはシートベルトを外して動き回るの?
3.3日で解決!車内で静かに座る対応は2つのポイント
①叱る基準を決める
②短期集中
1.すぐにシートベルトを外す!チャイルドシートは嫌がる!車の移動に困っていた過去
お子さんは、どんなタイプのチャイルドシートを使用していますか?
赤ちゃんから3~4歳頃までは、一度装着すると簡単には抜け出せないような、しっかりとしたチャイルドシートに乗せることが多いと思います。
けれど、窮屈だ、暑い!などの理由から、嫌がってチャイルドシートに乗りたがらなくなっていくことがありますよね。
そうして成長とともに、持ち運びしやすいコンパクトなジュニアシートにシートベルトをつけて車に乗るスタイルになる子どもも多いのではないでしょうか。
ところが、ジュニアシートとシートベルトに変えた途端、走行中でもお構いなしに、シートベルトを外して車内を自由に動き回ってしまう。
そんなお悩みはありませんか?
タブレットを見せておいたり、目的地に着いたらお菓子やジュースなどのご褒美をあげるからね、と約束したりしてみましたが、なかなかうまくいきませんでした。
どうしても、出発して数分後には、シートベルトを外して前の座席やリアの部分に自由に移動してしまうのです。
そのたびに停車して注意し、子どもがシートベルトをつけるのを待つため、なかなか目的地にたどり着けず本当にイライラしていました。

何度注意しても改善せず、シートベルトを外して動き回る子どもをどうにもできずに怒ってしまうばかりでした。
時間が決まっている保育園・習い事への送迎時は、危険を感じながらも遅刻しないことを優先させる場合もあり、危険な行為に本当に悩んでいました。
2.なぜ、発達障害の子どもはシートベルトを外して動き回るの?
実は、車内で動き回る主な原因は、発達障害ADHDの子どもに多い「衝動性」の特性によるものが大きいのです。
衝動性があるということは、こうしたい!という欲求が強く、思いついたらすぐに行動してしまうということです。
好奇心旺盛な子どもにとって、景色がどんどん移り変わる車内は、目に入るものや聞こえる音など、とにかく刺激にあふれています。
「ねぇ、見て!」「あっ、あそこに〇〇が見えた!」など、あちこちが気になって大好きなお母さんに伝えたくて、なかなかじっとしていられません。
注意力散漫で、好奇心のほうが勝ってしまうので、車内は危険だから座りましょうと何度言われても、ついついお母さんの言葉を忘れてしまうのです。
けれど、このような脳の特性があったとしても、運転中に車内で動き回るのはとても危険ですよね。
もしも事故に遭ったら大怪我をしたり、他人を巻き込んでしまう恐れもありますし、道路交通法にも違反するので、早急に状況を改善する必要があります。

そこで、車内で動き始めたら叱る、という関わり方を変えたところ、3日で静かに落ち着いて座れるようになりました。その驚きの対応をお伝えしますね。
3.3日で解決!車内で静かに座る対応は2つのポイント
◆①叱る基準を決める
発達科学コミュニケーション(以下、発コミュ)では、子どもの問題行動が起きたときに感情的に叱るということはしません。
問題行動をやめさせるためには、まずお母さんが子どもの問題行動に注目せず、見て見ぬふりをします。
そして、問題行動をやめたときにすかさず褒めるという方法を取ることで、次第に子どもの問題行動が治まっていきます。
この対応は子どもを肯定しながら良くない行動を改善できるので、とても有効なのですが、解決までに少し時間が必要な場合があります。

当初の私は、車内での息子の問題行動に対し、シートベルトを外すことや、座席を移動しても、注目せずにスルーするという対応をしていました。
静かに座れたらきちんと褒めることもしていましたが、車内では運転に集中しているため、褒めるタイミングが見つけづらいこともありました。

しかし、車内でシートベルトを外して動き回るという行動は、危険なので早急に改善する必要があります。
そこで、別の対応を取ることにしました。
発コミュ対応の中で、唯一すぐに叱らなければいけない事は「許しがたい行動」の場合とされています。
つまり、自分や他人を傷つける危険な行為と倫理道徳に反することの2つに限られています。
車の運転中に、座席間を移動したり、運転席横の助手席でもシートベルトを外すことは、発達障害とは全く関係のない「許しがたい行為」だと考えました。
そして、正しい叱り方をすることで車内で静かに座れるようにしよう!と決めました。
◆②短期間集中
シートベルトを外すことなく、静かに座れるようになる叱り方を始めるにあたり
・短期間で集中的に取り組もう
・保育園や習い事へ遅刻しそうでも、一貫した対応を徹底しよう
と決めました。
そして、この期間は特に、車内での「許しがたい行動」以外のことは、とにかく良いところを見つけて褒めることを意識しました。
普段から口うるさく言うようなマイナスの注目を意識して減らすことで、より車内での叱り方が子どもに伝わりやすくなります。
今できている事を見つけてほめているため、叱ることで子どもの自信が失われるということもありません。
「許しがたい行動」に対しての叱り方は、以下の声のかけ方と、私の態度を貫き通すこと、この2つのポイントです。
・シートベルトをつけてね。外したら、すぐに車を停めるよ。(事前に予告する)
・シートベルトをつけたら出発するよ。
・シートベルトをつけたら〇〇に行けるよ。(目的地に行きたい息子にとって意味のある行動制限)
そして、シートに座ったら、座れたね!シートベルトをつけたら、シートベルトできたね!とその都度たくさん肯定の声かけをしました。
初日は、やはり最初に約束の声かけをしていてもシートベルトを外して移動を始めたので、シートベルトつけてくれないと危ないから停まるよ、と声かけしました。
声かけだけでは、行動を正してくれる様子がなかったため、予告通り安全なところに停車しました。
「シートベルトをつけられたらママ運転するね。〇〇に行けるよ」と冷静に伝えます。
初日は「嫌だ!いいからこのまま行って!」などと言われたり、イライラしている様子も見られましたが、態度を曲げずに貫きました。

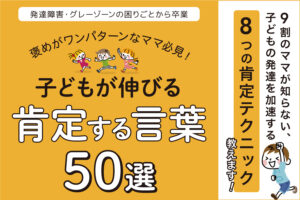
息子がイライラしている時には、感情に巻き込まれないよう冷静な態度で対応しました。
そして私の本気が伝わって座り直した際には、すぐに「シートベルトつけられたね!」と褒めました。
この対応で、たった3日で車内でしっかりと座ってくれるようになったのです。

時々、シートベルトを外して動きだしてしまうこともありますが、危ないからママ止まるねと声をかけると座りなおすといった形で行動が改善されています。
そのおかげで、私も運転に集中することができるようになり、車内で息子と何気ない会話をする時間も持てるようになりました。
車の中でじっとしていられないお子さんにお悩みの方、ぜひ試してみてくださいね!
▼あなたもすぐに褒めマスターになれる!▼
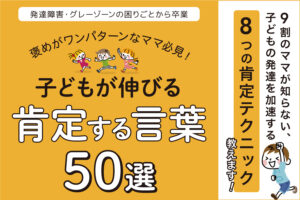
発達障害凸凹キッズとのかかわり方をお伝えしています
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
育てにくい子が3ヶ月で変わる!
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
↓↓↓
執筆者:守野有香
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)