アスペルガーの子が本ばかり読むことに、悩んでいませんか?読書好きはいいけれど、切り替えられない、疲れるほど本を読み過ぎる子どもには参りますよね。読書にこだわる理由と困り感を軽減する方法、好きを活かした行動力の伸ばし方をお伝えします。
【目次】
1.アスペルガー傾向の子が本ばかり読むことに困惑!
2.本を読み過ぎる発達障害の子どもが読書にこだわる理由
◆不安が軽減される
◆注意力が未熟
◆集中し過ぎる
3.読書好きな息子の「切り替え力」と「行動力」が伸びた!3つの対応
①見通しを持たせる
②興味関心を示す
③興味を行動につなげる
1.アスペルガー傾向の子が本ばかり読むことに困惑!
子どもが読書好きなのはとってもいいこと。
たくさんの言葉に親しんでほしい!と思いますし、好きなことは応援してあげたいですよね。
文部科学省も、「読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの」と位置づけています。
ですが、やるべきことそっちのけで本ばかり読んでいるお子さんに困ることはありませんか?
現在小学4年生でアスペルガーと注意欠陥多動性症候群(ADHD)の傾向がある私の息子も、読書好きです。
幼児期に文字に興味を持つと、好きなジャンルの本や説明書を熱心に読むようになりました。
自分の興味・関心への強いこだわりは、アスペルガータイプの強みですよね。
ところが、小学生になると身支度や宿題などやらなければならないことが増えます。
途端に、困る場面が多くなりました。
・ずっと本ばかり読んでいるので、朝の支度が進まない
・帰宅したらソファで読み始めて、夕食など声をかけても生返事
・寝る時間を守れない。読み過ぎて疲れている…
「やるべきことは先にやってから読んで!」と思わずイライラすることもありました。

そんな時、発達科学コミュニケーションに出会い、息子への対応を変えることができました。
「ブラックホールに吸い込まれるみたいに」読まずにはいられなかったと話す息子が、今では切り替えの時間が短くなりました。
それだけではなく、繰り返し読んだパソコン関係の本から知識を得て、今では我が家の「デジタル大臣」として活躍中です。
この記事では、読書が好き過ぎる子どもがやるべきことに切り替える力と好きなことから行動力を伸ばす親の関わり方をお伝えしたいと思います。
2.本を読み過ぎる発達障害の子どもが読書にこだわる理由
自閉スペクトラム症(ASD)・アスペルガー傾向のある息子が、 同じ本ばかり読んだり、切り替えが苦手なことには理由があります。
◆不安が軽減される
見通しを立てるのが苦手な息子は、いつもと違うことや変化に不安を感じやすいです。
この不安の強さが、「楽しいことは繰り返しずっと続けていたい」というこだわり行動につながります。
発達障害・グレーゾーンの子どもはみんなができていることに苦労する場面が多くありますよね。
日常生活をこなすだけで人の何倍も頑張っています。不安が強い子はなおさらです。
感覚過敏を持つ場合も多いので、刺激が多いと疲れてしまいます。
好きな読書に没頭すること、特に繰り返し読むことは周りの刺激を遮断して疲れを癒し、安心できる効果があるのです。
私はある時、息子が同じ本ばかり読む時は不安が大きい時期だと気づいて非常に納得がいきました。
◆注意力が未熟
アスペルガータイプは一度注意を向けたことに深く集中しすぎる傾向があるため、他の活動に移るのが難しくなります。
人間の注意力には4種類あり、
レベル1:一つのことに集中する
レベル2:大事な情報を選ぶ
レベル3:同時にいろんなことに注意を向ける
レベル4:今していることから別の行動に切り替える
この順番で難易度が高くなります。
ですから、息子にとって「レベル4:興味のあることから行動を切り替える」は、本来とても難しいことなのです。
◆③集中し過ぎる
アスペルガーの特性を持つ子はこだわりが強いため、環境や活動の変化に対応することが苦手です。変化を好まず、一つのことに集中してしまいやすいです。
このように、
・やり始めたことに深く集中しすぎる
・変化を好まない
・ストレスから逃れるために、同じ行動をし続けることで安心感を得る
という脳の特性により、過剰に読書に集中して他の活動に切り替えにくいのです。
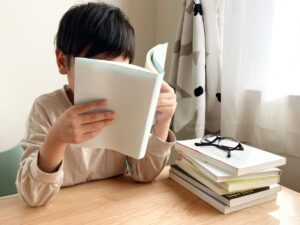
本を読み過ぎる理由を知ると、子どもに対するモヤモヤが少し軽くなりますね。
3.読書好きな息子の「切り替え力」と「行動力」が伸びた!3つの対応
このような特性のある子どもに普通に見通しを伝えても、なかなか読書から次の行動に切り替えられません。
そこで私が活用しているのが次の対応です。
◆①見通しを持たせる
切り替えの見通しを持たせるためには、予告とご褒美をセットで使います。
子どもが本を読み始める前に、
「タイマーが鳴ったら、しおりを挟んでおしまいにしようね。その後おやつにしようか」
と、終わった後の楽しい行動を提案し、タイマーを使って予告します。
終わりのタイミングが来たら、次の楽しい活動に誘えばいいので、切り替えがスムーズになります。
ずっと本を読んでいることによる疲れ過ぎも防げます。
◆②興味関心を示す
一方で、キリのいいところまで読み進めたい子どもの気持ちも分かってあげたいですよね。
子どもに近づいて、表情や残りのページ数、今どんな場面を読んでいるのかなどを見ると、声をかけるタイミングが掴みやすいですよ。
「面白そうだね」「この前の続きはどうなった?」
と、内容に興味を示してから、「どこまで読んだら終われそう?」と、やさしく聞いてあげましょう。
そして、たとえ途中でやめることができず約束の時間より遅くなっても、切り替えた時に必ず褒めます。
「できた時に褒める」を繰り返すと、子どもの脳に「切り替えるのはいいことだ!」という記憶が貯まり、スムーズに行動できるようになるからです。
また、いつも同じ時間帯に切り替えできなくて困る場合、食事やお風呂などルーテインの順番を入れ替えるだけで、親も子もストレスなく過ごせることがあります。
息子はこれらの対応を使って、徐々に切り替えがスムーズになりました。
焦らずに変化を見守っていきましょう!
◆③興味を行動につなげる
上記の声かけで子どもがどんな本を読んでいるか、何に興味関心を持ってるかが分かったら、それを広げる会話をします。
そして、日常生活の行動につなげる提案をしていきます。
車の図鑑が好きな子なら、車を洗う時に一緒にやらないか誘ってみます。
その時に、「クルマ博士の○○君」という風に、名前をつけてあげると子どもは乗ってきやすいです。 役割を全うしようとする気持ちが芽生えて、お手伝いを続けられるかもしれません。
車そのものでは思いつかなくても、「並べる」のが好き、「修理する」のが好き、などこだわりポイントを見つけると提案の幅がグンと広がりますよ。
物語が好きなら、本の中に出てくる場所にお出かけしたり、食べ物を作ってみたり、家族で同じ本を読んで感想を話し合ってみるのもいいですね!
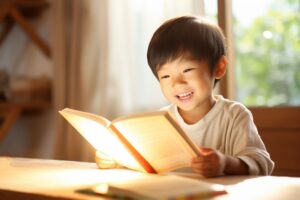
脳が成長するのは、楽しい活動をしている時です。
最近の息子は本で学んだIT知識を活かして、ミニ四駆のカスタマイズやパソコンの組み立てを自ら楽しみ、行動の幅を広げています。
修理関係とIT機器についてはわが家の「デジタル大臣」にお任せしています。
また、気持ちの理解に苦手さがあるにも関わらず、国語の文章題に意欲的に取り組めるのは読書で培った力だと思います。
適度な読書で気持ちが満たされると、やる気と行動力がアップします。
日常生活に支障がない程度であれば、読みたいだけ読ませて好奇心を満たすのも大事なことだと思います。
親も傍らで本を広げて一緒に読書を楽しめば、読み終えた後の会話が自然と弾みますよ。
お母さんが特性を理解して、お子さんが充実した読書タイムを過ごせますように。
アスペルガーの子が育てにくい理由がスラリと解ってラクになる!お役立ち情報をお届けします。
執筆者:小川陽子
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)





