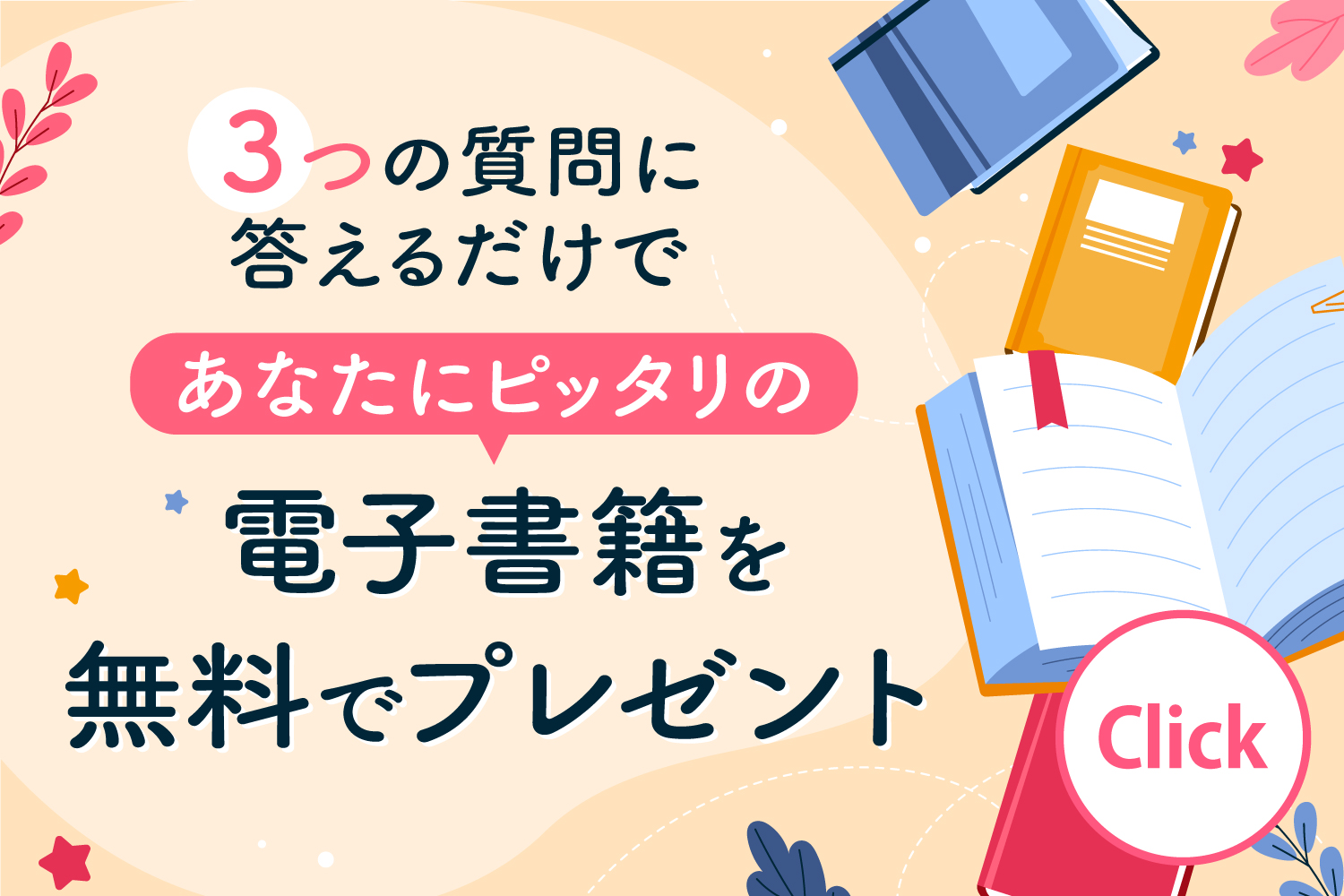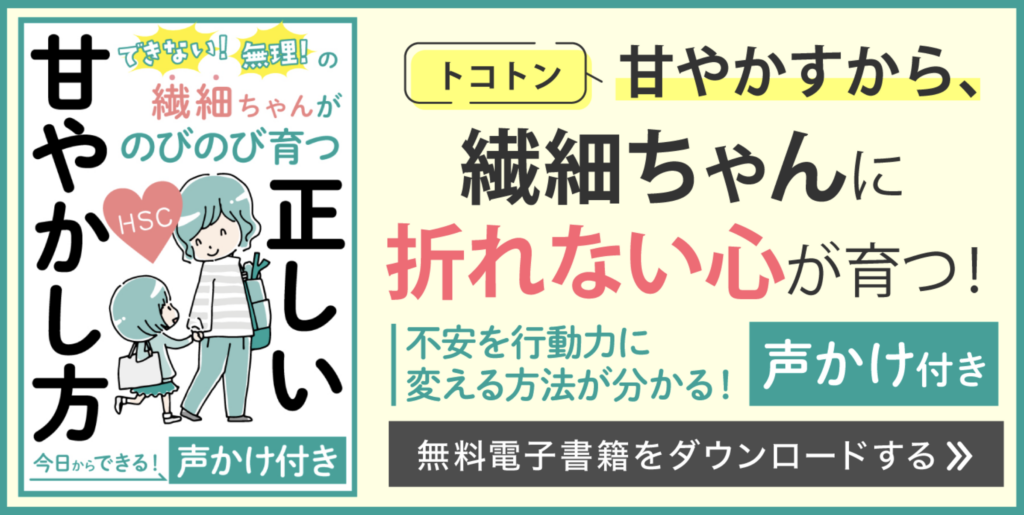ADHD・ASDの子どものおしゃべりが止まらないことに悩んでいませんか?一方的に自分の話ばかりする、早口で会話のペースについていけない…。発達障害の子がこんな話し方をする理由と、おうちで楽しくやりとりできるようになる対処法をご紹介します。
【目次】
1.発達障害の子どもが自分のことばかり話し続けるのにウンザリ!
2.ADHD・ASDの子の話し方の特徴とおしゃべりが止まらない理由
◆衝動性が強く、おしゃべりが止まらないタイプ
◆空気が読めず、早口でしゃべり続けるタイプ
3.一方的に自分のペースで話す子の話し方が変わる3つの対処法
①話すタイミングを約束する
②笑顔で遮らずに聞く
③ゆっくり合間を取ってしゃべる
1.発達障害の子どもが自分のことばかり話し続けるのにウンザリ!
子育て中のママはやることがいっぱいで毎日大忙し!にも関わらず、おしゃべり大好きなお子さんはその様子にお構いなし…。
・思いついたらすぐしゃべり出す
・話し出すと、おしゃべりが止まらない
・自分のことばかり一方的に話し続ける
・話すペースが速くて会話についていけない
こんなお子さんの話し方が気になったり、対処法に困っていませんか?
しつこく話しかけてきて、ずっとしゃべってる子に「忙しいから後でね!」とあしらったり、適当に聞き流したり、ついその場しのぎの対応をしてしまう。
公共交通機関の利用や映画館など大きな声で話してはいけない場所へのお出かけに、躊躇してしまうこともあるのではないでしょうか。
私の息子は注意欠陥多動性症候群(ADHD)と自閉スペクトラム症(ASD)の両方の気質を持っており、特に1年生の頃までこんな話し方が目立っていました。
唐突に、「思うんだけどさぁ…」と切り出して、ゲームの攻略法を一気に語り始めます。「ご飯だよ」と話しかけても自分の話ばかりで会話がかみ合いません。
忙しい時に手を止めないとならず、子どもの話に付き合うのが苦痛になりそうでした。
第一、「こんな話し方で友達とうまくやれるの?」と心配でした。

ですが、私の対応を変えることで少しづつ会話のキャッチボールを長く楽しめるようになりました。
その対応法をお伝えしますね。
2.ADHD・ASDの子の話し方の特徴とおしゃべりが止まらない理由
発達障害の特性を持つ子どもの話し方の特徴として、自分の話を一方的にしゃべり続けることが挙げられます。また、会話のペースが速く早口な子どももいます。
話し方の特徴が同じでも、ADHDとASDタイプでは理由が少し異なります。様々な特性を併発する子がいることも踏まえて、脳の特性を理解してあげることが大切です。
◆①衝動性が強く、おしゃべりが止まらないタイプ
思いつきで話す、自分のことばかりしゃべり続けてしまう子はADHDタイプに多いです。
これには、衝動性と注意のコントロールの苦手さの2つの特性が関係しています。
衝動性が強いと、待つことが難しく、じっとしていられません。
そのため、
・思いついたそばから話しだす
・一気に話す、おしゃべりが止まらない
・話してはいけない時もついしゃべってしまう
といったことが起こります。
また、注意のコントロールが苦手で、話すことに過剰に集中したり、興味の移り変わりが激しかったりします。
おしゃべりに夢中になりすぎて話すスピードが速くなる、自分の話ばかりしてしまう。話題が次々に変わりやすいことから、相手が話のペースについていけず自分勝手な印象を与えることがあります。
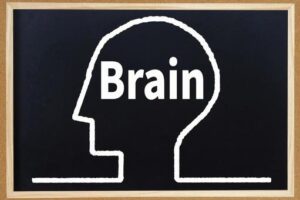
◆②空気が読めず、早口でしゃべり続けるタイプ
ASDやアスペルガーの特性がある子は、早口で一方的におしゃべりするため会話が成り立ちにくい傾向があります。
相手の立場に立つことが苦手なため、相手が会話に入る隙がないほど絶え間なく話し続けてしまいます。
「空気が読めない」と表現されるように状況を読み取れず、その場にそぐわない発言をしてしまうことがあります。
こだわりが強く詳細に語り過ぎる、まくしたてるような早口で熱弁をふるうなど、相手の状況やペースを無視するような話し方をして、相手が困ってしまうかもしれません。
3.一方的に自分のペースで話す子の会話が変わる3つの対処法
このような子どもが会話のやりとりを楽しめるようになる、おうちでできる対応が3つあります。
◆①話を聞くタイミングを約束する
思いついたらすぐにしゃべり出す子、周りの状況にかまわず話す子には、タイミングを待てるようになって欲しいですよね。
そこで、子どもの手を取るなどして注意を引き、
「いまお皿を洗っているから、終わったら聞くね」
と、今できない理由を言葉で説明し、いつなら話ができるかを約束するようにします。
手が空いたら、「待ってくれてありがとう!とっても助かったよ」と必ず褒めます。
肯定することで「待つことは正解だったよ」と子どもの脳に伝わるからです。
息子は、褒められたからまたやろう!と待つことに慣れてくれました。
◆②笑顔で遮らずに聞く
約束どおり話を聞く時は、「お待たせ!○○の話、聞かせて!」と、笑顔で相づちをしてリアクションをしっかり見せることが大切です。

「自分の話を受け入れてもらえた」という成功体験と安心感が多いほど、子どもは相手の話を聞けるようになっていくからです。

イライラしそうな時は語尾にハートマークをつけるつもりで話すと、自然といい感じの笑顔になれますよ。
もし主語が抜けたり言い間違っても遮らないでください!「〇〇君と△△したんだね」と話を端的にまとめながら、何気なく正しい言い方を教えてあげればOKです。
私は、しっかり話を聞いてあげるほどおしゃべりに拍車がかかると思い込んでいましたが、事実は逆でした!
息子は声をかけると話を短く切り上げたり、「待って!これだけは話したい!」と交渉するようになりました。
それに、「ずっとしゃべってる」と思う子の話を真剣に聞いてみると、意外と5分くらいのことも多いです。
遠回りに見えますが、「寝る前」や「お風呂」など少しの間でいいので、「ママがニコニコして自分の話を聞いてくれる時間」で成功体験を子どもに積ませてあげてください。
◆③ゆっくり合間を取ってしゃべる
会話のスピードが速すぎる子には、お母さん自身がゆっくりしゃべると効果バツグンです。
私が意識的に合間を取ってゆっくり喋ってみると、息子のしゃべる早さやトーンが落ち着いて、明らかに話しやすくなりました。
子どもは親の話し方を模倣する傾向があります。まわりの大人がゆっくり話すことで会話のスピードをゆるめることができます。
ぜひ一度、大人がしゃべるペースを見直してみてくださいね。
4年生になった息子は、自分の話ばかりし続けないよう、意識しながら友達と会話できるようになっています。思いついたことも、心の中で言えることがずいぶん増えました。
おしゃべりが止まらない、一方的な話し方が気になるADHD・ASDの子どもには、お母さんが、
・話すタイミングを約束する
・笑顔で遮らずに聞く
・ゆっくり合間を取ってしゃべる
この3つを試してみてくださいね。
自分の考えを言葉にできるのは、お喋りな子の強みですよね。
楽しいやり取りで、親子の会話がさらに豊かなものとなりますように。
おしゃべりが止まらない子どもの対応策、まだまだあります!↓↓↓
発達が気になる子に悩むママを一人にしない!今日から子育てに役立つ情報が毎日お手元に届きます。
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
育てにくい子が3ヶ月で変わる!
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
↓↓↓
執筆者:山中寧子
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)