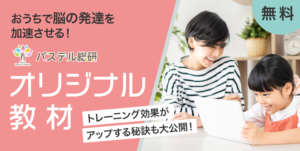発達障害小学生の忘れ物が多い理由は、ワーキングメモリの弱さが原因です。忘れ物が多い対策には、親の声かけと遊びでワーキングメモリを鍛えて対策できます!この記事では忘れ物対策に効果的な方法をご紹介します!
【目次】
1.発達障害小学生の忘れ物の多さに毎日ガミガミ怒った結末とは
2.小学生の忘れ物が多い原因はワーキングメモリの弱さが関係していた
3.ワーキングメモリを鍛える方法はママの声かけ3step
①ステップ1 忘れ物をしても怒らない!
②ステップ2 当たり前にできていることを褒める!
③ステップ3 忘れ物対策を子どもと一緒に考える!
ワーキングメモリを鍛える遊び
1.発達障害小学生の忘れ物の多さに毎日ガミガミ怒った結末とは
発達障害小学生の忘れ物の多さに毎日ガミガミ叱っていませんか?
発達障害の子どもは、一度にたくさんの事を同時に処理することが苦手という傾向がありその特性から忘れ物が多くなりがちです。
小学生になると自分で毎日の準備をしていかないといけなくなりますよね。
毎日の時間割を連絡帳に板書して、明日の持ち物、宿題、プリントなどたくさんのことを自分でやらないといけない機会が増えます。
息子も毎日の時間割を書いて帰ってこない、時間割を書いた連絡帳がない。
学校からのお便りがなく申し込み期限に間に合わないなど、本当にたくさんの忘れ物がありました。

息子の通う学校では忘れ物カードをつけていて、1学期中に20個以上つくと忘れ物が多いと判断されます。
息子はもちろん20個以上の忘れ物がありました。
学校からも注意の連絡があり、毎日の学校の準備に「〇〇は持った?宿題はやった?」と忘れ物をしないようにアレコレ指示をだしていました。
ところが一向に忘れ物は減らず、私のイライラが爆発し毎日ガミガミと叱り続けた結果…
息子は毎日全科目の教科書をランドセルに詰めて、毎日パンパンのカバンを持って学校へ行くようになりました。
2.小学生の忘れ物が多い原因はワーキングメモリの弱さが関係していた
発達障害小学生の忘れ物が多い理由は、ワーキングメモリが低いために起こります。
そもそも発達障害グレーゾーンの子どもは、脳の特性として「見る」こと「記憶する」ことが弱い傾向にあります。
この一時的に見て記憶する能力のことをワーキングメモリといいます。
忘れ物が多いのは、このワーキングメモリの低さが関係しています。
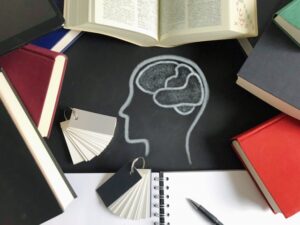
しかしこれは脳の特性であるため子どもが何とかしようと思っても何とかできるものではありません。
ワーキングメモリの低さは脳の特性ですが、その脳の活動を活発にさせることでワーキングメモリを鍛えることができます。
脳は楽しい、嬉しいと感じる時に活動が活発になります。
逆に楽しくない、嬉しくないと感じるときは活動が鈍くなります。
忘れ物が多いからとガミガミ叱ってしまうことは、子どもにとって嬉しくないと感じるため、脳の活動が鈍くなりワーキングメモリも鍛えられないため忘れ物が減る事はないのです。
また叱ることで子どもの自己肯定感が下がり、自信がなくなってしまうので行動することをやめてしまいます。
忘れ物をすることで叱られることが増え続けると、忘れ物が減らないだけでなく学校生活自体も楽しくない事となってしまう可能性もあります。
だからこそ 低年齢のうちにこのワーキングメモリを鍛えて自信をつけていくことが大切になります。
ワーキングメモリを鍛えて忘れ物が減り、学校生活が楽になれば子ども自身の自己肯定感も上がり自分から行動しようとする意欲が湧いてくるという嬉しい効果がたくさんあります!
3.ワーキングメモリを鍛える方法はママの声かけ3step
じゃあ、どうすればワーキングメモリを鍛えられるのでしょう?
それは忘れ物が多くても怒らず当たり前にできていることを褒め、子ども目線で忘れ物対策を一緒に考えるという3つの親の声かけです。
それではワーキングメモリを鍛えるために効果的な親の声かけ3stepをお伝えします。
あわせてワーキングメモリを鍛える簡単な遊びもご紹介しますね。
◆ステップ1 忘れ物をしても怒らない!
まず最初に親は忘れ物をした子どもに怒らないことです!
子どもは忘れ物をしたことを学校の先生に注意をされています。
そして家に帰ってもママに怒られるのです。
そうなると子どもは「自分はできないんだ…」と自信をなくしてしまいます。
どうせやってもできない!
怒られるだけならやりたくない!
と思い、次への行動を起こさなくなってしまうんです。
だから、せめてお家だけでも怒らないであげる場所を作ってあげる事が必要なんです!
◆ステップ2 当たり前にできていることを褒める!
毎日の生活で当たり前のようにできていることをしっかり言葉にして褒めてあげてください。

例えば「体操服出しておいてくれたね~!ありがとう」と、子どもが当たり前のようにやっていることを言葉にして褒めてあげるのです。
子どもは言葉にして伝えてもらうことで、「俺ってできてるんだ!」と 認識することができて自信に繋がります。
自分に自信がつくことで、次に何か行動を起こそうとする気持ちが生まれます。
当たり前のことを褒める事と忘れ物をなくすことは一見関係なさそうに思えます。
しかし、自分に自信を持つことで、次に行動を起こす時に「やってみよう」と自分で考えて行動をするようになります。
当たり前のことをしっかり褒めて、子どもが自信を取り戻す環境を整えてあげることが大切です。
もちろん注意しないといけない場面もあると思いますが、そんな時は2回褒めて1回注意するくらいの感じで注意だけにならないような工夫も必要です。
◆ステップ3 忘れ物対策を子どもと一緒に考える!
忘れ物をしないように子どもと作戦会議をすることです。
親が一方的に指示を出して子どもにやらせるのではなく、子どもがどんな段取りで動くかを一緒に確認し環境を整えてあげる事が大切です。
我が家の息子の学校は、翌日の時間割を午後から帰る時間までの間に担任の先生が黒板に書かれます。
子どもはそれを帰るまでのタイミングで自分でノートに書いて帰るという感じで時間割が伝えられていました。
この状況ではそもそも時間割を書き写して帰るということ自体忘れてしまいがち。
だから帰る前に必ず見る筆箱に「時間割や持ち物をノートに書いて帰る」と書いてメモを貼るようにしました。
また他のプリントと混ざらないように、持ち帰りプリント用のクリアファイルを準備することをしていました。
どんな準備をするかは、学校でのルーティンがわかる息子に考えてもらいました。
どんな対策が一番子どもにあっているかを一緒に考えることで、具体的な行動を事前に把握することができます。
仮に失敗してもまた次の作戦を考えればいいだけです。
◆ワーキングメリを鍛える遊び
このように親の声かけで忘れ物対策をとることも大切ですが、簡単な遊びからもワーキングメモリを鍛えることができるのでご紹介しますね。
簡単な遊びとは、「ハイバーしりとり」や「たぬき遊び」です。
遊び感覚でワーキングメモリを鍛えることができれば、親子で楽しみながら実践できますよね。
ちなみに「ハイパーしりとり」は、2つ前に戻ってするしりとりです。
例えば、「すいか」->「すいか・カメ」->「すいか・カメ・メダカ」」 ->「カメ・メダカ・カラス」という風に2つ前の言葉に戻ってしりとりをします。
「たぬき遊び」は、「た」という言葉を抜くだけです。
例えば、お母さんが「たこ」と言ったら、子どもは「た」を抜いた言葉を答えることになります。
だから子どもは「こ」と答えれば正解!といった感じです。

日常生活でも楽しみながらワーキングメモリを鍛え、偶然でも忘れ物をしない時があれば大げさなくらいに褒めてあげてください!
そうすることで失敗してもまた次の行動を起こし、最終的に忘れ物がなくなっていくようになりますよ!
子どもの忘れ物だけでなく登校渋りにも効果的なママの対応方法も多数紹介しています!
▼ご登録はこちらから
▼無料小冊子プレゼント▼
育てにくい子が3ヶ月で変わる!
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
子どもの脳を伸ばす
ママの声かけ100選
↓↓↓
執筆者:平野 加奈子
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)