外出先で子どもに落ち着きがない。静かにさせようと対応しているのに止まらないのはなぜ?実はそこに、見落とされがちな理由が隠れていることがあります。叱らずに外出がラクになる、感覚特性に基づいた関わり方を解説します。
【目次】
1.なぜ叱っても止まらないの?
2.子どもが落ち着きがなく動き回る・触り続ける理由
3.外出中に落ち着くための3つの対応法
4.日常の関わりで「落ち着く力」を育てる
5.落ち着きのなさは「今、育っているサイン」
1.なぜ叱っても止まらないの?
外出先で子どもが落ち着きなく動き回ると、「もしかしてADHD(注意欠陥多動性障害)なのかも」と不安になる親は少なくありません。
私も、まさにそうでした。
実は、子どもが動き回ったり何でも触って落ち着きがない原因として、ADHD以外の理由が隠れていることがあるのです。

わが家の娘は小さい頃から落ち着きがありませんでした。
お店に入ると、私の手をパッと離して走り出し、商品を次々に触る姿を見るたびに、私は反射的に「やめて、触らないで!」と叱っていました。
周りの目が気になり、娘を常に監視する自分にも、正直うんざりしていました。
今振り返ると、このときの私の関わり方が、娘の落ち着きのなさをさらに強めていたのです。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.子どもが落ち着きがなく動き回る・触り続ける理由
子どもが落ち着きなく物を触ったり走り回る行動は、必ずしも多動・衝動性と結びつくものだけではありません。
背景には、感覚の受け取り方に偏りがあり、体を使って刺激を確かめようとする「感覚探求」という発達特性が隠れていることがあります。
感覚に特性のある子どもは、触る・走る・ジャンプするという行動で足りない感覚を満たそうとします。
そのため、動きながら・触りながらでないと自分の体や気持ちを落ち着かせられないことがあるのです。そうとは知らず私は、
・無理矢理手をつないで行動を止める
・落ち着かせようと声をかけ続ける
・「触らないで・動かないで」と禁止する
という、子どもの感覚探求を途中で遮ってしまう関わりばかりしていました。

感覚を満たそうとしている子どもにとって行動を止められることは「落ち着くための手がかり」を奪われることでもあります。
これまで私がしていた「落ち着かせよう」とする関わりこそが、娘には逆効果だったのです。
▼▼子どもの落ち着きがないのにはタイプ別の理由があります。我が子の「脳のクセ」が分かれば対応策も分かります。
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.外出中に落ち着くための3つの対応法
では感覚を求めている子どもに対して、外出先ではどんな関わりをすればよかったのでしょうか。
私が試して効果を感じたのは「落ち着かせる」ことをやめ、感覚を満たす関わりに切り替えることでした。
◆①触ってもいいもの・いけないものを区別する
何もかも「触らないで」ではなく、「触っていいもの」を決める。
・商品、特に食品や割れ物は触らない約束をする
・買う商品をかごに入れる係に任命する
・手すり・壁・カートなど、商品でないものは大目に見る
多くの人が触れるものは「触ってほしくないな…」と感じるかもしれません。
ですが、帰ったら手を洗えば大丈夫!と割り切って、小さな探索をさせてあげましょう。
感覚が満たされれば、行動は落ち着いていきます。

◆②お気に入りの「さわり心地」を持って出かける
感覚を探している子にとって、止める声かけは逆効果。
代わりにお気に入りのぬいぐるみなど、本人が安心して触れるものを用意しておく方が行動は落ち着きます。
娘のポケットにはお気に入りの小さなぬいぐるみだけでなく、拾った小石や木切れなど、ザラザラ・ツルツルを感じられるものが入っていることもありました。
◆③感じたことを言葉にする
「落ち着いて」の代わりに、「ザラザラだったね」「冷たかったね」と、感じている感覚を言葉にします。
感覚を言葉にすることで、子どもの中で「今、自分は何を感じているのか」が整理されていきます。
すると、感じたまま反射的に動くのではなく、一度立ち止まれる状態が生まれてきます。
4.日常の関わりで「落ち着く力」を育てる
外出先で落ち着いて行動するために、毎回触ったり動き回ったりして感覚を満たす以外に方法はないのでしょうか?
実は、感覚で動く前に一度立ち止まれる状態を、日常の関わりの中で少しずつ育てていくことができます。
◆①“できていること”に目を向ける
できていないことを注意したい気持ちをグッと抑えて、
・ちゃんと座れている
・今は触らず見ている
そんな小さなできている行動に目を向けます。
子どものできていることに目を向けられるようになると、親のイライラが減り、自然と子どもの落ち着きが増します。
◆②できた経験を積み重ねる
当たり前の行動でも、できていることを言葉で伝えます。
「靴下履いてるね」
「ご飯食べてるね」
できた事実だけを短く伝えることで、「できる自分」の記憶が積み重なります。
この自信が、外出先で自分の行動を選び直せる力につながっていきます。
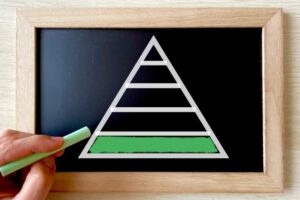
◆③行動のハードルを下げる
子どもの行動が進まないとき、何から始めればいいのかわかっていないことがあります。例えば着替えが進まないとき。
「着替えて」の代わりに「ズボン右足から履く?左足から履く?」。そして、片方でも履けたら「右足履いたね!」とできたことを言葉にする。
このように、行動のハードルを下げ、できたことに注目し、言葉で伝える。
この関わりの積み重ねが自分への自信につながり「できている自分」を感じる手がかりになります。
こうして「できている自分」を感じられるようになると、感覚で突っ走りそうになったときにも、立ち止まり考える力の土台になるのです。
5.落ち着きのなさは「今、育っているサイン」
子どもが落ち着きなく動き回り何でも触る行動は、親を困らせるためのものではありません。
その子にとって、今まさに必要な感覚を育てている最中なのです。
だからこそ、感覚探求を「止める対象」ではなく「今、何をインプットしているのか」を見る視点に変えてみてください。
子どもの行動を見る視点が変わると、親の関わり方も自然と変わっていきます。
私自身、娘が何でも触る姿を見て、
「今、ザラザラをインプットしているんだな!」
と、行動の意味を捉えられるようになってから、イライラせずに見守れる場面が増えていきました。

落ち着かせようとする関わりを手放し、感覚を育てる視点を持つこと。
それが、親子どちらにとってもラクな外出につながっていきます。
▼▼「やめて」といってもやめられない子への効果的な3つの対応法はこちら!
落ち着きがない子への対応でよくある質問(FAQ)
Q1:子どもが落ち着きがなく何でも触るのはADHD(注意欠陥多動性障害)ですか?
A1:必ずしもADHDとは限りません。感覚刺激を感じにくく、無意識に刺激を求めている「感覚探求」が原因の場合もあります。叱って止まらないときは、行動の背景にある理由を見立て直すことが大切です。
Q2:何度も注意したり叱ってしまいました。親の関わり方が悪かったのでしょうか?
A2:親の関わり方が悪かったわけではありません。多くの親は「止めなければ」と真剣に考えるからこそ厳しくなってしまいます。必要なのは反省よりも、子どもの行動をどう読むかという視点の切り替えです。
Q3:外出中に落ち着いて過ごすために、すぐできる対応はありますか?
A3:出かける前に体を動かして力を発散させる、触ってよい物を用意する、感じたことを言葉にする声かけなどが効果的です。叱るよりも、感覚を満たす関わりが切り替えを助けます。
わが子の「困りごと」の裏にかくれた本当の理由を知り、子育ての新常識を知りたい方に!
執筆者:本田ひかり
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)







