宿題のたびに「やりたくない!」と癇癪を起こして泣く小学生。実は「やりたくてもできない」サインかもしれません。癇癪を防ぎ、自分から宿題を始める習慣が身につく3つのサポート法を紹介します。
【目次】
1.宿題をやりたくないと泣くのは「わがまま」?小学生が癇癪を起こす理由
2.「宿題やりたくない」は脳のSOS?癇癪が起こる脳の仕組み
3.「やりたくない!」が「できた!」に変わる3つの宿題サポート法
4.宿題バトルを卒業!わが家の変化とママの心の余裕
1.宿題をやりたくないと泣くのは「わがまま」?小学生が癇癪を起こす理由
宿題の時間になると、急に不機嫌になったり、泣き叫んだり…。
「泣いてる間にできるでしょ!」「みんなイヤでもやってるの!」とつい言いたくなりますよね。
ですが「宿題やりたくない」と泣いて癇癪を起こすのは「わがまま」ではありません。
癇癪を起こす理由は、学校で集中し続けて子どもの脳がエネルギー切れになっているからです。
ものすごくがんばったあと、さらに「あともうひと頑張り!」と言われても、頭も心も動かないのは自然なことなんです。
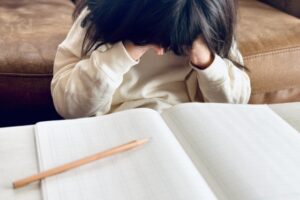
私の娘も1年生のころは、毎日の宿題に泣きながら取り組んでいました。
疲れて手が動かず、文字がぐちゃぐちゃになるたびに癇癪。
結局夜になっても宿題が終わらないので「明日学校行かない」と言い出す日もありました。
「泣かせてまで宿題をさせる意味があるの?」
そう悩んだ私が“宿題の目的”を見直し、サポートの仕方を変えたことで、娘は自分から宿題を始められるようになりました。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.「宿題やりたくない」は脳のSOS?癇癪が起こる脳の仕組み
「宿題やりたくない!」と泣いたり怒ったりするのは、わがままではなく脳からのSOSです。
小学生の脳はまだ発達の途中で、集中力や感情をコントロールする「前頭前野」が未熟。
学校生活では“手の抜きどころ”がわからず、スイッチが入りっぱなしになりやすいのです。
さらに発達障害やグレーゾーンの子は、目や耳から入る刺激をすべて処理しようとするため、脳が疲れやすい特徴があります。
たとえるなら、大人が車を自分で運転する時と、後部座席に乗る時の疲れ方の違い。
脳で処理する情報が多いほど、心も体もヘトヘトになってしまうのです。
そんな状態で「あとひと踏ん張り!」と宿題が出てきたら……涙が出てしまう気持ちもわかりますよね。

また、脳は「楽しい!」「わかった!」と感じたときにぐんぐん伸びます。
反対に「イヤだ」「ムリ!」と感じているときは、考える回路よりも感情の回路が優先され、学びが定着しません。
先生が宿題を出す目的は、学びの定着や勉強習慣を身につけることですよね。
けれど、泣きながら宿題をしても脳は働いていないため、定着どころか「勉強=つらい」と学習してしまいます。
しかも癇癪をくり返すことで「癇癪を起こしやすい脳」が強化されていくという悪循環も。
癇癪は「起こさせない」ことが何より大事なんです。
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.「やりたくない!」が「できた!」に変わる3つの宿題サポート法
「やりたくない!」と言われると、つい「ちゃんとやって!」と叱りたくなりますよね。
宿題バトルを減らすコツは、子どもの脳の“やる気スイッチ”を上手に押すことなんです。

子どもの脳には「報酬系」と呼ばれる“できた!うれしい!”を感じたときにやる気が高まるしくみがあります。
つまり、「できた!」という成功体験が積み重なるほど、脳が自然と「またやってみよう」と思えるようになります。
①できるところから選ばせる
子どもが「自分で選んだ」と感じると、脳のやる気スイッチが入りやすくなります。
たとえば、
・「この漢字の中で書きたいのはどれ?」
・「何回なら書けそう?」
・「ママが書くのを見ててくれる?」
自分で選ぶ体験は、報酬系を刺激して「やってみよう!」という気持ちを引き出してくれます。
②楽しい雰囲気でスタートする
「おやつや遊びは宿題の後」という親の常識を見直し、帰ったらまずおやつでひと息。
リラックスして笑顔がある時間は、脳にとっても“学びやすい時間”です。
「楽しい」「できた」という感情が、次のチャレンジへの原動力になります。
③「できた!」を見つけてほめる
できていないところを指摘するより、「ここはできたね!」を積み重ねていきましょう。
・字が汚くてもスルー、書けたことが〇
・音読が難しければ、ママが読むのを聞くだけでも〇
・漢字が書けないなら、指でなぞるだけでも〇
最後はどんな形でも「よくできました!」の二重マルで締めくくります。
これが“脳の報酬系”を刺激して、勉強を前向きな体験に変えてくれます。
「宿題を手伝うなんて甘やかし?」と思うかもしれません。 ですが、癇癪を起こしてまでやらせるよりも「できた!」の成功体験を重ねる方が、ずっと学びの土台になります。
4.宿題バトルを卒業!わが家の変化とママの心の余裕
「泣かせてまで宿題をさせる意味があるのかな?」
そう思って、まず“癇癪を起こさせない”ことを優先したわが家。
2年生になった今では、帰宅後すぐに「まず宿題しちゃおう」と自然に動けるようになりました。
学校でへとへとになり、宿題を多く感じてしまう時は今でも手伝っています。
それでも以前のように泣き叫ぶことはなくなり、「ちょっと休んでからやる」と自分で気持ちを切り替えられるようになりました。

この経験を通して感じたのは“できた!”の積み重ねこそが、子どもの主体性を育てるということ。
「自分で考えて行動できる力」は、こうした小さな成功体験から育っていきます。
勉強=イヤなこと、というイメージをつけてしまえば、長い人生で大きなマイナスですよね。
小さな宿題で、そんな大切な芽をつぶすのはとてももったいないです!
今日も頑張っているママの笑顔が増えますように。
宿題問題で癇癪になる小学生への対応法もあわせてどうぞ▼▼
宿題やりたくない!癇癪を日常の声かけで解決する方法がわかります▼▼
小学生の宿題問題でよくある質問(FAQ)
Q1:宿題を嫌がって泣くのは何歳まで続くものですか?
A1:脳の発達が進むにつれ、少しずつ「気持ちを切り替える力」が育っていきます。個人差はありますが、小学校中学年ごろになると宿題への抵抗は落ち着く子が多いです。焦らず、「できた!」を積み重ねていくことで自然と前向きに取り組めるようになります。
Q2:宿題を手伝うと依存してしまいませんか?
A2:最初はママのサポートが必要でも、「できた!」という成功体験を重ねるうちに、徐々に自分でやりたい気持ちが育っていきます。サポートは“甘やかし”ではなく“やる気を育てるステップ”と考えてOKです。
Q3:発達障害やグレーゾーンの子も同じ方法でいいですか?
A3:はい、基本の考え方は同じです。ただし、疲れやすさや集中の持続時間に個性があるため、「短時間で区切る」「視覚的に手順を見せる」など、脳への負担を減らす工夫をプラスしてあげましょう。
子どもの癇癪に困り果てているママ!対応策をご紹介しています!
執筆者:本田ひかり
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)




