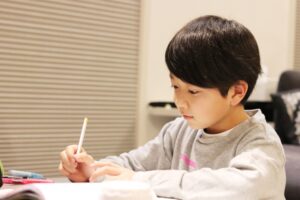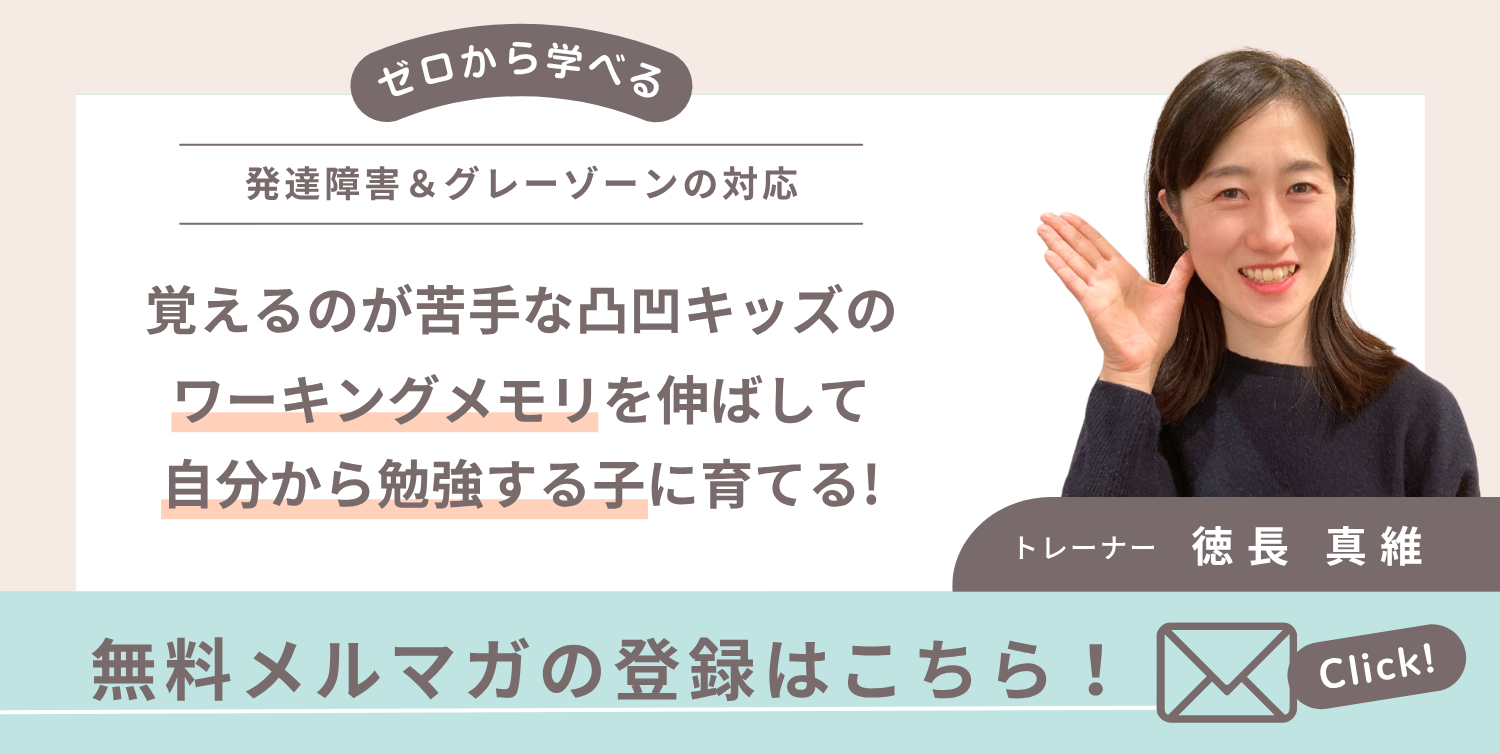ADHDの小学生が「読書が苦手」と感じる背景には、文章が読めない・理解できないといった特性があります。特性を理解してワーキングメモリを鍛えれば、子供の読書の苦手を克服することができます。
【目次】
1.本を読まない!文章が読めない!小学生に悩むママへ
2.ADHDの小学生が読書が苦手!文章が読めないのはなぜ?
3.読書の苦手克服!ワーキングメモリを鍛えて読解力を伸ばす方法
①活字にこだわらない
②興味のあることから伸ばす
1.文章を読むのが苦手!本を読まない!小学生に悩むママへ
ADHDの小学生が本を読まない、文章が読めない…と悩んでいませんか?
読書が苦手だと勉強への影響も心配になりますが、特性を理解して対応を少し変えるだけで克服できます。
我が家には注意欠陥多動症(ADHD)グレーゾーンの小学校4年生の息子がいます。
小学校2年生のときは「読むのが面倒!」と言って、
・本を読まない
・音読が大嫌い
・文章題はひと目見て拒否
といった状態でした。
文章が苦手だと学習全般への苦手意識につながってしまうのではと思い、本当に頭を悩ませていました。

読む力は、語彙力や表現力、そして考える力の土台になります。
だからこそ、子どもの読書への苦手意識を克服したいと思うママも多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな文章を読むのが苦手な小学生を「読書好き」にする対応をお伝えします。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.ADHDの小学生が読書が苦手!文章を読めないのはなぜ?
ADHDの子どもが読書が苦手な原因には、「不注意」「多動性」「衝動性」といった特性が関係しています。
・興味が薄いことには集中できない(不注意)
・じっと座って読むことができない(多動性)
・最後まで読みきれず途中で投げ出してしまう(衝動性)
これらの背景には、ワーキングメモリ(作業記憶)の低さがあります。
ワーキングメモリとは、頭の中で情報を一時的に記憶しながら処理する力のことです。
文章を読むときは、
・文字を目で追う
・内容を理解する
・前後の文をつなげる
という複数の処理を同時に行う必要があります。
ADHDタイプの子はワーキングメモリが低いため、この同時進行がとても苦手です。
だから、読めないのではなく、読むという作業に負担がかかりすぎている状態なんです。

また、ワーキングメモリには「言語的なもの」と「視覚的なもの」があり、ADHDの子どもには視覚的情報の処理が得意なタイプもいます。
逆に、言語的処理に負担を感じやすく、文章が頭に入らない・理解できないと感じることもあります。
しかし、この脳の特性を理解し、得意なワーキングメモリを伸ばすことで、文章への苦手意識が軽減され、少しずつ読書にも前向きになっていく可能性があります。
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.読書の苦手克服!ワーキングメモリを鍛えて読解力を伸ばす方法
本を読まない・文章が読めない小学生の読書の苦手を克服するには「得意」と「好き」からワーキングメモリを伸ばすことがポイントになります。
我が家が実践した2つの方法をお伝えしますね。
◆①活字にこだわらない
「読む=活字の本」と考える必要はありません。
絵と文字の両方がある本に切り替えるだけでも読書の負担は減ります。
例えば
・写真が多いカラー図鑑
・学習漫画(歴史・科学など)
息子はもともと、絵本の絵や図鑑を眺めるのが大好きでした。
視覚的な情報に強く、イメージで理解するのが得意なタイプです。
しかし、眼球運動に苦手さがあり、行を飛ばして読んだり、長文になるとすぐに疲れてしまうことがわかりました。
そこで、活字の本にこだわらず、代わりにマンガや図鑑を取り入れました。
すると、歴史漫画やドラえもんシリーズの漫画、好きなジャンルの図鑑を見るようになり、知らず知らずのうちに得意の視覚的ワーキングメモリが鍛えられ、スッと本を読み始めるようになったのです。
◆②興味のあることから伸ばす
子どもが「好き!」「面白い!」と感じることには、自然と集中力が高まり、学びにぐっと入りやすくなります。
実は脳が伸びるのは、「正しい」より「楽しい」と感じているときです。
自ら進んで取り組み、夢中になっている時こそ、脳はフル回転してワーキングメモリも育っていくのです。
だからこそ、まずは子どもの「好き」を入口にしてあげることが、苦手克服の近道になるのです。
我が家の息子の場合、「野球」に夢中になったことがきっかけでした。
「もっとルールを知りたい!」という気持ちから、ルールブックを自分から読み始め、気づけばスポーツ新聞や選手名鑑、データ年鑑まで読むようになりました。
そしてある日、自分で図書館から活字びっしりの「松井秀喜の自伝」を借りて、熱心に読み始めたのです。
すると、苦手だった音読も文章題も、自分でできるようになったのです。

ADHDグレーゾーンの子どもが読書に苦手意識を持つのは、ただのやる気不足ではなく脳の特性による読みづらさがあるからです。
でもそれは、親の関わり次第で変えられます。
・本にこだわらない
・興味のあることから始める
・「できた!」の体験を積ませる
この3つを意識するだけで、「読書って楽しい」「もっと知りたい」と思えるようになります。
お子さんの「好き」を一番よく知っているママだからこそ、ママの声かけひとつで、読書苦手な子を「本大好き!」に変えることができるのです。
苦手なことを無理にやらせるよりも、「これならできそう!」を一緒に見つけていってくださいね。
ママの対応が、きっとお子さんの読解力と自信を育ててくれますよ。
漢字が覚えられない小学生に効果的な勉強法を動画でご紹介!
よくある質問(FAQ)
Q1. 本を読まない子に無理やり音読させた方がいいですか?
A1. 無理やり読ませると「読書=嫌なこと」と刷り込まれてしまい、逆効果になることがあります。まずは短い文章やマンガ、興味のあるジャンルから始めて「読めた!」「わかった!」という成功体験を積ませてあげましょう。
Q2. ADHDの子におすすめの本や教材はありますか?
A2. イラストや図解が多く、1ページの文字量が少ない本が入りやすいです。マンガや図鑑、ゲームの攻略本などから始めるのもおすすめです。大切なのは「読める・理解できる」という体験を積むことです。
Q3. 読書が苦手でも、親は読み聞かせをした方がいいですか?
A3. 読み聞かせはとても効果的です。文字を追うことが苦手でも、耳から物語を理解する経験が「言葉の理解」や「物語を楽しむ力」につながります。短い絵本や子どもが好きなジャンルから始めると、親子で楽しく続けられます。
子どもが勉強が苦手で困り果てているママ!対応策をご紹介しています!
執筆者:徳長 真維
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)