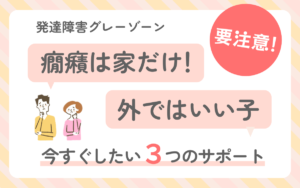2歳児の癇癪で叩かれたとき、思わず叩き返してしまうママへ。脳科学と実体験に基づく安全確保・感情代弁・自分ケアの3ステップで怒りを落ち着け、子どもの叩く行動を減らす方法を解説します。
【目次】
1.2歳のわが子に叩かれて「叩き返しそうになる自分」
2.脳科学の視点から考える「2歳児が叩く・叩き返す行動」
3.叩かれてもたたき返さない!3つの心の守り方
1.2歳のわが子に叩かれて「叩き返しそうになる自分」
2歳児の癇癪は突然スイッチが入り、泣き叫び、叩き、噛みつき…大人の想像を超える激しさになることがあります。
実は、2歳の癇癪は、ママが毎日必死に家事も育児も頑張っているからこそ起きやすいんです。
ママの睡眠不足や気疲れが積み重なり、心に余裕がなくなることが原因になるからなんです。
そんなときに “バシッ” と叩かれると、頭より先に体が反応してしまうんですね。
「もうやめて!!」
「いい加減にして!!」
心が追い詰められると、叩き返したくなるのはごく自然なことです。
だからまずは、“叩き返したくなる自分”を責めないでください。

中には「叩かれたら同じ痛みをわからせるために叩き返す」という方法をとる親御さんもいます。
確かに、その場では静かになることもありますが、それは子どもが納得してやめたわけではなく、「力で抑え込まれた」状態。
心の中の不安や怒りは解決されず、むしろ次の爆発の火種を残してしまうこともあります。
まずは、ママの心を落ち着けて叩いてくる2歳児に対応するのが大切です。
▼▼外ではいい子!家だけの癇癪にお困りの方はこちらの記事もどうぞ▼▼
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.脳科学の視点から考える「2歳児が叩く・叩き返す行動」
子どもが叩くと、 「うちの子、乱暴なのかな?」と不安になるママは多いのですが… 実は2歳児が叩くのは 乱暴さではなく「脳の発達途中」だからなんです。
●2歳児は “言葉より手が先に出る” のが普通
2歳はまだ、自分の気持ちを言葉で伝える力も、感情のコントロール力も未熟です。
・思いどおりにいかない
・ 注目してほしい
・ 空腹・眠気で不機嫌
・ 不安・怖さ・びっくり
これらの刺激が限界を超えると 手が出るしかないのです。
●前頭前野が未発達で衝動を止められない
感情コントロールを司る「前頭前野」は、20代までゆっくり育ちます。
2歳はまだブレーキ機能が弱いため、怒りや不安がわっと出ると手が出てしまいます。
●扁桃体が過敏で“戦う/逃げる”反応が強く出る
扁桃体は「危険!」と感じたら瞬時に体を動かす役割なので、2歳児はこの部分がとても敏感で、刺激に反応しやすいのです。
だから、 「叩かれた!」と感じる→反射的に叩き返すという行動が出てしまうのは当たり前のことなんです。
●悪意ではなく「SOSのサイン」
2歳児の叩く行動は、
・攻撃ではなく
・意地悪でもなく
・乱暴な性格でもなく
ただ感情の処理が追いつかないだけ。
この背景を知るだけで、 「なんで叩くの!?」から 「そうか、今しんどかったんだね」へと視点が変わりませんか?

最後に今日からできる2歳児の癇癪の対応とママの心の整え方をお伝えしますね。
▼▼「動画では、幼児(2〜5歳)の癇癪にどう対応するかを実際に解説しています。2歳のママも5歳のママも参考にしてみてください。」▼▼
▼▼毎日の兄弟喧嘩にお困りのママへ!兄弟仲良くなる秘訣はこちらです▼▼
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.叩かれてもたたきかえさない!3つの心の守り方
まずは、2歳児より先に大人が落ち着くこと。 これが癇癪を鎮める一番の近道です。
では、今日からできる3ステップを紹介しますね。
① 少し距離をとって“安全ゾーン”を作る
叩かれたら、2〜3歩下がるだけでOK。
・自分の安全
・子どもの安全
・ママの心のクールダウン
この3つが同時に守れます。 怒鳴る必要はありません。
静かに離れるだけで、ママの心拍数と怒りはゆっくり落ち着きます。
子どもが泣き止んだら 「落ち着けたね」 と一言ほめてあげましょう。
② 子どもの感情を“代弁”する
2歳児は“気持ちの翻訳家”を必要としています。
「嫌だったんだね」
「もっとやりたかったんだね」
「びっくりしたんだね」
「頭にきちゃったんだね」
この“代弁”が入ると、
・ わかってもらえた
・ 安心した
・ 泣く理由が整理された
と感じ、落ち着きやすくなります。
③ ママの気持ちを整える“自分ケア”を習慣にする
叩かれた瞬間に冷静でいるのは難しい。 だからこそ、日頃から自分ケアが必須です。
・深呼吸3回
・あたたかい飲み物を飲む
・信頼できる人にメッセージ
・ノートに感情を書き出す
・ひとり時間を10分でも確保
怒りは“溜め続けたコップ”がいっぱいになったときに溢れます。こまめに空にしておくことが大切なんです。

2歳の「叩く」はSOSのサイン。 そして、叩き返したくなるのは ママの自然な防衛反応。
だから自分を責めなくて大丈夫。
子どもが叩いてきたら
①安全確保 → ②感情の代弁 → ③自分ケアの3ステップで十分です。落ち着いたあとに
「落ち着けたね!大好きだよ」
とギューッとしてあげれば、それで満点の子育てです。
ママの愛情は、ちゃんと、子どもに届いていますよ。
2歳児の癇癪によくある質問(FAQ)
Q1: 2歳児に叩かれたら、本当に叩き返してはいけないの?
A1: はい、叩き返すのは避けましょう。叩き返すと一時的に静かになることはありますが、子どもの心の不安や怒りは解消されず、次の癇癪の火種になってしまいます。安全を確保し、感情を代弁して、ママ自身の気持ちを落ち着けることが長期的には効果的です。
Q2: 叩かれるとすぐに怒ってしまう自分が怖いです。どうすれば落ち着けますか?
A2: 怒りは自然な反応です。大切なのは怒りをコントロールする方法を持つことです。具体的には
●その場で少し距離をとる
●深呼吸する
●感情を言葉にして書き出す
●温かい飲み物を飲む
などで、心を落ち着ける習慣を作ると衝動をやり過ごしやすくなります。
Q3: 子どもが叩くのは乱暴だからですか?私の育て方のせいでしょうか?
A3: いいえ、2歳児が叩くのは脳の発達の未熟さによる自然な行動で、乱暴や性格の問題ではありません。言葉で気持ちをうまく伝えられないため、叩くという手段で感情を表現しているだけです。ママの愛情不足や育て方のせいではありません。
▼子どもの癇癪と暴言にお困りのママはこちらの記事も参考にしてくださいね▼
発達凸凹中学生の子育でのヒントをお伝えしています。
執筆者:神田久美子
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)