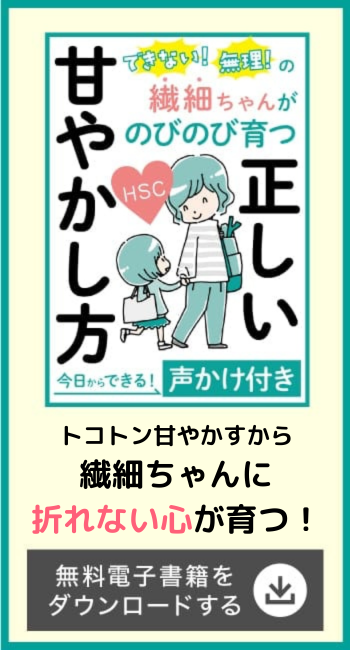先生に「板書が苦手ですね」と指摘をされて不安になっていませんか?板書が遅い小学生も、脳の見る力を育てれば変わります!親子で遊びながらできる視覚のトレーニングで、わが子の板書がスムーズになり、授業についていけるようになった方法を紹介します。
【目次】
1.「板書が苦手ですね」先生から指摘されて気づいた学校だけの困りごと
2.板書が遅いのは「見る力」が育っていないから
3.遊びながらできる!板書がスムーズになるおうち遊びトレーニング
◆親子で一緒に「見る」を楽しむ
◆ボール遊びが苦手な子は「風船遊び」から
1.「板書が苦手ですね」先生から指摘されて気づいた学校だけの困りごと
小学校の先生から「板書が苦手ですね」と言われて、不安になったことはありませんか?
板書の苦手さは、おうちで「見る力」を育てる遊びで伸ばしてあげることができます。
娘が小学2年生のとき、個人懇談で先生から「板書がちょっと苦手かもしれませんね」と指摘を受けました。
黒板をノートに写すスピードがクラスの中でも遅めで、このままだと3年生になって板書の量が増えたときに追いつけなくなるかもしれない、とのことでした。
娘にたずねると「黒板がちょっと見えづらい」とのこと。視力には問題がなかったので、「脳の見る力が関係しているのかも」と思い当たりました。

なぜなら、幼い頃から娘にはこんな様子がありました。
・「〇〇がない」と物を探していることが多い
・周りの動きに合わせるのが苦手で、行動がワンテンポ遅れる
・動くボールを目で追ったり、キャッチするのが苦手
・初めての場所や慣れない場所が苦手
こうした姿から「脳の見る力」が弱いのかもしれない、と感じていました。
そこで、発達科学コミュニケーションに出会った頃に教わった、脳の「見る力」を育てる取り組みに力を入れていきました。
すると、小学3年生になったある日、娘から思いがけない言葉を聞くことができたのです。
「え?黒板?ふつうに書けてるよ」
気づけば、板書の苦手さを自分の力で乗り越えていました。
この記事では、板書が苦手・板書が遅い小学生に隠れている「脳の見る力の弱さ」とその仕組み、そしておうちで簡単にできる具体的なトレーニング方法をお伝えします。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.板書が遅いのは「見る力」が育っていないから
「ノートをとるのが遅い」
「いつも書き終わらない」
そんなわが子を見て「集中力がないのかな?」「もっとがんばればできるはず」と思ったことはありませんか?
しかし、それは性格ややる気の問題ではなく、「目の使い方」=見る力に原因があることが多いのです。
◆見たものを覚えるのが苦手
子どもは黒板の文字を一度に全部覚えているわけではありません。
「国語 教科書 48ページ スイミー」
と書いてあれば、そのうちの一部をパッと覚えてノートに書き写し、また黒板を見て続きを覚えてノートに戻る…という作業を繰り返しています。
ところが見る力が弱い子は、この流れがとても大変です。
・黒板から目を離すと、さっき見た内容をすぐ忘れてしまう
・黒板に戻ったとき、さっき見ていた場所を忘れてしまう
こうしたことが起こるのです。
そのため、板書に時間がかかって「集中してない」「のんびりしている」と誤解されてしまうことも少なくありません。

◆黒板とノートの往復がしんどい
板書では「遠くの黒板」と「近くのノート」を何度も行き来します。
実はこのピントの切り替えは、大人でも案外負担が大きく、子どもの脳にとってはさらに大きなエネルギーを使う作業です。
さらに
・黒板のどこを見ていたか覚えて
・ノートに書いて
・もう一度黒板で続きを探す
ピントの切り替えが苦手だと、この一連の流れをテンポよくこなせず「どこまで書いたっけ?」となり止まってしまいます。
つまり、見る力が育っていないと、板書そのものがとても大変な作業になってしまうのです。
だからこそ、小学生のお勉強への苦手さを和らげるためにも、おうちで楽しく遊びながら「見る力」を育てることが大切です。
次では、わが子に実践して効果のあった方法をお伝えします。
繊細ちゃんに折れない心が育つ!
正しい甘やかし方がわかります
↓↓↓
正しい甘やかし方がわかります
↓↓↓
3.遊びながらできる!板書がスムーズになるおうち遊びトレーニング
「板書が遅い…」という子の多くは、まだ「見る力」が十分に育っていないことが多いです。
特に今の子どもたちはゲームやYouTubeなど近くの画面を見る時間が長く、遠くを見たり、焦点を切り替える力が育ちにくい環境にいます。
しかし、「見る力」はおうちでも、遊びの中で楽しく育てることができます。ここでは、わが家で実践して効果のあった具体策をご紹介しますね!
◆親子で一緒に「見る」を楽しむ
私がまず意識したのは、「外でいろんなものを見る」ことでした。とはいえ、特別な場所に行かなくても大丈夫です。
お散歩の途中で「あれ猫かな?」「このお花きれいだね」「あの雲おもしろい形!」と声をかけるだけでも立派なトレーニングになります。
なぜなら一人だと印象に残らない景色も、ママと一緒に会話しながら見ると記憶に残りやすくなるからです。
私は娘と、冬になると川に来る渡り鳥を見ながら「何羽いるか数えてみよう」とゲーム感覚で観察したり、
水族館では動くアシカショーを見たり、観光地では野生のシカを探したりしました。
「一緒に見て、一緒に話す」。これだけで、ただ眺めるよりもずっと「見て覚える力」が伸びていくのを感じました。
娘は今では、見たものついて「あの雲はプリンセスみたいだね」「見て!可愛い鳥がいるよ」などと会話をしてくれるようにもなりました。

◆ボール遊びが苦手な子は「風船遊び」から
板書には「遠くと近くを素早く切り替える力」が必要です。
これはボール遊びで自然に鍛えられますが、板書が苦手な子はボール遊びも苦手なことが多いのではないかと思います。
そんな時におすすめなのが、風船遊びです。
娘もボールをキャッチするのが苦手で、幼い頃から「怖い」と感じている様子がありました。そこで小学生になってからも、まずは風船から始めました。
・落とさないように自分で打つ
・「1、2、3!」と数えながらママと打ち合う
風船はゆっくり動くので目で追いやすく、「できた!」を積み重ねやすいんです。
「今の上手だったね!」と声をかけながら続けると、娘もどんどん自信をつけていきました。
慣れてきたら柔らかいボールへステップアップしましょう。
今ではキャッチボールやボール蹴りも楽しめるようになりました。
こうした体験を少しずつ積み重ねていくうちに、娘は黒板を見て書くことへの抵抗がなくなり、板書もだんだんスムーズになってきたようです。
3年生になってから個人懇談の前、娘に「板書、大丈夫?」と聞いてみたら、「え?ふつうに書けてるよ」と返事がありました。
半信半疑で先生に確認すると、「全然問題ないですよ」と娘のノートを見せてくださいました。
そこには黒板の内容が丁寧に書き写され、花丸までついていたのです。
「見る力」って、本当に遊びの中でちゃんと育つんだなと、私はそのときしみじみ感じました。
学校で「板書が苦手ですね」と言われても、親子で楽しみながら取り組めば、子どもの力はどんどん伸びていきます。
だから、もし今「板書が遅い」「授業についていけないかも」と不安に思っているママがいたら、一緒に楽しみながら、親子で「できた!」を増やしていきましょう。
参考文献
加藤俊徳『女の子は「脳の見る力」を育てなさい 女の子の「心配事」の9割はこれで消える』日本実業出版社, 2020年
繊細で不安が強い子の育て方に悩むママを応援する「脳科学の子育て情報」をお届けしています!
執筆者:藤井ハナ
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)