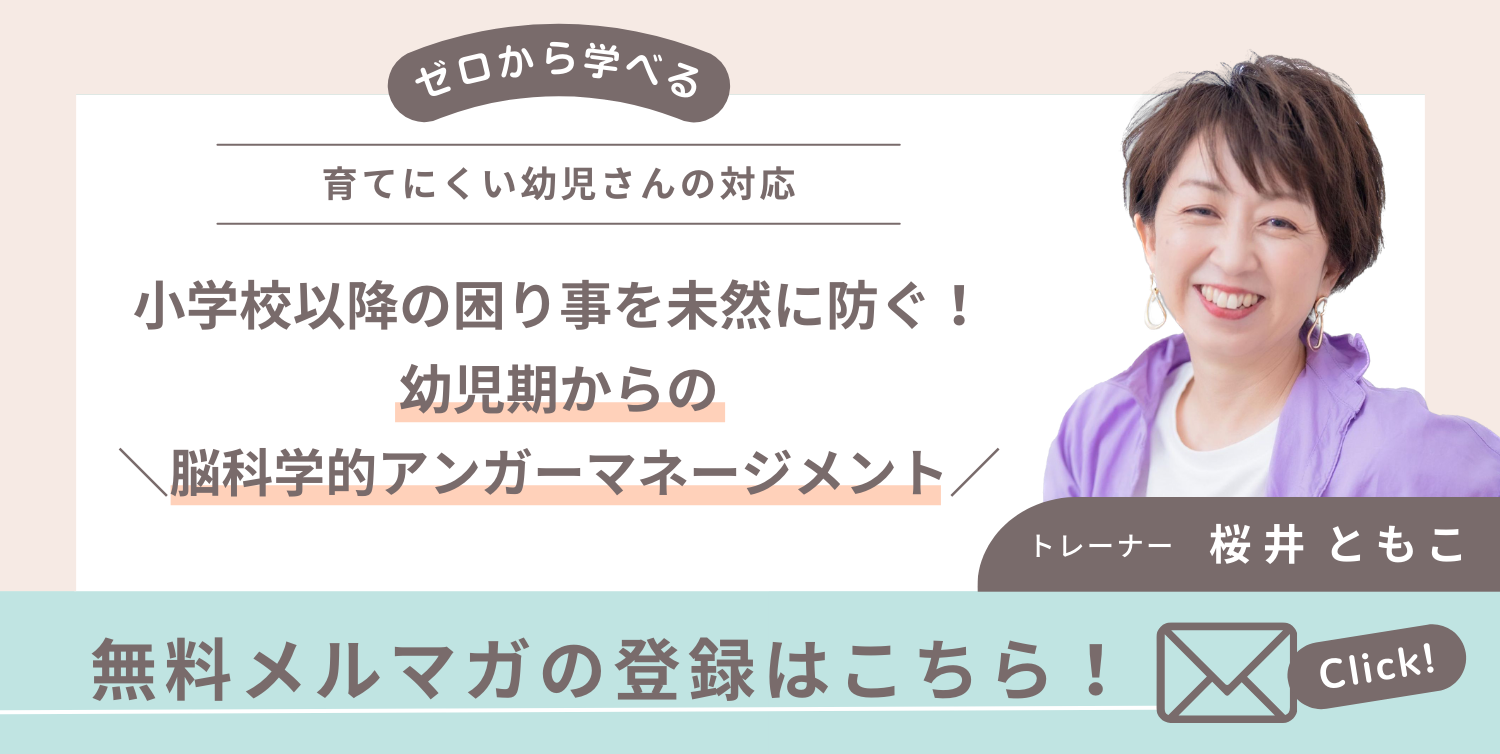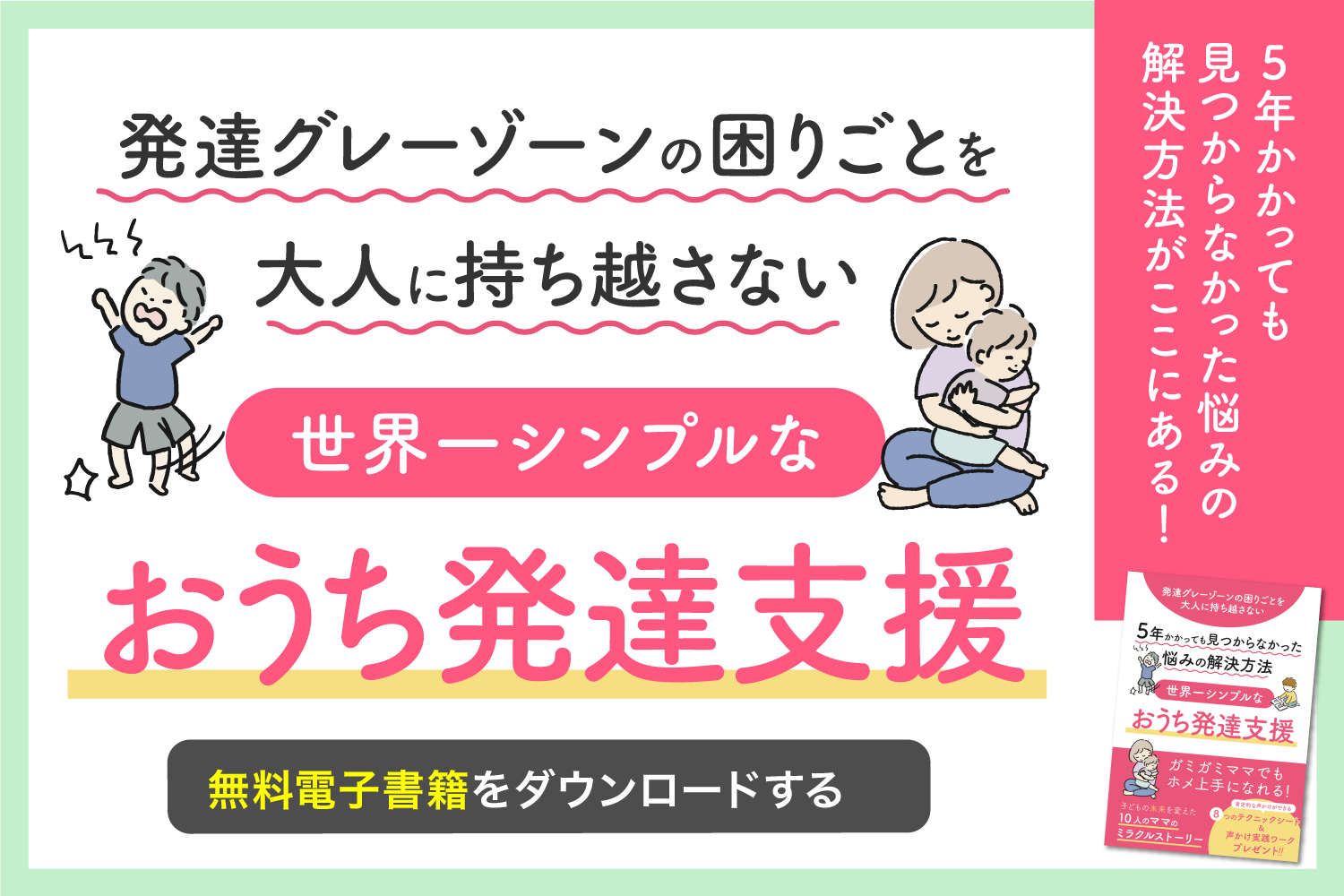3歳頃の子どものわがままや癇癪が爆発し、どうしていいかわからず悩んでいませんか?この「怒り」の対応をどうするかで、子どもの脳の発達が大きく変わります。本記事では、脳科学をベースに「怒らない脳」を育てる具体的な対応のコツをご紹介します。
【目次】
1.【魔の3歳児】幼児期から始めたい「怒り」への対応
2.脳の仕組みから読み解く!怒らない脳が育つ「順番」
◆怒らない脳を育てるには順番が大事!
◆使えば使うほど太くなる「癇癪のルート」
◆癇癪以外のルートを太くする
3.3歳のわがまま・癇癪が落ち着く!今すぐできる対応のコツ
◆肯定の注目:否定の注目=8:2
◆「褒める」より「できたこと」を伝える
1.【魔の3歳児】幼児期から始めたい「怒り」への対応
「魔の3歳児」とも言われる3歳頃の子どものわがままや癇癪に悩まされていませんか?
幼児期のわがままや癇癪などの「怒り」は、落ち着くのを待つのではなく、今すぐに対応を始めることをおすすめします。
脳に「怒り」がある間は、情報を脳が受け取れないからです。
◆ママの声かけが届かなくなる
脳は繰り返しを学習しやすい構造になっているので、「嫌なことがあるとすぐ怒る」というお子さんは「嫌なことがある→怒る」のルートができやすくなります。
その結果、「嫌なことがあるといつも怒る!」が定着しやすくなります。
怒っている時間が長いので、「常に情報が受け取れない脳になっている=ママの声かけが入りにくい状態」になってしまうのです。
◆考える力が育たない
もう1つ一番の問題は、「嫌なことがあると爆発!」になっているお子さんは怒っている状態が長いので「考える力」が育たないことです。
「言っても言っても聞かない」→「言うことが増えてまた癇癪」のエンドレスループに入っていってしまいます。
だからこそ、幼児さんに真っ先に育てて欲しい脳は「怒らない脳」なんです!
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.脳の仕組みから読み解く!怒らない脳が育つ「順番」
◆怒らない脳を育てるには順番が大事!
絶対に覚えて欲しい癇癪ぐずりの対応は、「癇癪には直接対応しない!」ことです。
これが癇癪ぐずりの絶対的な法則です。
脳を発達させ「怒らない脳」を育てる幼児期からのアンガーマネジメントで、一番大事なのは「順番」だからです。
脳には発達の順番があります。
①自信を育てる
②よい行動を引き出す
③困った行動に対応する!
この順番をすっとばして、いきなり「困った行動」をなんとかしようと対応していませんか?
・癇癪をなくそう!
・反抗暴言を言わないようにさせよう!
わたしも息子にこれをずっとやってしまっていましたが、そこがそもそもの大きな間違い。
癇癪や反抗暴言の対応で大事なのは、癇癪や暴言が起こっていない時に、どれだけ脳を発達させる関わりができるかが大事なんです。

◆使えば使うほど太くなる「癇癪のルート」
どうして順番が大事なのか?それは「使えば使うほど発達する」という脳の仕組みが関係しているからです。
例えば、言葉で自分の気持ちを表現するのが苦手な子は、
・嫌なことがあったらすぐ癇癪が起こってしまう
・すぐに暴言を吐いてしまう
ということがありますが、これは嫌なことがあったときに我慢ができないから癇癪を起こして、気持ち吐き出しているんです。
吐き出すと、溜め込んでいるよりラクになるので、「嫌なことがあったら癇癪を起こして吐き出す」という脳のルートが作られてしまいます。
何度も通っている道は、踏み固められて大通りのようにしっかり太い道になるので、細い路地より通りやすくなります。
どんどん通る回数が増えて、そのルートがさらに太く通りやすくなってしまうんです。
通りたがっているルートを「通らないで!」とママが通せんぼしてしまっても、子どもは「なんでー!」と余計に癇癪を起こしたくなったり、無理やり通ろうとしたりして、さらにヒートアップしてしまいます。
◆癇癪以外のルートを太くする
ではどうしたらよいか?
癇癪が起こっている時ではなくて、穏やかな時、落ち着いている時に別の細いルートを何度も何度も通らしてあげて、太い道を別に作ってあげることが大事なんです。
例えば「お!今、考えて動けてたね!よく考えられたね〜!」というように感情の脳ではなくて、「考える脳」つまり「思考の脳」を使ったことを褒めてあげます。
癇癪以外の別のルートを作ってあげることで、癇癪に直接取り合わなくても落ち着いていくんです!
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.3歳のわがまま・癇癪が落ち着く!今すぐできる対応のコツ
嫌なことがあっても癇癪を起こさず伝えられるようになったり、切り替えられるようになったりするためには、ママの声かけがお子さんの脳にスッと届くことが必要です。
◆肯定の注目:否定の注目=8:2
まず意識したいのは、声かけのバランスです。
ママの声かけを、肯定の注目:否定の注目=8:2に整えてましょう。
これは脳が育つ順番の「①自信を育てる」に当たります。
ママは褒めているつもりなのに「ママはいつも怒ってる!」と思っている子が意外と多いです。
子どもの脳は言葉の中身よりも「非言語情報」つまり、声の大きさや声のトーン、表情や、声色などを先に処理します。
なので、言い方によっては褒めが褒めと伝わらないことがあります。
また、繊細なお子さん、不安が強いお子さんは「全然できていないから褒めないで!」と元々褒めを受け取りにくい認知をしていることが多いです。
その場合も、認知のズレをなくしてあげてほしいので、まずは徹底的に肯定の注目:否定の注目=8:2に整えていきましょう!

◆「褒める」より「できたこと」を伝える
肯定の注目をするときのコツは「褒めない!」です。
「褒める育児」がちまたで流行っているので、「褒めたら脳が育つ!」と思っているママが多いのですが、そこが間違いのもと。
褒めるだけでは脳は伸びないので、褒めるのではなくて、「できたこと」に肯定の注目をしていきましょう!
間違っても、ぜったいにおだてないでくださいね!
おだててもその場はいい気分になるのですが、実態がともなっていないと本当の自信はつかないので、子どもの行動は変わりません。
おだてないで、素直にできたことに肯定の注目をしていきましょう!
私がよくやっているのは、シンプルに「〇〇したね!」と言うこと!
・テレビ見たね!
・ご飯食べたね!
・おやつおいしかったね!
で十分です!
「褒める」ことに慣れているママには逆に物足りないかもしれませんが、この「褒めない肯定の声かけ」が脳の栄養素になるので、まずは1週間やってみてください!
▼癇癪を卒業するヒントをを動画でお届けしています!
怒らない脳を育てる!声かけのヒントを配信しています。
執筆者:桜井ともこ
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)